| ニンニクとは? |
ニンニクの薬効や活用法について解説する前に、本項では、先ずそもそもニンニクとは如何なる植物か、また、歴史上ニンニクがどのように利用されてきたかを簡単に説明しました。
|
| ニンニクとは? |
ニンニクはユリ科の多年草で、一名をオオニンニク、古名をオオビル(大蒜)と言います。原産地は中央アジアまたはインドなどとする説もありますが、野生植物が発見されていないため必ずしも明らかではありません。鱗茎は扁球状に肥大し、放射状に着生した4〜10数個の鱗片から成っており、鱗茎は白または帯紅色の被膜に包まれ、葉は扁平で長く先は尖り、青白色を呈しています。花茎は円く高さ30〜60cmに直立、先端に散形花序をつけますいが、花はつけず、先端に珠芽を生ずることもあります。
|
| 人間はいつからニンニクを利用してきたか? |
そもそも人間がニンニクを利用するようになったのは古代エジプト時代で、紀元前3000年頃だと言われています。「不老不死の霊薬」としてクレオパトラも食していたという説や、ピラミッド建設に関わった奴隷や労働者が重労働に耐えるためにニンニクを常用していたという話しもあるそうです。その他、古代ギリシア人の間でもニンニクを口にしたものは神殿に入ることを許されなかったと言われ、また、古代ローマ人もその強い臭いを嫌ったが、強精な成分があるとして兵士や奴隷には食べさせたとも言われています。
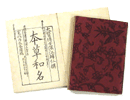 一方、日本では「本草和名」以後に記載が見られるところから、導入・栽培されたのは10世紀以前からのことで、中国や朝鮮からとニンニクが伝えられたと言われています。このように、「古事記」や「医心方」といった古い書物にもニンニクは既に登場しているわけですが、日本の場合は戦後になるまで薬用としての僅かな利用にとどまっていたようです。これは「ニンニク」という名前からも窺うことができます。すなわち、ニンニクという呼び名は仏教用語の「忍辱(にんじょく)」が語源で(※忍辱とは「あらゆる困難に耐える、辱めを忍ぶ」という意味)で、実は仏教ではニンニクは精力がつき過ぎて修行の妨げになるとして食用禁止になっていたのですが、僧侶たちはスタミナ食として「隠れ忍んで食べた」ということから「ニンニク」と呼ばれるようになったそうです。
このように、仏教では避けられていたニンニクですが、日本でも古くから「魔除け」としては使われていたようで、神前にニンニクを供え、民家の戸口にニンニクを吊るして悪魔や病魔から家族の身を守るという風習が江戸時代から続いていると言います。たとえば西洋においてもニンニクをかざしてドラキュラから身を守るというのはかなり有名な話で、遠く離れた日本とヨーロッパで「魔除け」として同じようにニンニクが用いられていたのです。
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|
| ニンニクの薬効 |
ニンニクに様々な効用があるとはよく聞かれる話しですが、では、具体的にニンニクの薬効とは一体どのようなものなのでしょうか?
|
| ニンニクの薬効 |
本節では、ニンニクの薬効につて簡単にまとめて紹介しました。
| ◆ニンニクの薬効 |
| ■1 |
疲労回復効果: |
|
疲労回復ビタミンと言われるビタミンB1は、糖質を分解してエネルギーに変える時に必要な栄養素で、これが不足すると糖質の代謝がスムーズに行なわれないため、疲れやだるさを感じるようになります。ビタミンB1は元々水溶性で直ぐに尿から排泄されてなくなりますが、ニンニクの香りの成分のアリシンがビタミンB1結合すると活性持続型ビタミンのアリチアミンになります。アリチアミンは体内でアノイリナーゼ菌による破壊を受けないので、ビタミンB1の吸収は格段に高まります。また、脂溶性に代わって排泄されにくくなり、B1単独の場合に比べて疲労回復に一層の効果を発揮するのです。その他、ニンニクにはアドレナリン分泌を促して交感神経を刺激する作用もあり強壮作用も示します。 |
|
| ■2 |
殺菌作用: |
|
ニンニクの香りの成分アリシンそのものはニンニクの中には存在せず、ニンニクを刻んだり摺り下ろしたりすると生成されます。つまり、ニンニク中の香りの前駆物質(含硫アミノ酸)、すなわちアリイン、メチイン、イソアリインは、包丁を入れると、香りの成分アリシンに瞬時に変わります。ニンニク細胞が破壊されて、これらの含硫アミノ酸がニンニク中の酵素アリイナーゼと接触して瞬時にアリシンに変化するのです。このアリシンは非常に不安定のもので、時間が経ったり加熱すると、安定型である別のイオウ化合物に変化します。ニンニクの薬効はアリシンだけでなく、安定で揮発性を示すこれらのイオウ化合物によるものであることが最近判明しました。アリシンやそのイオウ化合物は、糸状菌や大腸菌などの殺菌作用や菌の出す毒素の中和作用を示します。最近では、消化性潰瘍や胃がんの原因菌ともなるヘリコバススター・ピロリを抑制するとも報告されています。 |
|
| ■3 |
血栓予防効果: |
|
ニンニクの血栓予防効果は1970年代に報告され始め、アリシン、アホエン、ジメチルトリスルフィド、ジチインなどの硫黄化合物が血栓を予防することが確認されています。動脈血栓を防ぐには血小板凝集能を抑制し、静脈血栓を防ぐには血液凝固能を抑制し、線溶能を亢進させることが必須です。ニンニクのこれらの硫黄化合物は、血小板凝集能抑制効果、血液凝固能抑制効果、線溶能亢進効果の何れをも発揮すると報告されています。 |
|
| ■4 |
動脈硬化予防: |
|
アリシンとアホエンは中性脂肪を低下させたり血中LDLを低下させると報告されています。また、コレステロールの吸収を抑え、胆汁中への排泄を促進することで、コレステロールを低下させるとも考えられています。高血圧の場合、アリシン、アリルスルフィド、アリインは血管平滑筋を弛緩させ、血管を拡張させて降圧させることが報告されています。また、スコルジニンは毛細血管を拡張し、血行を改善して高血圧を予防します。このようにニンニクは動脈硬化を抑えて脳梗塞や心筋梗塞などの動脈硬化性疾患の予防に効果が期待できます。 |
|
| ■5 |
ガン予防: |
|
活性酸素を抑制することによって動脈硬化はもとよりガンが予防されることは今やよく知られているところですが、ニンニクの活性酸素抑制能は特に強力です。ニンニク多く含まれている硫黄化合物やアリキシン、テルペン、セレンなどがガンを予防します。ちなみに、10年ほど前にアメリカと中国が共同で行なった疫学調査では、ニンニクを年間1.5kg
(1日約5g≒ニンニク1カケ)食べている人は、殆ど食べない人と比較して胃ガンの発生率が半分にも抑えられたそうです。 |
|
|
| ニンニクと肝臓病 |
| ■ |
肝臓は我慢をする沈黙の臓器 |
|
肝臓は、栄養素の代謝、有害物質の分解、処理などという働きを始め、人間の体にとって欠くことのできない幾つもの働きをする重要な臓器です。 ところが、「沈黙の臓器」という別名にもよく表われているように、肝臓は少々のトラブルでは悲鳴を上げない臓器のため、
私たちが少しおかしいと感じた時にはかなり病状が進んでいるということが少なくありません。 |
|
| ■ |
肝臓は回復に時間のかかる臓器 |
|
肝臓はいったん機能が低下すると回復に時間がかかります。未だに特効薬がなく、「疲労を避け、高タンパクの食品を摂ってアルコールを控える」というのが基本的な対策とされています。 |
|
| ■ |
毎日ニンニクを摂りましょう |
|
ニンニクには肝臓の機能を総合的に高め強化する作用があります。また、ニンニクには肝臓障害の中でも特に急性肝炎を改善する作用があります。肝臓が弱っていると自覚している人はもちろん、アルコールなどで肝臓に負担をかけがちな人は、毎日少しずつニンニクを摂ることをオススメします。酒の付き合いがある時などは、前もって二ンニクを食べたりツマミとしてニンニクを摂ると二日酔いや悪酔い防止には効果的で、翌朝もすっきり起きられます。アルコールの飲みすぎは肝臓に脂肪のたまる脂肪肝を招きますが、ニンニクはその脂肪の蓄積をも防いでくれるので、酒飲みには特にオススメします。 |
|
|
| ニンニクと高血圧&動脈硬化 |
| ■ |
ニンニクと血圧 |
|
高血圧の治療には血圧降下剤が投与されますが、副作用もあるので、出来れば薬に頼らず、生活の改善で治していくのが理想的です。そのポイントは禁煙と減塩、動物性脂肪の制限など食生活に注意し、ストレスを溜めない生活を心懸けることです。こうした基本を守った上でオススメしたいのがニンニクです。 |
|
| ■ |
ニンニクと血液の循環 |
|
ニンニクには血管を拡張して血液の流れをスムーズにし、血圧を下げる働きがありますが、それだけでなく、過労を解消し、ストレスを和らげる効果もあるので、高血圧の方にはピッタリの食品です。 |
|
| ■ |
ニンニクと低血圧 |
|
ニンニクは高血圧だけでなく、低血圧も改善して血圧を安定させたり、血中のコレステロール値を下げ、動脈硬化の要因をとり除く働きもあり、成人病の予防に役立ちます。健康な人の血液100cc中には100mg〜200mgのコレステロールが含まれていますが、高脂肪の食事を続けていると、この血中コレステロールが増え、血管壁にこびりついて血管を細くしてしまいます。血管が細くなれば血液の流れは悪くなり、やがて完全に詰まり、脳や心臓で梗塞を起こすことになるのです。それでは、コレステロールが血管中にたまらないようにするにはどんな注意をすればよいのかというと、まずは動物性脂肪の摂りすぎなどを改め、糖分やアルコールを控えることです。さらにニンニクを毎日食べることがポイントになります。 |
|
| ◆ワンポイント1: |
ニンニクの成分・アリシンについて |
|
ニンニクの成分アリシンには、コレステロールを分解して血中コレステロール値を下げるという作用があります。肉やバターなどコレステロール含有量の多い食品も、ニンニクといっしょに食べると、血中のコレステロール値が上がらないことは既に明らかになっています。また、コレステロール値が高い人に2力月間ニンニクを与えた結果、その値が3分の2まで下がり、その後ニンニクを止めたところ、数力月後には元の状態に戻ってしまったという報告もあります。さらに最近の研究ではアリシンから出るアホエンに抗血栓作用があることも確かめられています。 |
|
|
| ニンニクと胃腸病 |
| ■ |
ニンニクと胃腸の働きの関係 |
|
ニンニク特有の臭いの成分であるアリシンには唾液や消化液の分泌を促進し、胃腸の働きを活発にして食欲を増進させる効用があります。また、アリシンが体内でビタミンと結合してアリチアミンという物質になると、胃腸の運動を活発にする働きをします。従って、胃下垂気味で胃や腸の運動も鈍っている人や消化液の分泌も不足しがちな人、お年寄りなどには、適量のニンニクを食事と共に摂り続けることが薬より効果が高い場合があります。
なお、美味しい刺し身など魚の生食は日本人には多い食習慣ですが、ニンニクには奇生虫駆除作用があるので、醤油やタレにほんの少々ニンニクを混ぜて食べるだけで、こうした病気の予防にもなります。鰹のタタキにニンニクを添えて食べるのも昔からの日本人の知恵です。 |
|
| ■ |
ニンニクとビフィズス菌 |
|
ニンニクは便秘にも大変な効果があります。これはニンニクが腸の平滑筋の働きを調整してぜん動運動を活発にするためで、慢性の便秘症で悩んでいた人が、ニンニクを常用するようになってからはすっかり便秘が解消したとはよくある例だそうです。また、ニンニクは腸内の善玉細菌であるビフィズス菌を増やす働きもあります。この時に発生する乳酸や酢酸が腸管を刺激して運動をより活発にするので便秘解消にもよいというわけです。
※このようにニンニクは確かに健胃・整腸に優れた効能を持ちますが、あくまでも正しい摂り方をしてこその効果です。さらに最近の研究で、アリシンから出るアホエンに抗血栓作用があることも確かめられています。 |
|
|
| ニンニクと疲れ&だるさ |
| ■ |
ニンニクとビタミンB1の関係 |
|
疲れだるさの原因には様々な病気が隠れてる場合があり、その場合には原因となる病気の治療が第一ですが、まずはビタミンB1欠乏症にならないようにすることが重要です。そこで効果を発揮するのがニンニクです。ビタミンB1は本来、体に一定量吸収されると、それ以上吸収されにくいのですが、上でも述べたようにニンニクにはこれを吸収しやすくさせる効果があります。すなわち、ニンニクの成分であるアリシンはビタミンB1と結合するとアリチアミンという物質に変わるのですが、このアリチアミンはビタミンB1と同じ働きがあり、腸から吸収されやすく制限なく吸収されるのが特徴です。さらに体外に排出されやすいビタミンB1と違って体内に長くとどまる性質もあります。なお、ビタミンB1はニンニク自体にも含まれていますが、ニンニクだけを大量に食べるわけにもゆかないので、ビタミンB1を多く含む食品とニンニクを組み合わせて食べればビタミンB1はさらに効率よく補給できます。 |
|
| ■ |
ニンニクは衰えた細胞を活性化する |
|
アリシンはビタミンB1以外の栄養素とも結合してその栄養素の特性を有効に引き出します。タンパク質と共に摂ると、アリシンとタンパク質が結合し、これが胃液の分泌を刺激してタンパク質の消化を助け、臭いも抑えるという相乗効果を発揮します。また、細胞は老化すると栄養素を吸収しにくくなり、内に溜まった老廃物を排出しにくくなって、細胞全体の機能が衰えてしまいます。ところがニンニクのアリシンには、この衰えた細胞(糖脂質でできた細胞膜)を活性化し、新陳代謝を活発にする働きもあります。 |
|
|
| ニンニクと風邪 |
| ■ |
ニンニクの殺菌作用について |
|
ニンニクは疲労回復、精力増強に効果があり、抵抗力を強めて総体的に健康増進に役立つことは既に知られている通りです。すなわち、ニンニクのアリシンには強い殺菌・抗ウイルス作用があるので、風邪の細菌やインフルエンザのウイルスを殺したり、その働きを著しく弱める働きをするのです。
ニンニクを常食していればウイルスを寄せ付つけにくくなり、侵入してきてもアリシンが直ぐにこれを破壊するので、風邪を引きにくくなり、もしも引いても余り重くなりません。ニンニクは、風邪を引いてしまってからの治療効果には限界がありますが、予防効果は大いに期待できるので、ニンニクで風邪を引かない抵抗力、引いても直ぐに回復する体力をつけるようにしましょう。 |
|
|
| ニンニクと糖尿病 |
| ■ |
アリチアミンという成分について |
|
糖尿病は食事療法が肝心ですが、その一環に加えたいのがニンニクです。ニンニクのアリシンはビタミンB1と結合してアリチアミンになりますが、これは普通のビタミンB1よりさらに糖質の代謝を促します。また、アリシンは体内のビタミンB6とも結合して膵臓の細胞の働きを活性化し、インシュリンの分泌を助けます。膵臓の機能全体を活発にし、血糖値を正常に戻すわけです。このニンニクの効果をさらに上げるために有効なのがビタミンCと共にニンニクを摂ることです。 |
|
| ■ |
ニンニクとビタミンC |
|
血糖値が200〜300mgの人にニンニクを1日2〜3片とビタミンCを1g併用したところ、ニンニクだけでは顕著な効果が出なかったのに見事に血糖値が正常に戻りました。これはビタミンCが糖の消費を高めるからだと考えられます。糖尿病をコントロールする基本となる食事療法や運動療法に加えて、ニンニクとビタミンCを併用する療法を実行するとよいでしょう。
|
|
|
| 参考:話題のニンニク注射とは? |
皆さんはニンニク注射って言葉を聞いたことがあるでしょうか?
ニンニク注射は、ハードスケジュールに追われる芸能人や身体が資本のスポーツ選手に愛用者が多いことで話題です。「最近どうもバテ気味で、ちゃんと寝てるのに全然疲れが取れない」とか「激務に追われて休む暇もなく、段々やる気が無くなってきた」「ひどい風邪を引いてしまって中々体調が元に戻らない」・・・そんな方にオススメなのがこのニンニク注射です。一般に料金は、ニンニク注射一本につき2000円〜3000円程度です。 |
 |
| ■ |
ニンニク注射で直ぐに疲労回復! |
|
蓄積されてしまってなかなか取れない疲れやだるさの原因は、疲労物質の乳酸です。ニンニク注射は、この体内に蓄積された乳酸を分解する成分を血液中からダイレクトに全身に届けます。そのため即効性は実に抜群で、注射してる最中に体が中からカッと熱くなってきたり、鼻やノドの奥に軽くニンニク臭を感じたりと、効果は直ぐに体感できます。 |
|
| ■ |
効き目の秘訣はビタミンB1 |
|
“ニンニク”注射とは言いますが、当然ニンニクの摺り下ろしを注射するわけではありません。ニンニク注射は疲労回復に重要なビタミンB1を始めとするビタミン類を豊富に含む総合栄養注射です。ビタミンB1は糖分を燃やしてエネルギーに変えるために必要な栄養素なのですが、燃えカスの疲労物質である乳酸も燃やしてくれる効果があるのです。ニンニク注射は、血液に乗って万遍なく全身にビタミンを行き渡らせ、蓄積した乳酸を燃やしてくれます。血行も良くなって新陳代謝が高まり、残った疲労物質を洗い流してくれます。 |
|
| ■ |
ニオイの秘訣もビタミンB1 |
|
ニンニク注射の後で微妙にニンニク臭がするのは、ビタミンB1に含まれる硫黄が原因ですが、臭いは直ぐに消えますし、揮発性成分ではないので、息がニンニク臭くなることはありません。ちなみに、このニンニク臭がニンニク注射の名前の由来ともなっています。 |
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|
| ニンニク活用法 |
ニンニクの効用や薬効については分かったが、臭いはキツイし、一体どのように調理したり、活用したらよいのでしょうか?
|
| ニンニクと相性がよい食材 |
| ● |
ニンニク+豚肉 |
|
ビタミンB1を豊富に含む代表的な食材は豚肉です。ニンニクのアリシンと豚肉のビタミンB1が結びついて疲労回復効果をパワーアップさせましょう。 |
|
| ◆ |
ビタミンB1を多く含む食材: |
|
小麦胚芽・ゴマ・豚肉・中華麺 |
|
| ● |
ニンニク+青魚 |
|
ニンニクが魚の蛋白質の消化を促進させます。また、イワシやサンマなどの青魚に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサぺンタエン酸)とニンニクの相乗効果でさらに血液サラサラ効果が期待できます。 |
|
| ※ |
DHA&EPAとは? |
|
不飽和脂肪酸の一種で、コレステロールを減らしたり血小板を固まりにくくすることで血栓を溶かす効果があるとして注目されています。 |
|
| ● |
ニンニク+卵黄 |
|
卵はコレステロールを高めるのでよくないと思われがちですが、実は卵黄に含まれる成分レシチンには、血管内にこびりついたコレステロールを掃除して悪玉コレステロールを下げる作用があります。もちろん食べ過ぎはダメですが、同じくコレステロールを下げる作用を持つニンニクと一緒に摂ることでさらに効果が期待できます。
また、もうひとつ注目したい成分が卵黄に多く含まれるビタミンEです。活性酸素を抑えるビタミンEとニンニクとの組み合わせによってより高い抗酸化作用を期待できます。さらにビタミンEには血管や肌の老化を抑える働きがあるので、血行を促進するニンニクと一緒に摂れば冷え性や美容にも効果的でしょう。 |
|
| ◆ |
ニンニクが苦手な人にもオススメ! |
|
ニンニクは体によいと分かっていても、あの強烈な臭いがどうしても苦手という人や口臭が気になるという人も多いでしょう。そんな人にはニンニク卵黄がオススメです。そもそもニンニク卵黄は、すり潰したニンニクに卵の卵黄を練りこんで、かまどの残り火で焦がさないよう釜煎りしたもので、薬が手に入らない時代には、九州地方を中心に家庭の常備薬的な存在として保存されていたものです。このニンニク卵黄は、強烈な臭いや胃への刺激が殆どないため、
場所や時間も問わず気軽に利用することが出来ます。 |
|
|
| 常備菜を作っておこう |
中国では酢ニンニク、韓国ではキムチ、イタリア料理のパスタと食卓に欠かせないニンニクですが、日本ではそれほど毎日ニンニクを食べる習慣はなく、何かの料理に使う方が多いでしょう。しかし、それではニンニクの健康パワーを感じるのは難しい。そこで本節では、作っておきたい常備菜を以下で紹介します。
| ■ |
ニンニクの醤油漬け: |
|
ニンニクの薄皮を剥き、小片に分けて清潔なビンに入れる。ニンニクが被るくらい醤油を入れ、密閉して冷暗所で保存。1週間くらい経つと食べられるが、2〜3ヵ月おくとより美味しくなります。半年以上おくと、ニンニクの臭いはそのまま食べても気にならない。また、醤油は炒め物などにも利用できます。 |
|
| ■ |
ニンニクの味噌漬け: |
|
ニンニクの薄皮を剥き、小片に分ける。ニンニク5個に対し150g程度の味噌と混ぜておく。密閉容器の底に味噌を敷き、味噌と混ぜたニンニクを入れ、その上に味噌を乗せて一番上にガーゼを貼りつけ、密閉して冷暗所で保存。10日くらい経つと食べられるが、半年以上おいた味噌漬けは箸休めにすると美味しい。 |
|
| ■ |
ニンニクのオイル漬け: |
|
薄皮を剥いて小片に分けたニンニクをビンの3分の2まで入れる。サラダオイルかオリーブオイルをニンニクが被るくらいまで注ぎ、密閉して冷暗所で保存。好みでトウガラシを一緒に漬けると、ピリッとするだけでなく日保ちする。 |
|
| ■ |
ニンニクの酢漬け: |
|
薄皮を剥いて小片に分けたニンニクをビンに入れ、被るくらいの酢を入れる。酢はリンゴ酢でも米酢でも好みのものでOK。また、甘党の人はハチミツや砂糖などを加えてもよい。1ヵ月くらい経つと食べられるようになる。 |
|
|
| 塗っても貼っても健康になる |
食べるばかりがニンニクの利用法ではありません。入浴や湿布など使い方は色々あります。体質や好み(臭いが気になるかどうかなど)に合わせて試してみて下さい。
| ■ |
ニンニク風呂: |
|
ニンニクは切ったりつぶしたりすると臭いが強烈になるので、切らずにそのままガーゼの袋などに入れてお風呂に浮かべる。もっと臭いを和らげたい場合には、薄皮を剥いて小片に分けたニンニクを電子レンジで30秒ほど加熱するとよいでしょう。冷え症や肩こり、腰痛、神経痛などの症状を和らげたり、肌をすべすべにし、保温効果が高いと言われます。ただし、肌に合わない人もいるので、最初は少しのニンニクで試してみましょう。 |
|
| ■ |
ニンニク汁: |
|
ニンニクの殺菌・抗菌作用を利用する方法。摺り下ろしたニンニクを水虫が出来ている部分に塗って1〜2時間程度おいて洗い流すか、または摺り下ろしたニンニクをガーゼなどに薄く伸ばして貼りつけたり絞り汁を塗ってもよい。ただし、必ずパッチテスト(肌に合うかどうかを事前に少量でテストすること)を行なうようにして下さい。また、摺り下ろしたニンニクの絞り汁を薄めたものでうがいをすると、風邪の原因になる細菌などが繁殖するのを予防出来ます。口臭が気になるようなら、牛乳を口に含んでから飲み込むと臭い消しになります。 |
|
|
| クサイのが苦手なら〜ニンニクのにおいを減らす調理法 |
ニンニクにどんなに効果があると分かっていても、やぱりニンニクを食べた後の口臭もそうだが、そもそもニンニクが放つ臭いが我慢出来ないという人も多いでしょう。本節では、そんな時に役立つ方法を紹介します。
| ■ |
ニンニクのにおいを減らす調理法 |
|
ニンニクの成分アリシンが空気に触れて酸化する時にあの臭いが発生します。だから、出来るだけ空気に触れる面が少ない丸ごとが一番匂わない。たとえば小片に分けて薄皮を剥いた粒のままホイル焼きにしたり、揚げニンニクや蒸しニンニクなどの調理法が余り臭いを気にせずに食べられます。 |
|
| ◆ニンニクを食べた後には? |
|
|
|
|
|
|
| ● |
ジャスミン茶を飲む(その他、プーアール茶、ほうじ茶、コーヒー、ミントなどのハーブティーも可も) |
|
|
| 参考:玉ネギやニンニクがビタミンB1の吸収を助ける |
| ■ |
ビタミンB1を吸収しやすくするアリチアミン |
|
食品中のビタミンB1は主としてチアミンピロリン酸エステルの形で蛋白質と結合したり澱粉に吸着して存在することが多いものですが、ビタミンB1の化学構造を少し変えた誘導体も多数開発されており、ジベンゾイルチアミンやアリチアミンなどがあります。これらは吸収率が優れているために医薬品或は食品添加物として使われています。 |
|
| ■ |
タマネギやニンニクの臭い成分から生まれる |
|
アリチアミンは、玉ネギやニンニクをすりつぶした時に発生する臭い成分アリシンとチアミンとの反応によって生じた脂溶性の成分ですが、これは小腸からの吸収性に優れており、ビタミンB1の補給に適しています。
|
|
|
| 注意!ニンニクの落とし穴 |
以上、色々とニンニクの効果・効用について解説してきましたが、
確かにニンニクには生活習慣病の予防やパワーを漲らせる作用があることは事実ですが、このニンニクを常食とすると危険な落とし穴が待っているのです。精力を付けるどころか、貧血になって体力減退などという逆作用を引き起こしてしまうこともあるのです。それは、ニンニクには多量のアリシンが含まれていますが、この成分が赤血球の中からヘモグロビンを追い出してしまう為に貧血を起こさせてしまうのです。そのため、ニンニクの摺り下ろしなどの生食の常食には注意が必要です。
要するに何事も「過ぎたるは及ばざるがごとし」で、このようにニンニクは刺激が強いので食べすぎは禁物です。特に空腹時に多量にニンニクを摂取すると胃を痛めるので注意が必要です。生なら1カケ、加熱したものなら2〜3カケを目安に摂るようにしましょう。子どもや高血圧の人はこの半分以下に留めましょう。また、ニンニクの臭いを消すには、ミネラルたっぷりの果物や野菜・牛乳・ヨーグルトを一緒にとるとよいでしょう。それ以外には卵・チーズなどでも効果があります。基本的に植物性より動物性タンパク質の方がニンニクの消臭には効力があると言われています。
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|




