| フリーターとニートの定義 |
フリーターやニートの増加が社会問題化しています。
学校卒業時点で就職も進学もしていない学卒無業者の増加や正社員ではないアルバイトなどの非正規で働く若者の増加が近年著しいと言われます。また、不況下にも拘わらず若者の自発的離職も増加しています。こうした若者の就業行動の変化の背景には一体どのような要因があるのでしょうか? 有効な対策を検討するためにも、まずその原因を解明する必要があります。
本項では、先ずは手始めにフリーターとニートの定義をしておきました。
|
| フリーター――正社員でない生き方 |
| □ |
フリーターの定義 |
|
フリーターとは、「フリー(英語)+アルバイター(独語)」を略した和製語です。80年代後半のバブル経済の時期に「組織に縛られない就業形態」として脚光を浴び、一般に定着した言葉で、1987年にリクルートのアルバイト雑誌『フロム・エー』が使い出したのが広まったキッカケだと言われています。
意味は「恒常的なアルバイトを主な収入源とする人」とほぼ同義で、会社や団体組織に正社員や職員をとして所属せず、 時給や日給による給与を主な収入源として生活する人のことを一般にフリーターと言います。
なお、「ミュージシャンや作家になるという夢を持ちながら日々の生活はアルバイトでつなぐ」という若者に対して、「プータローと侮蔑するのではなく、人生を真剣に考える若者として応援したい」という意味からフリーターという言葉が生まれたと言います。 |
|
労働経済白書におけるフリーターの定義は、年齢15歳〜34歳の学校卒業者に限定し、女性は未婚の者。アルバイトやパートで働いているか、現在無業の者は家事も通学もしておらず、「アルバイト・パートの仕事を希望する者」とされます。
また、フリーター数については厚生労働省が「労働経済の分析(労働白書)」で公表していましたが、内閣府の平成15年国民生活白書(2003年5月末発表)がフリーター数417万人という数字を公表した点に大きな関心が集まりました。
※ここで多少詳しく内訳を見ると、最近のフリーターの人数は、厚生労働省では201万人(2005年)、内閣府では417万人(2001年)としており、約2倍の違いがあります。また何れの定義によっても、フリーターの人数は10年間で倍増しています(なお、2004〜05年は景気回復に伴ってフリーターはやや減少傾向にあります)。
なお、内閣府定義の2001年のフリーター数では、若年人口(15〜34歳)の9人に1人(12.2%)、学生・主婦を除いた若年人口の5人に1人(21.2%)がフリーターとなっています。年齢別に見ると、1992年には20代前半で最も多かったフリーターが2001年には20代後半にピークがシフトし、30代でもフリーターが急増するなどフリーター生活の長期化が懸念されています。
なお、当初は正社員以外の選択肢としていわば自発的にフリーターを選択する者も多かったため、「フリーターの増加は日本人の生活形態が多様化しているためであり、フリーターは自分の判断で自由気ままな人生を送っているだけだから社会問題ではない」という認識を示す人もいますが、現在は、経済情勢の悪化等による就職難で正社員になれず、やむなくフリーターとなる人が増えていると言われています。また、リストラに遭ったサラリーマンがフリーター化する場合もあります。
| □ワンポイント1: |
フリーターの定義と人数の把握 |
|
フリーターの捉え方については、厚生労働省の定義は「フリーターという立場を選択している人(正社員になりたくない人)」、いっぽうの内閣府の定義は「フリーターにならざるを得ない立場の人(正社員になれない人)を含む」という違いがあります。現在無職の人のうち前者はパート・アルバイトを希望する人のみカウントし、後者では正社員を希望する人を含めてカウントしている点に違いが表われていると言えます。要するに後者は「正社員になりたくない人」と「正社員になれない人」を両方含んでいるので、当然数は多くなるわけです。なお、内閣府定義のフリーターでは、就業者としてパート・アルバイトばかりでなく最近増えている派遣・契約等も含めているので、なおさら数が多くなっているのです。
ちなみに、厚生労働省ではフリーターを最初に平成3年版労働白書で集計しており、当時は「正社員になりたくない人」という立場が着目され、そのまま定義が継続したものと考えられます。また、その後の内閣府(2003年)の定義ではフリーターの負の側面がより着目された結果、新定義となったものと考えられます。何れにせよ、パート・アルバイトで就業している若者の中には「主体的に選択している者」と「消極的に選ばざるを得ない者」との両面が従来からありましたが、要するに厚生労働省の最初の定義では前者に着目したということでしょう。 |
|
|
|
| ニート――無職で、かつ仕事を探そうともしない人 |
近年になって、フリーターよりさらに深刻な存在としてニート(NEET)が注目されています。
ニートは従来の就業支援策からこぼれ落ちてきた存在で、失業者としてもカウントされず、これまで把握されて来ませんでした。ニートは「働くという意味での社会参加に対する意欲を喪失し、または奪われている」とされ、現在日本でも社会問題化しつつあります。
本来これは英国における造語で、「NEET=Not in Employment,Education or Training」、直訳すると「就業・就学・職業訓練の何れもしていない人」を意味しています。1998年に英国の義務教育を終えた16〜18歳の若者のうち9%に当たる16.1万人が就業も就学もしていないことから国民にショックを与え、この言葉が生まれたと言います。
| ニートの定義 |
| □ |
英国におけるNEETの定義 |
|
本来は「16〜18歳の、教育機関に所属せず、雇用されておらず、職業訓練に参加していない者」と定義されています。また、場合によっては「離職中・求職中・育児または家族の世話・無給休暇中・病気や障害・ボランティア活動」までもニートの例として挙げられるほどで、日本のような「ひきこもり」とか「働く気のない若者」というイメージはありません。なお、英国ではこの語は余り一般には普及していないそうです。
※ただし、ニートという語は英国を始めとする諸外国では殆ど使用されておらず、類似した分類も普及してはいません。 むしろ近年欧米ではニートについて「日本における若年無業者問題を指す語」として認知されつつあるのが現状です。そのため、以下の説明は日本におけるニート(日本型ニート)に関する説明です。
もちろん欧米においても、「教育機関に所属せず、雇用されておらず、職業訓練に参加していない者」は存在するのですが、実はニート或いは類する語での分類・定義付けはされておらず、その概念も普及してはいないのが実情です。その原因のひとつは、ニートという分類が1999年当時社会問題となっていた「社会参加困難者」(被社会的排除者)の一部に過ぎないものであることが挙げられます。欧米における「社会参加困難者」は人種・宗教・言語による差別・格差問題の色が濃く、日本での若年無業者問題と同列に扱うことは困難なのです。その意味で、英国のニートの定義付けは将来的な「社会参加困難者」を予測する分析としての意義はありましたが、総合的な社会的排除対策が行なわれる中でニートという分類自体は重要視されなかったのです。 |
|
|
| □ |
日本におけるNEETの定義 |
|
内閣府の「青少年の就労に関する研究会」の中間報告によると、「若年無業者」を「学校に通学せず、独身で、収入を伴う仕事をしていない15〜34歳の個人」と定義しています。また、ニートとは、若年無業者のうち「非求職型及び非希望型」、つまり「就職したいが、就職活動していない者」または「就職したくない者」としており、日本でニートと言うと大抵はこの意味で用いられるのが一般的です。
※本来ニートとは労働政策における分類としての用語に過ぎませんでしたが、日本においてはニートは本来の意味から離れ、、2002年頃から社会問題として認知されていた「就労意欲を喪失した若者」や「ひきこもり」と混同されて用いられるようになり、否定的なニュアンスで使われる傾向があります。 |
|
|
| □ |
日本におけるNEET人口 |
|
平成16年の労働白書から初めてニートに当たる存在を「若年層無業者」と捉えるようになりました。そこでは「若年無業者」は4つの「非」で定義されています。すなわち、「非就業・非求職・非通学・非家事」の4つです(最初の2つで非労働力人口となります)。
なお、平成16年の労働白書において「若年層無業者」(ニート)の数は2003年に52万人と集計されました。平成17年以降の労働白書では「若年無業者」として新たに家事・通学をしていない既婚者・学生も加え、2003年64万人、2004年・2005年も同じ64万人と発表しています(これは対象となった15〜34歳人口の2.0%に当たります)。また、2005年3月に内閣府が行なった若年無業者に関する調査によると、ニートは2002年に85万人という数字がはじき出されています。 |
|
| □ワンポイント2: |
ニートを見る社会の目〜評価と差別 |
|
ニートを見る社会の目はフリーター以上に厳しいものがあります。ニートは一般に「働かない若者たち」と表現されますが、実際の状況を分析すると、実は「働けない若者たち」の割合が相当数含まれており、「働かない若者たち」といった一方的な表現ではニートの状況を的確に示していないとの見解もあります。しかしながら、「働かざる者食うべからず」「勤勉な労働こそ最高の美徳」とする日本の文化や、憲法で定められている「国民の義務としての労働」の硬直化した理解、また、「働かずに食べてゆこうとしているのは甘え」といった先入観、そして、これらの考えに基づく偏った報道と相俟って、「ニートは働かずにどうしようもないすねかじりだ」という偏見を生んでいます。その結果として、ニートを社会から除外し、復帰が困難な状況を形成してしまっているのではないかとの指摘もあるくらいです。さらに、「キレる若者」「引きこもる若者」といった若者に対する漠然としたネガティブなイメージを「ニート」という用語が引き継いでいる感も否めず、そのため、問題の根源である社会の問題、すなわち今日の厳しい雇用状況の改善という視点が忘れ去られているのではないかという意見もあります。ニートの多様性と画一的偏見はこの問題をさらに複雑化し、解決は長期化するであろうと考えられています。 |
|
| □ |
注意点――フリーターとニートは違う |
|
若年無業者(日本におけるニート)は、ある意味でフリーターにほぼ該当すると捉えることも可能ですが、正確にはフリーターはニートに含まれません。
また、就業意欲があっても求職活動していなければ日本的な意味でのニートになります。なお、家事手伝いについても統計上はニートとして扱われるのが一般的です。
※このように、ニートはしばしばフリーターと同列に語られることがありますが、これは両者が何れも労働・経済問題であるためで、本来はフリーターが臨時雇用という形で労働を行なう一方、ニートはそれを行なわないという違いがあります。また失業者とニートでは、前者が就業に向けた活動を行なっているのに対し、後者はそれを行なっていないという違いがあります。 |
|
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|
| フリーターの実態〜類型と特徴〜 |
フリーターの類型とその特徴・実態につき、以下に詳しく紹介しました。
|
| 誰が・何故フリーターになるのか? |
| フリーターには大きく3つ、細分化すれば7つの類型 |
フリーターには、(A)「モラトリアム型」、(B)「夢追求型」、(C)「やむを得ず型」の3つの類型があります。
これは、フリーターとなった契機と当初の意識とに注目した類型化で、以下でその内容を詳しく見てゆきます。
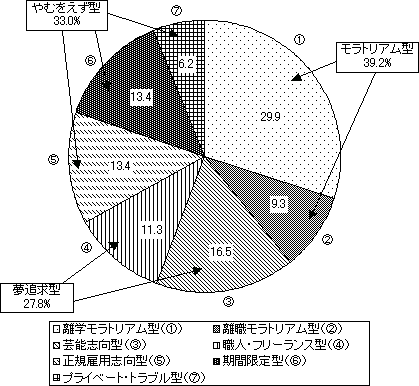
| □A |
モラトリアム型 |
|
※フリーターへの分岐点は随所に存在しています。卒業時に進路未定者を出さない進路指導だけでは問題は解決されません。
|
|
(A-a) |
離学モラトリアム型: |
|
|
高校や専門学校・大学からの中退者、大学受験失敗=進学断念者、進路未定のままの高卒者・大卒者などが含まれる。
|
|
(A-b) |
離職モラトリアム型: |
|
|
高卒・短大卒・大卒後、数ヶ月から2年程度の正社員経験を経て離職し、フリーターとなった者。離職理由は労働条件や人間関係で、彼らの正社員経験の印象は余りよいものではなく、離職時に正規雇用を強く志向してはいない。
|
|
| □B |
夢追い型 |
|
※若者の憧れる職業には参入ルートが不確かなものが多く、これらの職業そのものがフリーターという就業形態を要求していると見ることも出来ます。
|
|
(B-a) |
芸能志向型: |
|
|
バンドの練習やオーディション応募・養成機関所属など何らかの関連活動を行なっているが、夢への接近度は様々。
|
|
(B-b) |
職人・フリーランス志向型: |
|
|
経験を通した技能・技術の蓄積が要求される。関連するアルバイトをしたり、仕事を請け負ったり自ら作品を売り込んだりして市場への参入を図っている。
|
|
| □C |
やむを得ず型 |
|
※本人の意欲とは別の労働市場の悪化や家庭の経済事情やトラブルなどの事情から、「学校から職業へ」の円滑な移行が中断されることがあり得ます。
ただ、最近では就職難から正規雇用が減少しているため、正規雇用を志向することでさえ「(B)夢追い型」になってしまうケースもあり、この「やむを得ず型」は有名無実化しているという意見もあります。これは自立に関わる問題なので、本来「(C)やむを得ず型」を「(B)夢追い型」に分類するのは適当ではないものの、正規雇用を志向するだけで「(B)夢追い型」に分類される傾向も強いため、今後の議論になるものと思われます。
|
|
(C-a) |
正規雇用志向型: |
|
|
公務員など特定の職業への参入機会を待っている者、離職したが正規雇用を志向している者、就職活動に失敗した者、派遣を志向した者が含まれる。なお、企業の採用活動がもっと積極的に行なわれているか、或は特定の職業に関する労働市場の需給状況がもう少し緩んでいれば、このタイプの者の殆どはフリーターとはならなかったと考えられる。
|
|
(C-b) |
期間限定型: |
|
|
進路変更による専門学校への入学時期待ち、次の入学時期までの学費稼ぎ、ワーキングホリデーのための費用稼ぎなどが含まれる。
|
|
(C-c) |
プライベート・トラブル型: |
|
|
トラブルにより学校を離れたタイプ。当初の将来展望がはっきりしておらず、その意味では(A)モラトリアム型と共通している。
|
|
|
| フリーターの特徴 |
| □1 |
フリーターの6割は女性、年齢層は20歳代前半層までが中心 |
|
・女性が約6割を女性が占めており、フリーターには女性が多い。
・23歳までの者がおよそ3分の2を占める(平均年齢は23歳)。
・高卒までの学歴の者が半数強。何らかの教育機関からの中退者が2割を超える。 |
|
| □2 |
元からの首都圏在住者と地方からの流入者が混在。7割強が高校時代にアルバイトを経験 |
|
・東京の高校出身者は半数弱。2割強が千葉・埼玉・神奈川で、その他の地方の高校出身者が3割弱。
・7割強が高校時代にアルバイトを経験(特に高卒以下の女性では殆どが経験)。地方高校出身者ではアルバイト経験者は比較的少ない。 |
|
| □3 |
フリーターには大きく3つ、細分化すれば7つの類型 |
|
フリーターには、(A)「モラトリアム型」、(B)「夢追求型」、(C)「やむを得ず型」の3つの類型があります。詳しくは上記項目をご参照下さい。
(A)モラトリアム型:(a)離学モラトリアム型 (b)離職モラトリアム型
(B)夢追求型 :(a)芸能志向型 (b)職人・フリーランス志向型
(C)やむを得ず型 :(a)正規雇用志向型 (b)期間限定型 (c)プライベート・トラブル型 |
|
| □4 |
類型別の傾向 |
|
・最も多いのは「(A-a)離学モラトリアム型」。次いで、「(B-a)芸能志向型」、「(C-a)正規雇用志向型」及び「(C-b)期間限定型」、「(B-b)職人・フリーランス志向型」。また、男女共に「(A-a)離学モラトリアム型」が最も多いが、男性では「(C-b)期間限定型」「(B-a)芸能志向型」「(C-a)正規雇用志向型」、女性では「(B-a)芸能志向型」「(B-b)職人・フリーランス志向型」がこれに次いでいる。
・「(B-a)芸能志向」は高卒以下に多く、「(C-a)正規雇用志向型」は高卒超の男性に、「(B-b)職人・フリーランス志向型」は高卒超の女性に多い。
・4割の者が正規就業を経験。「(C-a)正規雇用志向型」では7割、正規就業経験者(契約・派遣・見習社員経験者を含む)は4割。なお、「(A-b)離職モラトリアム型」「(C-a)正規雇用志向型」以外の類型では正規就業経験者比率は2〜3割。 |
|
| □5 |
フリーターとなった背景に家庭の経済事情や父母の離婚・家族の病気などの事情があるケースが2割弱 |
|
|
| フリーターを考え始めた時期(フリーター志向・予定進路別) |

|
|
| フリーターはどのような生活をしているのか? |
| □1 |
フリーターの週労働日数は平均4.9日、月収は平均139,000円 |
|
・ヒアリング対象者の週当たり労働日数は5日が半数弱。平均は4.9日
・月収は10万円以上15万円未満が全体の4割弱を占める。平均月収は約139,000円 |
|
| □2 |
3分の2が親と同居、同居者の半数以上は何らかの経済的な負担 |
|
親と同居している者は63.9%。同居者の半数以上は何らかの経済的な負担(生活費を入れる、学費の一部を負担する、年金や保険を支払う等)をしている。別居者の殆どは自活 |
|
|
| フリーターはどのような就業意識を持っているのか? |
| □1 |
フリーターの語るメリットは「自由」「時間の融通がきく」「休みが取りやすい」「様々な経験ができる」、デメリットは「収入が少ない」「社会に認められていない」「不安」「不安定」。正社員は「金銭面」でよく「安定」しているが、「拘束」される、という認識 |
|
・デメリットのうち「社会に認められていない」は「(A)モラトリアム型」や女性で、「不安」「不安定」は「(C)やむを得ず型」で挙げる者が多い。
・フリーターに対する世間の厳しい目は認識しているが、「気にしない」者が多い。 |
|
| □2 |
「やりたいこと」への強いこだわり |
|
1.「やりたいこと」があるフリーターとないフリーターを区別して評価
2.「やりたいこと」であれば、正社員でもフリーターでもこだわらない
3.「やりたいこと」を見つけようとしている「(A-a)離学モラトリアム型」、また、「やりたいこと」があってフリーターをしている「(B-a)芸能志向型」「(C-b)期間限定型」 |
|
| □3 |
フリーター経験による主な自覚的な変化はソーシャル・スキルの向上 |
|
|
| キャリア形成・能力開発の問題はあるのか? |
| □1 |
多くの者が将来のキャリア形成を意識し、探り、方向を捉えようとしているが、夢が夢のままとどまっている者、モラトリアム状況を続ける者、消極的に現状を肯定している者などキャリア形成という面では停止状況にある者も少なくない。 |
|
| □2 |
フリーターの就業職種は限定されており、フリーターとしての就業経験が基本的なソーシャル・スキルの形成以外の職業能力形成に結びついている場合は少なく、フリーター就業が長期に及べばキャリア形成の貴重な時期を逸するおそれがある。 |
|
・フリーターとして就いてきた職種は、ファミリーレストラン、ファーストフード、カラオケボックス、漫画喫茶などの「サービス関連」、レジ、コンビニ店員などの「販売関連」、テレフォン・アポインターなどの「営業関連」、組立・加工、交通量調査などの「現場作業関連」などが中心。
・接客や社員とのコミュニケーションなどからソーシャル・スキルの向上を意識する者は少なくないが、専門的な知識・技術の習得に役立ったという例は少ない。 |
|
| □3 |
希望職種の就業可能性、学校入学後の入職可能性、資格取得の効果などに関する認識は必ずしも十分ではない。 |
|
| □4 |
20歳代後半にはフリーターに限界を感じ、「焦り」も(ただし、女性には職業キャリアへのこだわりのない者も見られる)。
|
|
|
| 学校から職業への移行の仕組みに問題があるのか? |
| □1 |
大学進学・専門学校進学・就職の何れの進路を取った者でも、職業選択についての意識が不明確であったり、実際の就業の可能性について余り考えていなかった者も多い。 |
|
| □2 |
高校時代からフリーターを志望していた者には、「夢」があったタイプと、「やりたいこと」が定まらない限り進学も就職も選択しないというタイプの2つの類型がある。しかし、何れも現実的な職業キャリア形成という意味では問題を抱えている。 |
|
| □3 |
進学に偏らない進路指導、企業人の関与、詳しい職業情報、早期の段階からの進路指導などを求める声も。 |
|
|
| 求められる支援にはどのようなものがあるのか? |
| □1 |
職業意識の啓発 |
|
・小中高を通じての総合学習・職場体験による職業観の育成と職業選択能力の向上
・高校生インターンシップ等の勤労体験学習の普及等 |
|
| □2 |
職業ガイダンスの充実 |
|
・新卒者並びに既卒者を対象とした専門相談・紹介機関の増設拡充
・専門キャリアカウンセラー・業界アドバイザーの配置
・現実的具体的な職業情報の提供と生徒の適性・能力・希望進路の現実性等の評価・助言
・「フリーター就業」の具体的得失についての情報提供等 |
|
| □3 |
進学に偏らない進路指導、企業人の関与、詳しい職業情報、早期の段階からの進路指導などを求める声も。 |
|
・教育訓練制度の活用による就職促進
・就業機会情報の積極的提供による就職促進
・採用における学歴・年齢要件の緩和等 |
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|

