
| ヤマト生活情報館 |
|
| 昨今、社会問題にまでなってきている早期教育。この早期教育が日本に生まれて既に約半世紀になりますが、早期教育は今なお賛否両論で様々な意見があります。一体どちらの意見が正しいのでしょうか? 人間の基本的人格が作られる乳幼児期に行なわれる教育は人生最初で最高に重要な教育です。育児不安に悩む母親に対して、早期教育機関は子育てのマニュアルを教材という形で提供しています。でも、そのような早期教育の在り方に対して危惧の念を抱く人もいます。今月は早期教育に対する賛成者と反対者の代表的な意見を紹介し、幼児教育や早期教育のあるべき姿を考えるよすがとなるよう特集を組みました。 |
 |
| 【1】早期教育とは?〜早期教育の定義とその内容〜 |
| 【2】早期教育のメリット〜早期教育論者側の主張〜 |
| 【3】早期教育のデメリット〜早期教育反対論者の主張〜 |
| 【4】早期教育流行の背景とそのあるべき姿 |
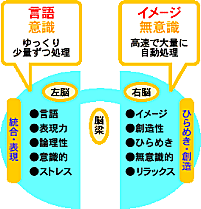
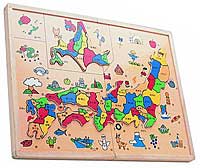 上記と深く関連して、早期教育論者は大脳生理学を理論的根拠とし、「新生児の知的能力は最高で、開発されないと早期に退化してしまう」とか「知的教育を怠れば、知的能力に乏しいぼんやり型の子どもになってしまう」、或は「詰め込み型のガリ勉教育をすると、定年後に早期に惚ける」などと主張します。そのため早期教育機関では、乳幼児の知的教育を遊び中心の右脳を使った教材で行なっているのです。
上記と深く関連して、早期教育論者は大脳生理学を理論的根拠とし、「新生児の知的能力は最高で、開発されないと早期に退化してしまう」とか「知的教育を怠れば、知的能力に乏しいぼんやり型の子どもになってしまう」、或は「詰め込み型のガリ勉教育をすると、定年後に早期に惚ける」などと主張します。そのため早期教育機関では、乳幼児の知的教育を遊び中心の右脳を使った教材で行なっているのです。
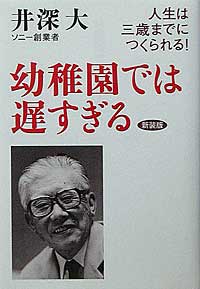
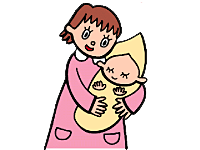
 色々な経験が必要な大切な赤ちゃんの時期に、早期教育機関の与える教材ばかりやっていてよいのかどうかを疑問視する人は多くいるでしょう。専門家によると、赤ちゃんの時というのは実はものすごく課題が多いのです。たとえば赤ちゃんは毎日のように言葉を覚えたり人間関係を学んだり、或は世の中のことを知ったりしなければなりません。その上、手の使い方や歩き方など身体の使い方まで覚えてゆかなくてはならないのです。そういった大事な時期に、現実には日常生活の中にない特殊な教材を使って特定の能力を伸ばすことは、貴重な経験のための時間をそれらの学習教材に取られてしまっていると考えることも出来ます。
色々な経験が必要な大切な赤ちゃんの時期に、早期教育機関の与える教材ばかりやっていてよいのかどうかを疑問視する人は多くいるでしょう。専門家によると、赤ちゃんの時というのは実はものすごく課題が多いのです。たとえば赤ちゃんは毎日のように言葉を覚えたり人間関係を学んだり、或は世の中のことを知ったりしなければなりません。その上、手の使い方や歩き方など身体の使い方まで覚えてゆかなくてはならないのです。そういった大事な時期に、現実には日常生活の中にない特殊な教材を使って特定の能力を伸ばすことは、貴重な経験のための時間をそれらの学習教材に取られてしまっていると考えることも出来ます。
 確かに早期教育も充分に遊びを取り入れた教材を開発しているのですが、ところが、本来の遊びと早期教育の与える遊びとではその本質が違っているのです。繰り返しになりますが、遊びは本来自発的に作り上げてゆく世界であるのに対し、早期教育の場合は準備された活動を受動的に受け入れることで成立する世界です。また、そのような環境の中で集団遊びが減ることで協同作業が苦手になる危険性もあり、協調性のない子どもに育ってゆく危険性もあるとも考えられます。
確かに早期教育も充分に遊びを取り入れた教材を開発しているのですが、ところが、本来の遊びと早期教育の与える遊びとではその本質が違っているのです。繰り返しになりますが、遊びは本来自発的に作り上げてゆく世界であるのに対し、早期教育の場合は準備された活動を受動的に受け入れることで成立する世界です。また、そのような環境の中で集団遊びが減ることで協同作業が苦手になる危険性もあり、協調性のない子どもに育ってゆく危険性もあるとも考えられます。