| 【3】メタボリック・シンドロームの予防と改善〜いま直ぐ始めよう!脱メタボ〜 |
メタボ検診によってメタボリック・シンドロームだと診断された場合、或は予備軍とされた場合、私たちはどうしたらよいのでしょうか? そういった場合は当然ながら医師による指導を受ける必要がありますが、それ以外にも私たちが心懸けるべき様々な生活改善法があります。また、メタボリック・シンドロームとは診断されなかった人でも、不衛生な生活を続けていれば、いつメタボ予備軍になるか分かりません。いま健康な人も、メタボリック・シンドロームの予防を兼ねて生活改善を試みることはとても意義のあることだと言ってよいでしょう。
本項では、食生活の改善や適度な運動などメタボリック・シンドロームの解消・改善に役立つと思える様々な「生活改善法」について、参考までに以下でなるべく詳しく取り上げ解説しました。
|
| メタボリック・シンドロームの治療と予防 |
基本的に“痛い”とか“辛い”といったいわゆる「自覚症状」に乏しいのがいわゆる生活習慣病の特徴で、当然ながらその治療は「自覚症状の緩和」ではなく、この病態を長期間・慢性的に持続させた結果として生じてくる「合併症の予防」に目標が置かれることになります。メタボリック・シンドロームの場合、動脈硬化の発生及び進展防止が治療目標となり、そのための脂肪蓄積の進行防止・解消を目的に食事療法による摂取カロリーの適正化と、また脂肪燃焼を促す目的での運動療法が基本となります。さらに食事・運動といった生活習慣の改善によって解消されない危険因子(耐糖能異常や脂質代謝異常、高血圧など)に対しては薬物療法を並行して実施する場合もあります。また、喫煙は個別の動脈硬化の危険因子であることが疫学的に証明されているので、禁煙努力も並行して行なうべきだとされています。
なお、検診・脳ドックなどで無自覚のまま動脈硬化の進展が検査などによって発見されたり、或は動脈硬化性疾患(狭心症や心筋梗塞、脳卒中など)を発症した場合は、降圧薬(※降圧効果以外にも動脈硬化進展抑止作用があるとされるアンジオテンシンII受容体拮抗薬などがよく用いられます)や、或は抗血小板剤(アスピリンなど)の投与などが検討され、またバルーンカテーテル等による血管内療法や血栓溶解療法、さらに冠動脈バイパス術のような外科的治療法が取られる場合もあります。
また、メタボリック症候群を予防するためには、肥満者の「流行」を予防することが重要視されています。
現在BMI30以上の肥満の頻度は、アメリカでは30%以上、日本では3%程度で、これは肥満が個人の生活習慣というよりも、集団レベルの生活環境によって「流行」することを示していると考えられています(※最近の研究では、肥満が社会的絆を介した「伝染病」で、異性よりも同性に「伝染」しやすいことが明らかにされているそうです)。この肥満の「流行」を防ぐためには、個人の努力のみでは困難なことから保健上の政策・制度的取り組みの必要性が生じているわけです。その中で特に高カロリー食品の規制が重要と考えられており、たとえば野菜や魚、米を中心とした日本食を見直しの機運が高まっていますが、日本国外でもこうした日本食が肥満防止に役立つために「日本食ブーム」とまでなっています。
ちなみに、肥満者は世間から自分が責められていると感じることからメタボリック・シンドローム自体を否定することがあるようですが、肥満防止として個人の努力や家族の協力、政策・制度上の取組み実行がメタボリック・シンドロームの予防に効果があると考えられています。
■News:
神奈川県立循環器呼吸器病センターで
「メタボリック症候群改善コース」が開設されました |
|
 横浜市金沢区にある神奈川県立循環器呼吸器病センターでは、「メタボリック症候群改善コース」が設けられています。これは、2泊3日の短期入院による集中的な検査及び面接と、各患者に合った減量プログラムによる月1回の外来通院でフォローする半年間のコースです。健康保険(3割負担)で3〜4万円程度の入院費で済むので、健康診断等で(内臓)肥満を指摘され、高血圧か高血糖、高脂血症の何れかに該当する方は一度受診を考えてみるのもよいのではないかと思います。 横浜市金沢区にある神奈川県立循環器呼吸器病センターでは、「メタボリック症候群改善コース」が設けられています。これは、2泊3日の短期入院による集中的な検査及び面接と、各患者に合った減量プログラムによる月1回の外来通院でフォローする半年間のコースです。健康保険(3割負担)で3〜4万円程度の入院費で済むので、健康診断等で(内臓)肥満を指摘され、高血圧か高血糖、高脂血症の何れかに該当する方は一度受診を考えてみるのもよいのではないかと思います。
申込み方法その他の具体的な内容については、下記URLをご参照下さい。 |
|
神奈川県立循環器呼吸器病センター「メタボリック症候群改善コース」:
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/byouin/junkoc/topics/060807.html |
|
|
メタボリック・シンドロームを予防・改善するには?
〜1に食事! 2に運動! しっかり禁煙! 最後にクスリ〜 |
本節では、メタボリック・シンドロームを解消・改善するための生活改善法について役立つであろう情報を簡単ながら以下にまとめて紹介しました。
| メタボリックシンドロームを予防・改善するには? |
それでは、メタボリック・シンドロームを予防・改善するには一体どうしたらよいでしょうか?
メタボリック・シンドロームの主な原因は食べ過ぎや運動不足で蓄積した内臓脂肪ですから、毎日の生活習慣を改善するという身近な方法で、まずは内臓脂肪を減らしてゆくように心懸けましょう。幸い内臓脂肪は皮下脂肪に比べて蓄積されやすく、エネルギーを消費することで解消されやすいという特徴があり、比較的減らしやすいと言われています。なお、既に高血圧や糖尿病、高脂血症(=脂質異常症)などと診断されている場合にはもちろんそれらの治療をしっかりとやってゆくことが大切になります。
|
| 食生活を改善しよう! |
脱メタボを考える上で最も効果的なのが「食生活の見直し」です。
しかし、皆さんもよくご存じの通り、通勤途中やレジャーでの外出先などでは食欲を刺激する様々な誘惑が嫌が応にも目に入ってきます。そこで、ついその誘惑に負けてしまいがちな人に考えてもらいたいのが、「1日に摂取可能なカロリーの上限を把握すること」です。
最近ではファミリーレストランのメニューやコンビニの商品でもきちんとカロリー表記されることが増えてきました。実際、カロリー表記をきちんと見ると、意外な食べ物が意外とカロリーが高かったりすることが分かります。特に下記の高カロリーの食べ物は要注意なので、それぞれの食品のカロリー値を参考までに掲げておきます。
| ■参考:代表的な食品のカロリー |
| ■寿司(100グラム当たり) |
| 1 |
大とろ 322kcal |
| 2 |
ぶり 257kcal |
| 3 |
はまち 242kcal |
|
| ■居酒屋(1人前当たり) |
| 1 |
とりの唐揚げ 305kcal |
| 2 |
ツナサラダ 253kcal |
| 3 |
肉じゃが 241kcal |
|
| ■そば・うどん(1人前当たり) |
| 1 |
鍋焼きうどん 625kcal |
| 2 |
きつねそば 479kcal |
| 3 |
肉南蛮そば 443kcal |
|
| ■定食(1人前当たり) |
| 1 |
ハンバーグ定食 944kcal |
| 2 |
コロッケ定食 886kcal |
| 3 |
とんかつ定食 851kcal |
|
| ■中華(1人前当たり) |
| 1 |
ラーメン 863kcal |
| 2 |
タンメン 763kcal |
| 3 |
春巻 535kcal |
|
| ■アルコール(100グラム当たり) |
| 1 |
ラム 262kcal |
| 2 |
ウィスキー 250kcal |
| 3 |
ブランデー 250kcal |
|
|
| 基礎代謝を把握しよう! |
カロリー計算の上限を把握するには「基礎代謝」を知る必要があります。基礎代謝とは簡単に言うと「何もしなくても消費するカロリー」のことで、たとえば心臓が血液を送ったり発汗したりするために必要なエネルギーのことを言います。基礎代謝は自分の性別と年齢・体重から測定可能ですが、10代を境に徐々に減少してゆく傾向にあります。なお、この基礎代謝を0.6で割ることで「1日に摂取可能なカロリー」の目安が出てきます。
|
男性 |
女性
(※妊婦、授乳婦を除く) |
| 年齢 |
基礎代謝
基準値
(kcal/kg/日) |
基準体重
(kg) |
基準体重での基礎代謝量
(kcal/日) |
基礎代謝
基準値
(kcal/kg/日) |
基準体重
(kg) |
基準体重での基礎代謝量
(kcal/日) |
| 1〜2 |
61.0 |
11.9 |
730 |
59.7 |
11.0 |
660 |
| 3〜5 |
54.8 |
16.7 |
920 |
52.2 |
16.0 |
840 |
| 6〜7 |
44.3 |
23.0 |
1,020 |
41.9 |
21.6 |
910 |
| 8〜9 |
40.8 |
28.0 |
1,140 |
38.3 |
27.2 |
1,040 |
| 10〜11 |
37.4 |
35.5 |
1,330 |
34.8 |
35.7 |
1,240 |
| 12〜14 |
31.0 |
50.0 |
1,550 |
29.6 |
45.6 |
1,350 |
| 15〜17 |
27.0 |
58.3 |
1,570 |
25.3 |
50.0 |
1,270 |
| 18〜29 |
24.0 |
63.5 |
1,520 |
23.6 |
50.0 |
1,180 |
| 30〜49 |
22.3 |
68.0 |
1,520 |
21.7 |
52.7 |
1,140 |
| 50〜69 |
21.5 |
64.0 |
1,380 |
20.7 |
53.2 |
1,100 |
| 70〜 |
21.5 |
57.2 |
1,230 |
20.7 |
49.7 |
1,030 |
|
|
| 1日に必要なカロリーを知ろう |
| ■1日に必要なカロリーの算定法 |
|
|
|
たとえば
- 30歳 68kgの男性の場合 ⇒基礎代謝量1520kcal÷0.6=2530kca
- 30歳 53kgの女性の場合 ⇒基礎代謝量1140kcal÷0.6=1900kcal
|
|
| ■適正体重1Kg当たり 1日に必要なエネルギー量の目安 |
| ●デスクワーク中心の人 |
25〜30 Kcal |
| ●立ち仕事や外回りが多い人 |
30〜35 Kcal |
| ●身体をよく動かす仕事の人 |
35〜40 Kcal |
|
| ■1日の必要なエネルギー量(kcal) |
| 身長 |
適正体重 |
1日の必要なエネルギー量(kcal) |
| 25(kcal/kg) |
30(kcal/kg) |
35(kcal/kg) |
40(kcal/kg) |
| 1.8m |
約71Kg |
1,775 |
2,130 |
2,485 |
2,840 |
| 1.7m |
約64Kg |
1,600 |
1,920 |
2,240 |
2,560 |
| 1.6m |
約56Kg |
1,400 |
1,680 |
1,960 |
2,240 |
| 1.5m |
約50Kg |
1,250 |
1,500 |
1,750 |
2,000 |
|
|
|
| 参考5:メタボの予防・解消とダイエットとの違い |
メタボの予防・解消と言うと、「つまりはダイエットの薦めだな、要はダイエットをすればよいのだな」と考えられる人が多分殆どでしょう。確かに肥満の解消という意味ではダイエットとの共通点も多いのですが、メタボリック・シンドロームの場合は、一般のダイエットとは違って「内臓脂肪を落とすこと」がポイントになってきます。
今まで様々なダイエット法に挑戦しては失敗してきた人もいるでしょう。そのため、ダイエットを諦めてしまった人もいるかも知れません。でも、メタボの予防・解消を簡単に諦めないで下さい。皮下脂肪と違って内臓脂肪は意外に早く落とすことができますし、見た目は太っている場合でも内臓脂肪量は大したことないということもあるからです。とにかく、騙されたと思って挑戦してみて下さい。きっと検査結果にもハッキリと努力の効果が表われてくるでしょう。
|
| 参考6:気をつけるべきこと〜食事と運動をバランスよく!〜 |
メタボリック・シンドロームを解消・改善するための生活改善法で却って健康を害しては意味がありません。本節では、生活改善法を実行する上で気をつけるべき事柄を参考までに以下で幾つか取り上げ解説しました。
| 食事だけでダメ 運動だけではムリ |
内蔵脂肪を減らすには、(A)「運動によるエネルギー消費」と、(B)「食事減による摂取エネルギー抑制」の両方をバランス良く実行してゆくとよいでしょう。
運動や日常生活の活動量を増加させれば消費カロリーが増えるのだから、体重が減るのは当然だと考えるのは早計です。人間は因果な生き物で、気持ちよく運動をすればお腹が空き、その分食べてしまうものです。結局、“運動を頑張ったはよいが、体重は余り減らなかった”という話しはよく聞きます。従ってメタボリック・シンドローム改善のためには、運動だけでなく食生活の改善が不可欠です。運動ばかりでは疲れて挫折してしまいますし、また、食事のみの減量では必要な栄養素を取り損ね、筋肉量が減少して、結局リバウンドの可能性を却って高めてしまいます。「食事だけではダメ、運動だけではムリ」ということをしっかり頭に入れて、無理せず時間をかけて行ないましょう。
|
| 気をつけなければいけない食事 |
1人暮らしの人や外食の多い人は、ついつい自分の好きなものばかり食べてしまいがちですが、その中でも特に控えた方がよい食事があります。それは、たとえばラーメンやハンバーガーなどのいわゆるファーストフードです。これらは塩分量も多く、ものによっては脂肪分もたっぷり入っています。また、ラーメンと御飯類、チャーハンやライスを一緒に食べると、麺の炭水化物と、御飯の炭水化物でダブルになってしまいます。カップラーメンに至っては、厚労省の指針である1日の塩分摂取量10g以下をこれだけで摂ってしまうことになります。また、ハンバーガーは高カロリーの上に、揚げ物のポテトや、ジュースとのセットで食べることによってさらに摂取カロリーが多くなってしまいます。このような訳で、これらの食品の摂取には今後くれぐれも注意しましょう。
|
| 激しい運動はダメ! |
激しい運動をすれば、その分、痩せられると思うかも知れませんが、意外なことに必ずしもそうとは限らないのです。確かに軽い運動ではエネルギー源として糖質と脂質の両方が使われ、消費することができますが、これに対して激しい運動では糖質の消費ばかりが高くなり、余り脂質の消費にはならないのです。もちろん軽い運動ならば短い時間の運動でも脂質の消費につながるので、激しい運動よりも軽い運動を続けることが大事です。
|
|
| 参考7:メタボリック・シンドローム対策にデンタルケアが重要!?〜〜 |
従来、歯周病は歯周病菌によって惹き起こされる口内の感染症の1つで、従来は生活習慣病とは別に考えられてきましたが、ここ数年の研究の結果、主に次のような理由から歯周病をメタボリック・シンドロームの1つとして捉える専門家が増えてきました。
本節では、そのことも含め、参考までに歯周病について以下で簡単に取り上げ解説しました。
| 歯周病はメタボリック・シンドローム? |
歯周病の原因は歯と歯ぐきの隙間などに溜まった歯周病菌ですが、この歯周病菌が出す毒素が体内に入ると、糖尿病や肝臓病、動脈硬化など生活習慣病のリスクが高まるということが最近の研究で分かってきました。事実、心筋梗塞の患部から歯周病菌が発見されてもいるのです。歯周病の状態を続けるということは、まさに口内を常に毒の巣窟にし、炎症状態を放置するということに他なりません。
最近メタボリック・シンドロームが歯周病とも関係の深い病気であることが分かってきました。メタボリックシンドローム対策としてのデンタルケアの重要性がいま歯科医によって指摘されています。
| □1: |
喫煙や食生活、ストレス、歯磨き(方法や時間)など生活習慣と関係が深い |
|
| □2: |
太っている人ほど歯周病になりやすい
(※肥満の人は3.4倍、重度肥満の人は8.6倍) |
|
| □3: |
歯周病や動脈硬化などの生活習慣病との合併率が高い
(※歯周病の人は生活習慣病になりやすく、また、生活習慣病があると歯周病になりやすい) |
|
|
| 参考:歯周病と関係の深い病気 |
歯周病は酸素を嫌う嫌気性菌の1つです。そのため、菌は歯と歯ぐきの間など空気に触れないところに住み着き、奥へ奥へと入りこんでゆきます。嫌気性菌の特徴は毒性が強いこと、そして、強烈な匂いを出すことなどです。そして、この歯周病菌が悪さをすると、免疫系の白血球(マクロファージ)がそれを食べて処理しますが、その際TNF-αという悪玉サイトカイン(生理活性物質)が放出されます。この悪玉サイトカインが様々な病気を惹き起こしたり悪化させる要因となるのです。
| ■歯周病と関係の深い病気 |
| ● |
糖尿病 |
|
歯周病と糖尿病の合併率は80%以上にもなります。そのため、歯周病は糖尿病の6番目の合併症とまで言われているほどなのです。
歯周病が進み口内で慢性的に炎症が起こるようになると、常に大量の悪玉サイトカインが分泌されている状態になります。悪玉サイトカインは血糖値を調整するインスリンの働きを妨げ、その結果、糖尿病を発症させたり悪化させることにつながってゆきます。一方、糖尿病に罹っている人は、口内の糖分の量が増え、逆に唾液の量が減り免疫力が低下してしまうため、口内が歯周病菌の増殖しやすい環境になってしまいます。糖尿病と歯周病が併発すると、相互に悪影響を与え合い、症状はどんどん悪くなってしまうという悪循環に陥ります。 |
|
| ● |
腎臓病 |
|
口内は血管が密集していて菌が血管に入りやすくなっているのですが、歯周病で炎症・出血があると、菌も多い上に傷口も開いているということになるので、そのリスクは一層高まります。
血管内に進入した細菌は腎臓によって濾過されますが、その時に産生される悪玉サイトカインは腎機能を低下させてしまいます。ちなみに、慢性腎臓病の発症率は歯周病の重症度に応じて3〜5倍に増加するとも言われています。 |
|
| ● |
胃潰瘍・胃癌 |
|
胃潰瘍や胃癌を惹き起こすとされるピロリ菌は歯垢の中からも発見されています。歯周病になっていると、口の中がピロリ菌の温床となり、それがそのまま胃に入ると、胃潰瘍や胃癌のリスクを高めてしまうのです。 |
|
| ● |
動脈硬化(脳・心臓血管疾患など) |
|
歯周病が重症化すると、歯周組織だけではなく血管まで慢性的に炎症状態になります。そして、炎症のある箇所では炎症性の悪玉サイトカインが発生し、動脈を硬化させてしまいます。事実、心筋梗塞などの動脈硬化層から歯周病菌が発見されたという例も報告されているそうです。
動脈硬化は高血圧とも密接に関連し、生活習慣病として括られる多くの病気の引き金ともなる極めて危険性の高い病気です。動脈硬化が脳血管で起きれば脳梗塞、心臓血管で起きれば心筋梗塞と言うように、文字通り生命に関わるような深刻な病気にもつながってゆきます。 |
|
| ● |
骨粗鬆症 |
|
閉経前後の女性の歯周病患者対象の調査では、骨粗鬆症と歯周病は歩調を合わせるように同時に重症化するということが確認されています。 |
|
| ● |
肥満 |
|
肥満と歯周病は一見無関係のように思えますが、実は肥満の人ほど歯周病を発症しやすいという報告があります。事実、内臓脂肪に過剰に溜まっている脂肪組織は、歯周病に起因して分泌される悪玉サイトカインと同じ物質を放出しているのです。肥満はメタボリック・シンドロームの最大の要因として警戒されていますが、これに糖尿病と歯周病が重なると、その危険性は足し算ではなく掛け算的に増大します。 |
|
| ● |
早産 |
|
歯周病による炎症に起因して放出される悪玉サイトカインは子宮筋の収縮を引き起こすということが報告されています。その結果、低体重児早産のリスクも高まります。 |
|
|
|
| 参考8:社内で簡単に始められる8つの運動 |
ダイエットのために絶食して2kg痩せた、1週間毎日サウナに入って3kg痩せたといったことで一喜一憂する人がいますが、無理なダイエットは健康被害をもたらす可能性もあります。もちろん基礎代謝を向上させるためには運動をするのが一番なのですが、中々時間が取れないという方も多いと思います。そこで本節では、オフィスの椅子周りでできる運動やストレッチを参考までに以下で紹介します。
| ■1: |
足上げストレッチ |
|
椅子に座った状態で両足を宙に浮かし、つま先を天井に向けます。そのままの状態で1〜3秒間くらい維持します。 |
|
| ■2: |
座りスクワット |
|
椅子に座った状態で足を抱え込むように屈み込み、足首又は地面に手を付けます。何度か繰り返すことで腹筋に刺激を与えるようにします。 |
|
| ■3: |
背もたれストレッチ |
|
椅子に座った状態で背もたれの上に腕を乗せてぐっと後ろに反り返ります。片腕ずつ交互にやるのがよいでしょう。 |
|
| ■4: |
座り腹筋 |
|
椅子に座った状態でお臍の下付近を覗き込むようにします。余裕があれば片足を交互に上げてみましょう。 |
|
| ■5: |
手首プラプラ |
|
手首をぷらぷらさせてみましょう。手首だけでなく肩も合わせてぷらぷらしてみましょう。8つの運動の中で1番簡単な運動です。 |
|
| ■6: |
両手ストレッチ |
|
片手の手首をもう一方の手で持ち、そのまま上に持ち上げます。身体を横に傾けるのもよいでしょう。 |
|
| ■7: |
数え指 |
|
片手もしくは両手の指で数字を数えるように順に開いて閉じるようにします。開く指はしっかり広げるのがコツです。 |
|
| ■8: |
首ぐるぐる |
|
首を縦横自由に動かします。最後にぐるっと何周かさせてみましょう。なお、勢いよく動かしたり後ろに反ると、首に過度な負担がかかることがあるので注意が必要です。 |
|
|
| 参考9:生活習慣改善のためのアドバイス |
本項の最後に当たって、メタボリック・シンドロームとは多少離れて、生活習慣病克服のためにも役立つであろう「生活改善法」を、(1)「食事編」、(2)「運動編」、(3)「生活全般編」の3つに取りあえず分類して、参考までに本節では詳しい解説なしで以下に列記して紹介しました。
| 1)食事編 |
| ● |
鍋料理で野菜をたくさん摂りましょう |
| ● |
丼物にはサイドメニュー(副菜)を追加しましょう |
| ● |
調理方法でカロリーを減らしましょう |
| ● |
青魚で悪玉コレステロールを下げましょう |
| ● |
食事のリズムを整えましょう |
| ● |
脂を使った料理は1食1品にしましょう |
| ● |
麺類は汁を残しましょう |
| ● |
イモ類で塩分を身体の外に出しましょう |
| ● |
玄米やライ麦パンを食べましょう |
| ● |
汁物は具だくさんにしましょう |
| ● |
手計りで野菜の量を計りましょう |
| ● |
蛋白質は血管を丈夫にするので、積極的に摂取しましょう |
| ● |
悪玉コレステロールを作らない |
| ● |
歯応えのある料理をよく噛んで食べましょう |
| ● |
サラダのドレッシングは別にもらいましょう |
| ● |
バイキング形式の食事には気をつけましょう |
| ● |
醤油は“かける”から“つける”へ |
| ● |
コンビニ食もバランスよく |
| ● |
濃い味の料理は1品で我慢する |
| ● |
小鉢のオカズは油を使わずに |
| ● |
隠れた油に注意しましょう |
| ● |
大豆を上手に摂りましょう |
| ● |
炭水化物のコントロールは甘いものから |
| ● |
玄米で食物繊維を摂りましょう |
| ● |
夜遅い時間の食事には気をつけましょう |
| ● |
食べる野菜の種類を多くしましょう |
| ● |
お昼のサービス・メニューに注意しましょう |
| ● |
揚げ物の衣はなるべく薄くしましょう |
| ● |
朝食を摂る習慣を作りましょう |
| ● |
野菜やキノコを先に食べましょう |
| ● |
野菜不足はジュースで補いましょう |
| ● |
食材選びで炭水化物をコントロールしましょう |
| ● |
お肉を食べる時は部位に注意しましょう |
| ● |
料理は小皿に盛り付けましょう |
| ● |
無理せず減塩を実現しましょう |
| ● |
野菜は茹でて、リンゴは皮ごと食べましょう |
| ● |
お酒の肴に注意しましょう |
| ● |
魚でコレステロールを抑えましょう |
| ● |
食べたい欲求をコントロールしましょう |
| ● |
栄養素のバランスを考えましょう |
| ● |
薄味に慣れましょう |
| ● |
単品よりも定食を目指して |
| ● |
食事は1日3食時間を決めて |
| ● |
食事はゆっくり食べましょう |
| ● |
自分に合った摂取エネルギーを考慮しましょう |
| ● |
料理の品数や皿数を増やしてみましょう |
|
|
| 2)運動編 |
| ● |
肥満防止のポイントは基礎代謝の維持なので、筋力をしっかり使う運動を心懸けましょう |
| ● |
積極的に階段を利用しよう |
| ● |
エレベーターやエスカレーターの使用を我慢しましょう |
| ● |
満員電車でこっそり筋トレをしましょう |
| ● |
電車内で筋肉をほぐして頭をスッキリさせましょう |
| ● |
ランチタイムは遠めのレストランを選ぶようにしましょう |
| ● |
バスの停留所は1つ手前で降りて歩きましょう |
|
|
| 2)生活全般編 |
| ● |
飲酒日記をつけましょう |
| ● |
節酒スタート前には準備期間を設けましょう |
| ● |
節酒仲間を作ってチャレンジしましょう |
| ● |
節酒のご褒美を考えましょう |
| ● |
お酒を断る「一言」を用意しましょう |
| ● |
お酒の席では会話を楽しみましょう |
| ● |
お酒はゆっくりチビチビやりましょう |
| ● |
強いお酒は薄めましょう |
| ● |
酒の肴は蛋白質が多い料理を取り入れましょう |
| ● |
お酒に近づかないのもひとつの方法です |
| ● |
タバコにかかるお金を計算してみましょう |
| ● |
「吸ったら勿体ない」で禁煙を成功させましょう |
| ● |
「禁煙」貼り紙をつくりましょう |
| ● |
タバコを吸わない人の隣りに座りましょう |
| ● |
小さな成功で「禁煙」への自信をつけましょう |
| ● |
タバコを吸いたい気持ちをどこかへ逸らしましょう |
| ● |
禁煙チャレンジ直後のイライラは落書きで解消しましょう |
| ● |
干し昆布で禁煙しましょう |
| ● |
喫煙できない環境を整えましょう |
| ● |
禁煙開始後1週間は早めの帰宅を心懸けましょう |
| ● |
禁煙中は腹八分目を徹底しましょう |
| ● |
禁煙成功でも油断は禁物、さらに気持ちを引き締めましょう |
| ● |
行動パターン変えることで禁煙しましょう |
| ● |
禁煙の伝道師になりましょう |
| ● |
壁を使って猫背を解消しましょう |
| ● |
朝の一番の“伸び”をしましょう |
| ● |
起きる時間をいつも同じにしましょう |
| ● |
朝起きたら、まず外の光を浴びましょう |
| ● |
室温調整で快眠を心懸けましょう |
| ● |
眠くなったら布団に入りましょう |
| ● |
寝る前4時間はカフェインを避けましょう |
| ● |
眠りが浅いなら、あえて遅寝・早起きをしてみましょう |
| ● |
15分の仮眠で午後もスッキリします。積極的に昼寝を取り入れましょう |
| ● |
睡眠時間は多くても少なくてもダメ、適切な睡眠時間を取るように心懸けましょう |
| ● |
ぬるめのお風呂で新陳代謝を高めましょう |
| ● |
身体をたくさん動かして楽しいお食事をいただきましょう |
| ● |
歯磨き剤は最後に使いましょう |
| ● |
深呼吸でリラックスしましょう |
| ● |
日常を離れた旅行でリラックスしましょう |
| ● |
1日30分、自分だけの時間を見つけましょう |
|
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|
| 【4】メタボリック・シンドロームそのものへの異義〜メタボ検診の利点と欠点〜 |
メタボリック・シンドロームの恐ろしさや、またメタボ検診の意義については上で解説した通りですが、実はそのメタボ検診の内容やその義務化について従来より様々な異論が提出されてきました。そればかりか、専門家によってはメタボリック・シンドロームの病態そのものについてすら疑問視する人が少なからず存在するのです。
多少難しい議論も一部にはありますが、本項では、それらメタボリック・シンドロームに関する異論や、メタボ検診の利点と欠点について、また、流行語になった感すらある「メタボ」が世間に与える影響について、以下でなるべく詳しく取り上げ解説しました。
|
| メタボリック・シンドロームの病態に対する異論 |
| ■メタボリックシンドロームに対する代表的な異論 |
| ● |
診断基準が曖昧で不完全。基準値の根拠がきちんと説明されていない |
|
|
|
| ● |
インシュリン抵抗性が共通の原因かどうか不確かである |
|
| ● |
他の心血管危険因子を含むか除外するかの明確な根拠がない |
|
| ● |
心血管疾患の危険度は含まれる個別の危険因子によって様々である |
|
| ● |
心血管疾患の危険度は各危険因子の総和以上ではないと考えられる |
|
|
|
|
|
メタボリック・シンドロームは世界ではインシュリン抵抗性を基礎とした病態と考えられていますが、日本では現在、「蓄積された内臓脂肪組織は様々なサイトカイン(内分泌因子)を分泌し、その中のアディポネクチンやレプチン、TNF-α、ビスファチンなどの遺伝子発現レベルでの産生異常が代謝異常を惹き起こし、動脈硬化などに繋がると考えられ、内臓脂肪面積の測定によってこの病態が把握できる」とする大阪大学医学部チームの学説が、メタボの概念として厚生労働省によって特定健診という形で法的に国民に強要されています。内臓脂肪の細胞レベルの性質と個体レベルの内臓脂肪面積との間には大きなギャップがあるにも拘らず、これを短絡的に直結したのは問題と言わざるを得ないとして、一部の人たちから懸念が表明されています。
何れにせよ、この疾患の概念や診断基準については日本国内でもこの学説に異議を唱える動きも出てきており、また実際にWHOやIDFなどの機関毎、或は国毎に大きく異なる部分があるのです。さらに05年にアメリカとヨーロッパの糖尿病病学会は「メタボ診断をしてはならない」とする共同声明を発表するなど、とにかくメタボリック・シンドロームに対する世界的に統一された概念は現時点では未確定で、議論が続けられている段階なのです。
そのような実情にも拘らず、日本医師会は生涯教育シリーズ『メタボリック・シンドローム』において、これが心血管疾患のリスクを35.8倍にするようなイラストを掲載しています。ところが、それに対して世界のこれまでの疫学データのメタ・アナリシスでは心血管疾患のリスクは平均1.74倍と報告されています。事実、日本の疫学研究では、日本肥満学会の診断基準によるメタボリック・シンドロームは男性では心血管疾患の相対危険度が1.4倍で、統計学的に有意なリスクにならないことが一部の研究者によって指摘されてもいるのです。
肥満とインシュリン抵抗性の間に炎症(TNFα)が介在することが93年に突き止められ、また、最近の色々な遺伝子操作による動物実験では、身体計測上の肥満や内臓脂肪ではなく、脂肪細胞の肥大化・壊死とそれを冠状に取り囲むマクロファージ(=炎症性細胞)の集積が炎症とインシュリン抵抗性をもたらし、これがメタボリック・シンドロームの病態の基礎となっている可能性が次第に明らかにされてきています。また、内臓肥満や超肥満でも脂肪組織の組織像が正常でメタボリック・シンドロームの病態を伴わない動物モデルや、逆に肥満も内臓肥満もないのに脂肪組織の組織像が脂肪細胞の肥大化・壊死とそれを冠状に取り囲むマクロファージの集積という肥満症の所見を呈してメタボリック・シンドロームの病態を伴う動物モデルが報告されてきてもいます。実際に06年には、肥満も内臓肥満も脂肪細胞の肥大化もないのに脂肪組織の組織像にマクロファージの集積が見られ、メタボリック・シンドロームの病態を呈する動物モデルが日本の2つの異なる研究グループによって報告されました。また、07年には、マウスの脂肪酸延長酵素を欠損させることで、脂肪蓄積があっても耐糖能異常を来しにくい動物モデルを筑波大学のグループによって報告されました。また最近、内臓脂肪だけに炎症が生じてメタボの病態を呈する正に「内臓脂肪症候群」とも言うべき動物モデルが報告されましたが、驚くべきことに、このモデルでは内臓肥満は認めず、皮下脂肪と肝臓の脂肪増加が認められたのです。さらに最近の高脂肪食によるマウスの研究では、メタボリック・シンドロームの病態の進行の途中で内臓脂肪は増加から減少に転じたとも言います。
従って、内臓脂肪面積を測定すれば内臓脂肪の病的状態が把握できるとか、或は皮下脂肪は内臓脂肪の悪影響を抑制するとかといういわゆる「メタボリックシンドローム(=内臓脂肪症候群)」なる学説は、短絡的であると批判せざるを得ないと一部の研究者によって指摘されるわけです。
とにかく脂肪病またはメタボリック・シンドロームの本質は、肥満とか腹部肥満とか内臓肥満といった見かけ上の問題ではなく、過剰なエネルギーによる脂肪組織の炎症であるというデータが集積されてきており、長鎖脂肪酸とセラマイドの種類と濃度がこの炎症と関係しているらしいというデータも出てきていて、今後も多方面からの研究による解明が期待されているのが実情です。
|
| メタボ検診の利点と欠点 |
本節では、メタボ検診の利点と欠点、またその有効な利用法について、そして、メタボ検診義務化の孕む問題点について、以下で取り上げ解説しました。
| メタボ検診の利点 |
08年4月から始まったメタボ検診ですが、実施される前からその必要性については到る所で議論されてきました。実際にメタボ検診を行なうことで国民にとって本当にプラスになるかというと、そうだと必ずしも断言できるわけではありません。それというのも、まだ実施されてまだ余り日時が経っていないので、これといった問題点がハッキリと現われていないのです。何事も実際にやってみて初めて出てくる問題点は確実にあるので、今後それを政府がどう対応するかによって、メタボ検診のトータル的な価値が漸く分かってくるのです。
従って、今の時点で考えられるメタボ検診の利点は、上でも若干触れましたが、メタボ検診が医療界にとって有益であるということでしょうか。検診の義務化によって安定した検診料が得られますし、また、国の補助も大きくなります。さらに、これまでは放置しておいたメタボリック・シンドローム予備軍がこぞって医療機関のお世話になることは間違いなく、その利益も充分に期待できるでしょう。
それでは、国民にとってはどうなのでしょうか?
メタボ検診で国民が得られる利点は、自分自身でも気がついていなかったメタボリック・シンドロームや生活習慣病の予兆に気がつくことが出来るという点が最初に挙げられます。次に血糖値やコレステロール値などは日頃会社勤めをしているサラリーマンなどにとっては滅多にお目にかかれる数字ではないので、こういった検査機会が設けられるのことはやはり利点と言ってよいでしょう。(もっとももう既に自覚していながら改善の意思がない人にとってはそれほどよいこととは言えな無いかも知れません。また、そういう人に対しての対処法についても、どうやってゆくのかはまだ不透明です。)
とにかく、メタボ検診の利点は今後徐々に作ってゆくことになるというのが実状で、今後メタボ検診を義務化してよかったという声が増えてゆくことが当面の政府及び医療界の目標ということになるのではないでしょうか。
|
| メタボ検診の効果的な利用法 |
メタボ検診の義務化によって、自らの体型にルーズな認識だった人達にはひとつの転機を迎えることになります。やはり、これまで目を逸らして来た部分が1つの社会的ステータスとして見なされてしまうとなると、どうしても目を逸らすわけにはゆかなるでしょう。そういう意味では、メタボ検診の義務化はダイエットにとって非常に有効だと言ってよいかも知れません。
メタボ検診が義務化されたことで、これまでの普段の生活習慣を見直す人が増加しています。実際、ダイエット食品等のダイエット効果をもたらす製品も市場によりたくさん出回わるようになり、ダイエットに効果的な流れができつつあります。この流れは、もしかすると今ふくよかな体型の人にとっては苦痛かもしれません。これまでは個性として見なされてきたものが、今後は、社会的に劣る、悪であるなどという誤解を受けかねない様子が窺われるのがその理由です。太っていることが悪いことだと見なされてしまう、というような不安に駆られている人も中にはいるかも知れません。けれども、逆に「自らの体型と普段の生活習慣を見直すよいチャンスだ」と考えてみてはどうでしょうか。
もちろん太っていることそのものは決して恥ではないです。ただし、それに伴って生活習慣病、そしてメタボリック・シンドロームという恐ろしい病に罹る恐れがあるようならば、それは改善しなくてはなりません。
太っているように見えても、それらの病気には何ら縁のない人もいます。そういう太り方も存在します。それをしっかり確認するよいチャンスだと思ったらよいのです。たとえば、これまでは太っているというだけでメタボだと言われていた人は、今回のメタボ検診によって「太っていても健康」というステータスを得ることが出来るかも知れません。これは非常にポジティブなことだと言ってよいのではないでしょうか。
とにかく、折角のチャンスなのだから、それを有効に活用してみることをオススメします。
|
| メタボ検診義務化がもたらすデメリット |
メタボ検診の義務化によって、メタボリック・シンドロームに対する議論が最近活発に為されています。また、様々な医療問題から現在の医療そのものに対しても議論も活発に為されるようになっています。特に近年では、インターネット上に自らの意見を活発に書くことができる掲示板やブログがあるため、その意見は千差万別で、とても活発な意見交換が日々行なわれています。その中にあって、メタボ検診の義務化に関しても当然ながらかなり話題となっているわけです。そして、そのメタボ検診義務化に対しても、肯定的・否定的な意見が双方の立場の人たちによって積極的に表明されているのですが、ただ、どちらかと言うと否定的な意見が多いように見受けられます。
なお、まずここで注意しておきますが、メタボ検診そのものは必ずしも悪いものではありません。メタボ検診そのものも、実際はそれほど時間や料金がかかるわけではなく、深刻な病気に発展する以前にそれを未然に食い止めることが可能なので、病気の予防策としても、欠点よりは利点の方が多く、非常に有意義なものがあるのです。何れにしても、メタボリック・シンドロームからは様々な生活習慣病やいわゆる成人病が発症しやすくなりますので、これを未然に食い止めることができるというのは逆にメリットの方が多いと言ってよいでしょう。
では、メタボ検診の一体何が問題にされているのでしょうか?
問題は、メタボ検診がいくら病気の予防に有意義だからと言って、それをを義務化した点にあるのです。すなわち、メタボ検診を義務化したことで、国民は確実に検診を受けることになります。義務化は強制を意味しますが、それは同時に検診料や指導を受ける時の治療費、また病院へ通う時に発生する交通費も当然ながら個人負担になります。このように、メタボ検診の義務化によって国民はほぼ確実に何らかの形でお金を使うことになるわけですが、それは今まではなかった新たな出費で、当然ながら多少ながら家計を圧迫することは否定できません。長引く不況と100年に1度と言われる金融危機の中、こういった負担を強いられること自体に庶民は抵抗感を抱き、今ひとつ納得が出来ないという人は決して少なくないのでしょう。
もちろんメタボ検診の義務化することで発生する欠点は他にもあります。それは環境の整備です。現在の医療体制では、必ずしも全国各地どの医療機関でもメタボ検診が行なえるというわけにはゆきません。多少遠方の病院へゆく人も出て来ますし、そのための交通費は個人の負担になります。従って迅速な環境整備が早急に必要とされれいるのですが、当然ながらこれにも相当な費用がかかります。
恐らくメタボ検診が実施されて月日が経てば、ここで挙げた以上に欠点と言われるものも増加してゆくことでしょう。そして、政府や医療機関がそれらに対して今後どういった対処を行なってゆくのか、その動向に注目が集まることは間違いないでしょう。ただ何れにせよ、上でも述べた通りメタボ検診そのものは意味のあることなので、これを上手に活かしながら自分自身の健康管理をしてゆくことも賢明な対応のひとつと言ってよいでしょう。
|
| メタボリック症候群の診断基準検討委員会の問題点 |
| ■日本のメタボリック・シンドローム診断基準の問題点 |
| ● |
メタボリック・シンドローム(内臓脂肪症候群)は必ずしも科学的に確立された概念ではない |
|
| ● |
日本肥満学会(JASSO)が腹囲基準値を決めた方法は論理的に矛盾している |
|
| ● |
腹囲85cmを基準に診断された男性のメタボリック・シンドロームは必ずしも心血管疾患発症の有意なリスクとはならない |
|
| ● |
腹囲90cmを基準に診断された女性のメタボリック・シンドロームは多くの高リスクの女性を見逃すことになる |
|
| ● |
肥満をメタボリック・シンドロームの必須条件とすると、心血管疾患リスクの高い多くの人を無視することになる |
|
| ● |
メタボリック・シンドロームの診断は元々困難である |
|
| ● |
日本の診断基準はメタボリック・シンドロームの国際比較研究の障害となる |
|
| ● |
内臓脂肪面積の臨床的有用性が確立していないにも拘らず、メタボリック・シンドローム診断基準検討委員会がCT等による内臓脂肪面積の測定を研究目的以外でこれを奨励したことは倫理的にも問題である |
|
現在、日本においてメタボリック・シンドロームの診断基準とされているものは、日本動脈硬化学会や日本肥満学会、日本糖尿病学会などの7学会から選出された14人の委員で構成された「メタボリック・シンドローム診断基準検討委員会」が、日本肥満学会の提案した「内臓脂肪症候群」を約1年間かけて検討して承認し、05年4月8日に日本内科学会総会で発表されたものです。内臓肥満を必須項目とし、その基準は臍レベル腹部断面での内臓脂肪面積100cm2以上とされました。ただ、内臓脂肪面積を直接測定することは健康診断や日常臨床の場では容易ではないため、腹囲の測定によりこれを代用し、男性85cm以上、女性90cm以上を内臓脂肪型肥満と診断されます。しかし、できれば腹部CT撮影等により内臓脂肪面積を精密に測定することが望ましいとされました。
ただし、内臓脂肪面積の基準値を男女混合で決めて、そこから男女別に腹囲基準値を決めたのは論理的に誤りで、そのため、その後の内臓脂肪面積も腹囲も一貫して男女別に検討した複数の研究では全く異なる数値が提唱されています(※たとえばNTT・京都大学グループの研究では、内臓脂肪面積の最適基準値は男性100平方cm、女性65平方cmとなっています)。事実、各方面から日本肥満学会に対してこの基準を撤回することが求められていいるのですが、しかしながら結局、07年10月19日、日本肥満学会はそれら多くのエビデンスを無視して腹囲基準値を修正しないと発表しました。
とにかく、内臓脂肪面積の測定はその臨床的有用性が確立していないので、患者にその旨を説明し、放射線を浴びせることと費用がかかることへの同意を得た上で、あくまで研究目的で施行すべき検査であると考えられます。ところが、目下メタボリック・シンドローム診断基準検討委員会の「CT撮影等により内臓脂肪面積を測定することが望ましい」とした勧告を受けて、臨床レベルでの内臓脂肪面積測定が全国で横行しているのです。従って、メタボリック・シンドローム診断基準検討委員会とそれに迎合した厚生労働省の倫理的責任は重大で、看過できないという意見も一部には見られます。
また、それ以外にも、放射線を浴びせて内臓脂肪面積を測定することの臨床的有用性を検証したデータが皆無であるにも拘わらず、経済産業省と大阪大学グループとN2システム株式会社が産官学共同で内臓脂肪面積計算ソフトを全国の病院に販売して、07年9月現在既に5億1,600万円の売上げを上げており、厚生労働省の特定保健指導がこのメタボ商法を支援する構図となっていることも問題と言ってよいでしょう。
|
|
| メタボ検診義務化がダイエット市場に与えた影響と今後の予想 |
08年4月より義務化されたメタボ検診ですが、実はダイエット商品の市場にこの制度の導入が大変大きな影響を与えました。今後も益々影響を与えるでことしょう。
メタボ検診が義務化されたことで、自分が肥満体質であることを容易に知ることができるようになりました。そして、メタボ検診によって「要指導」との結果判断が下されれば、誰でも多少はそれを恥ずかしく思うはずです。或はそれによって健康不安を懐く人もいるでしょう。当然、今までやってきたような、お笑いのように笑い飛ばすことは段々できなくなってくると思います。こういったことを予測して、メタボ検診の義務化が制度導入されて以来、ダイエット食品を始めとしたダイエット商品の開発販売に各企業が力を注ぎ始めてているのです。
今までダイエット商品の爆発的なヒット商品も幾つかありましたが、ダイエット商品は瞬間的に売れることが多く、大抵は1年程度のヒットで終わってしまいます。ロングセラーとなるダイエット商品は殆どありません。この理由は、特に日本人の場合、ダイエットを長期的に継続する人が少ないためだと考えられます。たとえば10kg痩せたいと思い立った人がいたとした場合、何ヶ月か後に10kg痩せたとしたら、大抵はそこでダイエットは終わりになります。続けての健康管理・体重維持まで行なう人は非常に少ないのが現状です。しかし、折角落とした体重も、ダイエットを止めてしまったばっかりにリバウンドしてしまうケースも決して少なくありません。リバウンドしたからと言って再びまたダイエットに取り組む人は実際にはそれほど多くないのが現実です。特にダイエットの場合、苦痛を乗り越えて達成させる面があるため、ある一定の成果や満足を得たならば、つまりダイエットに一度成功したならば、ダイエットに対して興味を失ってしまいがちなのです。
けれども、これからのダイエットは、今までのような一過性のブームと違って来なければなりません。そして、メタボ検診の義務化がこれに拍車をかけるでしょう。恒久的な継続性のあるダイエットを行なう人が増えてくるのではないかと予想されます。そして、健康維持や体重の維持といった継続性のあるダイエットが今後は注目されるようになるはずです。実際はメタボ検診義務化の導入はこの現われでもあるのです。今後は健康体質であることが社会的にも評価の対象となってゆくことでしょう。
メタボ検診がダイエット市場に与える影響は、まずは1回目の検診が終わった後に現われて、その後ますます拡大の一途をたどってゆくことが予想されます。メタボ検診義務化によってダイエット市場が拡大してゆくことは間違いないと予想されています。
なお、最後に注意をしておきますが、今までも色々と問題のあるダイエット法が世間に横行していたのも事実で、メタボ検診の義務化によって今後はそのようなダイエット法がますます増えてくる恐れもあります。メタボ検診の義務化によって活性化されたダイエット市場にはそのような問題点も少なからずあるので、特に今後は、ダイエットを試みるに当たって、私たちは正しいダイエット法を見つけるようくれぐれも注意しなければなりません。「健康のためと思ってダイエットを試みた結果が病気になってしまった」ではシャレにもならないので、とにかくダイエットを試みるならば科学的で合理的な正しいダイエット法を選択するように心懸けましょう。
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|


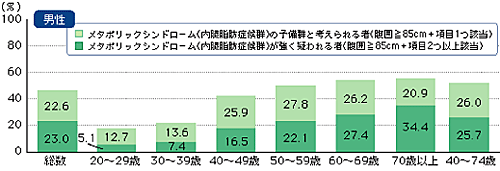
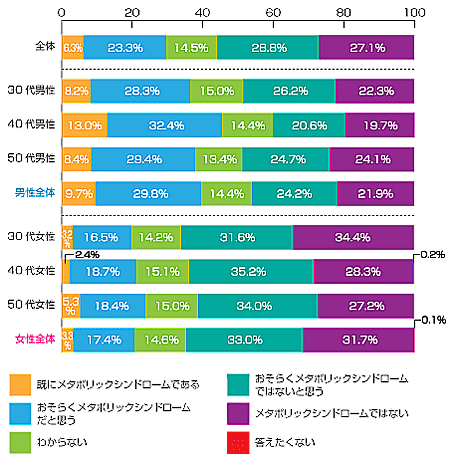


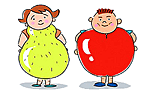

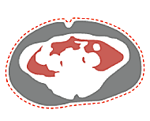
 メタボリック・シンドロームは食べ過ぎや運動不足という生活習慣の乱れから始まり、肥満、特に内臓脂肪が蓄積して生じます。内臓のまわりに脂肪が溜まる「内臓脂肪型肥満」は、食べ過ぎや運動不足などによって大量の脂肪を含んで大型化した脂肪細胞がお腹の臓器の間にある腸間膜などに蓄積された状態を言います。腰まわりやお尻、太股などの下半身を中心に溜まる皮下脂肪の脂肪細胞からは、動脈硬化を抑制しインスリン抵抗性を減少させる物質も分泌されていますが、一方で内臓脂肪の脂肪細胞からはこれらの分泌が少なく、逆に高血圧や高血糖、脂質異常症(=高脂血症)など動脈硬化のリスクを高める複数の物質が多く分泌されます。このため、「内臓脂肪型肥満」は高血圧や糖尿病、脂質異常症(=高脂血症)をもたらし、動脈硬化などのリスクを増大させる悪性の肥満で、メタボリック・シンドロームの主役とされています。
メタボリック・シンドロームは食べ過ぎや運動不足という生活習慣の乱れから始まり、肥満、特に内臓脂肪が蓄積して生じます。内臓のまわりに脂肪が溜まる「内臓脂肪型肥満」は、食べ過ぎや運動不足などによって大量の脂肪を含んで大型化した脂肪細胞がお腹の臓器の間にある腸間膜などに蓄積された状態を言います。腰まわりやお尻、太股などの下半身を中心に溜まる皮下脂肪の脂肪細胞からは、動脈硬化を抑制しインスリン抵抗性を減少させる物質も分泌されていますが、一方で内臓脂肪の脂肪細胞からはこれらの分泌が少なく、逆に高血圧や高血糖、脂質異常症(=高脂血症)など動脈硬化のリスクを高める複数の物質が多く分泌されます。このため、「内臓脂肪型肥満」は高血圧や糖尿病、脂質異常症(=高脂血症)をもたらし、動脈硬化などのリスクを増大させる悪性の肥満で、メタボリック・シンドロームの主役とされています。
 大人のメタボリック・シンドロームの診断基準というのは05年に作られたものですが、2007年になって今度は子どもにもメタボリック・シンドロームの診断基準(6〜15才向け)が設けられました。すなわち、07年4月、厚生労働省の研究班は「子どものメタボリック・シンドローム」の診断基準を設定、「生活習慣病の予防は子どもの頃から」と言うことで、6〜15歳を対象とするメタボリック・シンドロームの診断基準が作成されたのです。
大人のメタボリック・シンドロームの診断基準というのは05年に作られたものですが、2007年になって今度は子どもにもメタボリック・シンドロームの診断基準(6〜15才向け)が設けられました。すなわち、07年4月、厚生労働省の研究班は「子どものメタボリック・シンドローム」の診断基準を設定、「生活習慣病の予防は子どもの頃から」と言うことで、6〜15歳を対象とするメタボリック・シンドロームの診断基準が作成されたのです。 横浜市金沢区にある神奈川県立循環器呼吸器病センターでは、「メタボリック症候群改善コース」が設けられています。これは、2泊3日の短期入院による集中的な検査及び面接と、各患者に合った減量プログラムによる月1回の外来通院でフォローする半年間のコースです。健康保険(3割負担)で3〜4万円程度の入院費で済むので、健康診断等で(内臓)肥満を指摘され、高血圧か高血糖、高脂血症の何れかに該当する方は一度受診を考えてみるのもよいのではないかと思います。
横浜市金沢区にある神奈川県立循環器呼吸器病センターでは、「メタボリック症候群改善コース」が設けられています。これは、2泊3日の短期入院による集中的な検査及び面接と、各患者に合った減量プログラムによる月1回の外来通院でフォローする半年間のコースです。健康保険(3割負担)で3〜4万円程度の入院費で済むので、健康診断等で(内臓)肥満を指摘され、高血圧か高血糖、高脂血症の何れかに該当する方は一度受診を考えてみるのもよいのではないかと思います。
