| 【1】ポリフェノールの特徴 |
植物にたくさん含まれるそのポリフェノールが健康に極めて効果的だということで、昨今脚光を浴びています。
まずは本節では、ポリフェノールとは一体何なのか、その特長や期待される効果・効用について簡単に紹介・解説しました。
|
| ポリフェノールとは何か? |
ポリフェノールとは、単語に分解すると、poly(たくさんの)+phenol(フェノール)という2つの化学用語の合成語になります。具体的に言うと、光合成を行なう性質を持つ植物においてはなびらや実、茎などに含まれている成分がポリフェノールです。これは色や苦みなどを作り出すもので、細胞を生み出したり、その活動を活発化させる手助けをしています。また、ポリフェノールは5,000以上という多様な種類を持つことでも知られています。さらにフェノールは有機化合物の一種でもあります。かくして、ひとつの分子の内部に複数のフェノールを含んでいるものがポリフェノール(=たくさんのフェノール)と呼ばれ、多くの植物に含まれているものの総称でもあるのです。そして、従来からその性質を利用して、ポリフェノールは食品やコスメ用品などの製品開発においては香料や色素などとして用いられてきました。昨今、健康に関する効果が着目されて以降、ポリフェノールを含む食品は健康食品であるかのように、その健康効果が強調されるようになっています。そして、その契機となっているものが1990年代初頭に発表されたとある研究で、西欧諸国の人々の食生活に照らして、心臓疾患による死亡率の低さと土地で愛されている赤ワインとの間に有効な関係があるとされたのです。すなわち、ブドウ由来のポリフェノールを含む赤ワインを飲むと動脈硬化や脳梗塞を防ぐ抗酸化作用が働くということで、世界中で赤ワインブームが起こるほどとなりました。このように、ポリフェノールに関して様々な研究が現在でも続けられており、各種の成分が抽出され、また、配合された多くの健康食品や医薬品が登場しています。
| ◆参考図書1: |
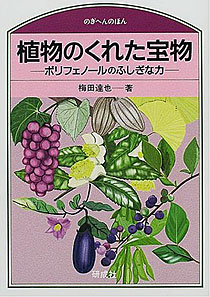 |
| ■ |
梅田 達也・著 |
|
『植物のくれた宝物――ポリフェノールのふしぎな力』 |
|
飛鳥新社・107年4月刊、¥1,365 |
|
ポリフェノールのふしぎな力が私たちのからだを活性酸素や紫外線から守る。赤ワイン・緑茶などに含まれるガンや糖尿病を予防するポリフェノール、大豆・ココアなどに含まれる動脈硬化や老化を防止するポリフェノールなど人の身体を活性酸素や紫外線から守るポリフェノールの不思議な力を解説。 |
|
|
|
| ポリフェノールの抗酸化効果 |
ポリフェノールと聞くと、皆さんはまずどの食べ物を思い出されます? 赤ワインや緑茶、チョコレート、コーヒー・・・その他にも果物全般や緑黄色野菜、納豆などの大豆製品などがあります。そして、その効果として抗酸化という言葉がよく聞かれますが、ポリフェノールの抗酸化作用とは一体どのようなものであるのか、ご存知でしょうか?
読んで字の通り、ポリフェノールの抗酸化作用とは「酸化を防ぐこと」です。人間は呼吸することで生きています。そして、酸素は空気中に含まれる成分のうち2割ほどで、酸素と栄養素とが結びついてエネルギーを作り出します。このとき未使用となってしまったエネルギーが酸化することになります。要するに金属に錆びが生じるように、体内にも錆びが生じるというわけです。つまり、ポリフェノールの抗酸化作用とは、ポリフェノールを含む食品が体内に入ることによって、体内の酸化を防止することの出来る体質がもたらされる、というものなのです。なお、最近の研究によって、ポリフェノールが余分な活性酸素によってダメージを受けた細胞のうち脂の部分を溶かす作用が確認されています。また、ポリフェノールは細胞膜を守るばかりでなく、血栓を予防し血流を改善し、血管も保護します。ポリフェノールは、まさに健康に欠かすことのできない成分として求められるものです。
|
| ポリフェノールと癌の予防 |
ポリフェノールとは、先にも触れたように植物の光合成によって作られる色素や苦味の成分ですが、そのポリフェノールが癌の予防になるという根拠は、その性質である抗酸化作用によります。
本来は体内の菌などと戦う活性酸素が増えすぎた場合、活性酸素の酸化力は遺伝子をも傷つける可能性があります。そして、傷ついた細胞が癌細胞に変異する恐れもあるのですが、増えすぎた活性酸素を抑える役割を果たすものがポリフェノールの抗酸化作用なのです。すなわち、ポリフェノールが活性酸素を抑えることで癌細胞が発生するリスクを低減することができるということです。また、癌細胞そのものを自殺に導くという働きもあり、多様なアプローチによってもポリフェノールは癌の予防になるのです。要するに、ポリフェノールは癌を含む3大成人病、そしてその原因にもなる生活習慣病をも予防する効果があることになります。そのような訳で、日々の食生活において、ポリフェノールが含まれている食物を極力摂取することが健康への第一歩に繋がるということになります。
|
| ポリフェノールと動脈硬化の予防 |
メタボリックシンドローム(メタボ)という言葉もすっかり一般的なものになりました。そして、病気の危険がいっぱいな状態でもあるこのメタボの方にとって最も恐ろしい病気は動脈硬化です。動脈硬化とは動脈の弾力が失われて硬くなっている状況で、その中をニコチンや脂肪によって粘り気を増してしまったドロドロ血液が流れるうちに血液の通り道が狭まり、最終的には血管が詰まってしまう危険性があるのです。
ポリフェノールは動脈硬化の予防になることが最近の研究によって明らかになっています。ポリフェノールは体内で脂肪の吸収を促す活性酸素の働きを抑え込みます。それは血液の粘性を高める原因を排除するということです。その他、血管の瘤や血管の障害物となる血栓を作らせないといった意味で、ポリフェノールが動脈硬化の予防になると言われているのです。このように、ポリフェノールを毎日摂取することで確実に血液や血管は健康な状態になりますし、それによって脂肪の吸収が防がれますから肥満の予防にも効果的であるということになります。とにかく、野菜や大豆製品などを毎回欠かさず食べているだけでも違います。動脈硬化は、なってしまってからでは手遅れです。そんな訳で、ポリフェノールは動脈硬化の予防になるのですから、これを役立てない手はないと言ってよいでしょう。
| ◆参考1: |
生活習慣病以外にポリフェノールには糖尿病の予防作用も |
|
ポリフェノールには様々な種類があり、そのそれぞれのポリフェノールの種類によって、抗酸化作用や抗菌作用(虫歯菌の増殖を抑えるなど)、血圧降下作用、ストレス抑制効果、肝機能向上効果、脂質の吸収抑制効果、また、女性ホルモンのバランスの調整効果などの作用があると言われています。さらに、リフェノールには一般的に強い抗酸化作用があり、老化や癌、また、動脈硬化などの生活習慣病を発症する原因のひとつとされる体内での活性酸素の発生を抑制する効果があると言われています。また最近では、ポリフェノールの長期間に及ぶ摂取によって、血糖値を下げて糖尿病を予防する作用なども報告されています。 |
|
|
| ポリフェノールと女性ホルモン促進作用 |
女性ホルモン促進作用が向上するということでもポリフェノールは注目されています。
ポリフェノールは光合成によって生み出される植物の色素や苦味の成分で、抗酸化作用を持つものです。ポリフェノールには、日々のストレスや喫煙、偏った食生活、飲酒などによって増えすぎた活性酸素の働きを抑制する効果があります。さらにポリフェノールは、女性ホルモン促進作用が向上する効果をもたらす種類として、女性ホルモンによく似た性質を持つイソフラボンが活躍します。イソフラボンには女性ホルモンのエストロゲンと同様の働きがあります。そして、エストロゲンは女性ならではの体内現象である月経や妊娠などに大きく関わるもので、これが不足すると更年期障害などの原因になります。なお、更年期障害の治療法として、エストロゲンを投与する場合に副作用の懸念があることから、食品を通じてイソフラボンを摂取することがより効果的であるということになります。そんな訳で、女性ホルモン促進作用が向上することもあって、ポリフェノールが最近女性に注目されているのです。また、イソフラボンが血流の改善にも効果があることで、むくみなどの解消を通じて肌の改善をも期待されることになります。日々の食生活から意識的に摂取することでバランスの良い食生活として、更年期障害の不安を打ち消し、健康的な美しさにも繋げたいところです。
|
| ポリフェノールと花粉症 |
現在、日本人の5人に1人は花粉症を発症していると言われています。2月下旬から春の終わりまで猛威を振るうアレルギーの症状に市販の機能性食品などで対応している方も多いのではないかと思いますが、実は市販されている機能性食品に含まれるミントや甜茶の成分、シソの葉に含まれるロズマリン酸、また、お茶類に含まれるカテキンといった成分は、何れもポリフェノールの一種なのです。このようにポリフェノールが花粉症に効く成分として、花粉症対策効果のある食品に配合されているのです。
それでは、何故ポリフェノールは花粉症に効くのでしょうか? その秘密は、ポリフェノールの持つ高い抗酸化力にあります。アレルギー反応が起きる理由は、原因物質であるアレルゲンが刺激を与えているためで、アレルギー反応によって炎症が起こると大量の活性酸素が発生し、さらに症状が酷くなります。しかし、ポリフェノールには活性酸素を分解抑制する作用があるため、花粉症によって起こるアレルギー反応や炎症を和らげることができるのです。そんな訳で、日常的にポリフェノールを多く含む食品を摂取することで花粉症を予防する対策にもなります。予防手段としても、ポリフェノールは花粉症に効くのです。
なお、サツマイモやニンジン、ほうれん草やトマトなどお馴染みの野菜にもポリフェノールは多く含まれています。お茶類にも多く含まれているので、意識して多めに飲むようにするとよいでしょう。また、アレルギーに飲酒はよくないとされていますが、楽しむならばポリフェノール含有量が多いとされる赤ワインにしましょう。さらに、脂分や糖分の過剰摂取はアレルギー症状に悪影響を及ぼしますので、花粉症の予防や症状の緩和を考えるには、まずバランスの良い食生活に気をつけるところから始めましょう。
|
| ポリフェノールと美容 |
| ポリフェノールの美白効果 |
美白効果があるポリフェノールも多く見つけることができます。たとえばエラグ酸というポリフェノールに美白効果があると認められています。エラグ酸という名前は余り聞き慣れない名前ですが、れっきとしたフラボノイドの一種で、シミやソバカスなどの原因となるメラニン色素を抑制する効果を持つものです。エラグ酸はイチゴから発見されたもので(※ただし、実際にイチゴ1粒に含まれるエラグ酸の量は微量です)、その美白効果が認められ、もちろんポリフェノールの特徴である抗酸化作用も持っていることから、化粧品や健康ドリ
ンク、成分を抽出したサプリメントにも使用されています。また、タラという植物の実を包む鞘などからもエラグ酸が抽出されます。タラも余り有名な植物ではありませんが、マメ科に属し、ペルーを原産としており、一定量を配合する必要のある化粧品などにはタラから抽出されたエラグ酸が使用されています。その他マメ科の萩の仲間であるキハギに由来するポリフェノールに美白効果があることが分かっています。
なお、美白効果が期待される各種のポリフェノールには、美白効果の高い成分として前から知られていたハイドロキノンやアルブミンにも劣らないメラニン抑制効果を持っています。たとえばハイドロキノンの場合、美白効果の高さと併せてアレルギーなどの症状が懸念されるケースもありますが、天然の植物成分であるポリフェ
ノールであればその点も安心することができます。
|
| ポリフェノールとアンチエイジング |
ポリフェノールがアンチエイジングにも効果を発揮していることが分かっています。
ポリフェノールがアンチエイジングに効果を発揮することについて明らかになったそもそもの背景には、赤ワインに含まれるポリフェノールが健康によい影響を与えているという研究発表があります。そして、ポリフェノールについて研究が進む中で、体内の酸化を防ぐ抗酸化作用についての詳細が徐々に明らかになってきました。そして、ポリフェノールがアンチエイジングに効果を発揮することには、その抗酸化作用が関係しているのです。抗酸化作用は血流の改善などにも結びつくもので、連動して代謝の改善や脂肪の燃焼効率の向上が期待されることになります。そして、血流がよくなることは、むくみやシミ、ソバカスといった症状の解消にも繋がります。また、女性ホルモンのエストロゲンと似た働きを持つイソフラボンには肌の保湿効果や美白効果、体内では生成されず年齢とともに減少してゆくヒアルロン酸の働きを促す効果もあります。このように、色素の沈着による悩みがある方にもポリフェノールは効果的な成分であるのです。積極的に摂取して、体内から健康及び美しさを育みましょう。
体調不良や病気・疾患は、基本的に日々の生活習慣や食生活が整っていれば回避することが出来ます。特に生命にも関わる3大成人病の予防について、 食習慣の中で主要栄養素のひとつとしてポリフェノールを摂取することが推奨されています。
|
| ポリフェノールとダイエット |
ポリフェノールは植物に由来し、一定の性質を持つ成分の総称なので、「ポリフェノールにダイエット効果がある」というと余りにも大雑把な話になってしまうのです。しかし、ひと口にポリフェノールと言っても非常に多くの種類があり、たとえばダイエットに効果的であるとよく言われているカテキンもポリフェノールの一種です。従って、ポリフェノールにダイエット効果があることは間違いではないということになります。
カテキンは緑茶やリンゴ、ブルーベリーなどにも含まれている成分で、発癌性物質の働きを抑える他、糖質を消化する消化酵素の働きも阻害します。カテキンの働きによって糖質が吸収されにくくなり、血糖値の急激な上昇を防ぐことにもなるのです。また、脂肪の吸収を防ぎ、脂肪を排出する働きもあります。運動前にカテキンを補給することによって代謝が高まり、脂肪の燃焼にも活躍してくれます。もちろん単純にカテキンを摂取を続けていれば痩せるというわけではなく、適度な運動にカテキンの働きが作用することでダイエットに繋がるということになります。その補給を手軽に行うものとして、特定保健用健康食品として大ヒットしたヘルシア緑茶などもあります。そんな訳で、カテキンは体脂肪が気になる方などに適したポリフェノールであるということが出来るでしょう。
|
|
| 参考1:ポリフェノールと頭痛 |
ポリフェノールの種類によってその効用は様々で、女性ホルモンの働きを補ったり、アレルギー反応を抑制したり、或は生活習慣病の予防になったりといったよい点が多く挙げられます。ただ、症状によってはポリフェノールは頭痛に悪影響を及ぼす可能性も指摘されています。
日本人のうち3割程度の方が慢性的な頭痛に悩まされています。その多くが緊張型というもので、肩や首の凝りが原因です。この凝りによる頭痛は、筋肉の緊張によって血のめぐりが悪くなるために引き起こされるものであり、筋肉を和らげることで症状は落ち着きます。
抗酸化作用によって血のめぐりを改善するポリフェノールは、そのため、図らずも頭痛に悪影響を及ぼす役割を果たしてしまう可能性があるのです。それは頭痛が偏頭痛である場合です。偏頭痛は頭部をめぐる血管が急激に拡張・収縮するような場合に起こりやすいもので、身体が急激に冷えたり温められたり、或は緊張状態から解放された場合に偏頭痛に気をつけなければなりません。その他アルコールのように血管を拡張させる性質を持つものを摂取したことがキッカケとなって偏頭痛となることがありますが、ポリフェノールもこの性質を持っています。抗酸化作用はポリフェノールの長所でもあるのですが、血流を改善するということで血管が拡張することになるのです。すなわち、偏頭痛を誘発させ、また悪化させる原因になり得るという意味では、ポリフェノールは頭痛に悪影響を及ぼすことになります。
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|
| 【2】ポリフェノールの種類と効能 |
ポリフェノール (polyphenol) とは、「ポリ(たくさんの)+フェノール」という意味で、分子内に複数のフェノール性ヒドロキシ基(ベンゼン環、ナフタレン環などの芳香環に結合したヒドロキシ基)を持つ植物成分の総称です。ポリフェノールの種類は極めて多様で、それぞれ様々な働きをします。
本節では、代表的なポリフェノールを取り上げて、それぞれについてなるべく詳しく解説しました。
|
| アントシアニン |
アントシアニンは紫のポリフェノールの色素で、抗酸化物質として知られるポリフェノールです。
アントシアニンは抗酸化物質として知られるポリフェノールの一種で、アントシアニンには、活性酸素の生成を抑制する作用や血液をきれいにする作用、目の疲れを改善する作用などがあると言われています。これは、アントシアニンの機能に目の網膜にあって視覚情報を脳に伝える重要な役割りをしているロドプシンの再合成を促進させる働きがあるからだと考えられています。なお、アントシアニンによる目に対する作用は近視の改善による視力の回復ではなく、夜盲症の予防から夜間における見え方が改善することのようです。また、アントシアニンは果実や花を赤や青、紫色に彩るポリフェノールの色素で、ブルーベリーや黒大豆、黒米、黒ゴマ、紫芋、イチゴ、ブドウなどに多く含まれています。
| ■ |
アントシアニンによる視覚向上 |
|
アントシアニンには視覚を向上する作用があると言われています。アントシアニンを摂取することによって脳に視覚の情報を伝達する物質の再合成を助け、その結果として見え方が改善すると考えられています。
眼球の網膜内部にはロドプシンという色素が存在していますが、ロドプシンが視覚の情報を脳に伝達することによって視覚が生じます。そして、脳に情報を伝達する時にはロドプシンは分解と再合成を繰り返します。アントシアニンにはこのロドプシンの再合成と活性化を助ける働きがあり、そのために夜間の視力が改善すると言われています。ただ、アントシアニンを人が摂取した場合に実際にどの程度の効果があるのか、その詳しいところは残念ながらまだ余り究明されてはおりません。 |
|
| ■ |
アントシアニンで動脈硬化を予防 |
|
アントシアニンが血をきれいにし、動脈硬化を予防する効果が動物実験で確認され、そのため、アントシアニンには動脈硬化を予防する働きがあると考えられています。たとえばネズミにストレスを与えて血をドロドロにした後でアントシアニンを飲ませると、そのネズミの血液がサラサラになるそうです。また、実験によると、アントシアニンには血圧を下げる作用もあるそうで、高血圧になったネズミの最大血圧は、アントシアニンの含有物を飲んで数時間で下がるそうで、さらに、アントシアニンの含有物を食べている間は血圧が下がったままであったそうです。 |
|
|
| カテキン |
カテキンは緑茶のポリフェノールの成分で、強い抗酸化作用や殺菌作用があることで知られるポリフェノールです。
カテキンは緑茶の渋味の源となるポリフェノールの成分で、カテキンは強い抗酸化作用や殺菌作用があることで知られるポリフェノールの一種です。カテキンには抗酸化作用や抗菌作用(虫歯菌の増殖を抑えるなど)、活性酸素の消去効果、コレステロールの上昇抑制効果、血糖や血圧の上昇を抑制する作用などがあることが知られています。また、カテキンには抗アレルギー作用も有するようです。
カテキンを継続的に摂取することで体脂肪を減少させる効能があると考えられています。これはカテキンに肝臓内で脂肪の燃焼効率を向上させる作用があるとされているからで、その他に血中コレステロールを低下させる効果もあり、動脈硬化など生活習慣病の予防に繋がると考えられています。また、カテキンには抗菌作用・抗ウイルス作用があることから、虫歯予防やインフルエンザ予防などにも効果的であると言われています。またさらに、カテキンを適度に摂取することで癌を抑制する作用があるのではないかとも考えられています。カテキンは緑茶に多く含まれていますが、緑茶の産地である静岡県中川根町の男性の胃癌による死亡率は全国平均の5分の1であると言われています。
| ■ |
カテキンの種類と作用 |
|
緑茶にはカテキンが含まれていますが、ウーロン茶や紅茶にもカテキンが変化した形で含まれています。お茶の種類には様々ありますが、お茶ほど世界的に多く飲まれるものは多くありません。しかし、日本人にとって一番なじみのあるお茶の種類と言言えば何と言っても緑茶でしょう。緑茶は茶葉を蒸した後に乾燥させたもので、茶葉を発酵させない状態で飲むものですが、そのため緑茶にはカテキンがそのままの形で含有されています。一方、ウーロン茶は緑茶とは違い、茶葉を半分まで発酵させたもので、摘み取った茶葉を途中まで発酵させ、その後に熱を加えて発酵を止めます。緑茶のカテキンとは種類が異なりますが、ウーロン茶にもウーロン茶重合ポリフェノールというものが含まれています。ウーロン茶重合ポリフェノールは、カテキンが発酵の過程で酸化することで生成されるのですが、リパーゼ阻害に基づく抗肥満作用があることが報告されています。他方、紅茶は茶葉を完全に発酵させたもので、茶葉を完全に発酵させることで紅茶独特の色合いと香りを引き出します。その紅茶にも茶葉に元々含まれるカテキンが酵素で酸化することで生成されるテアフラビンという成分が含有されています。そして、このテアフラビンにも虫歯抑制作用や抗菌作用など緑茶のカテキンとよく似た作用があります。ただし、紅茶には鉄分の吸収を阻害する作用があると言われます。
カテキン類には、このように発酵させない形で存在するカテキンや半発酵により生成されるウーロン茶重合ポリフェノール、完全発酵で生成されるテアフラビンと言ったように種類は様々に異なりますが、そのどれもが健康に好影響を及ぼす作用を有する点では共通しています。 |
|
| ■ |
カテキンとお茶の渋み |
|
お茶の渋みはカテキンによるものですが、カテキンにも複数の種類と共に渋みの強弱があります。従って緑茶とウーロン茶や紅茶の渋みが異なるのは、それぞれを構成するカテキン類の種類と含有量が異なるためです。また、お茶の渋みの元となるのはタンニンなのですが、お茶のカテキン類はタンニンを構成する成分であり、タンニンの約85%がカテキン類で占められているのです。
なお、お茶を構成する主要なカテキンにはEGCG(エピガロカテキンガレート)、EGC(エピガロカテキン)、ECG(エピカテキンガレート)、EC(エピカテキン)という4つの種類があります。緑茶類にはEGCGとEGCの含有量が多く、ECGとECの含有量はそれに次ぎます。なお、ウーロン茶では、緑茶に比べてこれらの成分が概ね4分の1から5分の1程度です。また、紅茶ではEGCGとEGCの含有量がゼロになり、ECGが同程度、ECが3分の2程度の含有量となります。すなわち、お茶の種類によるカテキン類の含有量は緑茶が最も多く、その次にウーロン茶、最も少ないのが紅茶という順番になるわけで、茶葉の発酵に伴ってカテキン類の含有量が減少するようです。また、カテキンのうちで渋味と苦味が共に強いのはEGCGとECGで、渋味が弱いが苦味があるのはEGCとECとなります。そのような訳で、緑茶の渋みが一番強く、ウーロン茶と紅茶の渋みは緑茶よりも弱くなります。ちなみに、玉露やかぶせ茶は渋みと苦味が少なく旨みが多いという特徴がありますが、これは栽培中に遮光することでEGCとECの含有量が少なくなるためです。 |
|
| ■ |
カテキンの抗癌作用 |
|
カテキンには抗癌作用があると言われています。そして、カテキン類で抗癌に作用するのは主にEGCGであると言われています。そして、お茶類でEGCGの含有量が多いのが緑茶類であることを考えると、抗癌作用が期待できる種類も緑茶であると言えます。また、EGCGにはコレステロールの吸収を阻害する作用があるとも言われています。さらに、オリゴ糖には腸内の悪玉菌を減少させる作用がありますが、カテキンにも同様の作用があると考えられています。オリゴ糖が腸内悪玉菌を減少させる仕組みはオリゴ糖の摂取で増える腸内善玉菌の生産物(酢酸と乳酸)が悪玉菌を死滅させることによるものです。これに対してカテキンが悪玉菌を減少させる仕組みはカテキンの殺菌作用によるものです。カテキンにはビフィズス菌に対する殺菌作用はなく、悪玉菌に対しては殺菌作用があるようです。そして、カテキンの殺菌作用は摂取する間のみ有効で、摂取を止めると腸内細菌群の構成も元に戻ると考えられています。なお、お茶の主要なカテキン類である4種類それぞれに殺菌作用がありますが、EGCGとECGの殺菌作用が比較的高いと言われています。
なお、癌の抑制はカテキンとビタミンAの併用で、癌の抑制にはカテキンに加えてビタミンAを同時に摂取するとその効果が増すとされています。ある研究によると、まずビタミンAを摂取すると、癌細胞に対してカテキンを取り込ませやすくすることができるらしいという結果が出ています。そのため、癌細胞がこのような状態である時にカテキンを摂取すると、そうでない場合に比べてより多くの癌細胞の増殖を抑えることができるということになります。そんな訳で、緑茶を飲む時にはビタミンAの摂取を併用した方が抗癌作用が上昇すると考えられます。 |
|
| ■ |
カテキンの吸収率 |
|
カテキンの吸収率は非常に悪いため、お茶としてそのまま飲んでもその殆どが吸収されることなく排出されてしまいます。そこで、カテキン類でも抗癌作用があると言われるEGCGは脂溶性であるため、お茶を飲む時には、油を使って調理したものや油脂類の食品を一緒に摂取すればEGCGの吸収率が上昇します。そして、脂溶性の栄養素には、たとえばビタミンAやビタミンEといった脂溶性ビタミンがあり、これらの脂溶性ビタミンもカテキンと同様に油と一緒に摂取しなければ吸収率が低下します。なお、脂溶性の成分はその名の通り油に溶ける性質があり、従って、油に溶けることによって腸管から油ごと吸収される性質があるわけです。 |
|
|
| フラボン |
フラボンはフラボノイド系色素のポリフェノールで、白い花のポリフェノールの色素です。
フラボンはフラボノイド系色素のポリフェノールの一種で、一般的に淡色(主に無色や黄色)の色素です。フラボンは多くの植物に存在するポリフェノールの色素で、サクラソウ属の葉などから分泌される白色の粉や、一般的に白色をした花びらに多く含まれています。ちなみに、お茶に含まれる色素は主にフラバノールという成分ですが、フラバノールはフラボンの一種で、従ってお茶にはカテキンと共にフラボンも含まれていることになります。
| ■ |
フラボンの色合い |
|
フラボンの色素は無色や黄色なので、フラボンが無色の場合は非常に識別しにくい色です。また、その他の色素としてはアントシアニンが青や赤、カロチノイド類が黄色です。
なお、植物や果実の色には何らかの意味が備わっています。たとえばリンゴが真っ赤でミカンが鮮やかなオレンジ色をしていれば、それを食べる動物にいち早く発見されることで種子が運搬されやすくなります。私たちが色鮮やかな青や赤色、或は黄色の花びらを見れば、その存在を直ぐに発見することが出来ます。しかしながら、フラボンの色は淡く、動物に発見されやすい色であるとは言えません。それでは何故フラボンの色は無色や黄色の淡い色なのでしょうか? それは、フラボンの色素は私たちには淡く見えるだけですが、実は昆虫類には違う色に見えているのです。私たちは紫外線の色を識別することが出来ませんが、昆虫には識別出来ます。昆虫は紫外線の他に青と緑色を識別することが出来ますが、赤色を識別することが出来ません。それに対して、フラボン類の色素は赤色光と緑色光を反射して紫外線を吸収します。このようなフラボン類の色素の特徴から、昆虫類にははっきりと意味がある色であると識別することが出来るわけです。たとえば紫外線を吸収した白色の花びらは、昆虫にとっては明るい青緑色として認識されます。そして、フラボン類の色素は実際に昆虫類を誘引しているのです。 |
|
| ◆参考2: |
ルチンはフラボンの一種 |
|
ルチンはフラボンの一種で、ソバに含まれる抗酸化作用を持つ成分として知られています。なお、韃靼ソバにはルチンが多く含まることで知られていますが、韃靼ソバにはフラボンの一種であるルチンがケルセチンという形で含まれています。そして、ルチンやケルセチンは、ソバの苦味の成分でもあります。なお、ルチンの別名はビタミンPと言い、抗酸化作用の他にも血圧を下げる作用や血管を強くする作用などが知られています。従って、ソバを茹でた後の湯を飲むと身体によいと言われるのは、ソバの茹で汁にルチンが含まれるからです。 |
|
|
| イソフラボン |
イソフラボンは植物女性ホルモンと言われるポリフェノールの一種で、体内でエストロゲンと同じような働きをするポリフェノールです。
イソフラボンは大豆に含まれるポリフェノールの仲間で、大豆イソフラボンのサプリメントとしてよく知られる成分です。またイソフラボンは女性ホルモンであるエストロゲンと化学構造が似ていることから、フィトエストロゲン(植物女性ホルモン)といった呼び方もされています。イソフラボンは体内でエストロゲンと同じような働きをすることで知られています。
既に述べたようにイソフラボンは大豆などのマメ科の植物に多いポリフェノールで、女性ホルモンのエストロゲンとよく似た作用があることから、イソフラボンの効能としては、更年期障害の様々な症状を和らげる効果があるとされています。さらに、イソフラボンには骨粗鬆症の予防にも効果があると言われています。また、その他にも癌細胞の増殖を抑制する作用があると言われており、特に乳癌や前立腺癌に対して予防効果が見られるとされています。ただし、大豆イソフラボンの成分を濃縮したサプリメントによる多量摂取を行なうと、健康によい影響を持たず、却って悪影響を及ぼすとも言われていますので、注意が必要です。
| ■ |
更年期障害をイソフラボンで改善する |
|
更年期障害の改善にはイソフラボンの摂取が有効であるとされています。これは、更年期障害は体内で女性ホルモンのエストロゲンが不足することが一因なので、体内でエストロゲンと同様に作用するイソフラボンを補えばよいという原理です。従って、実際に更年期障害の対症療法としてはエストロゲンを投与することで治療法が行なわれています。ただし、対症療法によるエストロゲンの投与は副作用が問題になりますので、古くから食べ継がれる通常食品の大豆でイソフラボンを補うことは更年期障害に対する安全な対策のひとつになり得ます。
ちなみに、大豆は日常の食卓に上るごく普通の食品ではありますが、イソフラボンの摂取を意識して食べ過ぎることもよくありません。もちろん通常食品によるイソフラボンの摂取はサプリメントと比べれば安全性は格段に優れますが、大豆製品の過剰摂取もまたイソフラボンの過剰摂取に繋がってしまうのです。なお、大豆には重量の約0.2〜0.4%のイソフラボンが含まれていると言われ、イソフラボンの代表的なものにはダイゼインやゲニステイン、グリシテインなどがあります。従って、大豆を乾燥重量として毎日10g摂取することでイソフラボンを20〜40mg補えることになり、サプリメントによる許容上限摂取量が30mg以内であることを考えればこれで充分と考えられます。 |
|
| ◆注意1: |
大豆イソフラボンはサプリメントで摂取しない |
|
大豆イソフラボンのサプリメントは気軽に補えることが利点ですが、それと同時にイソフラボンの過剰摂取へと容易に結びついてしまいます。大豆イソフラボンを補うことは更年期障害の不快な症状を改善するには効果的な対策と言えるのですが、サプリメントによる過剰摂取は深刻な健康障害の原因ともなり兼ねないのです。
一般的に大豆イソフラボンを食品から適度に補うことは、更年期障害の改善と共に骨粗鬆症や乳癌の予防を期待出来ると言われています。ただし、サプリメントによる大豆イソフラボンの過剰摂取が問題になっているのは、乳癌の発症と再発のリスクを高める可能性が指摘されているからです。もっとも人体における大豆イソフラボンの有効性と安全性についての議論は確立されていないとされていますので、安全性が確認されている食品としての大豆から適度に摂取することが最も安全と言えるでしょう。 |
|
|
| フラバン |
フラバンはフラボノイドを構成するポリフェノールの一種で、フラボノイドの骨格として自然界に存在しています。
フラバンはフラボノイドを構成するポリフェノールの一種で、フラボノイドの骨格として自然界に存在しています。従ってフラバンという形では自然界に存在しません。フラボノイド系として存在するポリフェノールの主なものにアピゲニン、ケルセチン、アビイン、ヘスペリジン、ナリンジン、シトロニン、ダイジン、ルチン、トリシンなどがあります。また、フラボノイド系の各種のポリフェノールは主に植物の葉茎や果実、種子などに含まれています。フラボノイドはグレープフルーツやレモン、大豆、ソバ、小麦、コウリャン、パセリの葉、温州ミカン、ダイダイなどに含まれることでも知られています。
なお、フラボノイドの効能として毛細血管を保護して丈夫にする作用があると言われ、抗酸化作用や抗菌作用(虫歯菌の増殖を抑えるなど)、抗癌作用、抗アレルギー作用、血圧の上昇を抑制する作用などが指摘されています。
| ■ |
フラボノイド系のポリフェノール |
|
フラボノイド系のポリフェノールとして一般的に馴染みの深いものにはカテキンやアントシアニン、タンニン、ルチン、イソフラボンがあります。フラボノイドはフラバンの誘導体という位置付けで、誘導体とは元の物質が化学反応によって変換された後のものを指します。たとえばフラボノイドはフラバンが変換されて生成されたという位置付けからフラバンの誘導体になります。また、フラボノイドには強い抗酸化作用がありますが、カテキンやアントシアニンの抗酸化作用はよく知られています。 |
|
| ■ |
フラボノイドの抗酸化作用 |
|
フラボノイドには抗酸化作用がありますが、日常生活において偏食を行なわない限りある程度のフラボノイドの摂取がなされています。これを言い換えれば、偏食を行なえばフラボノイドが欠乏するということを意味しています。
フラボノイドには抗酸化作用以外にも、癌の抑制や免疫力の調節、殺菌作用など体に有益な作用を有します。そのため、日常生活でフラボノイドを含む野菜や果実類を多く摂取することは健康維持や生活習慣病の予防には大切なことであることになります。このように毎日野菜類を多用する食生活を行なうことの重要性は、カロチンや他のビタミン類と共にフラボノイドの摂取にもあるのです。癌や動脈硬化などの生活習慣病を予防するためには、生活習慣を改めると共に野菜を適量摂取する食生活への改善が必須であることになります。 |
|
|
| フラバノン |
フラバノンはミカン科に多いポリフェノールの一種で、フラバンを骨格とするフラボノイド系のポリフェノールです。
フラバノンはフラバンを骨格とするフラボノイド系のポリフェノールの一種で、植物に配糖体(糖質以外の物質とオリゴ糖が結合した成分)という形で存在します。また、フラバノンはミカン科の植物に多く、ミカン、レモン、ダイダイの外果皮の白色部分に多く含まれるポリフェノールです。なお、フラボノイドは毛細血管を保護して丈夫にすることで知られ、抗酸化作用や抗菌作用(虫歯菌の増殖を抑えるなど)、抗癌作用、抗アレルギー作用や血圧の上昇を抑制する効果が知られています。
| ■ |
温州ミカンのフラバノン |
|
温州ミカンにはフラバノンが含まれています。フラバノンはさらにヘスペリジンやナリンゲニンなどに細分化されますが、温州ミカンに含まれるものはヘスペリジンという種類のものです。そして、ヘスペリジンには毛細血管を強くする作用や抗アレルギー作用、抗ウイルス作用が指摘されていますが、ヘスペリジンは温州ミカンの果肉100g当たりで0.1gも含まれる場合があると言います。また、温州ミカン中のヘスペリジンは房の部分や房に付く白い部分に多く含まれると言われるので、出来るだけ房と白い部分ごと食べる方が健康には効果があるでしょう。そして、温州ミカンが健康にとってよいのは、フラバノン類のヘスペリジンが含まれているという理由だけでなく、ビタミンCとともにペクチンが含まれるからです。温州ミカンはフラバノンとペクチン、ビタミンCを含む機能性食品だったのです。
ちなみに、ペクチンは一種の水溶性食物繊維のことで、果物を原料にしてジャムを煮詰める時に固まる原因となる成分ですが、これは寒天を煮詰めて冷やすと固まる性質と同じと言えます。健康維持のためには食物繊維を1日当たりで20〜25g摂取することが推奨されていますが、機能性の大きな食物繊維は不溶性のものよりもペクチンのような水溶性のものです。水溶性食物繊維はジャムを作る時に水分を固める性質があるように、体内に取り入れると水分を多量に取り込んで消化器官や腸内でどろどろに膨れ上がります。水溶性食物繊維のこのような性質は、一緒に食べたものの消化吸収速度を緩めたり、便の嵩を大幅に増やして便秘解消にも働きます。 |
|
|
| クロロゲン酸 |
クロロゲン酸はコーヒーの生豆やヤーコンに多いポリフェノールの一種で、褐色脂肪細胞を活性化させることで知られるポリフェノールです。
クロロゲン酸はコーヒー豆やゴボウに含まれるポリフェノールで、クロロゲン酸は多機能なポリフェノールです。抗酸化作用の他に注目されている効能としては肥満の予防・改善が挙げられます。皮下脂肪など体内に貯えられていた脂肪がエネルギーとして利用される場合、いったん肝臓に運ばれるのですが、クロロゲン酸には肝臓で脂肪の燃焼を促進する作用があることから、脂肪の蓄積を予防すると考えられています。また、体内で発癌物質の生成を抑制する働きがあるといった効用の他に、知覚神経を刺激して認知機能の改善並びに向上効果があるとも言われています。
ちなみに、クロロゲン酸はヤーコンのポリフェノールの主要成分のひとつに数えられますが、クロロゲン酸はダイエット・コーヒーの主要成分としても知られています。クロロゲン酸がダイエット・コーヒーで注目されている要因には、クロロゲン酸に褐色脂肪細胞を活性化させる作用があると言われるためです。なお、褐色脂肪細胞とは過剰摂取したカロリーを熱エネルギーとして排出させる作用を持つ脂肪細胞で、基礎代謝の一部分にも組み込まれるカロリー消費の重要な役割を持つ部分です。
| ■ |
クロロゲン酸に認められる効能 |
|
- 癌の発生段階の抑制(抗変異原性)
- 糖の吸収を抑えて血糖値の安定化を促す
- アンギオテンシンI変換酵素阻害活性(血圧の抑制に関与)
- チロシナーゼ阻害活性(メラニンの生成抑制)
- 抗酸化作用による活性酸素の除去
|
|
| ■ |
クロロゲン酸の抗変異原性 |
|
癌の定義は悪性の腫瘍で、身体を作る細胞は古くなると自然に消滅することで新しい細胞と置き換えられるものですが、古くなった細胞が消えずに増殖を繰り返す組織を腫瘍と言います。クロロゲン酸には抗変異原性があると言われていますが、抗変異原性とは癌の発生段階を抑制する作用のことを指します。癌は細胞の突然変異によって引き起こされますが、細胞の突然変異を抑制する作用を抗変異原性と言います。そして抗癌性とは、既に発生した癌の成長を抑制する作用を指します。つまり、クロロゲン酸で指摘されている抗変異原性とは、細胞の突然変異によって癌組織が発生することを抑制する作用なです。 |
|
| ■ |
血糖値の安定を促す |
|
クロロゲン酸には血糖値の安定を促す作用が指摘されています。クロロゲン酸が血糖値の抑制に関与するのは、クロロゲン酸の摂取が血液中と脾臓や肝臓のマグネシウム濃度を上昇させるからであると考えられています。
糖尿病はインシュリンの作用不足に基づく慢性的な高血糖状態を特徴としますが、糖尿病患者は正常な血糖値を示す人に比べて血液中のマグネシウム濃度が低いことが観察されます。マグネシウムは体内酵素の正常な働きとエネルギー産出を助ける働きを持つのですが、インシュリンの分泌や標的細胞における作用にも関わることが知られています。クロロゲン酸のこのようなマグネシウム濃度を上昇させる作用は、インシュリン増感剤の一種であるメトフォルミンの作用と同様である可能性が指摘されています。 |
|
| ■ |
血圧の抑制に関与 |
|
クロロゲン酸が血圧の抑制に関与することも指摘されています。クロロゲン酸にはアンギオテンシンI変換酵素阻害活性があると言われています。
高血圧とは心臓が血液を送り出す時の血管内の圧力が高い状態を指しますが、血圧を上昇させるのは体内でアンジオテンシン2という物質が生成されるためです。腎臓で産生されたレニンはアンジオテンシノ−ゲンに作用してアンジオテンシン1を産生します。それがアンジオテンシン変換酵素(ACE)によってアンジオテンシン2に変換されることで強力な血圧の昇圧作用を有することになります。そして、クロロゲン酸のアンギオテンシン1変換酵素阻害活性とは、レニンがアンジオテンシン2へ変換されるまでの流れの一部を抑制する作用を指します。 |
|
| ■ |
メラニンの生成を抑制 |
|
クロロゲン酸にはメラニンの生成を抑制する作用もあると言われています。クロロゲン酸にはチロシナーゼ阻害活性が指摘されています。
メラニンが生成される仕組みには体内酵素の一種であるチロシナーゼが関与していますが、チロシナーゼとはメラニンの生成で中心的な働きをしている酵素です。そして、メラニンが生成されるために必須の体内酵素がチロシナーゼであるため、チロシナーゼが働かないようにすればメラニンが生成されることもありません。なお、クロロゲン酸のチロシナーゼ阻害活性とは、体内でチロシナーゼの働きを阻害する作用を指します。 |
|
| ■ |
クロロゲン酸の抗酸化作用 |
|
呼吸活動で取り入れる全酸素量の約3%が活性酸素に変化すると言われていますが、活性酸素は著しく化学反応を引き起こしやすい性質を持つために他の物質を酸化させてしまいます。動脈硬化が引き起こされる仕組みのひとつには、活性酸素が血液中のコレステロールを酸化させてしまうことが挙げられます。クロロゲン酸には抗酸化作用がありますが、抗酸化作用は多くのポリフェノールが一般的に有する特徴のひとつで、抗酸化作用は動脈硬化の原因になる活性酸素の生成を抑制する作用を指します。 |
|
|
| エラグ酸 |
エラグ酸は美白効果を持つポリフェノールの一種で、赤色のラズベリーやいちご、ザクロなどに含まれるポリフェノールです。
エラグ酸はイチゴやラズベリー、ザクロ、ナッツ類などに豊富に含まれるポリフェノールで、ユーカリやヒシの成熟実など幅広い植物にも含まれています。エラグ酸は抗酸化作用及び美白効果で知られるポリフェノールの一種で、その抗酸化作用から食品添加物に利用されています。また、エラグ酸には抗酸化作用以外にメラニン色素の生成を抑制する作用があることから、肌のシミやソバカスの発生を抑えて美白効果があると考えられ、その優れた美白作用から多くの化粧品の美容成分として配合されています。ちなみに、以前ザクロが植物性のエストロゲンを含むということで知られることとなりましたが、ザクロはエラグ酸も含むため美白にも有効な果実と言えます。
| ■ |
エラグ酸の美白効果 |
|
エラグ酸には美白効果がありますが、それはチロシナーゼの働きを抑制することによるものです。チロシナーゼとはメラニンの生成に必須の体内物質で、エラグ酸によってチロシナーゼを作用させないことでメラニンの生成を防止することが出来るのです。なお、エラグ酸の持つチロシナーゼの働きを抑制する作用はクロロゲン酸にもあります。
私たちの皮膚の上層部にはメラノサイトと呼ばれる色素細胞が存在し、メラノサイトによってメラニンが作り出されます。チロシナーゼはメラノサイトがメラニンを作り出す時に作用する酵素です。つまり、皮膚が紫外線を受けるとメラノサイトが刺激を受けますが、メラノサイトが刺激を受けることでチロシナーゼが活性化します。そして、チロシナーゼの働きによりメラニンが生成されるのです。メラニンが生成される条件にはもちろん皮膚が紫外線を受けるということもありますが、チロシナーゼの働きもメラニン生成の条件のひとつで、従って、チロシナーゼさえ活性化しなければメラニンが生成されることもありません。 |
|
| ■ |
イチゴの抗酸化作用 |
|
イチゴには抗酸化作用で知られるアントシアニンとビタミンC、エラグ酸が含まれています。また、イチゴが赤く色づくのはアントシアニンが含まれるためで、ビタミンCは100g当たりで62mg含まれています。そして、イチゴの抗酸化作用の約3割までがアントシアニンとビタミンCによるものであると言われています。そして、抗酸化作用の残りの7割の部分についてはイチゴに含まれる他の何らかの成分が影響しているためですが、その成分のうちのひとつに数えられるものがエラグ酸です。
なお、このようにイチゴはアントシアニンやエラグ酸、ビタミンCと抗酸化作用を有する成分が多く含まれる美白にもよい食品ですが、ただ、イチゴの栽培にはその性質上から農薬を多量に使用します。このため、イチゴはできるだけ減農薬として栽培方法を工夫したものを食べるか、或は食べ過ぎないように注意が必要です。 |
|
|
| リグナン |
リグナンは胡麻のポリフェノールの一種で、抗酸化物質として知られるポリフェノールです。
リグナンは抗酸化物質として知られるポリフェノールの一種です。リグナンは胡麻に多く含まれるポリフェノールで、セサミンやセサモール、セサミノールもリグナンの一種です。そして、胡麻に最も多く含まれるリグナンの種類はセサミンとセサモリンです。もちろんリグナンは幅広い植物に分布していますが、胡麻に含まれる含有量は突出しています。胡麻が含むリグナン類の量は胡麻の重量全体の約0.8%とも言われています。そして、リグナンには抗酸化作用以外にも血中コレステロールの低下やアレルギーの抑制作用、癌細胞の増殖を抑制する作用、肝機能を改善する作用などがあると言われています。
| ■ |
胡麻のリグナン |
|
胡麻はリグナンを豊富に含む食品ですが、しかし、料理にゴマ油を使用することでリグナンを効率的に摂取できるわけでもありません。ゴマ油を製造する時には原料である胡麻を搾るわけですが、搾って油を分離した後の残り滓は飼料に使用するか、廃棄しています。ただし、胡麻のリグナンは配糖体(糖を含む化合物)としての形で含まれる部分があり、リグナン配糖体はその全てが水溶性です。従って,ゴマ油の部分にはリグナン配糖体が存在せず、搾り滓の部分にその全てが存在しているのです。つまり、胡麻に含まれるリグナンの全種類を摂取するには胡麻そのものを食べた方がよいということになるわけです。 |
|
| ■ |
リグナンで更年期障害を改善 |
|
リグナンにも更年期障害を改善する作用がありますが、リグナンは体内で女性ホルモンと同様に作用すると考えられています。なお、日本を含めたアジア諸国では、女性ホルモン様物質としては大豆イソフラボンに注目が集まりますが、北欧では亜麻子や穀類に含まれるリグナンによる女性ホルモン様物質がよく知られています。
植物性の女性ホルモンと言えば大豆イソフラボンが注目されていますが、胡麻などからリグナンを摂取することでも体内で女性ホルモン様物質(フィトエストロゲン)に変化します。もっともリグナンそのものに女性ホルモン様物質としての役割はないのですが、リグナンを摂取して消化管内に達した時そこに駐在する菌によってエンテロラクトンという女性ホルモン様物質に変換されるのです。なお、リグナンは胡麻における含有量が突出しているため、他の食品にも含まれることが余り知られていませんが、リグナンは穀物や種子、ナッツ、野菜などに幅広く含まれています。 |
|
|
| クルクミン |
クルクミンはウコンのポリフェノールの色素で、抗酸化物質として知られるポリフェノールです。
クルクミンは抗酸化物質として知られるポリフェノールの一種です。また、クルクミンは抗酸化作用以外に発癌抑制効果も期待されています。クルクミンはウコンの黄色の原因であるポリフェノールの色素で、ウコン(ターメリック)やカレー粉、辛子、マスタードに多く含まれています。ちなみに、沖縄ではウコンのことを「酒飲みの薬」と言うそうですが、ウコンには胆汁の分泌を促進する作用から肝臓の解毒作用を活発にすると言われています。なお、ウコンの多量摂取は肝臓への悪影響があるらしいので、サプリメントによる摂取は問題があると言えるでしょう。
| ■ |
ウコンのクルクミン |
|
ウコンにはクルクミンが含まれています。ウコンは別名がターメリックで、カレー粉の黄色の色素として知られています。従って、クルクミンを手軽に摂取するならばカレーを食べるのが一番簡単であるということになります。もっともウコンはカレーの香辛料としてのみではなく、漢方薬(肝臓炎、胆道炎、胆石症、カタル性黄胆、健胃など)としても知られています。ウコンは生姜科の多年草で、インドなどの熱帯アジアが原産となります。なお、急性黄疸やヘルペス、妊娠中、肝硬変、胆嚢炎、消化性潰瘍のような時にはウコンの大量摂取を避けた方がよいとされます。ウコンの場合も多量摂取は健康を害するらしいので、サプリメントとして大量摂取するのではなく、カレー粉などの食品から程々に摂取するのが安全でしょう。
ちなみに、カレー粉にはウコン(ターメリック)の他にもサフランやパプリカ、クミン、ナツメグ、オールスパイス、キャラウェイ、ガーリック、クローブ、コリアンダー、フェンネル、シナモン、コショウ、ジンジャーなど多数の香辛料が含まれています。カレー粉に含まれる上記のような香辛料は何れも漢方薬に含まれるような材料ですので、カレー粉の摂取はウコンに限定されない健康に有利な幅広い成分を一度に少量ずつ補うことができます。ただし、健康作用を期待してカレーを食べるのであれば、市販のルーからではなく原材料としてのカレー粉から補う方がよいでしょう。ルーには確かにカレー粉が配合されているのですが、動脈硬化を引き起こす原因となる牛脂や数々の防腐剤と保存料が含まれることが問題となります。カレーを純粋に食べたいから食べるというのであればルーを使用しても問題はないでしょうが、健康のためを思って摂取するのであれば、少し面倒ではあってもカレー粉を使用してカレーを作るのがオススメです。 |
|
| ■ |
ウコンの肝臓への作用 |
|
ウコンは肝臓の働きを回復させる妙薬とされますが、ウコンは「主として医薬品として使用されるもの」として分類されているので、やはり多量摂取は避けるべきでしょう。
ウコンを摂取するとGOTとGPTの数値が下がると言われています。GOTとGPTの数値は肝機能が低下する時に上昇するとされますので、ウコンの摂取は肝機能にとって何らかの作用を及ぼすと考えられています。ただし、ウコンを摂取すると、それと同時に肝臓細胞の働きも抑える傾向があるとされますので、高年齢の方が多量に長期摂取するには注意が必要です。ウコンはカレー粉の材料として馴染みが深いため、カレーを食べる程度の摂取では問題がないと考えられます。「過ぎたるは及ばざるがごとし」で、何事も過剰は問題ありということです。 |
|
|
| クマリン |
クマリンは桜餅の香りのポリフェノールの成分で、配糖体の形で多くの植物に含まれるポリフェノールです。
クマリンは配糖体の形で多くの植物に含まれるポリフェノールの一種です。また、クマリンは桜餅の香りの成分であるポリフェノールで、桜や桃の葉及びキク科、マメ科、セリ科、イネ科の植物に多く含まれます。なお、クマリンには特有の香があるため香料として利用される他にも、医薬品(むくみ改善など)として使用されることもあります。ただし、メリロートエキス(有効成分、クマリン)配合のむくみやセルライト対策のサプリメントは国民生活センターに様々な健康被害に見舞われたという相談が寄せられ、厚生労働省のホームページにも健康被害事例が掲載されていますので、くれぐれも注意が必要です。
| ◆注意2: |
クマリンの肝毒性 |
|
ビタミンKには血液凝固に深く関わる作用がありますが、その一方でクマリンにはビタミンK拮抗による抗凝固作用、毛細血管損傷作用があります。また、クマリンには薬理作用があり、殺鼠剤として利用されることもあります。クマリン系の殺鼠剤及び獣忌避剤としてはクマテトラリルやフマリン、ワルファリンがありますが、これらには蓄積性の血液凝固阻止作用があります。たとえばクマリン系の殺鼠剤であるワルファリンをネズミに投与する場合、1回でかつ多量の投与では致命的にならず、少量ずつ連続投与する場合には、体腔や皮下組織などに浸潤性の出血を起こすため致命的になるようです。なお、クマリンには肝毒性があるので、サプリメントによって気軽に摂取すれば痛い目に遭う可能性があります。 |
|
| ◆注意3: |
クマリンのサプリメント |
|
クマリンのサプリメントはメリロートという名前で知られ、むくみの改善効果を有するとされます。その一方でクマリン誘導体(クマリンを化学反応で変換したもの)であるワルファリンは殺鼠剤として使用されています。ワルファリンは上記のように抗凝固作用を有するため医薬品としては抗血栓薬として使用されています。血栓とは血管内の血液が固まる症状なので、ビタミンKの働きを阻止することで血栓の予防や抑制を行なうわけです。
なお、メリロートとして知られるクマリンにはワルファリンと同様の薬理作用があると考えられます。たとえばメリロートとして知られるサプリメントのクマリンの作用には血液循環を改善し、むくみの予防や除去に優れた効果があります。そしてクマリンの薬理作用とは、すなわちクマリン誘導体であるワルファリンがビタミンKの働きを阻止し、血栓の予防や抑制に作用する仕組みです。要するに、クマリンを多量摂取すると殺鼠剤の例のように毒となりますが、少量摂取することは抗血栓剤としての薬理作用を有することとなります。ただし、心筋梗塞に進展する動脈硬化の原因となる血栓を予防する薬理作用が単なるむくみ改善に必要であるかという疑問もあります。なお、ワルファリンには催奇形性が指摘されるため妊婦に対しての投与は禁忌であることを考えると、メリロートによるクマリンの摂取も同様の危険性があると考えてよいでしょう。 |
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|
| 【3】ポリフェノールを含む食品 |
それでは、ポリフェノールは具体的にはどのような食材に主に含まれているのでしょうか?
本節では、ポリフェノールを含有する代表的な食品を取り上げ、その上で、参考までにポリフェノールの効率的な摂取方法を解説しました。
|
| ポリフェノールを含む食品 |
ポリフェノールを含む食品と言われて一番に思い浮かぶものは、やはりワインでしょう。1990年頃から赤ワインがポリフェノール効果を持つとして注目されるようになり、健康ブームをも引き起こす要因となりました。後で詳しく解説しますが、ワインにおいては、厳密にはポリフェノールは原料であるブドウに由来するものです。ブドウの皮や種にポリフェノールが多く含まれているので、同じワインであっても皮や種がそのまま含まれる赤ワインにはポリフェノールが多く存在し、皮や種が取り除かれている白ワインにはそれほど多くのポリフェノールは含まれていおりせん。
しかし、日本で古くから飲まれ食べられてきたものにもポリフェノールを含む食品はたくさんあります。たとえば飲み物で言うと緑茶がこれに該当します。緑茶に含まれているポリフェノールが胃癌の予防のために有効であるとされているのですが、未だ研究途上でもあり、喫煙者であるとそれほど予防効果が見られないという実験結果もあります。なお、癌の予防を意識して緑茶を飲もうというのであれば、濃くしたもので7杯以上が必要とされます。その他ポリフェノールを含む食品として大豆製品を挙げることが出来ます。大豆製品には豆腐や納豆、味噌などが含まれます。ポリフェノールは加熱によって失われるということもないので、豆腐の味噌汁などはよい調理法であると言ってよいでしょう。なお、ポリフェノールは植物の光合成によって生み出されるものなので、野菜や果物にはポリフェノールが必ず含まれています。
| ■ポリフェノール含有量ベスト5 |
| 野菜類 |
果物類 |
加工品類 |
| 春菊 |
バナナ |
赤ワイン |
| 蓮根 |
マンゴー |
納豆 |
| シシトウ |
ブルーベリー |
ミルクチョコレート |
| サツマイモ |
ブドウ |
日本茶 |
| ブロッコリー |
リンゴ |
コーヒー |
|
|
| チョコレートとポリフェノール |
カカオ豆はチョコレートやココアなどの原料となるもので、有効成分として、身体の健康を保つために有用であるカカオマスポリフェノールが豊富に含まれています。なお、チョコレートのポリフェノールは苦味の部分の源になっているものです。ポリフェノールは多くの植物に含まれているものなので、当然ながらカカオマスにも存在しています。カカオ豆に含まれているポリフェノールは、その頭文字を用いてCMPとも呼ばれています。
昨今、赤ワインにポリフェノールが含まれていることで話題となりましたが、チョコレートのポリフェノールは100グラム中に0.8グラム、赤ワイ ンのポリフェノールは100グラム中に0.3グラムで、実はチョコレートのポリフェノールが含有割合としては上回っているのです。そして、ポリフェノールは抗酸化物質であり、アルコール性の肝臓障害を予防する効果があることも分かってきています。
なお、チョコレートのポリフェノールが注目されたことを受けて、各メーカーではポリフェノールを前面に押し出した商品展開を行なっています。ただし、同じポリフェノールが含有されている食品でも、積極的に摂取することが推奨される野菜などとは異なり、チョコレートには糖分やデンプン、脂肪分なども含まれています。従って、ポリフェノールが身体にとってよいものであっても、チョコレートの食べすぎは勧められません。やはり栄養を補給するためには、ひとつの食品に固執するのではなく、豊富な種類の食品をバランスよく口にすることが肝要です。
|
| ウーロン茶とポリフェノール |

ウーロン茶ポリフェノールとは、その名の通り烏龍茶に含まれるポリフェノール成分で、抗酸化力が強いと言われています。ウーロン茶ポリフェノールは多くのカテキンが結合することで生じ、他のお茶の種類には見られない特有のポリフェノールであると言われています。ウーロン茶の茶葉は緑茶の茶葉と同じく植物カメリア・シンネンシスの葉から作られますが、ウーロン茶は茶葉を作る過程で、茶に含まれるポリフェノール成分であるカテキンの重合が進むため、カテキンのうち半分ほどはカテキンの重合体に変わってゆきます。この重合により食べた脂肪を消化・吸収させずに体外に排出させるカテキンの作用が高まると考えられています。なお、ウーロン茶のポリフェノールを専門的に「ウーロン茶重合ポリフェノール」と表現することもあります。
ウーロン茶ポリフェノールは血管内の脂肪分解酵素リパーゼを活性化するので、中性脂肪がいち早く遊離脂肪酸へと分解されるのを手助けすることとなります。また、ウーロン茶ポリフェノールには体脂肪の燃焼や活性酸素の減少、糖尿病の抑制、美肌効果もあると言われています。また、ウーロン茶ポリフェノールには脂肪分解を促進する働きがあり、筋肉細胞に遊離脂肪酸を取り込み、エネルギー源として利用するため、烏龍茶を飲み続けると、総コレステロール値や中性脂肪が減少します。その証拠に、食事の際にウーロン茶ポリフェノールを摂取することで、食後における血中の中性脂肪値上昇を抑制する効果があるといった実験結果も発表されているくらいです。
|
| ブルーベリーとポリフェノール |
ブルーベリーにもポリフェノールが豊富に含まれています。同じベリー類であるイチゴなどにもポリフェノールが含まれているように、実はこの種に属する植物にはポリフェノールが潤沢に含まれているのです。
 ブルーベリーのポリフェノールを効果的に摂取するには、果実を皮ごときれいに食べることが一番です。ただ、その粒はかなり小さ目のものです。入手する場合は生ブルーベリーや乾燥ブルーベリーが小売店でも販売されています。ただ、ブルーベリーは好き嫌いが分かれる食品でもあります。しかし、ブルーベリーのポリフェノールはアントシアニンと言われるもので、そのアントシアニンが抗酸化作用を持つ他に目にもよいということで、多くの方に受け入れられる形態としてサプリメントなども登場しています。 ブルーベリーのポリフェノールを効果的に摂取するには、果実を皮ごときれいに食べることが一番です。ただ、その粒はかなり小さ目のものです。入手する場合は生ブルーベリーや乾燥ブルーベリーが小売店でも販売されています。ただ、ブルーベリーは好き嫌いが分かれる食品でもあります。しかし、ブルーベリーのポリフェノールはアントシアニンと言われるもので、そのアントシアニンが抗酸化作用を持つ他に目にもよいということで、多くの方に受け入れられる形態としてサプリメントなども登場しています。
ポリフェノールを効率よく体内に取り入れるためには、普段から日常的に含有食品を口にするということになりますが、ブルーベリーについてはジャムもありますし、お菓子作りなどにも用いられます。毎日バリエーションを変えることによって、継続的に摂取することが可能になるでしょう。ただし、甘味としてブルーベリーを食べる場合については、その代わりに糖分を抑えるように注意しなければなりません。糖分が過剰になってしまうと、折角のポリフェノールの抗酸化作用が台無しになってしまう上に、肥満に結びつく恐れもあるからです。
|
| リンゴとポリフェノール |
ポリフェノールは多くの種類の植物に存在しているもので、植物の多くが太陽の光を浴びて自ら栄養を作り出す光合成の過程において作り出されます。もちろん日頃からデザートとして親しまれているイチゴやミカン、リンゴなどにも当然ながらポリフェノールが含まれています。その証拠に、イギリスではリンゴポリフェノールの存在を知るはずもなかった時代から、「1日1個のリンゴは医者を遠ざける」と言われてきました。
もちろんリンゴの有効成分はリンゴポリフェノールに限ったものではありませんが、長期に渡る研究によってその詳細が明らかにされてきています。
ポリフェノールは幾つかの構成成分から成り立っています。リンゴポリフェノールにおいてはプロシアニジンというものが中心となっています。プロシアニジンは緑茶などで知られるカテキン、エピカテキンといった成分が二量、三量などというように幾つか連なっているものです。その働きとしては、他の種類のポリフェノールと共通する抗酸化作用をもちろん備えています。そして、身体に悪影響を与える活性酸素に立ち向かうSODといった抗酸化酵素の必要以上な消費を防ぐことが出来ます。また、アレルギー体質を持つ方に関して、苦しんでいるその症状を和らげる抗アレルギー作用があることも分かっています。またその他、口腔衛生作用があることも特徴です。口臭の原因となる成分として挙げられるメチルメルカプタンの発生量を抑える働きがあり、虫歯菌による歯垢の生成が防止されるのです。
|
| 参考2:より効率よくポリフェノールを摂取するために |
| ■ |
朝はコーヒー、それともお茶? |
|
コーヒーにはクロロゲン酸が含まれていますし、お茶にはカテキンが含まれていますから、どちらを飲んでもポリフェノールは摂れますが、朝食のドリンクとしてはお茶が賢い選択です。その理由は、お茶のカテキンは他のポリフェノールに比べて吸収が非常に早いという特性があるからです。 |
|
| ■ |
紅茶にはミルクを入れるか、それともレモンを入れるか? |
|
お茶に含まれるカテキンは牛乳と組み合わせるとその効力を失ってしまうという弱点があります。従って、紅茶をミルクテイにするとポリフェノールの効果は半減します。逆にレモンティーはポリフェノールの効力を倍増するベストな組み合わせと言えます。 |
|
| ■ |
大根は葉も使うか、それとも葉は捨てて根だけ使うか? |
|
大根の葉と根のポリフェノールを測定してみると、葉は根の倍以上のポリフェノールを含んでいることが分かります。よって、効率の寄りポリフェノール摂取にとっては大根の葉を捨てずに使うことが何より大切であるということになります。 |
|
| ■ |
野菜は生、それともと煮る? |
|
生より煮た方がより効果的にポリフェノールを摂取することが出来ます。従って、野菜は生で食べず、煮て食べるようにしましょう。 |
|
| ■ |
食事の時にはビール、それとも水? |
|
アルコールにはポリフェノールの溶解性を高める働きがあるので、食事と一緒にお酒を飲むとポリフェノールの腸管での吸収率が高まります。従って、食事時にお酒を飲むのはよい習慣であることになります。また、飲酒をする時は何か食べながら摂るのがよいとよく言われますが、お酒を嗜む場合は、酒の肴にはポリフェノール含有食品を選ぶとよいでしょう。 |
|
|
| 参考3:ポリフェノールのサプリメント |
現在様々な種類のポリフェノールのサプリメントが販売されています。ポリフェノールを食品から摂取するとなると、多くの量を飲んだり食べたりしなければならず、必要量に達することには難しさもあります。その点サプリメントであれば必要な栄養分を手軽に摂取することが出来るため、ポリフェノールのサプリメントは人気が高まっているのです。
女性からの人気が特に集中しているポリフェノールのサプリメントとしては、イソフラボンが 挙げられます。やはり女性ホルモンの持つ性質に共通する部分があるため、単純に栄養として補給するというだけでなく、美容面での効果を期待してイソフラボンに注目する方が多くなっています。その他、優れた抗酸化作用のあるクロロゲン酸はコーヒーに多く含まれている成分です。そのため、コーヒー生豆のサプリメントや生コーヒー豆のエキスを凝縮したサプリメントといったものも販売されています。
サプリメントを効果的に利用することで、必要とされる成分だけをピンポイントで効率的に補給することが可能となります。しかし、サプリメントを使用する場合はあくまでも補助的なものであり、基本の食生活でどうしても不足するものに限って頼るようくれぐれも注意しましょう。
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|
| 【4】赤ワインとポリフェノール |
ポリフェノールを一躍有名にしたのは赤ワインです。それというのも、赤ワインに含まれるポリフェノールには心臓病死亡率を減らす効果や痴呆症を予防する効果があることがニュース等で発表され、他にも様々な健康効果があることが分ってきたのです。
本節では、アルコールの飲み過ぎに気をつけながら、赤ワインから効率よくポリフェノールが摂取できるようアドバイスしました。
|
| 赤ワインとポリフェノール |
 昨今の赤ワインブームに火をつけたキッカケは、いわゆる「フレンチ・パラドックス」の謎解きにあったことは有名な話です。謎解きをしたのは1992年にランセットという一流学術誌に掲載された論文だそうです。 昨今の赤ワインブームに火をつけたキッカケは、いわゆる「フレンチ・パラドックス」の謎解きにあったことは有名な話です。謎解きをしたのは1992年にランセットという一流学術誌に掲載された論文だそうです。
バターや卵、肉料理などをたくさん取るフランス人は、先進諸国の中でも脂肪の消費量が多いにも拘らず、冠動脈疾患の死亡率が他国に比べてむしろ低いと言われます。これがいわゆる「フレンチ・パラドックス」ですが、論文ではこの背景として、フランスでは赤ワインの消費量がズバ抜けて高いことを指摘しました。これによって赤ワインは世界中の注目を集めることになったのです。そして、その後の長期間に渡るアルコール摂取状況と死亡率の関係を調べた疫学的研究によって、1日2〜5杯程度のワインを飲む人で心臓病による死亡率が最も低いことが分かったそうです。さらに、1日1〜3杯程度のワインを飲む人では何と癌による死亡率も低下したと言います。
|
| 赤ワインはポリフェノールのオンパレード |
ワインによる健康効果は、ワインの中でも特に赤ワインに多量に含まれるポリフェノールの抗酸化作用によることが今ではよく知られている事実です。実は赤ワインの中には、フラボノイドやアントシアニン、カテキンを始め、シンプルフェノールやタンニンなどポリフェノールのオンパレードと言ってもちいくらいの多種類のポリフェノールが揃っているのです。その理由は、原料となるブドウの果肉だけでなく、果皮や種、それに茎の一部も一緒に発酵にかけ、その後は木の樽に詰めて長期間熟成させるからです。この間に、これらの素材から色々なポリフェノールたちが溶け出し、さらに反応や結合をしたりして、別のポリフェノールが作り出されると言うのです。
ポリフェノールは抗酸化力が強く、そのため、動脈硬化の原因となる悪玉コレステロールの酸化を抑え、心臓病を防いでくれます。また、癌や老化の原因になる酸化反応は身体の中で常に起きているのですが、毎日ワインを飲めば、それを防ぐことも出来るということになります。赤ワインを飲んだ後は、身体の抗酸化力が高まって活性酸素の発生が抑えられることを示す実験結果は、日本の学者によっても既に報告され、ポリフェノールの名を世界的に知らしめる結果となりました。なお、ブドウに含まれるポリフェノールの量は意外にも種に最も多く、全体の65〜70%を占めると言われます。果皮のポリフェノール含有量は25〜35%、果肉には2〜5%と少ない量しか含まれていません。このため、果皮と種を使わない白ワインではポリフェノールの含有量は赤ワインの約10分の1程度しかなく、ロゼは半分くらいだと言います。
|
| 赤ワインの健康効果 |
| ■ |
老人性痴呆や痛風の予防にもワインが効果 |
|
心臓病や癌だけでなく、ワインは老人性痴呆や痛風の予防にも効果があることも報告されています。たとえばある研究によると、ワインを1日2杯まで飲む人では痛風になるリスクがむしろ抑えられることが分かったそうです。1日2杯以上ビールを飲む人やウイスキーなどの蒸留酒を飲む人では、お酒を飲まない人に比べて、それぞれ2.5倍、1.6倍も痛風になりやすかったそうで、それに比べたら、痛風に対するワインの効果がどれほどであるか分かるというものです。また、ビールや蒸留酒を毎日飲む習慣のある人は、飲酒しない人に比べて約1.5倍もアルツハイマー病になりやすくなりましたが、同じ酒量でもワインを飲む習慣のある人は、飲酒しない人に比べてアルツハイマー病へのなりやすさが半減するとの調査結果も報告されています。
こうした痴呆に対するワインの予防効果は、やはりワインのポリフェノールが脳内の過酸化物質を抑えるからだと考えられます。また、赤ワインには血流をよくし、血小板が固まるのを抑える働きがあります。つまり、日常的に赤ワインを飲むことは、心臓病だけでなく、ボケの予防にも効果があることは確かなようです。ただ同じ赤ワインでも、ブドウの品種や製造方法によってポリフェノールの量は変わってきます。たとえば味わいが濃く、しっかりした重みのあるフルボディーと呼ばれるワインほどポリフェノールの含有量が多いとされています。なお、ポリフェノールが特に多い品種とされているのは、フランス産ではメルローやカベルネ・ソーヴィニョン、カベルネ・フラン、イタリア産はネッビオーロ、アメリカ産ではジンファンデルなどだそうです。 |
|
| ■ |
1日2〜5杯のワインで心臓病やがんの予防効果 |
|
1日あたり2杯(アルコール量21g)以上のワインは、心臓病による死亡率を非飲酒者に比べて30〜39%も低下させると言います。また、1日当たり2〜3杯のワインは、癌による死亡率を20%、全死亡率を30%も減少させます。しかしながら、1日当たり12杯では、逆に癌による死亡率は1.6倍、全死亡率も1.4倍に上昇し、全体ではJ字型曲線となります。 |
|
| ■ |
ワインを飲んでも痛風になりにくい |
|
アルコール摂取量が月に1杯未満の人が痛風を発症する可能性を1とした場合、ビールやウイスキーでは、摂取量の増加に伴い、痛風の発症リスクも上昇します。しかし、これがワインだけは1日2杯を超えるまで、月に1杯未満の人よりも痛風の発症率が低いのだそうです。 |
|
| ◆参考3: |
アルコール分を除いてワインのポリフェノール成分のみを摂取する方法 |
|
赤ワインが身体によいと言われても、アルコールが苦手な人は残念ながら赤ワインからポリフェノールを摂取することが出来ません。しかし、ポリフェノールは安定した物質で、熱を加えても栄養成分が壊れにくいため、赤ワインを煮沸することでアルコール分を飛ばし、ポリフェノールの健康効果のみを得ることも可能なのです。もちろんアルコールが苦手ならば、赤ワインにサイダーなどを混ぜて飲むのも一法でしょうが、それ以上にワインの飲み過ぎによる健康被害を避ける意味でも赤ワインを煮立てて摂取する方法を試してみることを特にオススメします。 |
|
| ◆参考図書2 |
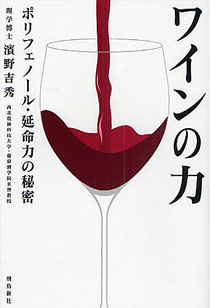 |
| ■ |
濱野 吉秀・著
(中国・西北農林科技大学葡萄酒学院名誉教授、理学博士。食品研究&開発家) |
|
『ワインの力――ポリフェノール・延命力の秘密』 |
|
飛鳥新社・107年4月刊、¥1,365 |
|
古来、ワインは薬だった。一日二杯の赤ワインで認知症を防止。(Amazonより) |
|
|
|
| 参考4:赤ワイン健康説への疑問 |
何事も過ぎたるは及ばざるがごとしです。赤ワインにポリフェノールが多く含まれ、健康にも効果的だからと言って飲み過ぎては却って心身の健康を害してしまい、何の意味もありません。
本項では、「フレンチ・パラドクス」に代表される赤ワイン神話について客観的な立場からその実際を検証してみました。
| フランス人より少ない日本人の心筋梗塞 |
フランス人の心筋梗塞による死亡率が他の欧米諸国に比べて低いことは確かです。しかし、日本人の心筋梗塞による死亡率は実はフランスよりさらに低いのです。日本では虚血性心疾患による死亡率は、人口10万人当たり60.8人(1995年)であり、フランス(84.8人)の約7割強です。フランスの虚血性心疾患による死亡率は、確かに米国の約3分の1、英国の約4分の1です。しかし死亡率だけで比較した場合、フランス人の生活習慣のよさを探して取り入れようとするよりも、フランス人よりもさらに死亡率の低い日本人の生活習慣のよさを探して、それを再認識しようと考える方が自然の成り行きなのではないでしょうか。
|
| フランス人の寿命は決して長くない |
フランス人の心筋梗塞が少ないと聞くと、直ぐにそれはとても素晴らしいことだと普通誰しも考えがちです。ところが、フランス人の寿命は欧米諸国の中で決して長くはないのです。その証拠に、たとえば1995年の統計における平均寿命は、フランス人男性が72.9才で、心筋梗塞の死亡率がフランスの3倍も多いイギリスの方が実は平均寿命が長く、74.2才だったのです。また、心筋梗塞の死亡率がフランスの2倍多いアメリカ人男性の平均寿命は72.2才で、フランスと余り差がありません。さらに、日本人男性の平均寿命は世界2位で、フランスより約4年も長く、平均寿命は76.4才です。しかもフランスでは消化器系疾患による死亡率が高く、その3分の1はアルコールつまりワインの飲み過ぎによるものです。そして、慢性肝臓疾患及び肝硬変は米国の1.5倍、他のヨーロッパ諸国の2〜3倍もあるのです。また、フランスでは精神疾患の3分1はアルコールの飲み過ぎによるもので、その殆どがアルコール依存症です。要するに、一般的な精神科の入院患者の約4割はアルコール依存症だという驚くべき実態があるわけです。ちなみにフランスでは、交通事故死の9%、他の事故死の7%、自殺の8.5%がアルコールの飲み過ぎによるもので、トータルのアルコール乱用死は年間3〜6万人と推定されています。とにかく、東洋人に比べてアルコール分解酵素の働きが活発で体質的にアルコールに強いフランス人にこのようにアルコールによる障害が特に多い事実に目を向ければ、欧米人に比べて体質的にアルコールに弱い日本人がフランス人並みに過剰にワインを摂取するようになれば一体どんな健康被害が生じるか、考えるまでもなく明らかだと言ってよいでしょう。そんな訳で、ワインを礼賛する人は、ワインをよく飲む人に虚血性心疾患が少ないことだけを取り上げて、必ずしもそれが寿命を延ばしているわけではないことに目を塞いでいる、ないしはそんなことに関心すら寄せていないのだと言ってもよいかも知れません。
もちろんワインのポリフェノールが心筋梗塞の発症を下げることは事実ですし、認知量の予防に効果があるのも事実です。しかしながら、ワインの飲み過ぎが他の病気を増やす結果となり、その結果として死因の順位が入れ替わるだけで、それが決して寿命を長くするようなものではない可能性も高いわけです。だから、心筋梗塞も少なく、寿命の長い日本人の生活習慣の中から、そのよいところを見つけ出して、それを大切にすることの方が本当に科学的と言えるのではないでしょうか。
|
| 赤ワインの色と渋み |
白ワインに対して赤ワインを特徴づけるのはその色合いと渋みです。この色合いや渋みをもたらすものは主にブドウの果皮や種子に含まれているフェノール類、特にフェノール類の中でベンゼン環についた水酸基が二つ以上あるもの、つまりポリフェノールと呼ばれる植物成分群です。ポリフェノール類は空気(酸素)に触れると酸化しやすく、たとえばブドウの果汁や皮を剥いたリンゴが茶褐色になりやすいのも、ブドウやリンゴに含まれるポリフェノール類が酸化されて起こる現象です。そして、ポリフェノール類の中でアントシアニンと呼ばれる一群の化合物が、赤色や紫色、青色などのもとになるものです。そして、赤ワインの保存中にアントシアニンが重合したり、カテキンなど他のポリフェノールと結合したりすると、赤ワインの色はくすんだ色合いに変わってゆきます。一方ポリフェノール類の中で渋みのもととなっているのがタンニンです。ワインが新酒のうちはタンニンは殆ど溶けていますが、貯蔵中にタンニンが互いに結合し、大きな分子になってゆきます。そのため、ワインは新酒では渋みが強く、次第に渋みが弱まってゆくのです。
赤ワインの製造に携わってきた人々は、如何に美しく、如何に美味しいワインを作るかに苦心してきました。そのために使った有力な2つの方法が二酸化硫黄の添加とオリ下げ処理でした。まず二酸化硫黄は酵母を殺さず、雑菌を殺し、ポリフェノール類の抽出を促し、その酸化を防ぐのです。そしてオリ下げ処理は、ポリフェノール類が赤ワインに多くなりすぎると渋みが強くなりすぎたり、瓶詰め後に沈殿物が多くなるので、適当なところまでポリフェノール類を沈殿除去することです。古くは卵白を加えたり、現在はゼラチンを加えて沈殿物を濾過処理しています。つまり、適度の色と渋みが赤ワインの命なのであって、ワインにとってはポリフェノール類が多ければよいというものではないのです。そんな訳で、「ポリフェノールが多いほどいい赤ワインだ」などと言っているのは、物事の一面しか見ない人の発言だと言ってよいでしょう。
|
|
| 参考5:酒の効用はあくまでも適量の範囲内で |
| ■ |
過ぎたるは及ばざるがごとし |
|
「酒は百薬の長」と言うように、飲酒の健康効果については既に20年以上も前から様々な研究報告ななされています。その証拠に、疾患などによっては相反する結果も見られますが、特に心血管系疾患の予防効果は幾つもの大規模な追跡研究で裏付けが得られています。ただし、くれぐれも勘違いしてはならないことですが、その何れも「1日1合前後」の飲酒においての話だということです。何事も「過ぎたるは及ばざるがごとし」で、飲みすぎは禁物です。 |
|
| ■ |
飲まない人よりも少し飲む人で最も死亡率が低い |
|
全死亡率(全ての死因による死亡率)は、全くお酒を飲まない人よりも、1日34gまでのアルコール摂取量(日本酒では約1.5合)の人の方が低いそうです。しかし、アルコール摂取量が1日34gを超えると再び死亡率は上昇し、全体ではU字型曲線となると言われます。(※ただ心血管系疾患に限って言えば、大量飲酒者の方が全く飲まない人よりも死亡率は低いそうです。) |
|
| ■ |
痩せ型の男性が酒を飲むと糖尿病になりやすい |
|
対象者をBMI毎に分けて飲酒量と糖尿病の発症リスクの関連を調べた研究によると、BMIが22以下の痩せ形の男性では、飲酒量が1日1〜2合の場合に、糖尿病の発症リスクが酒を飲まない人の約2倍に、1日2合以上の場合は約3倍に上昇したと言います。その一方でBMIが22を超えた男性では、お酒の量が増えても糖尿病の発症リスクは変わらなかったそうです。 |
|
※注:BMI(ボディー・マス・インデックス):その人の体重(kg)を身長(m)の二乗で割った数字。日本では25以上が「肥満」と判定される。 |
|
| ■ |
酒を飲む女性の急増とアルコールによる肝障害 |
|
ここ20年の変化をみると、男性の飲酒人口が数%しか変わっていないのに対して、女性の飲酒人口は何れの年齢層でも2倍以上と著しく増加していると言います。最近の傾向は不明ですが、さらに女性の飲酒人口が増えている可能性もあると言います。そして、アルコール性肝障害で入院する患者数はここ数年ほぼ横ばいで推移しているものの、女性の占める割合は約10%から約20%へと増加しているそうですが、その一方で男性は減少する傾向にあるとも言います。これは、女性の方が男性よりも少ない飲酒量及び短い飲酒期間で肝硬変になりやすい結果を現していのではないかと推察されます。 |
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|



