| 【1】クリスマスの起源と歴史 |
クリスマスとは本来、この世の救い主(メシア)であるイエス・キリストの誕生を祝うキリスト教のお祝いの日です。本来の意味を逸脱して年末の風物のひとつになっています。
本節では、そのクリスマスの起源と歴史についてなるべく詳しく取り上げ、解説しました。
|
| クリスマスとは? |
| メリー・クリスマスとはどういう意味? |
メリーとは、「楽しい」とか「愉快な」という意味で、英語ではMerryと書きます。つまりメリークリスマスとは、分かりやすく訳して言えば「楽しいクリスマスを!」という意味でなのです。たとえば「I
wish you a Merry Christmas!」とか「A Merry Christmas to you!」(楽しいクリスマスがありますように!)とも言います。日本的に言えば「クリスマスおめでとう!」といったところでしょうか。
|
| クリスマスって本当は何の日? |
クリスマスとは本来イエス・キリストの降誕記念日を祝うキリスト教の行事を言います。
クリスマスは英語ではChristmasと書きますが、これは「キリスト(Christ)のミサ(mass)」という意味を持っています。一方、X'masと書く場合のXは、ギリシア語のキリスト(クリストス)ΧΡΙΣΤΟΣの第1字を用いた書き方で、この場合はXの一文字でChrist(キリスト)を代用しているわけです。なお、他の言語で言えば、フランス語のノエル(Noel)
とイタリア語のナターレ(Natale)は共に誕生日を意味するラテン語から来ています。また、ドイツ語ではWeihnachtとも呼ばれ、これは「聖夜(キリストが生まれた夜)」という意味があります。また、12月25日をクリスマス・デー、その前夜をクリスマス・イブ、クリスマスから公現祭(1月6日)の前日(※時には1月13日または聖燭節=2月2日)までを特に降誕節(
Christmastide)と呼ぶこともあります。ちなみに12月24日はクリスマス・イブですが、イブ(Eve)とは「前夜」を意味します。 これで分かる通りクリスマスとはイエス・キリストが約2000年前にこの世に生まれたことをお祝いするキリスト教のお祝いの日なのです。
|
|
| クリスマスの起源 |
キリスト教の聖典である新約聖書には、処女であったマリアが神の霊に満たされてイエスを生んだ処女懐胎の話が書かれています(『マタイによる福音書』1:18〜25、『ルカによる福音書』1:26〜38など)。しかし、その日がいつかということは何も語られていません。このため、初期のキリスト教徒は1月1日や1月6日、3月27日などにキリストの降誕(誕生を神聖視する表現)を祝しましたが、教会として正式にクリスマスを祝うことはなく、たとえば紀元3世紀の神学者オリゲネスはクリスマスを定めることは異教的であるとすら非難しているくらいです。クリスマスが12月25日に固定され、本格的に基督の誕生が祝われるようになるのは教皇ユリウス1世(在位337〜352年)の時であり、同世紀末にはキリスト教国全体でこの日にクリスマスを祝うようになりました。長い議論の末にクリスマスが12月25日に固定されたのは初期教会の教父たちの体験と英知とによるものであったと言われます。
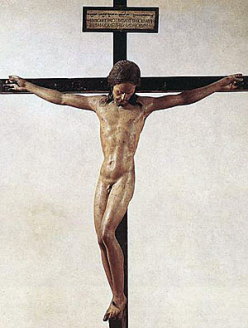 この時期に大きな祭りを行なうことは古い時代の社会の慣習でした。中でも揺籃期のキリスト教会が改宗を願っていたローマ人やゲルマン人の間には、冬至の祭が盛大に行なわれていました。納屋には収穫した穀物がたっぷりと積まれ、牧草の欠乏する冬を控えて環殺した家畜の肉も充分に貯蔵されているこの時、そして、1年の厳しい労働から解放され、何となく心豊かなこの時期、人々はやがて訪れる食糧不足の時をひと時でも忘れて、飲んだり食べたりの盛大な祭りを行ないました。生命の恵みを与える太陽の力を弱め、冬をもたらす自然の怒りを和らげるために、人々は神に生け贄を捧げ、豊作と豊穣を祈って火を焚きました。そして、大方の草木の枯れる時になお緑を保つ常緑樹は永遠の生命の象徴として飾られたのです。 この時期に大きな祭りを行なうことは古い時代の社会の慣習でした。中でも揺籃期のキリスト教会が改宗を願っていたローマ人やゲルマン人の間には、冬至の祭が盛大に行なわれていました。納屋には収穫した穀物がたっぷりと積まれ、牧草の欠乏する冬を控えて環殺した家畜の肉も充分に貯蔵されているこの時、そして、1年の厳しい労働から解放され、何となく心豊かなこの時期、人々はやがて訪れる食糧不足の時をひと時でも忘れて、飲んだり食べたりの盛大な祭りを行ないました。生命の恵みを与える太陽の力を弱め、冬をもたらす自然の怒りを和らげるために、人々は神に生け贄を捧げ、豊作と豊穣を祈って火を焚きました。そして、大方の草木の枯れる時になお緑を保つ常緑樹は永遠の生命の象徴として飾られたのです。
ユールというゲルマン人の冬至の祭について詳しいことは分かっていませんが、古代ローマ人の冬至の祭については詳細な記録が文学や絵画、彫刻などに残っています。すなわち、12月25日はローマの冬至の当日であったのです。その日は「征服されることなき太陽の誕生日」として、紀元3〜4世紀の古代ローマに普及していたミトラス教の重要な祭日でもありました。さらに12月17日〜24日まではサトゥルナリアと呼ばれる農耕神サトゥルヌスの祭が行なわれていました。この期間、家々には赤々と火が点され、常緑樹が飾られました。贈物が交換され、男たちは女の衣服や獣皮などを纏い、普段は禁止されていた賭け事に興じたりもしたのです。また、主人と奴隷が席を交換するどんちゃん騒ぎなども行なわれたと伝えられます。このようなローマのサトゥルナリアとゲルマンのユールの祭の時期がイエスの降誕を祝うクリスマスとして選ばれたのです。教会は既存の祭日を出来る限り利用することを考えていたからです。特にミトラス教はキリスト教の強敵でした。そんな中、キリスト教と類似点の多いミトラス教との習合を考えたコンスタンティヌス1世は、紀元321年に毎週の休日を「太陽の日
(dies solis=sun day)」と呼ぶことに決めました。クリスマスについても教会の同一の方針を見ることが出来る上、当時キリスト教徒の間にもイエスをこの世の光=太陽と考える習慣があったようで、その証拠に、たとえばミラノ司教アンブロシウスは「我が主イエスの降誕したこの聖なる日を『太陽の誕生日』と呼ぼう」と述べています。
もっとも、クリスマスがいつごろから祝われたかは不明です。初期の東方教会の人々は公現祭(1月6日)をキリスト受洗の日、その神性顕示の日として祝いました。彼らはアリウス派の人々で、イエスの受洗を重視し、降誕(誕生)そのものには余り意味を認めない人々だったからです。イエスの神性を降誕の時からと考えてこれを信じる正統派のキリスト教徒(ローマを中心とした西方キリスト教=後のローマ・カトリック教会)は彼らを異端と考えるようになりました。325年のニカエア公会議による東方教会に対する異端宣告とほぼ同時期に西方教会がクリスマスを12月25日に定めたのは、自分たちが異端として退けた東方教会との区別を明確にするためでもあった可能性も一部では指摘されています。そんな訳で、ローマでクリスマスが12月25日に祝われたのは336年以前であったことはほぼ確実です。もちろんこの日が決定するまでには様々な意見が出されました。たとえば12月末はイエスの生まれたパレスティナ地方は雨季に当たり、羊飼いは野に出ていませんし、また、この時期に大規模な人口調査が行なわれた(『ルカによる福音書』2:1〜3)という文献もありません。全てこんな風で、学者たちは別の根拠からクリスマスを推定しようとしましたが、何れの見解も充分に説得的なものではありませんでした。こうしてクリスマスは12月25日に固定されました。数世紀の間、異教の慣習はなお強く残り、教会はこれを懸念しながらも、キリスト教の教義と明確に矛盾しない限りこれを根絶することなく、同化及び習合の方針を取ったのです。
| ◆ |
イエス・キリストは本当に12月25日に生まれたの? |
|
イエス・キリストの誕生日に関する記録は残されていないため、イエスの誕生の正確な日付は分かりません。そこで、詳しくは次の項で書きますが、初期の頃は色々な日にイエスの誕生(降誕)を祝ったと言われています。それが次第に12月25日にイエスの誕生を祝うようになり、紀元4世紀に12月25日がイエスの誕生日であることが確立したのです。
また、ローマでは12月の冬至に太陽を祭るお祝いを盛大に行なっていました。ご存知の通り北半球で一番昼が短くなるのが冬至で、それまで次第に短くなってきた昼がこの日を境にまた長くなってゆくわけですが、要するに勢いの弱まってきた太陽が冬至に再び力を取り戻し、光が甦るということを当時の人々は祝っていたのです。そして紀元273年になると、時のローマ皇帝アウレリアヌスは12月25日を太陽神の誕生日と定めました。それに加えて、キリスト教ではイエス・キリストは「正義の太陽」とか「世の光」と呼ばれていることから、当時の教会はこの祭日を利用して336年にイエス・キリストの誕生を祝う日と定めたと言われています。 |
|
|
| クリスマスの変遷 |
それでは、古代以降クリスマスは一体どのようにして民衆に浸透していったのでしょうか?
本項では、主にイギリスを例として今日に至るクリスマスの歴史的変遷を解説しました。
| 中世におけるクリスマス |
597年、カンタベリーのアウグスティヌスがイギリス伝道を開始した時、クリスマスはローマ・カトリック教会の3大祝日のひとつになっていました。そして、アウグスティヌスはその翌年のクリスマスに1万人以上のアングロ・サクソン人に洗礼を施したと言います。ちなみに、約1世紀後にベーダという人は、この日が元々「母たちの夜」と呼ばれ、母なる女神の祝日だったと述べています。人々は改宗してもなお寛大な教会の配慮により異教の祭りを楽しんでいたのです。彼らは常緑樹を飾り、ユールの丸太を燃やし、仮面劇や呪い歌を誦し、踊りに興じました。このようにしてイギリスのクリスマスはユールと降誕節の習合として成立し、アングロ・サクソン暦はこの日から新年を数えることとなりました。そして、この慣習は中世末まで残りました。また、アルフレッド大王はクリスマスから公現祭(1月6日)までを「聖なる期間」と定め、労働を禁じました(王が878年デーン人に一時敗退したのはこのためであると言われています)。また、上記の期間がキリスト教会で正式に聖なる期間と定められたのは567年のトゥールの公会議においてです。また、クリスマスという用語は『アングロ・サクソン年代記』の1043年の項で初めて使用されています。それ以前は冬至祭または降誕を意味する
Nativity の語が使用されていました。(※なお、アングロ・サクソン人のキリスト教化はデーン人の侵寇によって遅滞ないし後退しましたが、11世紀のノルマン・コンクエスト〔※ノルマンディー公ギヨームによるイングランドへの征服〕までにはほぼ完成したと言われています。)
|
| 宗教改革以後におけるクリスマス |
ヘンリー8世とエリザベス1世の時代にもクリスマスはイングランド教会(アングリカン・チャーチ=英国国教会・聖公会)の3大祝日のひとつとして祝われていました。当時の文学作品などによると、クリスマスは神に感謝を捧げる時、正真正銘の喜びの時、友人や親戚との旧交を温め、貧しい隣人を歓待する時でありました。この時代は宮廷生活の華やかさに比して地方では貧富の差が激化し、過去の人間関係の絆が破綻し始めた時代でした。その証拠に、「クリスマスには貧しい隣人を歓待するように」という文言が著述家たちによって特に強調されています。また、エリザベス世とジェームズ1世は「故郷の人々を歓待するように」と言って、クリスマスには廷臣たちを帰省させたと言います。そして、地方自治体は貴族やジェントリにこの歓待を義務づけました。特に凶作の年にはそれが地方の治安維持にとって重大な役割を果たしました。たとえば1627年のクリスマスに、イギリスに亡命して来たフランスの新教徒救済のため、ロンドン主教に対して枢密院は主教区全体から寄付金を集めるように命じ、古きよき時代のクリスマス精神を懇請したのです。
|
| ピューリタン革命時代におけるクリスマス |
王党派とイングランド教会は楽しい伝統的慣習を象徴する日としてクリスマスを祝っていました。しかし、謹厳なピューリタンはこの日をローマ・カトリックの祝日として非難し、暴飲暴食やダンス、賭け事、乱ちき騒ぎその他諸悪に結びつく祭日として攻撃しました。たとえばそれ以前、『諸悪の解剖』(1583念)の著者
P. スタッブズは、劇場や演劇を誹謗し、仮面劇を装って盗みや売黒・殺人などがクリスマスほど横行する時期はないと記しました。17世紀のあるピューリタンは「クリスマスは主イエスの降誕を祝う日ではなく、酒神バッカスの祭りだ。異教徒はこれを見て、イエスは貪食な享楽主義者の大酒飲みで、悪魔の友人と思うだろう」とこれを嘆きました。
もちろん穏健派はゆきすぎを是正するに留めるつもりでしたし、議会もクリスマスに干渉する気はありませんでした。ところが1644年、スコットランドの長老派教会の圧力によって彼らも態度決定を迫られたのです。長老派は1583年にスコットランドでクリスマスを完全に禁止しました。その後、王の命令によってクリスマスは一時復活しましたが、彼らは再びこれを禁止しました。議会派の指導者たちは長老派のクリスマス禁止の要求をイングランドで実施することを拒んだのですが、それは議会派の支配する地域でのみ効果を収めただけで、ついに議会派も長老派の要求に屈服せざるを得ませんでした。こうして1647年、長老派の圧力の下、議会派はクリスマス禁止法案を可決しようとしたのですが、この時これに反対する暴動が各地に起こり、強硬な長老派にしても、家庭でのクリスマスをついに認めざるをえなくなったのです。
|
| 王政復古(1660)以後におけるクリスマス |
こうしてクリスマスは再び教会の3大祝日のひとつとなり、人々はこれを自由に祝うことが出来るようになりました。しかし、社会経済上の変化はかつて田舎の地主邸で繰り広げられた伝統的クリスマスの相貌を変え、素朴な人々のどんちゃん騒ぎも廃れて、次第に宗教心も薄れてゆくことになりました。この変化はゆっくりと、かつ不均等に進行しました。クリスマス休日が制定され、大学・学校・裁判所・議会はクリスマスから公現祭までを休日とし、官公庁はこの期間の数日を、多忙な部署はその一部を休日としました。また、一部の人々は聖燭祭(2月2日)までをクリスマスと考えました。ところが19世紀になると、産業革命の余波を受けて労働条件は極めて過酷となり、クリスマス休日は当日だけとなってしまったのです。もちろんクリスマスは富裕な家庭では華やかに祝われたのですが、一般にはこれを祝う費用のない人々が増大し、クリスマスはいよいよ死滅するかに見えました。
|
| ビクトリア時代におけるクリスマス |
そんな中、19世紀中葉にクリスマスが復活しました。それはチャーチスト運動の時代であり、大英帝国の威光が最も拡大された時期でした。新しいクリスマスでは隣人愛と慈善が重視され、宗教心の復活による宗教的側面の補正が行なわれ、その上に古い時代の賑やかな祭りの慣習が輝きを添えたのです。特にクリスマスが子どもを中心とする家族の祭りとなったことがこの時代の特徴であると言えます。クリスマス・ツリーやサンタクロース、クリスマス・カードが導入され、クリスマス・キャロルが復活し、クリスマス・プレゼントやクリスマス・ディナーが庶民の家庭に進出しました。今日見るクリスマスはこの時から始まったと言ってよいでしょう。
新しいクリスマスの成立に大きく寄与したのはビクトリア女王の夫君アルバート公と C・ ディケンズです。アルバート公はドイツからクリスマス・ツリーの習慣をウィンザー城の家庭クリスマスに持込み、ディケンズは『クリスマス・キャロル』を始め幾つかの文学作品を刊行し、クリスマスの楽しさや陽気さを伝えると同時に、クリスマスのあるべき姿、物質的楽しみを享受するために果たさねばならない慈善などの義務を教えました。新しいクリスマスは急速に浸透し、空論家や反対論者もこれを認めざるを得なくなり、非国教徒も子どもたちが友人仲間の楽しみの輪に入るのを阻止することが出来なくなりました。たとえば彼らの礼拝堂の一部は、自分たちの会員が国教会に流れ始めたのを見てクリスマス礼拝を開始したくらいです。こうして非国教徒の態度も軟化し,イギリス国民が新しいクリスマスを祝うようになった。こうした趨勢に応じて、短縮されていたクリスマス休日もボクシング・デー(※BoxingDay=クリスマスの翌日で、この日に使用人や郵便配達人などに祝儀の贈物を与える)まで延長されるようになりました。それは銀行や官庁のみならず、19世紀末までには一般の商工業従事者にも拡大されました。こうして、根治に見るような形の「みんなで祝う楽しいクリスマス」が成立したのです。
|
|
| 日本におけるクリスマス |

日本におけるクリスマスの風習は明治以降に広まります。
教会や在日外国人の手を離れ、初めて日本人によってクリスマスが祝われるのは1875年頃のことで、原胤昭が設立した銀座の原女学校においてであったと言われています。明治10年代には丸善がクリスマス用品を輸入し、この頃から大正期にかけてクリスマスは次第に一般家庭でも祝われるようになってゆきます。また、クリスマスの語は俳句の季題にも取り入れられ、たとえば正岡子規にも《クリスマスの小き会堂のあはれなる》の句があります。こうしてクリスマスの風習は日本人の生活に定着してゆきますが、宗教的側面が次第に軽んじられ、商店の歳末売出しに利用される傾向も強まってゆくことになります。
|
| 参考1:クリスマスについての参考図書 |
| ◆参考図書1:クリスマスについての参考図書 |
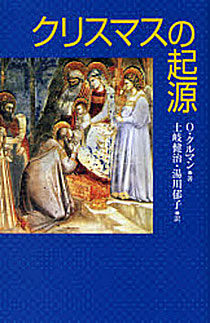 |
| ■ |
O.クルマン・著(新約聖書学者)
土岐健治+湯川郁子・訳 |
|
『クリスマスの起源』 |
|
教文館・06年11月刊、1,575円 |
|
紀元3世紀まで12月25日はクリスマスではなかった。何故12月25日がクリスマスになったのか? キリストは何月何日に生まれたのか? クリスマスツリーを飾るのは何故か? クリスマスツリーの本当の起源は? ……数々の疑問に分かりやすく答える。 |
|
|
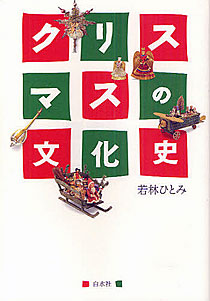 |
| ■ |
若林 ひとみ・著(クリスマス研究家、フリーライター) |
|
『クリスマスの文化史(新装版)』 |
|
白水社・10年11月刊、2,100円 |
|
サンタクロースって誰なの? クリスマスツリーは何故飾るようになったの? 多数の図版と共にその由来を説き明し、本場ドイツのクリスマスを中心に紹介します。 |
|
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|
| 【2】サンタクロースの起源とその特徴 |
クリスマスと言えばサンタクロースと相場が決まっています。では、そのサンタさんにモデルとなる人物がいたことをご存知でしょうか?
本節では、サンタクロースの起源や特徴を簡単に取り上げ、解説しました。
|
| サンタクロースの起源 |
クリスマス・イヴの夜に、良い子の許へこっそり現われてプレゼントを置いてゆくサンタクロース。その起源は紀元4世紀頃まで遡り、リキュア(現在のトルコ辺り)のミラという町に生まれた聖ニコラウス(ミラのニコラオス)の伝説がもとになっています。キリスト教の司祭で神学者でもあったニコラウスは、貧しい人や子どもたちを助けたことで多くの人に慕われ、後に聖人とされて、聖ニコラス(ミラのニコラオス、Saint
Nicholas)のと呼ばれるようになり、子どもや学問、海運などの守護聖人としても崇敬されるようになりました。
ある日のこと、ニコラウスは、町に貧しくて娘をお嫁に出すことが出来ない家があるのことを知りました。そこで彼は、真夜中にこっそりとその家を訪れて、煙突から金貨を投げ入れます。このとき暖炉のそばには靴下が下げられていて、金貨はちょうどその靴下の中に入りました。そして、その金貨のお陰で娘は身売りから逃れ、無事お嫁に行くことが出来たのです。後にこの逸話が世界中に広まって、「サンタクロースは真夜中に煙突から入って来て、靴下にプレゼントを入れてゆく」というお馴染みのサンタクロース像が出来上がりました。ちなみに、サンタクロースの赤い衣装も聖ニコラウスの着ていた司祭服が下になっていると言われます。
なお、聖ニコラスはカトリック教会によってクリスマスのお祝いと結び付けられるようになってゆくのですが、まずそれはオランダで続き、17世紀になってオランダ人がニューアムステルダム(今のニューヨーク)を建設した際、その伝統もいっしょにアメリカに渡りました。オランダ語でSinterklaasと呼ばれていたのが英語的な発音に直されて、Santa
Claus、すなわちサンタクロースとなったのです。そして19世紀に入ると、サンタクロースが夢物語に仕立てられ、トナカイのソリに乗ってやって来て、煙突から入って来る、といったイメージがつけられました。もっとも、「サンタクロースは子どもたちに夢を与えるから」とはいうものの、今ではイエス・キリストではなくサンタクロースがクリスマスの主役となり、さらにクリスマス商戦に利用されている実情です。こうして、本来のクリスマスの意味が失われてゆくのは、真面目なクリスチャンにとっては非常に残念なことでしょう。
|
| サンタクロースの衣装 |
 初めて赤い服のサンタクロースが登場したのは1849年のことです。それは、米国の大学教授クレメント・C・ムーアの詩「クリスマスのまえのばん」
(A Visit from St. Nicholas) の挿絵で、描いたのはテオドア・C・ボイドという人でした。また1862年には、同じ詩に触発されたトーマス・ナストという風刺漫画家が「ハーパーズ・ウィークリー」等でサンタクロースのイラストを描き、それが「赤い衣装に白髭の太ったニコニコ顔のお爺さん」という現代のサンタクロース像の元になったと言われています。また、現在お馴染みのサンタクロース像が日本で定着したのは1900年代初頭のことで、子供雑誌にイラストが掲載されるようになったからだと言われます。 初めて赤い服のサンタクロースが登場したのは1849年のことです。それは、米国の大学教授クレメント・C・ムーアの詩「クリスマスのまえのばん」
(A Visit from St. Nicholas) の挿絵で、描いたのはテオドア・C・ボイドという人でした。また1862年には、同じ詩に触発されたトーマス・ナストという風刺漫画家が「ハーパーズ・ウィークリー」等でサンタクロースのイラストを描き、それが「赤い衣装に白髭の太ったニコニコ顔のお爺さん」という現代のサンタクロース像の元になったと言われています。また、現在お馴染みのサンタクロース像が日本で定着したのは1900年代初頭のことで、子供雑誌にイラストが掲載されるようになったからだと言われます。
なお、サンタクロースの衣装の元になったのは、キリスト教の司祭服だと言われています。それも当然の話で、サンタクロース像の元になった聖ニコラウスがキリスト教の司祭だったからです。ちなみに、司祭服の色は季節や祝日によって変わり、カトリック教会では赤の衣装はイエスの受難日や聖人のための祝日に、正教会では十字架に関連する祭や致命者の記憶日、復活大祭の祭期に着用するとされています。
|
| 参考2:コカ・コーラとサンタクロースの関係 |
一説には、誰もが知っているあのサンタクロース像は実はコカ・コーラの広告から生まれたと言われています。その説によると、コカ・コーラ社のコーポレート・カラーはサンタクロースの衣装と同じ赤と白であり、サンタクロースの衣装はコカ・コーラの広告に由来するというのです。詳しくその説を紹介すると、――
コカ・コーラの広告にサンタクロースが最初に登場したのは1930年頃のことで、それまでのサンタクロースは緑の服を着ていたり妖精の姿をしていたりして、必ずしも特定のイメージを持っていませんでした。そこでコカ・コーラ社の広告担当者が描いたのが、赤と白(コカ・コーラの色)の衣装を着て、白髭に笑顔を浮かべたお爺さんでした。コカ・コーラ社は長年に渡ってこのサンタクロースを広告に登場させ、コーラの人気と共に「赤い服のサンタクロース像」を世界中に定着させた、
というのです。
しかしながら、信憑性がありそうに見えながら、この説は俗説です。その証拠に、米国コカ・コーラ社の広告にサンタクロースが初めて採用されたのは1931年のことで、しかもこの時には遠く離れた日本ですらサンタクロースのあのお馴染みの姿が既に確立されて十数年が経過していたからです。なお、日本での最初のコカ・コーラ輸入は1914年頃でしたが、間もなく販売中止となり、再度上陸したのは戦後の1949年になってからです。従ってコカ・コーラを手にしたサンタクロースが日本で紹介されたのは1949年以降の戦後のことなのです。
|
| 参考3:サンタクロースは実在する!?〜今年もサンタクロース追跡大作戦開始!〜 |
| ■ |
サンタ追跡!?〜サンタカメラの映像 - NORAD - |
|
2010年12月24日、サンタクロースが世界中の子どもたちにプレゼントを配るため、北極を出発します。サンタさんを乗せたトナカイのソリは新幹線の100倍とも言われる超高速で飛び回わっています。その姿はとても肉眼で確認することは出来ませんが、クリスマス・イヴにだけ世界中に設置されるNORADのサンタカメラなら、サンタさんとトナカイの姿をしっかりと捉えることが出来るかも知れません。
クリスマス・イヴの当日、公式サイト「NORAD Tracks Santa」【http://www.noradsanta.org/jp/home.html】では、現在のサンタクロースの位置とサンタカメラが捉えた動画を見ることが出来ます。 |
|
http://www.noradsanta.org/ja/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 参考4:サンタクロースについての参考図書 |
| ◆参考図書2:サンタクロースについての参考図書 |
 |
| ■ |
パラダイス山元・著&監修(公認サンタクロース) |
|
『サンタクロース公式ブック〜クリスマスの正しい過ごし方〜』 |
|
小学館・07年10月刊、1,500円 |
|
本物のサンタさんが正しいクリスマスを紹介。グリーンランド国際サンタクロース協会が認定したアジア地域初のただ1人の日本人サンタクロースがお届けするクリスマス・アドバイス・ブック。如何に家庭で心豊かなクリスマスを過ごすか、そのアイデアを紹介します。 |
|
|
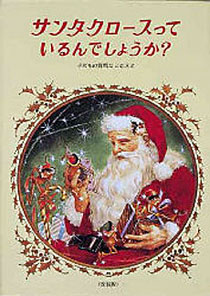 |
| ■ |
フランシス=P=チャーチ・著
中村妙子・訳、東逸子・画 |
|
クリスマスの絵本『サンタクロースっているんでしょうか?』 |
|
偕成社・1986年10月刊、840円 |
|
サンタクロースっているんでしょうか? そんな質問にピタリと答えた人がいます。今から90年ほど前のアメリカのニューヨーク・サンという新聞に出た社説です。この本はその社説を訳したものです。さあ、サンタクロースって本当にいるんでしょうか? |
|
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|



