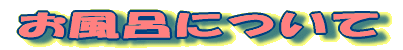| �y�P�z���{�l�̕��C�D���̂��̗��j |
�@���{�l�Ƃ����C�͐��Ă���Ȃ��W�ł��B
�@�{�߂ł́A���̂����C�̗��j�₨���C�ɗR������l�X�Ȏ����ɂ��ĊȒP�ɏЉ�E������܂����B
|
| ���{�̂����C�̗��j |
�@���{�͑S�����鏊�ɉ��N���Ă��܂��B���Ƃ��Έɓ��̒n���́A���N���o��Ƃ��납��u���C�Y���v�ƌĂ�A���ꂪ����ɏk�܂��āu�C�Y�v�Ɠ]�������ƌ����Ă��܂��B�܂��A���͌��̒n���́u���̗��ސ쌴�v�̈Ӗ��������ł��B�Ƃɂ����A�̂�����{�l�͉����Ε��C(�����R�̊�A�𗘗p�������C���̂����C)�Ȃǂɓ������Ă��������ł��B�܂��A�����C�̗��j�͂U���I�ɕ������`���ƂƂ��ɒ�������`����Ă����ƌ����Ă��܂��B�����ł́u�����C�ɓ��邱�Ƃ͎��a�������A������������v�Ɛ�����Ă������Ƃ���A�����C�ɓ��鎖�͌��N�ɂ悢�Ɨ�������Ă��܂����B�ȗ��A���@�ł͐g�̂��߂�Ƃ�����ȋƂ̂ЂƂƂ��ė�������������悤�ɂȂ�A�����̂Ȃ������ɂ��������{�������Ƃ���A�����C�ɓ���Ƃ����K�����n�܂����̂������ł��B���Ƃ��Α啧�l�ŗL���ȓ��厛�ɂ́A�����̊w�m��m���̐S�g�𐴏�ɂ��邽�߁A���@�Ƃ��Ďn�߂Ă̓���������܂����B1282�N�ɍ��ꂽ�Ƃ���錻������ŌÂ̗����A���厛�̑哒���́A��1000���b�g���̑劘�ł��������A�S���D�ƌĂ�闁���i2000�`3000���b�g���j�ɂ������������鋋���������̗p����Ă����ƌ����܂��B�܂��A��������ɂ����ẮA�㗬���Ƃ̓����͕��ʂP�����ɂS�`�T���������ŁA���̓��͍s�������Ă����Ƃ���Ă��܂�����A���Ȃ��Ƃ��㗬�̌��ƒB�͂Q�`�R�������ɂ����C���g���Ă������ƂɂȂ�܂��B���Ƃ��w�����L�x�ɂ́A����R�N�i1231�N�j�Ɋ֔��������Ɛe�q���A�����̕ʑ��ɗL�n�̓������Ԃ�200�����^���ē������Ă����Ƃ����L�q������̂������ł��B����ɍ]�ˎ���ɂ́u��a���v�ƌ����āA�M�C�̓���l�����S���ō]�ˏ�܂ʼn^��ł����Ƃ������܂��B
 �@���āA�]�ˎ���܂Łu�����C�v�Ɓu���v�͋�ʂ���Ă��܂����B�����C�Ƃ́A���ɓ������A���̏��C�𗁑����ɑ��荞�݁A�M�������C�ɂ��g�̂̍C���オ�点�āA�K���Ȏ��ԂɎ��O�ɏo�č��̗t�ȂǂŐg�̂�@�����蕏�ł��肵�čC�𗎂Ƃ��A�߂��ɗp�ӂ����ʂ�ܓ���␅�Őg�̂��[���ɐƂ������̂ŁA����œ��Ƃ́A������ʂ̉ƕ��C��K���Ɠ����ł������̂������ł��B�܂��A�܉E�q�啗�C�Ƃ́A���܂ǂ�z���Ċ����悹�A���̏�ɉ������t���A����W�Ƃ��A���̔ݒ��߂ē������܂��B�܉E�q�啗�C�̖��O�̗R���́A�L�b�G�g���ΐ�܉E�q�����䥂ł̌Y�ɂ����Ƃ����������琶�܂ꂽ���̂ł��B�Ȃ��A�܉E�q�啗�C���ꂪ�S���Ȃ̂ɑ��Ē��B���C�͑S�̂��S���ŁA���݂ł͒��B���C���܉E�q�啗�C�Ƃ��Ĉ�ʓI�ɌĂ�Ă��܂��B���B���C�́A�傫�ȓS�̓����������ŁA����ɕʂ̓S���łǂ�ǂ����A���̂����𗁑��ɉ^�ѓ��ꂽ��A���Ȃǂ𗘗p���ė������݁A�K���ɐ��𒍂��œ����������ē������܂��B����ł͌܉E�q�啗�C�Ɠ����悤�ɉ�������M���āA�������܂��B�܉E�q�啗�C�Ƃ̈Ⴂ�́A�̉������邩�Ȃ����������Ƃ���Ă��܂��B �@���āA�]�ˎ���܂Łu�����C�v�Ɓu���v�͋�ʂ���Ă��܂����B�����C�Ƃ́A���ɓ������A���̏��C�𗁑����ɑ��荞�݁A�M�������C�ɂ��g�̂̍C���オ�点�āA�K���Ȏ��ԂɎ��O�ɏo�č��̗t�ȂǂŐg�̂�@�����蕏�ł��肵�čC�𗎂Ƃ��A�߂��ɗp�ӂ����ʂ�ܓ���␅�Őg�̂��[���ɐƂ������̂ŁA����œ��Ƃ́A������ʂ̉ƕ��C��K���Ɠ����ł������̂������ł��B�܂��A�܉E�q�啗�C�Ƃ́A���܂ǂ�z���Ċ����悹�A���̏�ɉ������t���A����W�Ƃ��A���̔ݒ��߂ē������܂��B�܉E�q�啗�C�̖��O�̗R���́A�L�b�G�g���ΐ�܉E�q�����䥂ł̌Y�ɂ����Ƃ����������琶�܂ꂽ���̂ł��B�Ȃ��A�܉E�q�啗�C���ꂪ�S���Ȃ̂ɑ��Ē��B���C�͑S�̂��S���ŁA���݂ł͒��B���C���܉E�q�啗�C�Ƃ��Ĉ�ʓI�ɌĂ�Ă��܂��B���B���C�́A�傫�ȓS�̓����������ŁA����ɕʂ̓S���łǂ�ǂ����A���̂����𗁑��ɉ^�ѓ��ꂽ��A���Ȃǂ𗘗p���ė������݁A�K���ɐ��𒍂��œ����������ē������܂��B����ł͌܉E�q�啗�C�Ɠ����悤�ɉ�������M���āA�������܂��B�܉E�q�啗�C�Ƃ̈Ⴂ�́A�̉������邩�Ȃ����������Ƃ���Ă��܂��B
�@�����āA�����Ȍ��O����ł��邢����K�����o�ꂵ���͍̂]�ˎ���ƌ����A�ƍN���]�˓��肵�����N1591�N�ɂ͍]�˂ɓ������J�Ƃ��Ă��邻���ł��B�����̒��ɐ𑽂��u���A������Ă��Đ��𒍂����C�𗧂āA���̏���ł̎q��u���ē�����C���ł������ƌ����܂��B�v����ɍ��Ō����T�E�i�ł����A����͍]�˂̊X�̌��݂Ɍg���o�҂��̏����A�J���҂̃j�[�Y�ɉ�������̂ł������悤�ŁA���X�D�]�������ƌ����܂��B�܂��A�������C���獡���̑K���ɕς��O�Ɍ˒I���C�Ƃ��������C���ł��܂����B���̍\���́A�������C�̒�ɓ������A�����g�ɐZ���āA�㔼�g�����C�ŏ������̂ŁA�����C�Ɖ������~�b�N�X�����d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B�T�E�i�̂悤�ɒ��ʼn��܂��čC�̕������Ƃ�����Ő��Ƃ��܂����B�����˂�߂Č˒I�ɉB���悤�Ȋ�������˒I���C�ƌ���ꂽ�����ŁA�R���s���␅�s���̂��߂��������`�ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B�Ȃ��A���̌�A�˒I���C�͒ў��Ƃ������̂ɕς���Ă䂫�܂��B����́A�����̊O����j�������̏����ŕ����A�O�����H�ň͂�ł��܂��A����̓�����݂̂͊J���Ă��āA�ォ�甼���ʂ̂Ƃ���܂Ŕ˂̂悤�Ȃ��̂�����܂����B���̔˂ɂ́A�O�ۂ̏����≲�O�ɓ����q�Ȃǂ̊G���`����Ă��������ł��B�����āA���̍��E�̒��ɂ͎������F�̋�������Ă���A�����Ԃ�����������ƌ����܂��B���̓�����̂��Ƃ�ў��ƌĂ�ł��������ŁA�����C�̗����ɓ���q�́A���̔̒Ⴂ��������瓪�������ē���A�P�`�Q����ɐi�݂܂��B�����ɂ͂Qm70cm�l���œ��ʂ����Ȃ��Ă��ނ悤�ɐ�������������A�����͓��������̌��������Ȃ��āA�����C�̒����Ă��������C�ňÂ��A�l�̊��������Ȃ���Ԃ����������ł��B�Ȃ��A�K�����ł��������́A�����C�͍����ŁA�j���E�����̋�ʂ͂Ȃ������ƌ����܂��B�V��������M�ɂ�銰���̉��v�i1791�N�j�A���쒉�M�̓V�ۂ̉��v�i1842�N�j�Ȃǂō����͋֎~���ꂽ�����ł����A�O��ł��Ȃ������悤�ŁA��������ɂȂ��Ă������͑����Ă��܂����B�܂��A����������̓������������悤�ŁA�M����Ҋ����ȂǗ��p���Ă����ƌ����܂��B�v����ɍ��Ō����n�[�u���C�ł��B�����āA�K���͗��s�ɕq���ȍ]�˂��q�����̎Ќ���ł��������悤�ŁA�l�X�ȑK�����������܂�܂��B���̍�������{�ł͓����Ƃ����K���������̊Ԃō��Â��A���E�ɗނ����Ȃ����C�D�������ƂȂ����ƌ�����̂ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B
�@����10�N���A�����_�c�ɐV�����K�����ł��܂����A���̑K���͗�����Ԃɒ��߂ē��������Ղ�Ɠ���A����ɗ�����̓V����������ē��C��������݂����A�]���̑K���Ɣ�ׂĂ��Ȃ�J���I�Ȃ��̂ł����B������K���͖��邭�����ɂȂ��Ă䂫�܂��B�����Ė���17�N�A�x�����͒ў�������I��̖�肩��֎~�������߁A���݂̑K���̌`�ւƕς���Ă䂭���ƂɂȂ�܂����B�Ȃ��A��������̓��{�l�̂����C�̓�����Ɋւ���B.H.�`�F���o�����Ƃ����l�̎�L�ɂ��ƁA�u����������ւ��郈�[���b�p�̂�������݂�ƁA�����C����オ��Ƃ܂����������𒅂���{�l�̃X�^�C���͕s���Ɋ�����l�����邪�A�������A���{�̉��w�K���̐l�ł��A���������C�ɓ���A�g�̂�������������Ă��邩��A���{�l�̒����͊O���͚��ʼn���Ă��Ă��A�����������Ƃ������Ƃ͍l�����Ȃ��B���{�̑�O�͐��E�ł��ł������ł���v�ƌ����Ă��܂��B
|
| ���C�D���̓��{�l�`���C�̌ꌹ���畗�C�~�܂Ł` |
| �� |
���{�l�̂����C�D�� |
|
�@���{�l�̂����C�D���͐��E�I�ɗL���ŁA�̂��琴���ȍ����ƌ����Ă��܂��B����͓��{�̋C�y�ɂ��Ƃ��낪�傫���A���{�̓A�W�A�E�����X�[���n�т̈��M�ђn��ɂ���A���͂��C�ň͂܂�A���g�E�����ȋC��̂��߁A�����E�������D�܂ꂽ�Ƃ��l�����܂��B |
|
| �� |
���C�̌ꌹ |
|
�@�������邱�Ƃʎ������́u���C�ɓ���v�ƕ\�����܂��B�������A���C�Ƃ������t�͖{���������C���Ӗ����Ă��܂����B�������C�͏��C�𗁂тĐg�̂̉�����ӂ₩���A�C��o������A���ŗ����Ƃ����d�g�݂̂��߁A���C�����Ȃ����������i���j�ɂ�����܂��B���̂��߁A���i�����j����h�����ĕ��C�i�t���j�̌ꌹ�����܂ꂽ�Ƃ������Ă��܂��B���̈���ŁA���ݎ������������s�Ȃ��Ă�������X�^�C���́A�]�ˎ��㒆���ȍ~�i��270�N�O�j�m�����ꂽ���̂ŁA�u���C�v�ɑ��u���v�ƌĂ�Ă��܂����B�u���v�Ƃ͖{���g�̂ɂ�������́i���s���Ƃ����s�ׁj����S�g�ŐZ������̂ɕω����A������o��ɏ]���ď������C�����퐶���Ō����Ȃ��Ȃ�A���C�Ɠ��Ƃ͍������ėp������悤�ɂȂ�܂����B |
|
| �� |
�����݁i�䂠�݁j |
|
�@�����݁i�䂠�݁j�Ƃ́A�͂̐��ł���C�̐��ł���A�͂��܂������ł���A�����p���Đg�̂┯��A���߂邱�ƁA�܂蟔���i�����悭�j���Ӗ����܂��B�����݂́u���v�Ƃ́A���炩�Ȃ��́A�q�ꂪ�Ȃ��Ƃ����Ӗ�������A�܂��A�u���݁i���݁j�v�͗��т�Ƃ����Ӗ�������܂��B���̂悤�ɓ����݂Ƃ͌����͐����̂��Ƃł���A�]���āA�����������Őg�̂���Ƃ͕����̔��B��������ɂȂ��Ă���̂��ƂŁA�T���Ȑl�����łȂ���ł��܂Ȃ����Ƃł����B |
|
| �� |
���D |
|
�@���㐶���҂Ⓦ���E�]�ː�n��̂悤�ɐ��H�Ɏ��͂܂ꂽ���Z��̑K���̂Ȃ��ꏊ�őD�ɗ�����݂��ď���c�Ƃ����ړ����M���瓒�M�̌ꌹ�����܂ꂽ�ƌ����Ă��܂��B |
|
| �� |
�K�� |
|
�@1584�N�i�V��14�N�j�l�����̂��߂ɑK������ē����������̂��n�܂�ł��B�����������I�ɏ����������̂�1665�N�i����5�N�j������1703�N�i���\16�N�j�ŁA�����̌�y��Ƃ��ĉh���܂����B |
|
| �� |
���߁i�䂩���j |
|
�@�̂͒����𒅂ē������Ă������߁A���̒�����q�i�䂩���т�j�ƌ����܂��B���@�̗����ł́A�吨�̐l���������邽�߁A���I�q����悭�Ȃ��Ƃ������R�ŁA�����҂͕��T�ɏ]���ĕK�����߁i�����́j�Ƃ������z�̈߂��܂Ƃ��ē������Ă��������ŁA���̒�����q�i�䂩���т�j�ƌĂ�ł������Ƃ���A����i�䂩���j�ƂȂ�A���߂ƌĂԂ悤�ɂȂ����ƌ����Ă��܂��B�܂�A�]�˒��������症�œ�������悤�ɂȂ�ƁA����q�͎���ɉĂ̒����ł���u���߁i�䂩���j�v�ƂȂ�A������̊O�o���ƂȂ��Ă������킯�ł��B |
|
| �� |
���C�~ |
|
�@���C�~�͖{�������ނ��߂̕z�ŁA�u����݁i�Ђ�Â݁j�v�ƌĂ�Ă��܂������A���C�̒��ւ����̕~���ɂ�����A�E�����ߗނ��ނȂǂ̗p�r����������]�ˎ���ɕ��C�~�̌ꂪ���܂ꂽ�ƌ����Ă��܂��B�܂��A��������̑喼���������鎞�ɑ��̑喼�̈ߕ��ƊԈႦ�Ȃ��悤�ɂ��邽�߁A�Ɩ����ߔ������z�ňߕ����݁A���オ��ɂ͂��̕z�̏�ɍ����Đg�U�����������Ƃ��畗�C�̕~���Ƃ��ĕ��C�~�ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ������Ă��܂��B |
|
| �� |
�Y���i���Ԃ�j |
|
�@�l���̃X�^�[�g�̐��߂ł��韔������ɎY���ƌ����܂��B�����͉L�H���i����j�ƌ����Ă����悤�ł��B�����̒��ɏ��ł̂��߂ɍ����ȍ��������邱�Ƃ������������ł��B�Y���̓L���X�g����q���Y�[���A�C�X�������ł��s�Ȃ��A���E���ʂ̋V���Ƃ�����Ă��܂��B |
|
|
| �l�X�ȓ����X�^�C�� |
| �� |
�S�g�� |
|
�@��܂ł����C�ɐZ��������@�ŁA�����C�̉��x��38���`39�x���x�Ƒ����ʂ邭�����邭�炢�̕����悢�Ƃ���܂��B�S�g���͕��͂��S�g�ɂ�����̂ŁA�g�ْ̂̋������₷���A���s���悭�Ȃ�܂��B |
|
| �� |
���g�� |
|
�@���g���݂͂��������牺�������ɐZ������@�ł����A�����̉e�����w�ǂȂ���S���ɕ��S�̂�����Ȃ���Ԉ��S�ȓ������@�ł��B30���`40���Ԃ����ĉ����g�����߁A���s���悭����̂ŁA�ጌ����₦���̕��ɃI�X�X���ł��B�܂��A���̒��q���悭������A�����Ղ��̎��ɂȂ�ȂǂƂ������l�X�Ȍ��ʂ�����܂��B�D�P���̕��ɂ͓��ɃI�X�X���ł��B |
|
| �� |
���� |
|
�@�傫�߂̃^���C�ɂʂ�߂̂���38���`39���̂����������Ղ����āA�`�����炨�K�̕������������߂܂��B�㔼�g�͗m���𒅂��܂܂ł��\���܂���B�֔����ɂɌ��ʂ�����ƌ����܂��B |
|
| �� |
�藁 |
|
�@���ʊ�ɂ����C�̂���������⍂�߂̉��x�A40���`42����p�ӂ��܂��B�����āA���ʊ�ɗ�����Z���A15���Ԃ��炢�����ĉ��߂܂��B��̂Ђ�̃c�{����������y���}�b�T�[�W����Ƃ���Ɍ��ʓI�ł��B���r�A���̂��邳���������A���Â�ɂ����ʂ�����ƌ����܂��B |
|
| �� |
���� |
|
�@�[�߂̃o�P�c�ɂ����C�̂���������⍂�߂̉��x�A40���`42����p�ӂ��A���������A15���Ԃ��炢�����ĉ��߂܂��B�{��ǂ݂Ȃ���A�܂��e���r�����Ȃ���ł��ł���̂ł���y�ȕ��@�ł��B�����d�������������Â߂̎d���Ȃǂő������Ă�����A�ނ���ł��鎞�ɍœK���ƌ����܂��B�܂��A��[�a�╗�ׂ����������ɃI�X�X���ŁA�g�̂��悭���܂�܂�� |
|
| �� |
�����㗁 |
|
�@�M�������Ɨ₽���������݂ɗ��т鉷���㗁�́A���ǂ����k��g�傳����̂ŁA�S�����猌�t�𑗂�o���͂������Ȃ�ጌ���Ɍ��ʂ�����܂��B�܂��A���t�̏z���悭����̂ŁA�₦���ɂ����ʂ�����ƌ����܂��B����ŋC�y�ɉ����㗁���y���ޕ��@�́A�����C�̐�ŁA�������Ȃ��������ɗ₽�������������Ƃ����܂��B�C�����悭�����Ă�����A���҂��炢���琅���������Ƃ����A�܂������ɐZ����܂��B�����āA�����C����オ�钼�O�ɂ܂�����������ƁA���܂��ĊJ�����э��ǂ��M���b�ƈ������܂�A�S������ł����������Ȃ肪���ȑ���̌��t�̏z���悭���Ă���܂��B |
|
| �� |
�Q�l�F���̃V�����[ |
|
�@���M���V�����[�𗁂т�Ɩڂ���������Ɗo�߂܂��B���̃V�����[�͔M�߂̂����ŁA�����������|�C���g�ł��B�畆�ւ̎h���������_�o�̓������悭���Ă���܂��B |
|
|
[ �y�[�W�g�b�v ] [�A�h�o�C�X�@�g�b�v]
|
|
| �y�Q�z�����C�̌��p�ƌ��ʓI�ȓ����@ |
�@�����C�̌��N���ʂɂ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����̂ł��傤���H
�@�{�߂ł́A�����C�̌��p�Ƃ��̌��ʓI�ȓ����@�ɂ��ĉ�����܂����B
|
| �����C�̌��\�Ǝ�� |
| �� |
���M��p |
|
�@���D�ɐZ����Ƒ̉����オ��A�畆�̖э��ǂ��L�����Č������悭�Ȃ�܂��B����ɂ���ĐV��ӂ����܂��đ̓��̘V�p�����J��������菜����A��J��Â�E�ɂ݂��a�炬�܂��B |
|
| �� |
������p |
|
�@�g�̂ɂ����鐅�̈��͂̓E�G�X�g���R�`�Tcm���ׂ��Ȃ�قǂŁA�g�̂̕\�ʂ����łȂ��A�牺�̌��ǂɂ������܂��B���̂��߁A�葫�ɗ��܂������t�������߂���ĐS���̓����������ɂȂ�A���t����p�̗�����悭���܂��B |
|
| �� |
���͍�p |
|
�@�v�[����C�ɓ���Ƒ̂������悤�ɓ��D�ł����͂������Ă��āA�̏d�͕��i��10���̂P�ɂȂ�܂��B���̂��߁A�̏d���x���Ă���ؓ���߂��x�܂��邱�Ƃ��ł��A�̑S�ْ̂̋����ق���܂��B |
|
| �� |
�����N�[�[�V�������� |
|
�@�����C�ɓ���ƕ��͂������A�����Ȃǂ��d�͂���������܂����A����͕�e�̂����̒��ɂ������̑̓����o�Ɏ������̂ŁA�����b�N�X�ł���Ɠ����ɃX�g���X�����ɂ��Ȃ�܂��B |
|
|
| �₦�Ɍ��������@ |
| �� |
�₦�ɂ͉���V�����[���������I
�`���͉���V�����[�����s�Ȃ��A�g�̂�ڊo�߂��悤�` |
|
�@�����_�o�̓���������Ȃ�A���N����Ί������[�h�A��ɂ͋x�����[�h�ƃX���[�Y�ɐ�ւ����̂ł��B�������A�u���͂������܂ŃG���W����������Ȃ��v�Ƃ��u��͖ڂ��Ⴆ�Ė���Ȃ��v�Ƃ������l���ŋߑ���������悤�ɂȂ�܂����B�����������l�́A���̎����_�o�̐�ւ������܂������Ă��Ȃ��̂ł��B���̏�Ԃł́A�O�����牷�߂Ă��g�̂͗₦�����Ȃ̂ŁA�ǂ����Ă������_�o���ӎ��I�ɐ�ւ��Ă����邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B
�@�����ŁA���̂悤�Ȑl�ɂ͒��̉���V�����[���������Ă݂邱�Ƃ��I�X�X�����܂��B�����Ɨ␅�����݂ɗ��т�ƌ����_�o�̃X�C�b�`������܂��B�Q�Ă������ɓ����Ă����������_�o�������_�o�ɐ�ւ��̂ŁA�X�b�L���Ɩڂ��o�߂āA�S�g�Ƃ��Ɋ����I�ɂȂ�̂��i���������A�̒��̏���Ȃ�����S���ȂǂɎ��a��������A����҂͍s�Ȃ�Ȃ��悤�ɂ��ĉ������j�B�t�ɖ�́A�₦�Ɍ����ʂ�߂̔��g���ŕ������_�o�D�ʂ̏�ԂɃX�C�b�`�����܂��B�������邱�ƂŎ����_�o������ɓ����A���R�Ɨ₦�Ȃ��g�̂ɂȂ��Ă䂭�̂ł��B |
|
| �� |
�₦���̐l�͂ʂ�߂̓���20�`30����������Z����A�̂̐c�܂ʼn��߂悤 |
|
�@�₦�ǂ̐l�ɂ�38�`41���̂��ʂ�߂̂��������ʓI�ł��B�M�����ł͓��D�ɒZ���Ԃ����Z���ꂸ�A�g�̂̕\�ʂ��Ԃ��Ȃ����Őc�܂ʼn��܂�܂���B�ʂ�߂̓��Ȃ�A�������蓒�ɐZ���邱�Ƃ��ł���̂ŁA�p���Đg�̂���������Ɖ��܂�A���s�����i�����̂ł��B���̂��߁A���߂̓���20���ȏ��ڈ��ɓ������܂��傤�B�Ȃ��A�������鎞�ɒY�_�K�X�n�̓����܂�����Ɖ������ʂ����܂�A���������������܂��B�����āA������͖�X�����������A�g�̂����܂�����ԂŃx�b�h�ɓ���悤�ɂ��܂��傤�B |
|
|
| ���Â�Ɍ��������@ |
| �����Â�Ɍ��������@ |
| �@���Â����������ɂ͂܂��͌������悭���邱�Ƃ��|�C���g�ł��B���̂��߂ɂ́A�ʂ�߂̓��Ɍ��܂ł������Z�����Đg�̂��[���ɉ��߂Ă���A�����C�̒��ŊȒP�ȃG�N�T�T�C�Y���s�Ȃ��܂��傤�B�����Ɖ^����g�ݍ��킹�邱�ƂŁA��茌���𑣂����Ƃ��ł��A������̏Ǐa�炬�܂��B |
|
| ���P�F |
���� |
|
�@40���ȉ��̂ʂ�߂̓��Ɍ��܂ŐZ����A10���ԑS�g�������܂��B���Ԃ����鎞�͔��g����20���Z����܂��B |
|
| ���Q�F |
���ɓ��������� |
|
�@�݂������ӂ�܂œ��ɐZ����Ȃ��猨�ɓ��������܂��B�E��ō����ɁA����ʼnE���Ƃ����悤�Ɍ��݂ɓ��������܂��B |
|
| ���R�F |
��̉^�� |
|
�@42�����炢�̔M�߂̃V�����[����ɓ��ĂȂ������������܂��B |
|
| ���S�F |
���̉^�� |
|
�@42�����炢�̔M�߂̃V�����[��Е��̌��ɓ��ĂȂ��猨���܂��B���l�ɔ��Α��̌����s�Ȃ��܂��B���Ȃ��A(3)(4)�͂T�`10��s�Ȃ��ƌ��ʓI�ł��B |
|
| ���Q�l�F |
���Â�Ɍ����� |
|
�@�S�����牓�������͌�������₷���A���̕����������Ō��s�s�ǂɂȂ��Ă��邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B���̂��߁A�����̈������⑫��Ȃǐg�̂̐�[��������S���Ɍ������Đ̂����ʓI�ł��B���������A�S���ɉ���������悩��X�^�[�g���Č����𑣂��A�Â��a�炰�܂��傤�B |
|
|
| ���ɂɌ��������@ |
| �����ɂɌ��������@ |
| �@�����͌����𑣂��A���͂ɂ�荘�̕��S���y������̂ŁA���ɑ�Ƀs�b�^���ł��B�܂��A�ؗ͂̐����������ō��ɂ��N���邱�Ƃ��������߁A�y���̑���g�ݍ��킹�Č��ʃA�b�v��}��܂��傤�B������͊߂�ؓ������t���b�V������Ă���̂ŃG�N�T�T�C�Y�Œb���₷���A�Ǐ���y�������邾���łȂ����ɗ\�h�ɂ��q����܂��B�i���Ȃ��A�����ŏЉ����@�͂����܂ł������I�ȍ��ɂɌ��ʓI�ȃv���O�����ŁA�������荘��X�|�[�c���ɔP�������̒ɂ݂Ȃǂɂ͋t���ʂɂȂ邱�Ƃ�����̂ōs�Ȃ�Ȃ��悤�ɂ��ĉ������B�j�@ |
|
| ���P�F |
���� |
|
�@40���ȉ��̂ʂ�߂̓���20�`30�����g�������܂��B |
|
| ���Q�F |
���D�̒��ł̍��̑� |
|
�@���ɐZ����Ȃ���A�o�X�^�u�̕Б��𗼎�Ŏ��悤�ɂ��č����������P��܂��B�܂��A�o�X�^�u�̉��������Ȃ��獘�������グ����߂����肷��̂����ʓI�ł��B |
|
| ���R�F |
������̕��؉^�� |
|
�@�G�𗧂Ăċ����ɐQ�]����A�������ƋN���オ��܂��B���̏�Ԃ��T�b�ԃL�[�v���A������蓪�����ɖ߂��܂��B |
|
| ���S�F |
������̔w�؉^�� |
|
�@�����ŗ��G������A�G��������苹�ւƈ������܂��B����������߂������10�炢����Ԃ��܂��B |
|
|
| �����C�Ŕ��r��� |
�@��������Ƃ����Ƃ蔧�ɂȂ�܂����A����͂Ȃ��ł��傤���H�@����́A�玉�̕��傪�����ɂȂ�A����𗎂Ƃ��Ĕ��̏�����ۂ���ł��B�����������Ƃ蔧������ő�̌��ʂ͓��̉��M���ʂƐ������ʂɂ���܂��B�����ɂ̂�т�Z�����Ă���ƁA�Q�̌��ʂɂ���Č��t�̏z���悭�Ȃ�A�g�̂����܂��Ėь����J���Ă��܂��B�����āA���Ǝ��łł���玉�̕��傪����ɂȂ�A�畆�\�ʂ̉����G�ۂ����Ƃ��₷���Ȃ�A���������ɂȂ�̂ł��B�玉�ɂ͔��Ɋ܂܂�鏁�����������o���A�@�\������̂ŁA������h�����ʂ����܂�܂��B�܂��A���s���悭�Ȃ邱�ƂŐV��ӂ������ɂȂ�A�זE�̍Đ��𑣂��܂��B���N�ȏ�������28�������ŐV�����זE�ɐ��܂�ς��܂����A���̍Đ����Y�����X���[�X�ɂ�����ʂ�����̂ł��B����ɊԐړI�Ȍ��ʂ����҂ł��܂��B�Ƃ����̂́A���t�z���悭�Ȃ��ē����̓����������ɂȂ�A���R�Ȃ���g�̂̒����猒�N�ɂȂ�A�����Ƃ蔧�Â���ɖ𗧂��܂��B���������ɂ������Z�����ă��t���b�V������̂��傫�ȃ����b�g�ŁA�����Â���ɂƂĂ��悢�e����^����̂ł��B
�@���ɂ����Ƃ蔧�ɂ͓��̉��x����ŁA�M�߂��铒�̓J�T�J�T�������܂��B�����ɂ͂����Ƃ蔧����邽�߂̗l�X�Ȍ��ʂ�����܂����A�����C�̓�����ɂ���Ă͋p���Ĕ������������Ă��܂��ꍇ������܂��B���̈�Ԃ̌������M�߂��铒�ł��B�M�����͔��ւ̎h�������߂��Ĕ��̏���������ۂ玉�̑���������Ă��܂��̂ł��B����ɔM�����ł͂̂�т�ł��Ȃ��̂ŁA�����b�N�X���ʂɂ������Â�����]����҂ł��܂���B�����̂��߂��l����A���ʂ�߂�41�����炢�̓����I�X�X���ł��B
| �������Ƃ蔧�����邨�����ߓ������j���[ |
| �@���ʂ�߂̓��ɕێ����ʂ̂�������܂��g���܂��傤�B��{�I�ɂ����C�ɂ͖�������A�V�����[�����ł��܂����ɓ��D�ɐZ����悤�ɂ��܂��B�����āA���ʋ�̈������������āA���Ă��鎞����������蓒�D�Ŏ葫��L���܂��B���s��������Ĕ�ꂪ�����ɔ��ɂ��悢���ʂ��オ��܂��B |
|
| �� |
�����͂܂����ς𗎂Ƃ� |
|
�@�����蓒������ہA���ς����Ă��鏗���̓N�����W���O�N���[���ʼn��ς𗎂Ƃ��Ă����܂��B���D�ɐZ�����Đg�̂����߂�Ɩь����J���܂����A���ς����Ă��Ă͊�̖ь������[���ɊJ���Ȃ�����ł��B |
|
| �� |
���ɂ������Z���� |
|
�@���ʂ��38�`41���̓���20�`30���������Z����܂��B�g�̂���������c���牷�߁A�ь����[���J�����ĉ����ۂ��������܂��B���s���悭�Ȃ邱�ƂŔ��̐V��ӂ��A�b�v���܂��B����ɔ��r��ɗL���Ȗ�p�����t�����������Ɍ��ʓI�ł��B�ێ����������ɐZ�����Ċ�����h���܂��B |
|
| �� |
�D�����g�̂�� |
|
�@�Ό���{�f�B�V�����v�[���悭�A���ĂĐg�̂�܂��B���̎��A������������������Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B�V�����p���w������Ċ����𑣂��Ă��܂�����ł��B�ь����[���J���Ă���̂Ŋ��ɉ���͕��������A���Ő�����Ă��鉘�������܂��B�_�炩���^�I���ɐΌ���t���Čy�����ł���x�ŏ[���ł��B���ƃV�����v�[�����̎��ꏏ�ɍs�Ȃ��܂��B |
|
| �� |
�Ō�ɂ�����x���ɐZ���� |
|
�@�Ō�ɂ�����x���ɐZ����A�����b�N�X���܂��B���D�ɐZ����Ȃ��猌�s����董�����߂̃}�b�T�[�W�����Ă����ʓI�ł��B�Ō�ɃV�����[�����߂ɂ����đS�g�}�b�T�[�W�����Ă��悢�ł��傤�B |
|
| �� |
�Q�l�F��p�b�N�����鎞�� |
|
�@�g�̂�I������I�������Ƀp�b�N�����āA�����C����o��O�ɐ����܂��B�p�b�N������O�́A���e�t�����t��h���Ă�������ێ����Ă���p�b�N���{���悤�ɂ��܂��B |
|
|
| �Q�l�F���ׂ̎��ɂ����C�ɓ����Ă͂����Ȃ��̂��H |
| �� |
�Ȃ����ׂ̎��ɂ����C�ɓ����Ă͂����Ȃ��ƂȂ�������̂��H |
|
�@�̂���u���ׂ̎��͂����C�ɓ����Ă͂����Ȃ��v�ƌ�����̂́A�����Őg�̂����܂�ƌ��ǂ��g�����A�����C���ɔM�����U����āA�����铒��߂��N�����l��������������ł��B���ɐ̂̓��{�Ɖ��͌��ԕ�������̂�������O�̉Ƃ��������߁A����߂��N�����l�������A���ׂ̎��͓����͎~�߂������悢�Ƃ��ꂽ�̂��낤�ƍl�����܂��B�܂��A�ቺ���Ă���̗͂�����ɂ���Ă���ɏ��Ղ����Ȃ��悤�ɂ���̂��A���ׂ̎��̓����͍T���������悢�Ƃ���闝�R�ł��B���ׂŔM�����鎞�͊��ɑ̗͂����Ղ��Ă���̂ɁA���̏�ԂŔM�������C�ɓ���̂͗]�v�ɑ̗͂����Ղ��Ă��܂�����ł��B���ɂ��N����̗͂̂Ȃ��l�́A�p���ē��������S�ɂȂ�����A�����C���ɋ�������Ȃ����肷�邱�Ƃ�����܂��̂ŁA���ꂮ����C�����܂��傤�B�]���āA���ׂŔM�������Ԃł͓����͔������������悢�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������A�M���Ȃ��A�Ǐy����Ԃł���Γ������Ă��\���܂���B�����ɂ���ċC���������ς肵�āA�������薰���悤�ɂȂ�܂��B |
|
| �� |
�Ȃ����ׂ̎��ɂ͂����C�̓�����ɋC������ |
|
�@�����C�Őg�̂����߂Č��s���悭���A�g�̂̐V��ӂ�ɂ���������בގ��ɂ͌��ʓI�ł��B���������̍ۂɂ́A�̗͂̏��Ղ����Ȃ�40�����炢�̂ʂ�߂̂�����20���قǂ������Z�����Đg�̂����߁A��������f�����g�̂��������A�M���D����O�ɕz�c�ɓ����Đg�̂��x�߂�Α̗͂̉ɂ����ʓI�ł��B�Ȃ��A�V�����[�𗁂т邾���Ȃ�悢���낤�Ɠ��D�ɓ���Ȃ��l�����܂����A�g�̂��[���ɉ��߂邽�߂ɂ��A���Г��D�ɐZ����悤�ɂ��܂��傤�B�܂��A�����O�ɂ͕�����E�ߏ������߂���A��������͒����Ƀh���C���[�Ŋ��S�Ɋ������Ȃǂ̍H�v���K�v�ł��B |
|
|
| �Q�l�F�����Ɋւ���Q�l�� |
| ���Q�l�}�� |
 |
| �� |
�O�c���q �� |
|
�w�����C�̖����݁x |
|
�V�ЁE1999�N11���A��1,575 |
|
�H���Ƀ��j���[������悤�ɁA�����C�ɂ����j���[�������Ă����B����E�V�����v�[�������X����A�����܁E���ϕi�E�������܂ŁA���S�ł���ޗ��Ŏ�y�Ɋy��������{�f�B�P�A�p�i�̃��V�s�̐��X���G�b�Z�C�ƂƂ��ɏЉ�B |
|
|
|
|
|
[ �y�[�W�g�b�v ] [�A�h�o�C�X�@�g�b�v]
|
|
| �y�R�z�����C�̃����e�i���X�`�|���@�Ɛߖ�@�` |
�@�����̂悤�ɂ����C�ɓ���l������Ǝv���܂��B��������p�ɂɗ��p���邨���C�͂������K���o�ϓI�ɂɗ��p���������̂ł��B
�@�{�߂ł́A�����C�̌��ʓI�ȑ|���@�Ɛߖ�p�ɂ��ĊȒP�Ȃ���Љ�܂����B
|
| �����C�|���̃R�c |
�@����̓��{�̉Ƃ͋C�����������A���ʂ����悭�Ȃ����߁A�}���V�����Ȃǂ͓��Ɏ��C�����ߍ��݂₷���\���ɂȂ��Ă��܂��B���̒��Ɏ��x�Ɖ��x����ɍ������C�ꂪ����܂��B�J�r�̍D���͉��x�Ǝ��x�Ɖ���ŁA���ɐΌ���ⓒ�C�ȂǕ��C��̉���̓J�r�̉h�{�ɂȂ�܂��B�ƑS�̂ɃJ�r���L���Ȃ����߂ɂ��A���C��̉����J�r�𑝂₳�Ȃ����Ƃ��厖�ł��B���̂����ɂ�������|�����A���C�̉����~�Ɏ����z���Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B
| ���T�P�܂߂ɑ|���������ꏊ |
| �� |
�����̏� |
| �� |
�����̕� |
| �� |
�V�����v�[�{�g����Ό��u���Ȃǂ̏��� |
| �� |
�����̊W |
| �� |
�r���� |
|
| �� |
�����C�|���̃S�[���f���^�C�� |
|
�@�����O�ɑ|��������l�͌��\�����̂ł����A���͂����C�|���̃S�[���f���^�C���͓�������ł��B��������ɑ|��������K���̂���l�̂����C�͑�̂��ꂢ�Ȃ��Ƃ������ł��B�����͓�������ɔr�����Ȃ���V�����[�������ĐΉ��ꂪ���܂�ɂ����Ȃ�܂����A���Ɏ��̓������܂ő|�������Ȃ��Ɠ��R�Ȃ��牘��͎�菜���ɂ����Ȃ�܂��B�����A�c�蓒�����Ɏg������h�Џ�̗��R�Ŏc�����肷��l�͓�������̑|���͓���Ȃ�܂��B�c�蓒������Ɨ����ɃJ�r�������₷���͎̂����ł����A�ǂ����I�����邩�͊e���̃��C�t�X�^�C������ł��B
�@�܂��A�����̏���ǂ́A�T�P��|������̂����z�I�ł��B���͈ӊO�Ɖ���Ă��܂��B�ŋ߂͐g�̂����łȂ��A�y�b�g��C�𗁎��Ől�����܂�����A���C��ɂ͗l�X�ȎG�ۂ����݂��Ă��܂��B�ǂ��A�g�̂����Ă���A����юU�邽�߁A�ӊO�ƃJ�r�������₷���̂ł��B���̂��߁A�����ǂ����C�p�̃J�r���܂��g�p���ĐA��������J�r����菜�����Ƃ���ł��B���̍ۂɒ��ڂ������̂́A���Ƃ��ΕǂƏ��̋��ڂ�r���p�̍a�A�I�ƕǂ̋��ڂȂǂƂ������E�����ŁA���������E�Ƃ���̓J�r�������₷���̂ŗv�`�F�b�N�ł��B�����_����������A�J�r���܂��g���܂��傤�B�����_�͂���J�r�̑��ŁA��������J�r�̖E�q����C���ɕ����オ��A�J�r���L����܂��B���̑����Ȃ������Ƃ���ł��B |
|
| �� |
�ӊO�ȃJ�r�̉��� |
|
�@�z�������Ȃ������ꏊ���J�r�̑��ɂȂ��Ă���P�[�X������܂��B�悭����̂̓w�A�P�A�p�i��u���V�ނȂǂ̗����ł��B���������̂̎g��Ȃ��Ȃ����V�����v�[�Ȃǂ�ܑ̂Ȃ�����Ɨ������ɒu���Ă����ƁA�ő��ɓ������Ȃ�����{�g���̗��ɃJ�r�������Ă��܂��̂ł��B�v�����G���Ă��Ȃ��{�f�B�u���V��C�ȁA�w�`�}�Ȃǂ��A�C�Â��ΐ^�����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B�����������̂�p�����邾���ŃJ�r���������Ƃ����b�����邭�炢�ŁA�܂��͗v��Ȃ����̂��̂āA���̏�ŏT�ɂP��̓{�g����u���V�ނ̗��������Ɛ悤�ɐS�����܂��傤�B�܂��A�����̊W���������J�r�������₷���̂Œ��ӂ��K�v�ł��B���ɃW���o����̂��̂͑|�����ʓ|�Ȃ��߁A�����Ƃ����Ԃɍ����Ȃ肪���ł��B�g��Ȃ����Ԃ͊O�œ�����������悤�S�����܂��傤�B����ɁA���Č��ʂӂ���������Ȃ�r�������T�ɂP��͑|�����������̂ł��B�h���h��������Ԃ�����̂������Ƃ����l�́A�ŏ��ɃJ�r���܂������ĕ��u���A����������đł��甯�̖тȂǂ̃S�~��~�����Ƃ悢�ł��傤�B�Ȃ��A���C��ɃJ�r�������Ă��Ă���Ȃ�T�ɂP��̓J�r���܂��g���܂��B���܂߂ɃJ�r���܂��g�p���邱�ƂŁA�J�r���~�ς��č����Ȃ��Ď�菜���ɂ����Ȃ邱�Ƃ�h�����Ƃ��ł��܂��B�J�r���܂́A��x�ɑ�ʂɎg���Ē����ԕ��u��������A�K��̗ʂƎ��Ԃŕp�ɂɌJ��Ԃ��s���������ʂ͍����Ȃ�܂��B�Ȃ��A�J�r���܂��g�����́A���̐�܂ƍ�����Ȃ��悤�ɋC�����܂��傤�B |
|
| �����P��͑|���������ꏊ |
| �� |
���C�� |
| �� |
�C�X����ʊ� |
| �� |
�� |
| �� |
���C�� |
| �� |
�V�� |
|
| �� |
���C���̑|�� |
|
�@���ɂP��͕��i�ڂɂ��Ȃ��Ƃ���܂ő|�����܂��傤�B�����āA���̕M���Ƃ��āA�����Ȃ������ňӊO�Ɖ���Ă���̂����C���ł��B�������A���C���̒��͒��ڑ|���ł��Ȃ��̂ŁA����I�ɕ��C�����܂ŃL���C�ɂ��������̂ł��B���C�����܂̓X�[�p�[��h���b�O�X�g�A�Ŕ̔����Ă��܂��B���C���͒m��Ȃ������ɎG�ۂ̉����ɂȂ��Ă���\��������܂��B���z�͌��ɂP����x�A�Œ�ł��G�߂ɂP��͕��C���̑|�������������悢�ł��傤�B���C���́A�z�ǂɐ����z�����ĉ��߂�u�Q���^�C�v�v�ƁA�ǂ������@�\�����鋋������g���u�P���^�C�v�v������܂��B�Q���^�C�v�̕�������͌������ł����A�P���^�C�v�������̓����z���グ�Ēǂ���������̂ŁA�r���̔z�ǂɌÂ������c��A���̋����̎��ɂ��̉��ꂪ�ꏏ�ɏo�Ă��邱�Ƃ�����܂��B�ǂ���̃^�C�v�ł����Ă��A�C�����悭�������邽�߂ɂ͔z�ǂ̑|�������I�ɂ��ׂ��ł��傤�B���ɒǂ�������p�ɂɂ���������܂��g�����肷��ꍇ�͉���₷���̂ŗv���ӂł��B�����̎���g���Đ��Ƃ͂ł��Ȃ�����A�s�̂̕��C�����܂��g���܂��傤�B |
|
| �� |
���C���V����|���� |
|
�@�C�X����ʊ�A���A���C��Ȃǂ̔��i���J�r�������₷���ƌ����܂��B������͊���������悤�ɂ��āA���ɂP��̓J�r���܂ŃP�A���܂��傤�B���ł����ƕǂ̌��Ԃ��J�r�̑��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������̂œ��ɒ��ӂ��K�v�ł��B�܂��A���̑O�ʂɐ������̃~�l�����������t�����Ĕ�������Ă��鎞�́A�N�G���_�𐅂łT�����炢�ɔ��߂����̂�H�|��h����10���قǕ��u����Ή��ꂪ�ɂ݁A�X�|���W�ŗ��Ƃ��₷���Ȃ�܂��B�������A��ɃJ�r���܂ƈꏏ�ɂ͎g��Ȃ����Ƃ��̗v�ł��B�A���J�����̃J�r���܂Ǝ_���̂��̂�������̂͊댯�ł��B�g�����炫����ƑA�ʂ̓��ɉ��߂đ|�����܂��B����ɁA�V������ɂP��̃y�[�X�ő|�����������̂ł��B�V��ɃJ�r���܂��g���ꍇ�́A���̂����X�|���W�Ȃǂɕt���Đ���Ȃ��悤�ɐT�d�ɓh��A�G��G�ЂŐ@�����܂��B�V��S�̂ɃJ�r���L�����Đ^�����ɂȂ��Ă��܂����ꍇ�͎��͂ł͓���̂ŁA���Ǝ҂ɑ��k���܂��傤�B |
|
|
| �����C�ł̐ߖ�@ |
| �� |
�����@�ł��� |
|
�@������Ɛ����畦�����ł͂P�����S�~�̐ߖ�ł��B�ӊO�ɋ�����ł������͂�ƁA�����畦������莞�Ԃ��K�X��������ł��B�P��Ŗ�S�~�ƂQ�O���̎��ԒZ�k�ɂ��Ȃ�܂��B |
|
| �� |
�����C�̐� |
|
�@15�x�̐���20�x���畦�����ƂP�����13�~�̂����ł��B�ď�̂Ƃ��Ă��g�������́A�����C�ɒ����琅�����Ă����Ə����͐������㏸�������ł��B |
|
| �� |
���C�̊W |
|
�@�ǂ������łP�x�グ��ɂ͖�R�~�قǏ���܂��B���C�ɂ͊W�����Đ����������Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B�������A�ǂ��������肵�Ă��Ă͐ߖ�ɂȂ�܂���B�܂��A�W������̂Ƃ��Ȃ��̂ł͕ۉ����ʂ��S�R�Ⴄ�̂ŁA�K�X��̐ߖ�ɂ��Ȃ�܂��B |
|
| �� |
���C�͑����ē��� |
|
�@�ǂ������łQ�x�グ��ɂ͖�U�~�قǏ���܂��B�����ǂ���������ƌ�180�~�����ʎg�����Ă��܂��̂ł��B�����āA�����C�͕��������炷�������ē������܂��傤�B�W���������Ƃ��Ă��P���ԓ������P�x�͉��x��������܂��B |
|
| �� |
���C�͔��g�� |
|
�@�����C���������炢�܂œ���܂��傤�A���x�͂ʂ�߂�38�`40�����x�X�g�ł��B��͉���Ɠ����悤�Ȋ��o�ŕ��ʂɓ��D�ɐZ����A�g�̂���������Ɖ��߂܂��B�ӊO�ɂ�������g�̂����܂�A�I�X�X���̓����@�ł��B |
|
| �� |
�����C�ɕۉ��V�[�g |
|
�@�����C�͎��X�ɓ���ƔM�������ɓ���܂����A�ǂ����Ă������ē���Ȃ����ɂ͕��C�W�𗘗p����l���w�ǂ��Ǝv���܂��B�������A��������֗��Ȃ̂������x�t���ۉ��V�[�g�ł��B�g�����͊ȒP�ŁA�T�C�Y��70�~110�p�Ȃ̂ŗ����̑傫���ɐ�K�v�͂���܂����A����D�ɕۉ��V�[�g���ׂ邾���ł��B�����̉��x��������̂ŁA���x�����Ēǂ��������邩�ǂ����m�F���邱�Ƃ��ł��܂��B�l�i��1000�~������ƂŔ����Ă��܂����A100�~�V���b�v�ɂ����x�v�͕t���Ă��Ȃ��^�C�v�̕ۉ��V�[�g�������Ă��܂��B�Ȃ��A����͐g�̐ꏊ�Ɉ����}�b�g�ł���p�ł��܂��B�ۉ��V�[�g�����݂�����̂ŕۉ����ʂ������Ȃ�܂��B���̃}�b�g�𗁑��̑傫���ɍ��킹�Đ��āA�g��Ȃ����Ɏז��ɂȂ�Ȃ��悤�ɉ��������ɐ��Ďg���܂��B |
|
| �� |
�����͐��� |
|
�@�����G�ߒ��N���Ċ���ɂ킴�킴�����@�̂����Ő���Ă܂��H�@������߂����ɋ����@�����ƁA�K�X���d�C��ʂɏ���Ă��܂��܂��B�^�~�̐��͗₽���ł����A�C�������g�̂��������߂�Ƃ������ʂ�����A�ڂ��o�߂܂��B�����䖝���āA�����@�������ɐ��Ŋ��Ƃ��������œd�C�さ�K�X��̂�����Ƃ����ߖ�ɂ��Ȃ�̂ł��B |
|
|
| �Q�l�F�����C�ɓ����Ă鎞�ɒn�k���N���������̑Ή��@ |
�@�����C�͗��ōł����h���ł�����A�����C�ɓ����Ă���Œ��ɓˑR�O���b�Ɨ����瓖�R�p�j�b�N�ɂȂ��Ă��܂������ł����A�������Ώ��@���`�F�b�N���A���������čs������悤�ɐS�����܂��傤�B����ł��Q�ĂĂ��܂������Ȃ����C�ł̒n�k�ł����A�u�����C�͈ӊO�ƈ��S�v�Ƃ������Ƃ�Y�ꂸ�ɁA�������Ɨ��������Ĕ��܂��傤�B
| ���P�F |
�������A�h�ꂪ���܂�̂�҂� |
|
�@�����C��g�C���͋������A����ɕǂ�������������Ƃ��Ă���X��������A�����Ă���傫�Ȃ��̂��Ȃ��̂ŁA�ӊO�Ƒ��̕��������S�������肵�܂��B�ł�����A�Q�Ă��A���������Ă����C�̒��ŗh�ꂪ���܂�̂�҂��܂��B�܂��A���C��͊���₷���̂ŗ������܂܂ł��Ȃ��ŁA�K�����Ⴊ�ނ����荞��ł��܂��܂��傤�B�����āA�������Ȃǂ���g����邽�߁A�����C�̊W�Ȃǂœ������܂��B�܂��A���⋾�Ȃǂ̃K���X�̔j���ɂ��P�K�ɒ��ӂ��܂��B����ɁA�g�̈��S���m�ۂł��A�]�T������A�����C�̃h�A���ό`���ĊJ���Ȃ��Ȃ�A�����߂���̂�����邽�߂ɁA���������h�A���J���Ă����܂��傤�B |
|
| ���Q�F |
�����Ɋ댯���Ȃ������ӂ��� |
|
�@�h�ꂪ���܂�����A�䓁�⋾�ȂNJ�Ȃ����̂������Ă��Ȃ������悭�m�F���܂��B�����ł�����A�[�����ӂ��܂��傤�B |
|
| ���R�F |
�ǂ������⎩���X�C�b�`���A�����͔����Ȃ� |
|
�@�����C����オ�鎞�A�ǂ������⎩���X�C�b�`�������Ă�����A�Y�ꂸ�ɐ�܂��傤�B�K�X���~�߁A�Ђ��N���邱�Ƃ�h���܂��B�܂��A�f���̉\�����l���āA�����͔������A���̂܂܂ɂ��Ă����܂��B�������Ă����A���̐����g�C���𗬂��̂Ɏg���������Ȃǂɂ��g�����Ƃ��ł��܂��B |
|
| ���S�F |
�ǂ������⎩���X�C�b�`���A�����͔����Ȃ� |
|
�@�����C���オ������͗��ł����A�Ƃɂ�������D�悵�܂��傤�B����ɕ��𒅂Ă��ĂQ�x�ڂ̗h�ꂪ���Ă͑�ςł��B�ً}���������ꍇ�́A�o�X�^�I����ѕz�ő̂��݁A���ւ���Y�ꂸ�Ɏ����A�Ƃɂ����O�ɓ����܂��B�����������畞�𒅂�悢�̂ł��B���̎��A�C�͂������肵�����̂𗚂��悤�ɒ��ӂ��܂��傤�B |
|
|
[ �y�[�W�g�b�v ] [�A�h�o�C�X�@�g�b�v]
|
|
| �y�S�z�����܂̗��p�Ƃ��̒��ӓ_ |
�@�ŋ߂ł͓����܂𗘗p����l�������Ă��܂����B���悤�ɂ���ẮA���O�̓����܂��H�v���邱�Ƃœ������牷��C���𖡂키���Ƃ��\�ł��B
�@�{�߂ł́A�����܂̗��j����n�߂āA���̗��p�@�⒍�ӓ_�Ȃǂɂ��ĉ�����܂����B
|
| ��ԕ��C�Ɠ����� |
�@�̂��炳�瓒�i�W���j���͂��N���ɓł��ƌ����`�����Ă��܂����B���瓒�͂����̂����Ȃ̂ŁA�����̐����i���d�������F�J���V�E���A�}�O�l�V�E���j���M�̓`�d�����߂���A�Z�����̊W�ł������`�N�`�N�h���������܂��B���̂��߁A���ɔ��̎�����l�ɂ͕s������^���܂��B�����܂̐����͔��ɕs������^����d���������������p�����邽�߁A���炬�����߂���������y���߂܂��B
|
| �����܂̗��j |
�@���{�͐��E�ł��L���̉��ŁA�×����l�X�͓V�R�̉���𗘗p���āA�a�C�����̎��ÁA�܂����N�ێ����i�ɉ���𗘗p���Ă��܂����B�܂��A���l�̖ړI�Ŗ�p�A���̗��p������ɍs�Ȃ��č����܂œ`�����Ă��܂��B���̈Ӗ��œ����܂̔����́A�V�R�̉���Ɩ�p�A���ɂ��ɗR�����Ă�����̂ł�����܂��B�Ȃ��A��p�A����p�����́A�[�߂̐ߋ�̏Ҋ�����~���̗M�q���̂悤�ɌÂ����珎���̊ԂɊ��K�Ƃ��Ďp����A�]�ˎ���ɂ͎��Â�ړI�Ƃ������̂����ɏ���������A�畆�a�̎��ÖȂǂɗp�����Ă��܂����B���Ƃ��ΊL���v���́w�{���P�x�̒��ɂ͌ܖؔ������̋L�ڂ�����A�����ɗp����ꂽ�A���͌K�➾�A�ˁA�Ҋ��A�E�~�Ȃǂ�����܂��B
�@�ߔN�ɂ����ẮA���������ɁA��X�̐����z�����A�z�܂ɓ�����o���ėp���鏤�i�����ꂽ�̂����߂Ă̓����܂ł��B���̌�A�u��X�̌��ʂ�������i�q��̓��A�����̂̓��A���C�̓��A���l�̓��Ȃǁj���A�킴�킴����n�ɂ܂ł䂩�Ȃ��Ă��A�ƒ�ŊȒP�ɉ��p�ł��Ȃ����v�Ƃ����l��������A�V�R�̉����������E�������������̂���n�܂�A���a�����ɂ͖��@���ޓ����܁i�m�{�s���A�o�X�N�������j���J������Ĕ�������܂����B�����͉�����\�����Ă��鐬���̂������S���������A�܂����\���ʂ�L���A�i�������肵�Ċm�ۂ��₷����܂��I������܂����B����ɁA�����œ����郊���b�N�X�����������A�������y�������邽�߂ɐF�f�⍁�����Y������܂����B
�@��O�A�����܂͎�Ɍ��O����Ŏg���A��ʉƒ�̕��C��ň��p�����܂ł͎���܂���ł����B����́A�����͕��C�t�̏Z��������Ă���͓̂s�s���ł͂�������ꂽ�l�X�ł���A�w�ǂ͋߂��̑K���𗘗p����̂����ʂł������Ƃ����w�i������܂��B�������A���{�̏Z����1960�`70�N��ɂ����ă}�C�z�[������c�Z��A���Ԃ̃}���V�����Ȃǂ̌��݂������n�߁A���C�t�Z��펯�ƂȂ��Ă��܂����B���̍����猒�N�u������b�N�X��ԂƂ��Ă̂����C�̈ʒu�Â����F������n�߁A�y�f�n�����܂�Y�_�K�X�n�����܂̎s����ɂ��}���Ȏs��K�͂̊g�������Ɏ���܂��B���̌�A�ێ������ŃX�L���P�A���ʂ����҂��鏤�i�̊J��������ɍs�Ȃ��A�ƒ�łł����y�Ȍ��N�@�Ƃ��āA��X�̓����܂��g�p������������������Ă��Ă��܂��B���̂悤�ɍ����ɂ����ẮA�����܂͉������ʋy�ѐ�����ʂɂ�鏔�Ǐ�̊ɉA���N�ێ��̈�Ƃ��ėp�����A����ɃX�L���P�A���ʂ�������̃����b�N�X�������̉��P�ɍL����^���Ă��܂��B
|
| �����܂̌��ʂƃ��J�j�Y�� |
�@�����܂̊�{�I�Ȍ��ʂ́A�i�P�j�������̂��̂ɂ���ē����鉷�����ʁi�g�̂����߂�A�ɂ݂�a�炰�铙�j�ƁA�i�Q�j������ʁi����𗎂Ƃ��A�畆�𐴏�ɂ��铙�j�����߂邱�Ƃɂ���A���̍l��������ɏ��i�ɕ\�����͍L���ł����̓I�Ȍ��\���@�ɒ�߂��Ă��܂��B
| �� |
���@���ތn������ |
|
�@���_�i�g���E���A���_�}�O�l�V�E���A�Y�_�i�g���E���A�Y�_���f�i�g���E���A�Y�_�J���V�E���A�����i�g���E���A�����听���Ƃ�����̂ŁA�܌^�I�ɂ͕����A�����������B
�@���̃^�C�v�̍ő�̌��ʂ́A���ނ��畆�̕\�ʂ̒`�����ƌ������Ė����`�����A���̖����g�̂̔M�̕��U��h�����߂ɁA������̕ۉ����ʂ������A����߂��ɂ����Ƃ������Ƃł��B���ɗ��_�i�g���E���i䊏Ɂj�͔牺�g�D�̕�����p�ƏC����p������A��������ЂсA�������ꓙ�̗\�h�Ɍ��ʂ�����܂��B�܂��A�Y�_���f�i�g���E���i�d���j�͐Ό��Ɠ����悤�ɔ畆�̉����������A������ʂ�L���Ă��܂��B�ŋߊe�n�̉���n����t�������i����������Ă��܂����A���@���ނ̑��ɍ����F���ʼn���C���̃����b�N�X���������o���Ă��܂��B |
|
| �� |
�Y�_�K�X�n������ |
|
�@�Y�_�i�g���E���A�Y�_���f�i�g���E�����ƃR�n�N�_�A�t�}���_�A�����S�_����g�ݍ��킹�����̂ŁA�܌^�I�ɂ͏��܂◱��
�@���̃^�C�v�͒Y�_�K�X�̌��NJg����p��L�����p�������̂ŁA���ɗn�����Y�_�K�X�͔畆�z���ɂ��e�Ղɔ牺���ɓ���A���ڌ��ǂ̋ؓ��֓����������ǂ��g���܂��B���ǂ��g����Ɩ������ǂ̒�R����܂�̂Ō�����������A�����ʂ������܂����A���̌��ʁA�S�g�̐V��ӂ����i����A����ɂݓ������܂��B�����ɉ��������ɓ����Ă���Ȃ�Ό��t���̕\�ʂ̔M��S�g�ւƉ^�сA�g�̂̐c�܂ʼn��܂邱�ƂɂȂ�܂��B�Ȃ��A�牺���ɓ������Y�_�K�X�͔x����ċz�ɂ���đ̊O�֔r�o����܂��̂ŁA�g�̂̒��ɒ~�ς���悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B |
|
| �� |
��p�A���n������ |
|
�@�Z���L���E�A�g�E�L�A�{�E�t�E�A�`���s�A�J�~�c���A�n�b�J�t���̐����z�����Ă���A��������̂܂܍����́A����̃G�L�X�����o���đ��̐����Ƒg�ݍ��������̓���ނ͐F�X�B
�@���̃^�C�v�̌��ʂ͐���̎�ނɂ���ĈقȂ�܂����A����Ɋ܂܂�Ă��鉻�w�����̓����ƓƓ��ȍ���̓����Ƃ��琬�藧���Ă��܂��B����͂��ꂼ�꒷�����j�̒����琶�܂�A���̌��ʂ͈�Ö�Ƃ��āA���{����łȂ����Ăł������]������Ă��܂��B�܂��A�����܂ɉ��p�����ꍇ�ɂ����s���i���ʂⓒ��ߖh�~���ʓ����F�߂��Ă���A���̃��J�j�Y���ɂ��čŋߐ���Ɍ������Ȃ���A���X�ɉ𖾂������܂��B�����āA�����ЂƂ̌��ʂł��鍁��ɂ��ẮA����Ɍ��炸�A�A���}�e���s�[�i�F���Ö@�j���ŋߒ��ڂ���A�����̑ΏۂƂȂ��Ă��܂��B����ɂ�郊���b�N�X���ʂ͔]�g��S�������̑���ɂ��ؖ�����Ă��Ă��܂��B |
|
| �� |
�y�f�n������ |
|
�@�`���������y�f�A�p�p�C���A�p���N���A�`�����̍y�f��z���������̂ŁA���@���ނƑg�ݍ��킹�Ďg�����Ƃ������B
�@�y�f�͈��i�̏����܂���ܓ��ɂ悭���p����܂����A�l�Ԃ͂�������������A���Ȃǂ̐����̑̂̒��ō���A�`�����⎉�b�A�b���������ď����������������ʂ������Ă��܂��B�����܂ɍy�f��z������ړI�́A�畆�ɖ����Ȏh����^�����ɐ���ɂ��A���̐����ƈꏏ�ɓ������ʂ����߂邱�Ƃɂ���܂��B�l�̔畆�\�ʂ̊p���w�͊O�E�̉��x��h��������̂�ی삷�铭���������Ă��܂����A�O�E���̃`���⚺���畆�\�ʂŗ��܂��Ėь���畆�̍a�̒��ɓ��荞�݁A�����ɂ�������ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B�y�f�͂��̂悤�ȉ���ɓ��ٓI�ɍ�p���āA�����������������ʂ̌`�ɕς����肵�Đ����Ղ����܂��B���̌��ʁA����͐����Ŋ��炩�Ȏg�p���������炵�܂��B |
|
| �� |
�����n���p�� |
|
�@���|�����g�[���A�Y�_���f�i�g���E���A���_�A���~�j�E���J���E������z���������̂ŁA�܌^�I�ɂ͉t�́A�����A�����������B
�@���̃^�C�v�͉Ă̓��������K�ɂ��邽�߂̂��̂ŁA��ɂ��|�����g�[����z�����ė⊴��t�^���������̂�A�Y�_���f�i�g���E���◰�_�A���~�j�E���J���E����z����������̔����T�b�p�����������̂�����܂��B�܂��A�����̐F�͐F����ɂ������̂������A���o�I�ɂ��u������t�^���Ă���܂��B |
|
| �� |
�X�L���P�A�n������ |
|
�@�Z���~�h�A�R���X�e�����G�X�e���A�������A�G�X�e�����A�X�N�������A�z�z�o���A�~�l�����I�C���A�Ĕ��y�G�L�X���̕ێ���������ɔz���������̂ŁA�܌^�I�ɂ͉t�̂������B
�@���̃^�C�v�́A�ێ��������������ɔ畆�ɋz���Z�����A�X�L���P�A���s�����̂ł��B���ɓ~�̊������́A������ߓx�Ɋp�w���̐����������A�����̂��������N����₷���Ȃ��Ă���A�����܂ɂ��X�L���P�A���d�v�ƂȂ�܂��B�܂��A�����Ŗc�����������͐Z�����Ղ���ԂɂȂ��Ă��邽�߁A�ێ����������̕\�ʂɋz�����邾���ł͂Ȃ��A�p�w�����ɂ܂ŐZ�����Ă䂫�܂��B���̌��ʁA������͂����������Ƃ�A���ׂ��ׂɂȂ�܂��B |
|
|
| ���K�ȓ����@�Ɠ����܂̊��p |
| �� |
����₦�A�X�g���X�Ɠ����̌��ʂ̊W |
|
�@���g���̉e���ɂ��ҏ��ƁA����ɑ��ĒʋΓd�Ԃ�I�t�B�X�ł̉ߗ�[�A����ɂ���ɉ����ĉď�̑����Ƃ������O�����̃X�g���X�ɂ�莩���_�o�̋@�\���ቺ���A�̉����ߏ�Q�⌌�s��Q����ꍇ������܂��B���ɗ�[�������Ă��鎺���ɒ����Ԃ���ƌ��s��Q���A�g�́i�葫�⍘�j�̗₦�ƂȂ�܂��B���̌��ʁA�H�~�s�U��s���A���ӊ��Ȃǂ̉ċG���L�̏Ǐ�A�܂�ăo�e�������Ă��܂��B
�@�����ɂ��R�̕�����p�i���M�A�����A���́j�����ʓI�ɓ����A���ɉĂ̔���₦�A�X�g���X�̉����Ɍq����܂��B�������i35�`38���j�͋ؓ���o�ɂ����A�������_�o�̓����ɂ�萸�_�I�Ȉ��炬�Ɨ����������C���ɂȂ�܂��B����A�������i42�`44���j�́A�����_�o���h�����ĐV��ӂ����ߐS�g���Ɋ����I�ɂ��܂��B�܂��A�������̐����ɂ��x�e�ʂ��������Čċz�����㏸���A�S���̓����������ɂȂ�A�S�g�̌��s���悭�Ȃ�܂��B����ɁA�����ł͐g�̂��y���Ȃ邽�߁A���邳�������Ȃ��Ȃ�A�S�g���Ƀ����b�N�X�ł��܂��B |
|
| ������₦�A�X�g���X�����̂��߂̓����@ |
| �� |
�ʂ�߁i37���O��j�̓� |
|
�@�ʂ�߂̓��ɒ��߂ɓ��邱�ƂŁA�������_�o�̓����ɂ�胊���b�N�X�ł��܂��B�܂��A�݂��������牺���������ɂ��锼�g���ł������������邱�ƂŁA�������ƃ����b�N�X�ł��܂��B�����C�����ߏ�Ɋ����c�炸�����ς肵�܂��B |
|
| �� |
�M�߁i42���O��j�̓� |
|
�@�M�߂̓��ɒZ���ԓ��邱�ƂŌ��s���悭���A��J�����𑁂���菜�����ʂ����҂ł��܂��B�������ʂ����߂Č��s�𑣐i��������܂𗘗p������A�����ɔ��������z���Ȃ��悤�ɍD���ȍ���̓����܂Ń��t���b�V������̂��I�X�X���ł��B |
|
|
| �����������������ɃI�X�X���ȓ����� |
| �� |
�������ʂ����߂Č��s�𑣐i��������� |
|
- ���_���i���_�i�g���E���E���_�}�O�l�V�E���j�≖���i�g���E���Ȃǂ�z���������@���ތn������
- �Y�_�K�X��������܃^�C�v���Y�_�K�X�n������
- �Z���L���E��g�E�L�A�`���s���̐���₻�̃G�L�X��z��������p�A���n������
�@��L�����܂����p���邱�ƂŁA�������ʂ����߂��A�������ɂȂ���܂��B |
|
| �� |
�X�g���X�����A�����b�N�X�������Ƃ��ɂ������߂ȓ����� |
|
�@�����b�N�X����ɂ́A�G�߂Ɋւ�炸�����b�N�X�ł��Ȃ��v���A���Ȃ킿�X�g���X�̌�������菜���K�v������܂��B�����܂̎g�p�ɂ���ẮA��{�I�ȓ����̌��ʂł��鉷�����ʁi�g�̂����߂�A�ɂ݂�a�炰�铙�j�����ʁi����𗎂Ƃ��A�畆�𐴏�ɕۂ��j�����߁A����ɐF�⍁����y���ދ@�����Ă���܂��B
�@�Ȃ��A�ď�̓����ɓ��ɋ��߂�����ʂƂ��ẮA
- �����ɂ��s����
- ��[�ɂ��̒��s��
- �����������ɂ�锧�̃_���[�W���̉���
�@���������܂��B
�@(1)�ɂ͔��ɂ����ς芴��������܂芴��^���鐬���Ƃ��ĒY�_���f�i�g���E���◰�_�A���~�j�E���J���E������z���������́A�܂��A�����g�[�����ɂ�鐴������t�^�������̂��I�X�X���ł��B�܂��A�F���͊��F�n�i�A�Όn�F���j�̂��̂����o�I�ɂ�������^���Ă���܂��B����(2)�ɂ͗��_�i�g���E���◰�_�}�O�l�V�E���A�����i�g���E�����̖��@���ތn�����܁A�܂��A�Y�_���ƗL�@�_�ɂ��Y�_�K�X�n�����܁A�Z���L���E��g�E�L�A�`���s���̐���₻�̃G�L�X��z��������p�A���n�����ܓ������܂�⌌�s���i���ʂ����Ă���܂��B�����āA(3)�ł̓X�L���P�A�Ɏ���u���������܂Ƃ��ăZ���~�h��X�N�������A�~�l�����I�C�������܂ޓ����܂��������܂��B�Ȃ��A��ʂɃ����b�N�X�ł���F���̓p�X�e���n�Ƃ���ĂĂ���A�C��������߂������͊��F�n�A�J�T�ȋC����グ�������ɂ͒g�F�n���L�����ƌ����Ă��܂��B�܂��A�W���X�~���n������n�̍�����C���������b�N�X���A���t���b�V������ɂ͗L���ł��B |
|
| �� |
�Q�l�F�Ă̗�[�Ȃǂɂ��₦�������������Ƃ��̓����@ |
|
�@�Ă̏����Ƃ��ɗ�[�̌������ꏊ�ɓ���̂͋C�������������̂ł����A�������A��[�̌����߂��ȂǂŊO�C���Ǝ����̍����傫���Ȃ�ƁA�����_�o�̑̉����ߋ@�\�ɂ��邢�������܂��B���ꂪ��[�Ȃǂɂ��₦�̏�Ԃł��B�����������������@�́A�ʂ�߁i37���O��j�̂����C�ɒ��߂ɓ���A�₦���g�̂����߂邱�Ƃł��B�܂��A���������ɂ����C�ɐZ����C�����Ȃ��Ƃ����l�́A�ʂ�߂̂������݂��������炢�܂œ���A�������Z���锼�g�����I�X�X���ł��B |
|
|
| �₦���������������ɃI�X�X���ȓ����� |
�@�₦�̉����ɂ́A���@���ތn��Y�_�K�X�n�A��p�A���n�����܂��I�X�X���ł��B
| �� |
���@���ތn������ |
|
�@���ނ��畆�̕\�ʂ̒`�����ƌ������Ė����`�����A���̖����g�̂̔M�̕��U��h�����߂ɓ�����̕ۉ����ʂ���������߂��ɂ����Ȃ�܂��B |
|
| �� |
�Y�_�K�X�n������ |
|
�@���ɗn�����Y�_�K�X���畆�z���ɂ��e�Ղɔ牺���ɓ���A���ڌ��ǂ̋ؓ��֓��������Č��ǂ��g���A�畆�������������܂��B���̌��ʁA�������ʂ����܂�A�₦���⌨�Â�A�g�̂̔�J���A���邳�A���ɁA�_�o�ɂȂǂ̏Ǐ�ɑ��������P���ʂ�����܂��B |
|
| �� |
��p�A���n������ |
|
�@����Ɋ܂܂�Ă��鐬���̓����ƓƓ��ȍ���̓������琬�藧���Ă��܂��B����͂��ꂼ�꒷�����j�̒����琶�܂�A���̌��ʂ͈�Ö�Ƃ��ē��{����łȂ����Ăł������]������Ă��܂��B�܂��A�����܂ɉ��p�����ꍇ�ɂ����s���i���ʂⓒ��ߖh�~���ʓ����F�߂��Ă��܂��B |
|
|
| �����܂����S���Ďg���ɂ� |
| �l�̂ւ̉e�� |
| �� |
�畆�ւ̎h�� |
|
�@���݈�O�i�Ƃ��Č����J���Ȃ̏��F���Ĕ̔�����Ă�������܂́A���̐��������̏��i�Ŏ��{���Ă���畆�h�����e�X�g�̌��ʂ��猩�Ė��ƂȂ�悤�Ȕ畆�h�����͂���܂���B�������A�ɂ��H�ɃA�����M�[���������l�����܂��̂ŁA���̏ꍇ�͎g�p�𒆎~���ĉ������B |
|
| �� |
��� |
|
�@�q�ǂ��������܂�n��������������Ĉ���ł��܂��Ă����ɖ��͂���܂���B�܂��A���i���̂��̂������r�߂��肵���ꍇ�ł��A���ʂȂ��肠��܂��A���ʂ̏ꍇ�ɂ͈�҂ɐf�Ă��炢�܂��傤�B |
|
| �� |
��ɓ������� |
|
�@�����܂�n������������ɓ������ꍇ�A�ʏ�̎g�p�Z�x�ł���Ζ��͂���܂���B |
|
| �� |
�����A�D�w�ւ̎g�p |
|
�@�Ԃ����̔畆�͎����̕��啨����������₷����A�����܂����n�ōۊ����ɑ����R�͂����Ɏキ�A�I���c���Ԃ�⎼�]�Ȃǂ̃g���u�����N���₷����Ԃɂ���܂��B�]���āA���߂̂P�����A�ł��邱�ƂȂ�R�������܂ł͐Ԃ�����p�̗�����p���A�E�ۍ�p�̂��韔���܂��g�p���āA�畆�����肵�Ă����R��������������܂̂����C�Őe�䂳��ƈꏏ�ɓ������ĉ������B�܂��A�D�w�ւ̎g�p�ɂ��Ă͓��ɐ����͂���܂���B |
|
| �� |
�Q�l�F��ԕ��C�Ɠ����� |
|
�@�Ԃ����̔畆�͎����̕��啨����������₷����A�����܂����n�ōۊ����ɑ����R�͂����Ɏキ�A�I���c���Ԃ�⎼�]�Ȃǂ̃g���u�����N���₷����Ԃɂ���܂��B�]���āA���߂̂P�����A�ł��邱�ƂȂ�R�������܂ł͐Ԃ�����p�̗�����p���A�E�ۍ�p�̂��韔���܂��g�p���āA�畆�����肵�Ă����R��������������܂̂����C�Őe�䂳��ƈꏏ�ɓ������ĉ������B�܂��A�D�w�ւ̎g�p�ɂ��Ă͓��ɐ����͂���܂���B |
|
|
| ���A���A�_�앨�A�����ւ̉e�� |
| �� |
���A���A�_�앨�ւ̉e�� |
|
�@�����܂��g���������C�̎c�蓒�������p�̐��Ƃ��ė��p������A�A���ւ������肷�邱�Ƃ͔����ĉ������B�A���̎�ނɂ���Ă͓����܂̐������������̂�����܂��B |
|
| �� |
�����ւ̉e�� |
|
�@�e������܂̐����𐫂𑪒肵�����ʂł́A�����60%�ȏ�̐����𐫂������܂������A����͐Ό��⍂���A���R�[���n�E�ʊ����܂Ɠ����̃��x���ŁA�����܂̎g�p�������ɑ��Ĉ��e�����y�ڂ����Ƃ͂Ȃ��ƍl�����܂��B |
|
|
| �����A���C���ւ̉e�� |
| �� |
�����ւ̉e�� |
|
�@���{�ő����g���Ă��闁���̍ގ��͋����v���X�`�b�N(FRP)��z�[���[�A�X�e�����X���ł����A���̑��ɂ���^�C���A�嗝�Ȃǂ�����܂��B�s�̂���Ă�������܂̑啔���͗��������߂��菝�����肷�邱�Ƃ͂���܂��A�����z���̓����܂͋����H�����鋰�ꂪ����܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B�܂��AFRP�̈ꕔ��嗝�̗����ł́A��x�ɑ��ʂ̓����܂��g�p����Ɨ����\�ʂ̌���������Ă��܂����̂�����܂��̂ŁA���i�̒��ӏ������悭�ǂ�Ŏg�p�@�����悤�ɂ��܂��傤�B�Ȃ��A�ŋߓ�������^�C�v�̓����܂��o����Ă��܂����A���̃^�C�v�̓����܂�n�������c�蓒���ԗ����ɓ���Ă����ƁA�����̒��܂�肪�����Ȃ邱�Ƃ�����܂��B�������A�����ɂ͉e���Ȃ��A���C�p��ܓ��Ő����Ƃ��ꂢ�ɂȂ�܂��B |
|
| �� |
���C���ւ̉e�� |
|
�@�����̓����������ɂ́A�i�P�j�����������璼�ډ��M������@�A�i�Q�j�����������������痁���֓������@�i�������j�A�i�R�j�����ƕ��C�����p�C�v�łȂ��œ����z��������@�i�z���j��������܂����A�����̓������ڕ��C����p�C�v�ƐڐG����̂͏z���̏ꍇ�ł��B�z���ɂ͎��R�z�����ƃ|���v�ɂ�鋭���z�����Ƃ�����A���̍ގ��ɂ͓���A���~�j�E������ʓI�ɗp�����Ă��܂��B�]���āA�����ւ̉e���Ɠ��l�ɁA�啔���̓����܂͕��C���������߂��菝�����肷�邱�Ƃ͂���܂��A�����z���̓����܂͏z���̕��C����p�C�v�H�����鋰�ꂪ����܂��̂Œ��ӂ��ĉ������B�܂��A�����z�����ɂ͏z�r���Ƀt�B���^�[���Z�b�g����Ă��܂����A�є��≘��Ȃǂɂ��ڋl�܂���A���̏z�ʂ����Ȃ����߂ɉ��������Ă��܂����Ƃ��H�ɂ���܂��̂ŁA�[���������ĉ������B���ɓ�������^�C�v�̓����܂ł́A���C�������̓��C���ɑ��萬�����ꕔ�t�����ďz�E���痁�����֏o�Ă��邱�Ƃ�����܂��̂ŁA���C��������z�E�̃t�B���^�[���z�[�X�Ȃǂ��g���Ă悭�����邱�Ƃ��I�X�X�����܂��B |
|
| �� |
�Q�l�F�����A���C���̎戵���������ɂ��� |
|
�@�����╗�C���̎g�p��̒��ӂƂ��āu���_�A���A���J����܋y�ї��������܂ޓ����܂≷�́A�����y�ѕ��C���̍ގ�������A�����Ȃ����Ƃ�����܂��̂Ŏg�p���Ȃ��ʼn������v�Ƃ������L�ڂ�����܂����A���ݎs�̂���Ă�������܂̑唼�͎g�p���Ɏ_����A���J�����ɂ͂Ȃ�܂���B�]���āA�����╗�C���̍ގ��Ȃ����Ƃ͂���܂��A�g�p�ɍۂ��Ă͓����܂̏��i�p�b�P�[�W�ɋL�ڂ̒��ӎ������悭�ǂ�ł����������̂ł��B |
|
|
| �����A���ւ̉e�� |
�@�����܂͓��̒��ɋK��ʂ𓊓����A�����������������^���A�������ʂɂ�鏔�Ǐ�̊ɉ������҂ł���ƔF�߂�ꂽ���̂ł��B���R�̂��ƂȂ�������܂̓����������̔畆�ɑ�����S���ɂ��Ă͏�ɒ��ӂ������Ă��܂��B���̓����������Ɏg�p���Ă��Ό����痿�A�V�����v�[���̐��͂ɂ͖w�lje�����܂���B�܂��A�畆��є��������߂邱�Ƃ�����܂���B�Ȃ��A�ƒ땗�C�ɂ����ĉƑ���������̓��́A�玉��p�Г��̉��������R�l�����܂��̂ŁA�q����̊ϓ_����������܂��͓�����̎c�蓒�ł̐�������͔�������������ł��傤�B�c�蓒���������Ɏg�������́A���瓒�ŏ[�����Ƃ��I�X�X�����܂��B
|
| ����ւ̉e�� |
�@�����܂��g�p�����ƒ땗�C�̎c�蓒�͐���p���Ƃ��Ďg���邱�Ƃ���������܂��B���̎c�蓒�͐�܂̐��͂ɂ͖w�lje���͂���܂���̂ŁA����p���Ƃ��ď[���g�p���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�����܂ɂ͗L�������̑��ɐF�f�y�э��������z������A��������Ɣ������F���̗����͔�������A�ЂƎ��̃o�X�^�C�����y���܂��Ă���܂��B�������A���̒W���F�̎c�蓒�����Ɏg�p���邽�߂Ɉߗނւ̒��F�����Ƃ��Ď��グ���邱�Ƃ�����܂��B���Ɉߗޗp�_��d�グ�܂��g�p����ꍇ�A�܂��͂��낵���Ă̈ߗނ̂悤�ȏ_��d�グ�܂ŏ����������̂����ꍇ�Ɉߗނɒ��F���邱�Ƃ�����܂��B����́A�_��d�グ�܂̗L�������ł���z�C�I���i�J�`�I���j�E�ʊ����܂ƐF�f���������Đ��s�n�������������A�ߗނɔ������F���N���������̂ł��B��ɔ��n�̐��n���Ɏ��Ⴊ�����܂����A��܉t�Ő���Δ�r�I�ȒP�ɐ��Ƃ����Ƃ��ł��܂��B����ɗ����Ȃ����ɂ͕Y���܂��g�p���ĉ������B���ꓙ�𖢑R�ɖh�����߂ɁA��ʂɓ����܂��g�p�����c�蓒�����Ɏg�p���鎞�́A��܂�p���Đ�������Ɛ������ł悭�A��ɏ_��d�グ�܂��g�p���邱�Ƃ��I�X�X�����܂��B�Ȃ��A�w�ǂ̓����܂͎g�p���@�̒��ӏ����ɁA�c�蓒�Ə_��d�グ�܂̕��p�������悤�ɕ\�������Ă��܂��B���Ȃ݂ɁA�ŋߏ�s����Ă���_��d�グ�ܓ���܂Ő���ꍇ�ɂ́A�����܂��g�p�����c�蓒�Ő��Ă����F���̖��͂���܂���B�܂��A�����܂������ƌ�F�����P�[�X�Ƃ��Ĉڐ��̖�肪����܂��B�F���Ɣ��n�̈ߗނ��ꏏ�ɐ������̈ڐ��␅���̓S�C�I���iFe3+�j�ɂ�鉩�ݐ�����������܂��̂ŁA�[���Ȓ��ӂ��K�v�ł��B
|
|
| �Q�l�F��������܂ʼn���C�� |
| �� |
�����C |
|
�@�V�R�����ЂƂ��݂����C�ɓ���܂��B���͔畆�̘V�p����]���Ȕ玉����菜���A���s��ǂ����Ă���܂��B�g�̂����܂�̂ŁA�����G�߂ɃI�X�X���ł��B |
|
| �� |
�t���[�c���C |
|
�@�I�����W������A�����S�Ȃǂ̔���e�B�[�|�b�g�ɓ���A�M���𒍂�5���قǏ��炵�Ă��炨���C�ɔM����炲�Ɠ���܂��B����̂悤�ɐg�̂̐c���牷�܂�A����߂��ɂ��������C�ɂȂ�܂��B |
|
| �� |
�I�����C |
|
�@�I������Q���炢�������C�ɓ���A�悭�~�������܂��B�I���̓r�^�~���E�~�l�����𑽂��܂�ł���̂ŁA���ɉh�{��^���Ă���܂��B�܂��A�E�ی��ʂ�����A���𐴌��ɕۂ��Ă����̂ŁA�j�L�r���ł��Ă��鎞�ȂǂɌ��ʓI�ł��B |
|
| �� |
���C�����C |
|
�@���C���Q�J�b�v���炢�������C�ɓ���悭�~�������܂��B���C���͘V����h���A���t�@�n�C�h���L�V�_�i�`HA�_�j���܂�ł���̂ŁA������X�����ۂ��Ă���܂��B��ʓI�ɐԃ��C���͎��ʌ��ʂ�����A�I�C���[���̐l�����A�܂��A�����C���̓h���C���̐l�����Ƃ���Ă��܂��B |
|
| �� |
�n�[�u���C |
|
�@�n�[�u�ɂ͗l�X�Ȗ��������܂��B�|�b�g�Ƀn�[�u�e�B�[��Z���߂ɓ���A�|�b�g���炨���C�ɒ����ł悭�~�������܂��B�܂��A�h���C�n�[�u������ΖؖȂ̑܁i�K�[�[�Ȃǁj�ɓ���Č���A���̂������痁���ɓ���ĕ������܂��i�������Ȃ���20���قǎϏo�������̂������C�ɓ���܂��j�B�h���C�n�[�u���g���ƁA�̂悤�ȃ��[�h�̂����C�ɂȂ�܂��B |
|
| �� |
�~���N���C |
|
�@�����R�J�b�v���x�������C�ɓ���Ă悭�~�������܂��B�����͔��ɉh�{��^���A�����_�炩�����Ă���܂��B�~���N���C�ɓ���ƁA���������Ƃ�Ƃ��āA���ɂȂ�܂��B |
|
|
[ �y�[�W�g�b�v ] [�A�h�o�C�X�@�g�b�v]
|
|