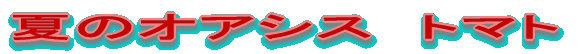| 【1】食品としてのトマト~その歴史と料理~ |
健康にもよいと言われ、様々な料理にも使われるトマトですが、本節では、トマトはどんな食品なのか、その歴史も含めて解説しました。
|
| トマトとは? |
 トマトはアンデス西斜面のペルーやエクアドル地方が原産地で、熱帯から温帯地方にかけて広く栽培されています。温帯では一年生で、熱帯では多年草になりますが、栽培上は一年草として扱われます。茎は1~1.5mに達し、直立ないし匍匐(ほふく)し、自然には直立できず、地面に這う形になり、茎の下部が地面に接するところからは不定根を出します。葉は多数の小葉からなる羽状複葉で茎に互生し、長さ15~45センチメートルの羽状複葉で柔毛があります。小葉は5~9対で、長さ5~7.5㎝。花は黄色で直径約2~3㎝、花房は総状花序で4~10数花よりなり、花房は通常茎の基部から数えて7~9節の節間に形成されるのをはじめとして、先端に向かって順次3節間おきにつくのが普通です。個々の花は両性かつ合弁で、花弁は5~6裂し、黄色、時に白色を呈します。葉腋(ようえき)に3~7花が房に成って付きます。また、果実の内部は数室に分かれ、多数の種子が入っています。果実の形は品種によって大小様々で、また果色も赤、紅、黄色など様々ですが、日本では生食用には桃紅色の果実が好まれるため殆どが桃紅色の品種です。また、直径2~3センチメートルの赤または黄色の果実を房成りにつける品種や、また卵形や西洋ナシ形の小形の果実の品種も普及しています。植物全体に特有の臭気がありますが、この臭気は黄色透明の揮発性油によるものです。なお、日本への伝播は1580年頃にポルトガル人によって伝えらたのが初めで、主に観賞用として楽しまれていました。また、明治時代には赤茄子として洋食には使われていたものの、一般の人の間で本格的に食べられるようになったのは昭和30年代からだそうです。
|
| トマトの歴史~その起源と伝播~ |
トマトの起源と普及は比較的新しく、栽培トマトの成立は紀元後1000年頃と考えられています。現在広く世界で栽培されているトマトの祖先種は、その一つの変種ケラシフォルで、これには野生型と最も原始的な栽培型があります。この分布地域はトマト属の野生種と同じくエクアドルからチリ北部に至る幅150キロメートルの狭長な海岸地帯(赤道から南緯30度)ですが、さらに北はメキシコの南部から中央部の東海岸沿いの低地にまで及びます。特にベラクルスを中心として豊富に自生し、その栽培型も明らかに栽培トマトとの移行型を示す種々な型があります。従って、トマト属野生種の中心であるペルーにおいてケラシフォルメの野生型から栽培型が成立してメキシコ地域において現在見られる最も進化したトマトが成立している点から、トマトはメキシコ起源であると考えられます。この地域はアステカ文化圏で、アステカ人は好んでホオズキを食用に供し、トマトに似たホオズキの育成・栽培をしていることから、ケラシフォルメの栽培と育成に努めたことが考えられます。また、アステカ人はその栽培トマトの品種の語尾にナワトゥル語のトマトルをつけますが、この言葉が世界各国に伝播しました。
トマトは、ヨーロッパ人による新大陸発見後、1523年のスペインのメキシコ征服後、スペイン人によってヨーロッパに入り、1544年イタリアに、1575年イギリスに、さらに中欧諸国に伝播しました。最初は観賞用で、食用に供したのは18世紀以降である。アメリカには18世紀末にヨーロッパから入ったが、19世紀末までは普及しませんでした。アジアへはスペイン人によって太平洋経由でフィリピンに入り、1650年以降マレーシア東部でも栽培されます。日本へは寛文年間(1670年頃)に長崎に伝来し、『大和本草(やまとほんぞう)』(1709)に記載されています。その後、明治初年に開拓使によって欧米から品種が導入され、赤茄子の名で試作されました。しかし、当時は独特の臭みのため普及せず、大正時代に入って北海道と愛知県を中心として栽培が増加したものの、現在のように普及をみたのは第2次世界大戦後です。
上で既に触れたように、アンデス高原地方ではアメリカ大陸発見以前からトマトが食用として栽培されていたと言われ、インディアンの移住によってアンデス高原から次第に中央アメリカやメキシコに伝播しました。ヨーロッパへは大陸発見後16世紀の初めにイタリアに導入されますが、当初は観賞用として栽培されたにすぎず、18世紀中頃になって食用として栽培されるようになりました。また、北アメリカへは18世紀の後半に導入されました。アメリカとイタリア両国では19世紀に入って急速に栽培が増加し、現在世界の主要な生産国となっています。また、日本へは18世紀初めの貝原益軒の『大和本草』にトマトのことが「唐柿」と記されていることから、それ以前に南方や中国を経て渡来したと考えられます。当時は観賞用として栽培されるのみで、食用としての栽培は明治初年の開拓使による新品種の再導入を機に始まりますが、しかし、食味が一般の嗜好に合わず、栽培は大正末頃まで僅かでした。それが昭和に入ってから食生活の洋風化に伴って需要が増加し、また加工利用の道も開けて、その栽培は急速に増えてゆきます。各種の作型が発達し、生果は年間を通じて供給され、その一方で総生産量の20~25%は加工用に回されています。なお、主産地は熊本や千葉、愛知県などです。
|
| トマトの栽培 |
トマトは、明治初年から昭和初めにかけてアメリカやイギリスから多くの品種が導入されますが、それらのうち桃色大果で酸味の少ないポンデローザが歓迎され、広く栽培されます。また、導入された品種を下に選抜淘汰や交雑育種も試みられ、1935年頃から次第に導入品種に代わって日本で育成された品種が主体を占めるようになってゆきました。第2次世界大戦後は一代雑種育種が盛んになり、福寿2号や新星、ひかり、宝冠2号、栄冠などの大果で酸味の少ない品種が多数発表されてゆきます。近年は料理用の酸味の強い小果品種も見直され、家庭用ミニトマトとして栽培が広がっています。もっとも産地の固定化が進み、また連作が重なると、種々の病害、特に青枯病など土壌伝染性の病害が栽培上問題となりますが、しかし、このような状況の中で耐病性育種も進み、現在広く栽培されている品種は殆ど耐病性品種となっていて、さらに接木用の耐病性台木品種も開発されています。また、トマト栽培の作型は大別して次の5通りがあり、年間を通じての供給が維持されています。(1)露地栽培:3月蒔き、6月下旬~8月収穫。(2)促成栽培:9~10月蒔き、2月上旬~5月中旬収穫。(3)半促成栽培:11月蒔き、4~6月収穫。(4)高冷地抑制栽培:4月蒔き、8月下旬~10月下旬収穫。(5)ハウス抑制栽培:7月上旬~中旬蒔き、10~12月収穫。何れも育苗で定植して栽培し、生果用には支柱を立てて仕立てますが、世界的にみれば無支柱の栽培が一般です。
トマトの栽培は、まず苗床に種子を播いて苗を育て、畑やハウスに定植します。葉腋から盛んに腋芽を出して茂りまするが、日本で生食用果実を得る目的で栽培する時には、腋芽を全部摘み取って1本の茎だけを支柱を立てて仕立てることが多いです。一方ジュースやケチャップなど加工用の目的で栽培する場合には、支柱をせず腋芽も摘まずに育てる無支柱栽培が行なわれます。なお、トマトは低温には比較的強いものの、1回でも霜に当たれば枯死してしまいます。土壌病害である青枯病に侵されると急に茎の先から萎れ、数日中に地上部全体に及んで枯死するのです。土壌伝染性の病害を避けるため、トマトはもとよりナスやジャガイモなどナス科の作物との連作は避け、また、土壌病害抵抗性の台木専用トマト品種、たとえばBF興津(おきつ)101号などに接木もされます。旬は夏ですが、現在では促成・抑制栽培などによって一年中生産されています。しかし、低温期の栽培では着果不良になりやすく、パラクロルフェノキン酢酸(商品名:トマトトーン)を花房に噴霧して着果と果実の肥大を促進させています。なお、現在日本で経済的に栽培されている品種は全て一代雑種品種(F1)です。
|
| 食品としてのトマト |
トマトの果実成分は95%が水分で、トマトの果実成分は水分95%、全糖3~4%(※蔗糖が主で、果糖やブドウ糖を含む)。酸類は0.5%でクエン酸を主とし、シュウ酸やリンゴ酸も含みます。タンパク質0.7%、脂質0.1%、糖質3.3%、繊維0.4%、灰分0.5%を含んでいます。ビタミン類の含量に優れ、100グラム当りカロチン390マイクログラム、ビタミンC20㎎、B10.05㎎、B20.03㎎の他、B6、K、P、M、ルチン、ナイアシンなども含みます。特にビタミンAとCが多く、灰分はカルシウムやカリウム、リンなどが多く含まれます。その他、アデニンやトリゴネリン、アルギニンを含んでいます。また、果実の赤色はリコピン、橙黄色はカロチンによるものです。さらに甘味の成分は果糖とブドウ糖で、酸味の主体はクエン酸とリンゴ酸です。このように、トマトはビタミン食品であるだけでなく、アルカリ食品としての意義が大きいのです。そんな訳でトマトは健康によい食品とされており、「トマトが赤くなると医者が青くなる」とか「トマトのある家に胃病なし」などと言われていることもよく頷けます。
トマトは生食する他、加工用として缶詰やジュース、ピューレ、ペーストなど料理にも色々と使われています。それぞれ生食用品種と加工用品種がありますが、加工用は汁気が少なく、皮も堅くて生食用には適していません。加工品としてはジュースやピュレー、パウダー、或は調味料を加えたトマト・ケチャップやトマト缶詰があります。一方生食用トマトは、流通経路での痛みを少なくするため、果実が緑色で堅いうちに収穫し、小売店の店頭でちょうど食べ頃になるように出荷されます。しかし、このようなものは畑で完熟させた果実に比較して食味が劣るのも事実で、そこで最近では、特に完熟トマトと表示された完熟した果実を収穫したものが店頭に出回るようになりました。また、観賞用とされる品種も存在します。
|
| 変わり種のトマト |
| ■ |
塩トマトは甘味と酸味の絶妙なハーモニー |
|
塩トマトと呼ばれるトマトがあります。塩トマト発祥の地は九州地方の熊本県八代地域の海岸を埋め立てた干拓地で、その農業に向かないとされていた塩分濃度が高い土壌から塩トマトが生まれました。塩分が多い土壌のため、水分を充分に吸収できないため、トマトそのものは小ぶりです。しかし、塩トマトの果肉は密度が高くしっかりとした歯応えがあります。なお、甘いトマトと言えば果物のような甘さのフルーツトマトがありますが、塩トマトもそれと同じくらいの甘さを持ち合わせています。塩トマトはフルーツトマト並みの甘さだけではなく、トマトが本来持っている酸味もしっかりあるのです。その甘味と酸味の絶妙なハーモニーは今まで食べたことのないトマトの旨みを作り出しました。塩分濃度が高い土壌という特殊な環境で育つ塩トマトの出荷量は非常に少なく貴重なトマトです。 |
|
| ■ |
トマト嫌いの人にも人気のフルーツトマト |
|
フルーツトマトという名の果物のようなとても甘いトマトがあります。トマトの糖度というのは普通4とか5くらいなのですが、フルーツトマトは糖度が8以上もあり、その糖度の基準をクリアしないとフルーツトマトを名乗ることはできないのです。また、フルーツトマトの大きさは通常のトマトに比べると小さいのですが、プチトマトほどではありません。普通の大きさのトマトとプチトマトの中間くらいの、食べるには程よいくらいの大きさです。そして、フルーツトマトの栄養素はカリウムやペクチン、ビタミンB6、ビタミンK、そしてリコピンで、普通のトマトと全く変わりはありません。ただ果物のような甘さがあるだけが違いです。そして、その甘いフルーツトマトから作られたジュースは格別に美味しいです。また、フルーツトマトの糖度は普通のトマトの約2倍くらいですから、トマト嫌いの方でも美味しく食べられる人もいるでしょう。トマトの酸味がダメという方でも、フルーツトマトなら大丈夫です。少なくとも通常のトマトほどの酸味はフルーツトマトにはありませんし、とにかく甘いですから、これなら食べられるという人も多分いるのではないと思います。 |
|
| ■ |
ミニトマトと普通のトマトの違い |
|
 ミニトマトは栄養的にみると、普通のトマトよりもカロチン及びビタミンCが豊富です。また、カリウムや鉄、亜鉛などのミネラルの含有量も多くなっており、さらに普通のトマトよりも赤みが強くて、リコピンの含有量も多くなっています。ただし、味や食感は普通のトマトの方が美味しいと言う人が多いようです。 ミニトマトは栄養的にみると、普通のトマトよりもカロチン及びビタミンCが豊富です。また、カリウムや鉄、亜鉛などのミネラルの含有量も多くなっており、さらに普通のトマトよりも赤みが強くて、リコピンの含有量も多くなっています。ただし、味や食感は普通のトマトの方が美味しいと言う人が多いようです。
トマトは茄子の仲間で、漢字では蕃茄と書きます。トマトは他の野菜と同様ビタミンCを多く含み、癌予防の効果が高いと指摘されているリコピンも大量に含んでいます。また、最近よく目にする小さいトマトはミニトマトまたはプチトマトなどと呼ばれていますが、欧米ではチェリートマト(cherry
tomato)と呼ばれています。ちなみに、ミニトマトはミニ(mini 英語)+トマト(tomato 英語)、プチトマトはプチ(petit 仏語)+トマト(tomato 英語)の合成語で、何れも和製語です。ミニトマトは普通のトマト(大玉トマト、中玉トマト)に対して、エネルギー(カロリー)、蛋白質、カリウム、カルシウム、食物繊維などが約1.5倍、ビタミンAは約2倍も含まれていて、栄養上非常に優れています。また、トマトは一般に連作を嫌いますが、ミニトマトは落ち葉や堆肥を十分入れて土作りをすれば連作も不可能ではないそうです。栄養豊富で手軽にできるミニトマトで健康増進を図るのもよいかも知れません。 |
|
|
| トマトと料理 |
| トマト料理 |
トマトは料理の付け合せとして、また、スープやソース、シチューなどの煮込み、また、バター焼きや蒸焼きなどにも利用します。また、トマトはサラダやサンドイッチの具などとして生食する他、ジュースやピュレー、ケチャップなどの原料になります。たとえばスタッフドトマトは、トマトをくり抜いてケースを作り、サラダを詰めて付合せにしたり、挽肉やタマネギなどを炒めて詰め、オーブンで焼いたりします。またフランスでは、裏漉しして作ったピュレーを色々な料理に使い、イタリアではトマトを刻んで、肉やニンニク、タマネギなどと共に油で炒め、スープで伸ばしたものをスパゲッティその他に多用します。この方式の利用は日本ではあまり行なわれていいませんが、カレーやシチューに加えても美味ですし、もっと多面的に使いたいものです。
なお、トマト特有の青臭い臭いは青葉アルコールと呼ばれる成分を中心にしたもので、これには生臭みを消す働きがあるため、シチューやミートソースなどを作る時、肉と共に煮込むと肉の臭みが消えます。また、加熱調理には適熟トマトの他、水煮或はトマトジュース漬けにした缶詰も利用が可能です。最近は糖分の多い小粒のトマトも多く出回っていて、これらは料理の飾りやデザートのフルーツのかわりとしても食べることができます。また、トマトの皮は果実を熱湯にくぐらせると手で容易に剥けるようになります。
|
| イタリア料理とトマトソース |
イタリア料理の歴史はヨーロッパ諸国の中でも最も古いとされます。その証拠に、紀元1世紀頃ティベリウス帝時代のローマの富豪と言われたアピキウスの著と推定される調理書が写本で残されていますし、ローマ帝政時代に属州から珍しい物産を集めて食事に贅の限りを尽くした貴族の生活ぶりは当時の文献からも窺い知ることが出来ます。また、11世紀にはビザンティン帝国からベネチアにフォークが伝えられています。さらに16世紀には、カテリーナ・デ・メディチがフランスのアンリ2世に嫁いだ時は、調理人まで連れて行ったばかりか、ルネサンスの中で開花したフィレンツェの食事文化をフランスの宮廷に紹介したと言われます。このように、イタリア料理は西洋料理の先駆的役割を果たし、その後のヨーロッパ各国の食事文化に影響を与えてきたのです。なお、イタリアはまた世界有数のブドウ酒とオリーブ油の産出国でもあります。食用油は、南部はオリーブ油、中部はラードとオリーブ油、北部はバターとラード、オリーブ油の順に消費されていますが、ブドウ畑はイタリア北部ピエモンテ地方から南部シチリアに至るまでほぼ均等に分散しており、こうした自然の産物がイタリア料理文化を形成していると言えます。しかし、フランス料理の統一化に比べてイタリア料理の方は大幅に遅れており、19世紀フランスで開花した料理の絢爛たる豪華さはイタリア料理には見られません。いわば素朴な地方料理が比較的修正を加えられずに今日あることにイタリア料理の特質があると言えばよいでしょうか。
 今日のイタリア料理を体系化したのは,P. アルトゥージが1891年に出版した『調理科学と食事法』という本によるところが大きいとされます。中世以降のイタリアは、教皇領や王国、都市国家、大公国、伯領など無数の小国に分断され、料理も一部の都市国家や特権階級を除いては自給自足経済に基礎を置く郷土料理でした。それが1861年に近代統一国家が成立すると、産業革命の影響も受けて中世紀的雰囲気は一挙に崩れます。この時機にアルトゥージはイタリア各地の郷土料理の境界を取り除いて、スープ、ミネストレ(※パスタ、ポレンタ、リゾットなどの総称)、オードブル、ソース、卵、パイ生地、詰物、揚物、茹で物、煮物、冷製、野菜、魚料理、焼物、菓子、トルテ、シロップ、保存食、リキュール、アイスクリームその他の項目別に整理することによって、現代イタリア料理の基礎を確立したのです。 今日のイタリア料理を体系化したのは,P. アルトゥージが1891年に出版した『調理科学と食事法』という本によるところが大きいとされます。中世以降のイタリアは、教皇領や王国、都市国家、大公国、伯領など無数の小国に分断され、料理も一部の都市国家や特権階級を除いては自給自足経済に基礎を置く郷土料理でした。それが1861年に近代統一国家が成立すると、産業革命の影響も受けて中世紀的雰囲気は一挙に崩れます。この時機にアルトゥージはイタリア各地の郷土料理の境界を取り除いて、スープ、ミネストレ(※パスタ、ポレンタ、リゾットなどの総称)、オードブル、ソース、卵、パイ生地、詰物、揚物、茹で物、煮物、冷製、野菜、魚料理、焼物、菓子、トルテ、シロップ、保存食、リキュール、アイスクリームその他の項目別に整理することによって、現代イタリア料理の基礎を確立したのです。
イタリアはローマ帝国以来の歴史的背景と地中海に突出している地理的条件から、その料理も多様性に富んでいます。たとえばヨーロッパ各国では、スペインのパエーリャのような例を除いてパンを常食としていますが、イタリアにはパン以外にパスタやリゾット(※米をタマネギとバターで炒め、ブイヨンで煮込んだもの)、ポレンタ(※トウモロコシ粉をブイヨンで火にかけながら練った料理)があります。米はポー川の中流域平原に位置するロンバルディア州とピエモンテ州で生産され、トウモロコシはイタリア北部の傾斜地で生産されるため、リゾットやポレンタの料理はイタリア北部に起源を発しています。それに対してスパゲッティやマカロニなどの乾燥パスタがイタリア南部で常食とされたのは、硬質小麦の耕作地がかつてはイタリア南部に広がっていたことと、機械生産以前のパスタの自然乾燥条件がナポリ周辺のカンパニア地方に備わっていたことに由来しています。乾燥パスタの発展はまた、ナポリで成功したソース用トマトの品種改良を抜きにしては考えられません。17~18世紀と推定されるトマトソースの出現で、乾燥パスタ料理は急速に中部&北部へと普及してゆきます。さらに、トマトソースはまたピッツァの普及にも大きく貢献しています。ピッツァがいつ頃・どのように作られたのかは仮説の域を出ていませんが、トマトをパセリとアンチョビー、オリーブ油で煮込んでオレガノを加えたいわゆるピッツァソースがピッツァに塗られ、モッツァレッラチーズ(※水牛の乳で作るチーズ)をその上に散らしたナポリ風ピッツァは、イタリア南部、殊にカンパニア州の州民の心を捉えました。歴史的起源を14世紀にまで遡ることのできる手打ちパスタは、イタリア北部、殊にエミリア・ロマーニャ州で今日もよく食べられています。基本的には小麦粉を卵だけで練り上げ、1mm前後の厚さの薄板状にのして様々に切り、スープの浮身や詰物、グラタンにするなど、その用途は多様です。イタリアは三方が海に囲まれている関係から、フランスのブイヤベースに似た魚介類の寄せ鍋料理や、その他エビやカニ、イカ、タコ、アサリ、ムール貝、イワシ、マグロを使った料理も数多くあります。恐らくヨーロッパで最も魚介類を食する民族だと言ってよいでしょう。なお、このようなイタリア料理が諸外国に伝わるのは20世紀前後からのことで、アメリカに移民したイタリア南部の農民は伝統的イタリア料理の食習慣を絶ち難く、イタリアからパスタ食品を取り寄せながらイタリア料理を定着させてゆきました。また、日本では明治末期にマカロニが輸入された記録がありますが、しかし、それがイタリア料理として親しまれるようになるのは1970年代からのことで、ピッツァやスパゲッティなどのパスタ料理が注目され、日本人の麺類嗜好と重なって定着してゆきました。
|
| ケチャップ |
 トマトやマッシュルーム、クルミなどに各種の調味料や香辛料を加えて作るソースの一種で、catchup、catsupとも書きます。東南アジアから中国南部にかけての地域で古くから調味に用いられてきた塩蔵魚貝類の浸出液に起源を持つもののようで、中国福建省厦門(アモイ)周辺ではこうした魚捺(ぎよしよう)をケチャップと呼ぶところがあり、類語は各地にあったそうで、これが伝わったものか、18~19世紀のイギリスの料理書には牡蠣やマッシュルーム、クルミ、キュウリの他、魚や漿果(しようか)類に食塩や酒、香辛料などを配した各種のケチャップが記載されています。その後これらの大半は廃れ、現在ではトマトやマッシュルーム、クルミなどのものが作られています。代表的なのはトマトケチャップで、これはトマトを砕いて裏漉ししたものに食塩や酢、砂糖などの他、多種類の香辛料を配して濃縮したものです。テーブルソースとされる他、米飯やスパゲッティの味付けなどに用いられます。ちなみに、マッシュルームケチャップは、マッシュルームの塩蔵汁に香辛料と香草を加えて加熱したもの、クルミケチャップは磨り潰したクルミに酢と醤油、タマネギ、香辛料などを加えたもので、共にウースター・ソースの風味付けに用いることが多いです。 トマトやマッシュルーム、クルミなどに各種の調味料や香辛料を加えて作るソースの一種で、catchup、catsupとも書きます。東南アジアから中国南部にかけての地域で古くから調味に用いられてきた塩蔵魚貝類の浸出液に起源を持つもののようで、中国福建省厦門(アモイ)周辺ではこうした魚捺(ぎよしよう)をケチャップと呼ぶところがあり、類語は各地にあったそうで、これが伝わったものか、18~19世紀のイギリスの料理書には牡蠣やマッシュルーム、クルミ、キュウリの他、魚や漿果(しようか)類に食塩や酒、香辛料などを配した各種のケチャップが記載されています。その後これらの大半は廃れ、現在ではトマトやマッシュルーム、クルミなどのものが作られています。代表的なのはトマトケチャップで、これはトマトを砕いて裏漉ししたものに食塩や酢、砂糖などの他、多種類の香辛料を配して濃縮したものです。テーブルソースとされる他、米飯やスパゲッティの味付けなどに用いられます。ちなみに、マッシュルームケチャップは、マッシュルームの塩蔵汁に香辛料と香草を加えて加熱したもの、クルミケチャップは磨り潰したクルミに酢と醤油、タマネギ、香辛料などを加えたもので、共にウースター・ソースの風味付けに用いることが多いです。
|
| ピュレー |

ピュレーとは、野菜や果物、肉、魚などを潰して裏漉ししたものを言います。野菜のピュレーは茹でた野菜を潰して裏漉しし、バターや牛乳、生クリーム、塩・胡椒などで調味し、付合せにしたものです。ピュレースープはニンジンやグリーンピースなどを炒めてブイヨンで煮込み、裏漉しにかけて牛乳などを加え、塩・胡椒などで味を調えたものです。また、肉や魚のピュレーは卵白や生クリームを加えて滑らかに仕上げ、これを茹でたり蒸したりしてムースにしたものです。そして、市販のトマトピュレーは、トマトの裏漉しを煮つめて濃縮したものです。
|
| ペースト |
ペーストとは、魚肉やレバー、トマトなどを磨り潰して柔らかく滑らかにした食品を言います(※なお、この言葉はパイ皮用に小麦粉を練った生地のことを指すこともあります)。たとえばレバーペーストは、牛や鶏、豚のレバー(肝臓)を茹でて裏漉しし、これにバターや香辛料、調味料などを加えて練ったものです。パンに塗ってそのまま食べたり、オードブルのカナッペなどに使います。そしてトマトペーストは、トマトを煮て裏漉しして皮や種を除き、さらに煮詰めて水分を少なくしたもので、西洋料理の煮込みやソースなどの調味料として用います。この他、アンチョビーペーストやアーモンドペーストなどもあります。
|
|
| 参考1:トマトを保存用に加工する方法 |
農家ではトマトの収穫時期には捨てる程の量が採れて食べられずに処分に困ることがあります。この場合はトマトを煮ておくと保存が効きます。その後、小分けにして冷凍にしておくと料理に使うのに便利です。リコピンやトマトのビタミンCは熱にも強いので、煮てケチャップを作るのもよいのではないかと思います。
|
| 参考2:トマトに関する参考図書(1)~その歴史とレシピ~ |
| ◆参考図書(1)~トマト、その歴史とレシピに関する本~ |
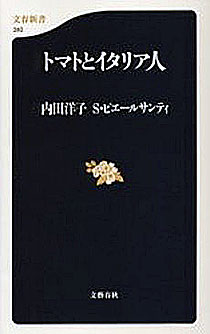 |
| ■ |
内田洋子+S.ピエールサンティ・著 |
|
『トマトとイタリア人』 |
|
文春新書、文藝春秋・2003年03月刊、735円 |
|
食と人生を愉しむ天才、イタリア人にとって、「トマト」は欠かせない食卓のパートナー。日本人にとっての「米」と同じ関係なのだ。ところがこのトマト、原産はイタリアではなく、新大陸から渡ってきた当初は、「魔の果物」と怖れられ、誰も食べようとはしなかったという。それがなぜ、相思相愛の関係となったのか?「イタリア料理はトマトの登場を何世紀も待ち続けてやっと完成した」とは著者の言葉。トマトから辿る、イタリア人と料理の文化史。 |
|
|
 |
| ■ |
石原結實・監修 |
|
『いいことずくめのトマトレシピ
シミ・シワ、メタボ、脳にいい!』 |
|
角川SSCムック・毎日が発見ブックス、
角川マーケティング(角川マガジンズ)・2008年06月刊、980円 |
|
赤い色素のリコピンが、動脈硬化やがん脳の老化も抑えます! 大好評の石原結實医師が監修の「いいことずくめシリーズ」。第4段はトマト。
赤い色素「リコピン」の栄養効果がどんどん解明されていますが、最大の効能は、活性酸素を無毒化する強い抗酸化力! 呼吸で取り入れた酸素が体内で生みだす猛毒物質・活性酸素は、まるで鉄を酸素がさびさせるように、細胞などを攻撃します。リコピンは、活性酸素が引き起こす、脳神経細胞の記憶力低下や、シミやシワ、がんの発生、動脈硬化などを予防します。さらに、血糖値の上昇を抑える、悪玉コレステロール、高血圧も改善するなど、メタボにいいことも解明済み。丸ごと食べるメニューをはじめ、トマトのうまみ・グルタミン酸を最大に生かした、ごはんに合うおかずや、作り置きレシピ、ジャム、スープ、そしてジュースなど。 |
|
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|
| 【2】トマトの効用~トマトとリコピン~ |
昔から「トマトのある家に胃腸病なし」とか「トマトが赤くなると医者が青くなる」と言われるほどその薬効が大きいことが分かってきました。事実トマトにはカリウムやカロチン、ビタミンC、ビタミンB群、ケルセチン、リコピンなどが多く含まれています。
本節ではトマトの効用を取り上げ、参考までにトマトジュースの効用を取り上げ解説しました。
|
| トマトの薬効 |
| トマトに多く含まれるビタミン類 |
トマトには清熱解毒作用、つまり、血液を浄化して脂肪の消化を助けてくれる作用があると考えられています。事実、トマトに含まれるクエン酸やリンゴ酸、酒石酸、コハク酸等の有機酸が胃液の分泌を促して消化を促進しますし、ナトリウムやカルシウム、マグネシウム、カリウム等のアルカリ性のミネラルが酸血症を中和してくれます。特にカリウムの働きは体内のナトリウムを排泄する働きがあり、必然的に血圧を下げてくれますし、血管を丈夫にするケセルチンと共に心疾患や動脈硬化を予防し、肌をきれいにしてくれます。さらに、トマトにはカロチン(ビタミンA)やビタミンC、ビタミンB群、ビタミンP(ルチン、フラボン)がとても多く含まれており、トマトは一般的にビタミンの多い野菜と言われています。これらのビタミンの血管強化作用や拡張作用によって、高血圧や眼底出血の予防に効果が期待できるのです。
|
| トマトのリコピンと酸味の作用 |
リコピンはカロチン(カロテン、カロチノイド)の1種で、トマトジュースやケチャップ等に使われる赤色系のトマトに多く含まれています。リコピンは赤みを作っている色素で抗酸化作用があり、活性酸素を消す働きがあります。免疫力を強化して、癌の予防にも有効だと言われています。また、リコピンは熱にも強いので、煮てケチャップを作るのもよいでしょう。なお、トマトの酸味はクエン酸やリンゴ酸、コハク酸などの有機酸で、胃の調子を整えて乳酸等の疲労物質を取り除く働きもあります。
|
| トマトに含まれるその他の有効成分 |
トマトには血液をサラサラにするというピラジンという香り成分が含まれています。ピラジンはニラやパセリやタマネギやセロリ等にも含まれている独特の香り成分で、血小板の血液の凝固作用を抑制する働きがあります。つまり、血栓を出来にくくする効果があり、動脈硬化の予防に有効です。また、トマトにはアミノ酸の1種のグルタミン酸が多く含まれ、トマトを魚と共に煮込むと、魚に含まれるイノシン酸とトマトのアミノ酸との相乗効果で旨味が多くなり、とても美味しくなります。また、グルタミン酸やアミノ酪酸には健脳効果があります。なお当然、野菜である1種のトマトには食物繊維のペクチンも多く含んでいるので整腸作用があり、コレステロール値の改善や便秘にもとても有用なものです。
|
|
| リコピンとトマト |
| 皮膚のシミや皺、たるみの原因 |
皮膚のシミや皺、たるみの原因には、加齢による肌の老化モ当然ありますが、その原因の8割は紫外線による光老化だと言われます。紫外線が皮膚に当たると、紫外線による炎症を防ごうとして色素細胞からメラニンを出します。シミの原因となるメラニン色素は通常28日周期で表皮から抜け落ちますが、しかし、ひどい日焼けの場合メラニン色素が真皮に落ち込んで色素沈着を起こしてシミになり、さらに紫外線が皮膚の奥まで達するとコラーゲンを破壊してしまいます。紫外線は骨を丈夫にするビタミンDを生成しますが、日光に当たる時間はほんの少し、1日に10分~15分くらいでよいと言われます。直射日光に長時間当たる必要はなく、規則正しい食生活で充分な栄養を摂取し、適度の運動をすることが大切です。
|
| リコピンの効果 |
リコピンの効果が話題を呼び注目されています。トマトに含まれる色素リコピンが皮膚のシミの原因となるメラニンの生成を抑え、同時に肌の瑞々しさを保つコラーゲンの量を増やし、皺やたるみを予防する効果がある可能性が期待されているのです。
リコピンとはカロテノイドの一種で、トマトやスイカ、ピンクグレープフルーツなどに含まれる脂溶性の赤色の色素です。カロテノイドとは自然に存在する色素のことで、カロチノイドと呼ばれることもあります。緑黄色野菜に多く含まれ、現在600種類以上が知られています。カロテノイドは活性酸素を消す抗酸化力が強いのが特徴で、代表的なものとしてはαカロテンやβカロテン、ルティン、リコピンなどが知られています。その中でもリコピンは抗酸化力が強いのが特徴で、βカロテンの2倍、ビタミンEの100倍の抗酸化力を持っています。
リコピンの効果及び効能としては、強力な抗酸化力から得られ、血糖値を下げる、動脈硬化の予防、癌の予防、喘息の改善、美白効果、ダイエット効果などがあると言われています。リコピンの癌予防効果は肺癌、前立腺癌で有効性が示唆されています。また、基礎研究レベルですが、リコピンにはLDLコレステロールの酸化防止や乳癌及び肺癌、前立腺癌の増殖を抑える効果があると言われています。なお、リコピンはトマトやスイカ、金時人参などの赤い色に含まれており、以前からトマトを食べるときれいな肌になるとよく言われていましたが、それはリコピンの効果ということが分かってきたわけです。リコピンは紫外線によって生じるメラニンの生成を促進する活性酸素を消去し、しかもコラーゲンを生成する効果があり、皮膚のシミや皺、たるみの予防に効果が期待できるわけです。
|
| リコピンの効果的な取り方とサプリメント |
リコピンは脂溶性のため、生のトマトを単独で食べるよりも、サラダにしてドレッシングをかけたり調理した方が吸収率がよくなります。リコピンの摂取量の目安は1日15mg~20mg程度です。大きめのトマト1個のリコピン含有量は7~8mg程度なので、トマト2個で約15mgのリコピンが摂取できます。また、トマトジュースは10ccで1mgのリコピンが摂取でき、従って200ccのトマトジュースなら20mgのリコピンを摂ることができます。なお、リコピンのサプリメントは、リコピン単独ではなく、ルティンやβカロテンなどのカロテノイドが配合された製品が発売されています。抗酸化という観点から見るとマルチビタミン・マルチミネラルのサプリメントにリコピンが配合されている製品が最もよいと考えられます。ただし、食べ物やトマトジュースからでも充分な量のリコピンを摂取できるので、特にリコピンだけを意識したサプリメントを摂る必要はないと思います。毎日食べる食材ではトマトやトマトジュースがオススメです。
| ■ |
リコピンと抗酸化 |
|
リコピンの働きは強力な抗酸化作用です。人間の体内では一定の割合で活性酸素が発生しています。活性酸素とは酸化力が強い酸素のことで、触れた体内の組織を錆びさせてしまいます。血管が活性酸素によって錆びてしまうと動脈硬化、細胞内のDNAが錆びてしまうと癌になってしまいます。活性酸素の発生原因はストレスや喫煙、飲酒、電磁波、紫外線、食品添加物を食べた時、排気ガスなど様々です。なお、健康を害する根本的な原因とも言える活性酸素を消去する物質を抗酸化物質と言いますが、代表的な抗酸化物質はビタミンAやビタミンC、ビタミンEの他、リコピンやアスタキサンチン、カテキン、ポリフェノールなどがあります。活性酸素が発生した時に体内に充分な抗酸化物質が存在しないと体内の至る所が錆び付いてしまいます。リコピンは脂溶性なので主に細胞膜に存在し、細胞が活性酸素に攻撃されるのを防いでいます。 |
|
| ■ |
リコピンと美肌 |
|
リコピンの美肌効果も最近注目されていますが、これもリコピンの持つ抗酸化力から来ています。紫外線が肌に当たると活性酸素が発生し、皮膚のシミや皺、たるみの原因になります。また、リコピンはシミの原因になるメラニンを生成するチロシナーゼの働きを抑制する効果があります。リコピンの美肌&美白効果は抗酸化とチロシナーゼ抑制の2つの働きから来ています。 |
|
| ■ |
トマトジュースとビタミンEがオススメ |
|
リコピンの効果には、皮膚のシミや皺、たるみを予防する可能性があることが最近分かってきました。真っ赤に熟成したトマトはリコピンの効果が高い食べ物で、リコピンの含有量は完熟トマトの方が多く、脂溶性であるので油と一緒に摂取すると吸収性が高まります。紫外線は春から夏にかけて強くなりますが、冬でも雪の照り返しには注意が必要で、1年中紫外線とは上手に付き合っていく必要があります。そこで、その予防としてトマトジュースを1日1缶飲むのが最も手軽なリコピン接種法となりますが、トマトジュースが苦手な人は、トマトの煮込み料理やトマトソースを使った料理を摂るのもよいでしょう。また、リコピンとビタミンEを一緒に摂取すれば美白効果があることも分かってきました。ビタミンEを多く含むひまわり油などの植物油やマーガリン、アーモンド、落花生、小麦胚芽、大豆などと一緒に摂取することで、シミや皺、たるみのない美しい肌を維持することに期待が持てそうです。 |
|
|
| リコピンの科学的データ |
| ■ |
肺癌に対する疫学調査 |
|
非喫煙者の30~75歳がリコピンを男性12mg、女性6.5mg以上食品から摂取すると肺癌のリスクが低下する。 |
|
|
|
| ■ |
前立腺癌に対する疫学調査 |
|
食品由来のリコピンを6mg/1日以上摂取すると、前立腺癌のリスクが低下する。 |
|
|
|
| ■ |
喘息に対する有効性 |
|
リコピンが運動性誘発性喘息を低減する。 |
|
|
|
| リコピンの副作用と安全性 |
リコピンは非常に安全性の高い成分で、一般的には重大な副作用などは報告されていません。また、医薬品との相互作用も現在の所ありあません。
|
| 参考:リコピンのサプリメント |
|
|
| トマトジュースの効用 |
| 飲酒時のトマトジュースで血中アルコール濃度が低下 |
お酒が好きな方に朗報です。トマトジュースを飲酒時に一緒に飲んだ場合、飲んでいない場合と比べて血中のアルコール濃度が低下することが判明したそうです。アルコールといっしょにトマトジュースを飲んだ人は血中のアルコール濃度や体内に留まる量が平均で約3割減少し、体内からのアルコール消失も50分早まるのだそうです。これは飲酒時にトマトジュースをいっしょに摂ることで酔いのまわりが遅くなり、飲酒後の酔い覚め(体内からアルコールが消失した状態)も早くなる可能性が示されたものです。
|
| トマトジュースの塩入りと無塩 |
トマトジュースには塩で味付けしたものと食塩無添加の無塩タイプものとがあります。塩で味付けしたトマトジュースは飲みやすいですが、中には塩分の摂り過ぎを心配される人もいるかも知れません。トマトジュースの塩分はあまり気にする必要はないそうですが、それでもどうしても塩分が気になるのであれば、塩分が含まれていない無塩タイプのものを選ぶとよいでしょう。なお、塩入りのトマトジュースを飲んでいる人でも、健康のためには自然塩入りのものを選ぶといいかもしれません。自然塩は天然塩とも呼ばれる何も付け足していないそのままの塩のことです。自然塩には、汲み上げた海水を使って塩田で作られたものや、岩塩のように自然に結晶化されたものなどがあります。これらには精製塩(食塩)に比べミネラル成分等がより豊富に含まれています。
|
| トマトジュースのリコピンで美肌&美白効果 |
女性にとって日差しが強くなる暑い季節は、お肌の天敵とも言える紫外線との戦いの日々が待ってます。そのためには 紫外線そのものを浴びないことが一番ですが、外出しない訳にもゆきません。
紫外線から直ぐに連想されるものにメラニン色素がありますが、これがお肌のシミなどの原因として嫌われています。でも、実はメラニン色素によってシミが作られ、そのシミが壁となって、紫外線がそれ以上肌へ侵入するのを防御してくれているというそういう側面もあるのです。しかし、一番の理想は、やはり肌にシミが出来ないことです。トマトに含まれるリコピンにはメラニンの生成を促進する活性酸素を少なくする効果があります。そこで、リコピンを含むトマトジュースを活用して、より一層の美肌、美白を手に入れるのがよいでしょう。
|
| トマトジュースの美味しい飲み方 |
| ● |
トマトジュースにレモンを適量垂らして飲む |
|
同じサッパリ系でお酢、黒酢やビネガーを入れてもよいでしょう。朝に飲むと身体が目覚めてシャキッとする感じです。酸っぱいのが苦手な人はトマトジュースを牛乳で割るとまろやかになって飲みやすくなります。 |
|
| ● |
グラス一杯のトマトジュースに黒のスリ胡麻を大匙1杯ほど入れて飲む |
|
摺ったゴマの方が栄養成分の吸収によいそうです。ゴマには美肌効果もあり、アンチエイジング効果も確認されています。 |
|
| ● |
トマトジュースにコンソメスープの素を溶かして飲む |
|
そのままで飲むというより、色々な野菜を入れて野菜スープとして飲むのがよいでしょう。 |
|
| ● |
ビールとトマトジュースを半々で割って飲むレッドアイ |
|
あくまで適量にとどめるる必要はありますが、お酒の好きな人には、食前&食後に美味しくいただけて健康にもよいのでオススメです。 |
|
|
| トマトジュースの栄養の効果 |
トマトジュースの原料であるトマトは非常に栄養豊富な野菜です。トマトには栄養の成分として他にもミネラル分が程よく含まれていて、トマト単体だけで優れた効能を持つ野菜です。そして、トマトの燃えるようなあの真っ赤な色。その真っ赤な色の元はリコピンと言われるカロチノイド色素の一種です。トマトの代名詞とも言えるリコピンですが、先にも述べたように研究によってリコピンには抗酸化作用があることが発見されています。しかもトマトの色が赤ければ赤いほど抗酸化作用(※抗酸化作用とは、生活習慣病や老化などの原因ではないかと考えられている活性酸素を抑えることを言います)が強いのだそうです。ということは、完熟したトマトなら最高だということになります。トマトジュースって完熟した真っ赤なトマトだけを原料にして作られます。従って、トマトジュースにはリコピンがふんだんに含まれていることになります。そんな訳で、トマトジュースは最高の飲み物です。なお、トマトジュースには幾つのトマトが使われていると思いますか? 有塩タイプの190g入りの缶には完熟トマトが3個分が入っているそうです。また、無塩タイプの160g缶には完熟トマトが2個半分、900gのペットボトルには完熟トマトが14個分も入っているそうです。従って、トマトジュースならコップ1杯で充分だということになります。
また、トマトジュースは二日酔いにもよいそうです。さらに、トマトに含まれる栄養素の一つであるビタミンKは骨粗鬆症の予防に効果があると言われます。さらに、トマトに含まれる栄養の成分である食物繊維やビタミン、ミネラルなどは、トマトが熟してゆくにつれてそれぞれの量が増してゆきます。従って、その意味でも完熟したトマトを原料に作られるトマトジュースは栄養豊富な健康に良い飲み物なのです。しかも、トマトジュースには糖分もあまり使われておらず、カロリーも低い飲み物です。従って、トマトジュースはダイエットにも効果を発揮します。飲み方としては、食前に栄養豊富なトマトを食べるか、またはトマトジュースを飲んでお腹が膨らんだ分の食事の量を減らすとよいそうです。トマトジュースにビネガーやお酢、黒酢などを少し混ぜると一層美味しくなります。先にも述べましたが、このトマトジュースでのダイエットは、美味しく続けられる、身体に優しいダイエット法です。
|
| トマトジュースでダイエットする方法 |
最近トマトの効果が新たに発見されました。それは、トマトの成分の一つに中性脂肪などを減少させる効果があり、メタボリック症候群の改善に役立つというものです。発見された脂肪燃焼の効果があるトマトの成分は生のトマトよりも加熱処理をしたトマトジュースに多く含まれているそうです。
トマトジュースにはトマトに含まれている食物繊維やミネラル成分、ビタミン成分など豊富な栄養素が丸ごと詰め込まれています。飲むサラダとも言われているのも頷けます。ダイエットにトマトジュースを利用する場合には、食前にトマトジュースを飲んでお腹を膨らまし、その分の食事を少なくする方法(※トマトジュースの栄養の効果)があります。
また、食事を利用したダイエットにも色々あります。たとえば一つの商品だけを食べ続ける○○ダイエットなどとしてよくテレビや雑誌などで取り上げられたりしています。これらの方法で上手くゆかなかった人も多くいることでしょうが、この単品の食品を用いての○○ダイエットの場合、多少なりとも栄養的にバランスが崩れてしまいがちです。しかし、トマトジュースを使った方法なら、トマトジュースそのものがサラダのようなものですから栄養的には申し分なく、安心・安全に健康的に痩せられます。さらに運動でダイエットする際に水分補給としてトマトジュースを飲むこともよいでしょう。また、トマトジュースにビネガーやお酢類、クエン酸(※白い顆粒状のもの)などを混ぜて飲むと、疲れが溜まりにくくなり、身体に力が漲ってくる感じがします。トマトジュースとビネガーやお酢類、クエン酸を上手く使うことで元気に健康的にダイエットすることができます。
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|
| 【3】トマト・ダイエット~その効果的な方法~ |
トマトは健康一般によいだけでなく、ダイエットにも効果的であることが分かってきました。本節ではトマトを使ったダイエット法を取り上げました。
|
| 最近話題のトマトダイエットの成功率を上げるために |
最近ニュースにもなったのでご存知の人もいると思います、2012年2月10日に京都大大学院農学研究科の河田照雄教授らがトマトに脂肪燃焼効果を持つ脂肪酸の一種、すなわち脂肪を燃焼させる遺伝子を活性化する働きがある成分が含まれていることを発見し、その研究結果が米科学誌プロスワン電子版に掲載されたそうです。それによると、肥満マウスにトマトのダイエット効果のある成分を餌に混ぜて与えたところ中性脂肪が減少し血糖値が低下、餌だけを与えたマウスとの間に有意な違いが見られたそうです。欧州には「トマトが赤くなると医者が青くなる」という諺があり、トマトを食べれば医者に行く必要がなくなると言われているそうですが、これでトマトの健康効果はもちろん、トマトが持つ脂肪燃焼効果=ダイエット効果が科学的に証明された形になりました。
最近トマトダイエットが話題になっているのは、食生活の中にトマトを取り入れてるだけなので簡単にダイエットできる、ということが大きな理由のようです。確かにトマトは色々な料理に使えるので、単品を食べ続ける朝バナナやコンニャクなどに比べて飽きにくいとは確かです。しかし、それでも毎日トマトを食べ続けることは、やはり思っている以上に大変です。第一、トマトを買ってきてメニューを考えて食事を作るのを毎日繰り返さなければなりません。たとえば外食の時トマトを買い忘れた、料理するのが大変など続けられない理由は日常の中には幾らでもあります。そこでトマトダイエットを成功させるためには、どんな時でも簡単かつ手軽にトマトのダイエット成分を摂れる方法を用意しておくことが成功の鍵となります。
ちなみに、上記の実験で結果が出た効果が上がる量は、トマトジュースで1日に約600ml、トマトジュース約3缶分です。確かに毎日続けるのはちょっと大変な量です、そのため、ダイエット成分を摂り出したトマト成分のサプリメントを併用することも考えてよいかも知れません。また、脂肪燃焼効果のある成分は生のトマトよりも加熱処理されたトマトジュースなどに多く含まれています。つまり、トマトを生で食べるよりもサプリやトマトジュースで摂った方が遙かに成功率が高くなるということです。
|
| 朝食トマトダイエット |
| 朝食トマトで血糖値の上昇とストレスを抑制して爽快な一日を |
真っ赤に熟したトマト。かねて生食用にはピンク系のトマトが主に用いられてきましたが、実はトマトは皮の厚めな赤系のトマトの方に栄養が豊富であることが分かりました。そこで、最近では赤系のトマトを生食用や加熱調理に用いることが増えてきました。赤色のトマトに含まれる抗酸化成分のリコピンの含有量は、ピンク系トマトの5~10倍近くも多いと言われ、クエン酸や食物繊維、カリウムなどのミネラルも赤トマトが断然多く含んでいるのです。
この赤系のトマトを朝食の時に摂る習慣をつけると、ダイエットや健康維持に効果が高いことが話題になっています。朝は1日のうちで最もストレスを感じやすい時間帯で、ストレスは活性酸素の大きな発生源となっていますから、朝のうちに赤色系のトマトから抗酸化成分のリコピンを補給しておくと、活性酸素の悪影響を予め抑制することができます。活性酸素は脳卒中や心臓発作などの突然死を引き起こす原因となるばかりか、皮膚のシミや皺などの老化にも関わっていますので、美容にも効果があるのです。また、トマトには抗ストレス成分のGABAも含まれていますから、朝食のトマトは1日のスタートにはぴったりの食材です。また、トマトには朝食後に上昇することの多い血糖値を抑える働きがあり、朝の血糖値を低く抑えることで、糖尿病やメタボリック症候群の治療にも有効です。その他、トマトは癌や心臓病、認知症、COPDなどにも効果があります。健康の維持にもよい朝のトマトを習慣にしてみてはいかがでしょうか。
|
| 朝のトマトで抗酸化成分リコピンを補給して美容&ダイエットに活かす |
赤系のトマトを朝食に食べると様々な美容と健康の効果が得られますが、それではどういう食べ方をすれば効果があるのでしょうか。
まずは抗酸化成分のリコピンは、美容&健康面の効果を得るためには1日当たり約20㎎程度の摂取が適当だと言われており、これは赤系の完熟トマトなら中サイズ1~2個分に当たります(※ミニトマトの場合は5~10個は食べる必要があります)。トマトジュースや缶詰、ケチャップ、ピューレなどの加工食品は主に赤系トマトを使用していますので、リコピン補給に最適です。トマトジュースなら1缶で20㎎のリコピンが補えますから、毎朝コップ1杯で充分です。非常にイージーなダイエット&健康法とも言えるでしょう。
リコピンは熱に強い物質なので、加工食品でも効率よく補うことができるのもポイントです。そして、脂溶性の性質も持っているので、トマトジュースやトマトソースにオリーブ油や牛乳を加えて調理すると、リコピンの吸収率が飛躍的に高まるのです。朝食に赤系トマトを使った料理を加えたり、トマトジュースを飲む習慣をつけ、1日の始まりにリコピンを補給しておけば、ダイエットだけでなく、スキンケアやメタボリック症候群、そしてストレス解消に効果が期待できます。ぜひ朝食トマトダイエットを試してみましょう。
|
| 参考:トマトジュースと寒天で出来るトマト寒天ダイエット食 |
朝食にトマト寒天を食べると、ダイエットやメタボ退治に非常に効果的です。寒天は糖尿病食によく使われますが、栄養たっぷりのトマトを加えることで美味しくて腹持ちのよい理想的なダイエット&脱メタボ食となります。
| ◆ |
作り方 |
|
無塩トマトジュース(450ml)、水(50ml)、粉寒天(4g)を鍋で掻き混ぜながら弱火で1分煮立て、冷ました後カップに入れて冷蔵庫へ。 |
|
|
|
| 夜トマトダイエット |
| 夜のトマトで基礎代謝をUPさせる |
夜トマトダイエットとは、まさに夜にトマトを食べるダイエットのことです。痩せるのに欠かせないものに成長ホルモンがありますが、これを分泌させて代謝を上げることを目指す簡単な方法です。成長ホルモンが分泌されるのは寝ている間だけですから、分泌に必要なビタミンやミネラルが多く含まれるトマトを夜に食べることが、まずは何よりも大切で、これを続けることで痩せやすい身体になってゆきます。さらに、ただ痩せるだけではなく、トマトに含まれるリコピンや食物繊維のお陰で美肌を手に入れるメリットもあります。リコピンと食物繊維は悪玉コレステロールを減らし、血液をサラサラにしてくれる効果があり、さらにリコピンには活性酸素を消す肌荒れ防止効果もあります。トマトのビタミンが肌を強くすることから、化粧のりがよくなったりなど、夜トマトダイエットにはまっている人も増えていると言います。昔から「トマトが赤くなると医者が青くなる」という諺もあるように、健康的に痩せるなら夜トマトです。
|
| 夜トマトダイエットのルール |
| ● |
ルール1:夕食と一緒にトマトを摂取する |
|
生のトマトでも、加熱調理しても、トマトジュースでも構いません。成長ホルモンの分泌をアップさせるために、夜食べるのがオススメです。 |
|
| ● |
ルール2:最低3ヶ月、理想は6ヶ月続ける |
|
数週間続けただけでは何事もあまり変化が見られないものです。肌や爪の生まれ変わりサイクルが平均6カ月なのと同様に、身体の変化もこのくらいの期間で表われます。なので、無理しない程度に6カ月ほど継続してみましょう。 |
|
| ● |
ルール3:できるだけ規則正しい生活を心懸ける |
|
これはどのダイエットにも共通することですが、暴飲暴食や睡眠不足、偏食は駄目です。基礎がしっかりあってこそのトマトのパワーなので、起床・就寝時間、食生活などを整えて、日頃から健康を保つように心懸けましょう。 |
|
| ● |
ルール4:1日にリコピンを15mg以上摂る |
|
効果が出るか否かは、トマトに含まれるリコピンの量で決まると言っても過言ではありません。代謝を上げるのに必要なリコピンの量が、約15mgです。より赤い方がリコピンが多いので、なるべく赤いトマトを選びましょう。
- 分量の目安
- 生で食べるなら:大2個、ないしミニトマト17個
- トマトジュースなら:350mlを2~3本が効果的
- 料理なら:ホールトマト缶なら1缶弱
|
|
|
|
| トマトの食べ過ぎに注意しましょう |
トマトを生で多く食べ過ぎると、冷え性の人や胃腸の弱い人は体調が悪くなることがあります。普通はそう気にすることはありませんが、トマトには身体を冷やす作用がありますので、たくさん食べる場合は煮たりして火を通しましょう。また、希にトマトアレルギーの人がありますので、その場合は気をつけて下さい。なお、一般に野菜はカロリーが少ないので、たくさん食べても太ることはまずないでしょう。
|
| 参考3:トマトに関する参考図書(2)~トマトダイエット本~ |
| ◆参考図書(2)~トマトダイエットについての本~ |
 |
| ■ |
唐沢明・著 |
|
『夜トマトダイエット』 |
|
ぶんか社・2009年01月刊、1,100円 |
|
やせてお肌ボロボロ…なんて意味がない。“夜トマト”の美やせ+美肌の神秘をあなたも体験しませんか。おいしい料理、楽しい種類で、ヘルシー身体、うれしい減量。 |
|
|
|
|
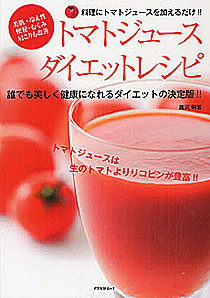 |
| ■ |
唐沢明・著 |
|
『トマトジュースダイエットレシピ 料理にトマトジュースを加えるだけ!!』 |
|
アスペクトムック、アスペクト・2012年05月刊、940円 |
|
今!大注目の“トマトダイエット”レシピの大本命!! いつもの料理にトマトジュースを加えるだけで、カラダにやさしくダイエット。“トマト赤デミー”代表でもある唐沢明さんが、そのままトマトより効率よくとることができて栄養たっぷり!肌荒れやむくみ、便秘にもよく効くトマトジュースを使った美味しいレシピを紹介します!!
|
|
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|