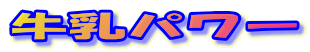| 【1】牛乳の特徴と種類 |
本節では、まずは手始めに牛乳の特徴と種類、そして、その歴史について取り上げました。
|
| 牛乳とは? |
| ■ |
6月1日は牛乳の日 |
|
2001年、国連食糧農業機関(FAO)によって、牛乳への関心を高め、酪農及び乳業の仕事を多くの方に知ってもらうことを目的に6月1日を「世界牛乳の日(World
Milk Day)」と定められました。また、これに因んで日本でも2008年から毎年6月1日を「牛乳の日」、6月を「牛乳月間」となっています。 |
|
| ■ |
牛乳は酪農家の愛情と牛からの贈りもの |
|
牛乳は牛から絞った乳(生乳)を加熱殺菌したもので、水や添加物などは一切加えられていない自然の恵みです。良質な乳を出してもらうため、酪農家は乳牛に栄養バランスを考えた飼料を与え、暑さに弱い牛たちのために、牛舎の温度管理や健康管理など365日休みなく細心の注意を払ってようやく私たちの口にする牛乳となって出荷されるのです。 |
|
|
| 牛乳の特徴 |
牛乳(milk)とは、誰もがご存知の通り牛の乳汁のことを言います。ただし、牛乳とひと口に言っても、生乳を指す場合や、これを原料として脂肪分増減したもの、また乳糖を分解したものも含める場合もあり、さらに人によっては様々な食品を混ぜて作った嗜好飲料(いわゆるコーヒー牛乳、イチゴ牛乳、フルーツ牛乳、レモン牛乳など)を言うこともあります。なお、牛乳はしばしば脱脂粉乳、バター、生クリーム、チーズ、ヨーグルト、アイスクリームなどに加工されます。
牛乳には、タンパク質やカルシウム、脂肪、必須アミノ酸(人間にとっての必須アミノ酸)などの栄養成分がバランスよく豊富に含まれており、特にアミノ酸スコアはパーフェクトと言ってよい包含率です。(なお、アメリカでは牛乳100g当たりのカルシウムの含有量は113mgであるとされているが、土壌などの関係で
日本では一般に単位重量当たりの食品に含まれるカルシウムの量も少ないとされる。日本の4訂食品成分表によれば乳牛の種類による差や個体差、季節変動などがあり、その成分が一定していないことを断わった上で、ホルスタインの牛乳100g当たりのカルシウムの含有量は100mgであるとされている。このように牛乳の場合も日本産のものはカルシウムが少ないとされています。要するに牛乳も産地によって含有成分が異なっているわけです。また、牛乳にビタミンCが殆ど含まれていないのは、子牛が自らビタミンCを合成できるので摂取する必要がないためで、逆に人の母乳にビタミンCが含まれているのは、ヒトの乳児がビタミンCを合成できないので摂取する必要があるためです。)
次に牛乳中の必須脂肪酸の含有比率については、牧草等の葉には微量ではあるものの、リノール酸に比べてα-リノレン酸が比較的多く存在しており、このため牧草を飼料として与えられている乳牛の乳ではα-リノレン酸とリノール酸との比率が高くなり、α-リノレン酸をほとんど含まない穀物の飼料を多く与えられている乳牛の乳はα-リノレン酸とリノール酸との比率が低くなります。 なお、牛乳が白いのは水分中に離散している脂肪やカゼイン(タンパク質)の微粒子が光を散乱して白く見えるためです。また、牛乳を温めると表面に膜が張るが、これをラムスデン現象と呼ぶ。
|
| 牛乳の種類〜法律による定義〜 |
日本では牛乳について、食品衛生法の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)いわゆる乳等省令で定められており、それによると「直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む)する牛の乳」を牛乳となっています。
牛乳は、添加物及び成分調整の有無によって、まず大まかに、(A)無添加の牛乳(原材料は生乳100%)と、(B)添加した牛乳(原材料は生乳100%ではない)に分類されます。また(A)の無添加の牛乳は、さらに(1)無調整の牛乳と(2)調整した牛乳に細分されます。
| 成分無調整牛乳 |
生乳(原乳)に含まれる成分を調整していないため、季節による成分の変動があり、冬場は成分が高まる(無脂乳固形分8.7%以上、乳脂肪分4%以上になることがある)一方、逆に夏場は牛が乳脂肪分の元となる繊維質の含量の少ない青草を多く摂るために脂肪分が減り、味が薄く感じられるケースもあります。
| ■ |
牛乳(種類別牛乳) |
|
無脂乳固形分8.0%以上、乳脂肪分3.0%以上(市販されている製品では無脂乳固形分8.3%以上、乳脂肪分3.5%以上としているものが殆ど)。細菌数(標準平板培養法で1ミリリットル当たり)50,000以下、大腸菌群陰性、摂氏63度で30分間の加熱殺菌(またはこれと同等以上の効果のある方法での加熱殺菌)を行なうことが必要とされています。 |
|
| ■ |
特別牛乳 |
|
牛乳のうち、乳等省令(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)に定められた規格・基準に従って特別牛乳搾取処理業の許可を受けた施設で製造された牛乳で、特別牛乳として販売されるものを言います。無脂乳固形分8.5%以上、乳脂肪分3.3%以上。細菌数(標準平板培養法で1ミリリットル当たり)30,000以下、大腸菌群陰性、加熱殺菌を行なう場合は摂氏63度〜65度で30分間が必要とされています。なお、特別牛乳は現在こどもの国内の株式会社雪印こどもの国牧場や北海道の想いやりファームなど数箇所の施設でのみ製造されており、何れも主に施設での直接販売や通信販売により購入することができます。ちなみに想いやりファームの想いやり牛乳は、2010年7月現在、特別牛乳中でも唯一の無殺菌牛乳として販売されています。 |
|
|
| 成分を調整した牛乳 |
2002年(平成14年)より制定されたもので、乳脂肪分の一部を除去したり水分を一部除去して濃くするなどして生乳から乳成分などを除去したもので、無脂乳固形分8.0%以上のものを言います。
| ■ |
低脂肪牛乳 |
|
乳脂肪分のみを調整した牛乳のうち、乳脂肪分0.5%以上1.5%以下のものを言います。 |
|
| ■ |
無脂肪牛乳 |
|
乳脂肪分のみを調整した牛乳のうち、乳脂肪分0.5%未満のもの言います。 |
|
| ■ |
成分調整牛乳 |
|
調整した牛乳のうち、「低脂肪牛乳と無脂肪牛乳に該当しない」ものを言います。具体的には、脱水処理による乳脂肪分が4%の濃い牛乳や、脱水処理による乳脂肪分が濃い牛乳にさらに乳脂肪分を調整し、1.5%以下にした牛乳、或は乳脂肪分のみを調整したが、1.5%を上回る牛乳などを指します。乳等省令改正で新設された種類別で、原乳の生産者価格が引き上げられた2008年辺りからこの「成分調整牛乳」(乳脂肪分を2
- 3%に調整したもの)が多くなっています。 |
|
|
| 添加した牛乳 |
| ■ |
加工乳 |
|
生乳及び牛乳と、これらを原料とする規定された乳製品(脱脂粉乳やバターなど)から製造し、無脂乳固形分8%以上のものを言い、低脂肪乳、無脂肪乳と濃厚タイプがあります。
加工乳は生乳(牛乳)を主原料とし、低価格の実現を目的として、脱脂粉乳やクリーム、バターなどの規定された乳製品を加え、消費者の嗜好に合わせて加工されたものを指します。成分調整牛乳では、製品の原料となる牛乳から分離した脂肪分などをバターやチーズなどの加工品に転用できる分だけ牛乳よりも価格が安くなりますが、加工乳ではさらに脱脂粉乳やバターなどを混ぜることができるため、一層の低価格化が実現できのです。また、製品パッケージには「加工乳」の表示が義務付けられていますが、ミルクという表示など一見すると無調整の牛乳と見分けが付かないものが多く存在します。ただ、乳製品以外の成分が加えられていない点が乳飲料と異なります。ちなみに、2000年6月〜7月にかけて起こった雪印集団食中毒事件発生前までは一定の成分を満たしていれば商品名に「牛乳」と命名することが可能でしたが(特濃牛乳など)、発生後は商品名に「牛乳」は使用できなくなりました。 |
|
| ■ |
乳飲料 |
|
乳製品を主原料とした飲料で、乳等省令の規定で乳固形分3%以上のものを言います。カルシウムなどを加えた栄養強化タイプや、いわゆるコーヒー牛乳、イチゴ牛乳、フルーツ牛乳、レモン牛乳など、また、乳糖でお腹を壊す人のための乳糖分解乳もこれに含まれます。
乳飲料とは、生乳(無調整の牛乳)や乳製品を主原料とし、カルシウムやビタミンなどを加えて特定の栄養素を強化したり、果汁やコーヒーなどを加えたりして消費者の嗜好に合わせて加工されたものを言い、原材料に乳製品以外のものが使われていることが加工乳と異なっています。ちなみに、雪印集団食中毒事件発生前までは乳飲料でも一定以上の成分を満たしていれば商品名に「牛乳」と命名することが可能でしたが、事件発生後は「牛乳」と表記してはいけないことになったため、「オーレ」(au
lait; フランス語)や「ミルク」(milk; 英語)、「ラテ」(latte; イタリア語)などと表記されることが多くなりました。なお、乳飲料には「白物乳飲料」と「色物乳飲料」があり、「白物」のカルシウムやビタミン、鉄、繊維等を加えた白が基調のもので、牛乳に色々な成分を混ぜ強化したものと、「色物」のコーヒーやココア、果汁等を加え、白以外が基調のもので、消費者の嗜好に合わせて加工したものに大別されます。その中で「白物乳飲料」は「機能性牛乳」ないしは「低脂肪牛乳」(低脂肪乳とも)とも言われ、鉄分やカルシウム、ビタミンなどを付加したものを言います。カロリーを下げる目的で、通常より脂肪分を減らしたものも多く存在します。また、「色物乳飲料」は、いわゆるコーヒー牛乳やフルーツ牛乳、いちご牛乳、マンゴー牛乳などがあります。また、コーヒー利用のものを分別して「コーヒー系乳飲料」とする場合や、チルドカップに入っている場合じゃ「カップ乳飲料」と言うこともあります。なお、ご当地商品としては栃木県内で流通している「レモン牛乳」が有名です。 |
|
|
| 牛乳の商品名 |
昔加工乳や乳飲料であっても一定以上の成分(無脂乳固形分8.0%以上、乳脂肪分3.0%以上、生乳50%以上)が含まれていれば商品名に「牛乳」という名称を使用できたのですが(濃厚牛乳、カルシウム牛乳、コーヒー牛乳など)、2000年(平成12年)の雪印集団食中毒事件をキッカケに消費者から「ややこしい」という声が起こり、2001年(平成13年)に公正競争規約が改正され、生乳を100%使用していないものは「牛乳」とは名乗れなくなりました(2年間の経過措置あり)。この結果、商品名から「牛乳」を外したり「ミルク」への言い換えなどを余儀なくされ、コーヒー牛乳は「コーヒーミルク」「カフェ・オ・レ」「カフェ・ラテ」、またはただの「コーヒー」などに商品名を変更されました。
なお、いわゆるコーヒー牛乳は、生乳などを原料に乳製品以外のコーヒー成分を加えた乳飲料で、牛乳とは異なります。カルシウムや果汁を加えたものも乳飲料の仲間で、バターやクリームなどの乳製品を加えた「特濃○×牛乳」などは「加工乳」と言います。これらは牛乳パックの表示の「種類別」を見ると分かります。これまでは牛乳でなくても、脂肪分などの成分が一定以上あれば商品名に「コーヒー牛乳」や「フルーツ牛乳」、「特濃○×牛乳」など「牛乳」の文字を使うことができましたが、特に雪印集団食中毒事件後、消費者から「本当は牛乳でないのに紛らわしい」という声が相次いだため、表示法が変えられることになり、現在は「牛乳」と「特別牛乳」だけが以前と同様に商品名に「牛乳」という言葉を使えるようになったのです。また、生乳の割合も3段階に分けて表示することになりました。従って、乳製品以外のものを混ぜた「コーヒー牛乳」は、以前のように「牛乳」と呼べなくなったわけです。
「コーヒー牛乳」や「フルーツ牛乳」の名が消えるのは少し寂しい気がしますが、消費者にとって本当に欲しい商品が正しく選べるようになったのだと前向きに捉えたいものです。
|
|
| 殺菌方法による牛乳の違い |
| 処理方法による牛乳の違い |
牛乳は、主にホルスタインやジャージー種などの乳牛から得られる生乳(搾っただけで何もしない乳)のみを原料として均質化(ホモジナイズ)や加熱殺菌工程を経てガラス瓶(牛乳瓶)や紙パックに詰められて製品(市乳)となります。なお、これ以外にも、窒素を使うなどして溶存酸素による酸化を抑制しながら加熱殺菌した商品もありますし、またごく少数ながら、牛の乳頭から生産設備までを無菌に保ち、加熱殺菌をしない無殺菌牛乳も存在します。
ちなみに、特別牛乳など均質化を行なっていないノンホモ牛乳では、瓶詰めから数日経つと白いトロリとしたクリーム状のものが浮いてきますが、一般の牛乳や低脂肪乳、加工乳には見られない現象です。これは、搾乳された後に均質化処理をしていないため、粒子の大きな脂肪球が壊されず、そのまま残っているためで、この浮いたものが本来の意味でのクリームであり、遠心分離を用いる近代工業的な製法が普及する前はクリームとはこのように生乳を静置して表面に浮上するものを採取したものを言い、これを撹拌して脂肪球をさらに大きくしたものがバターとなります。
|
| 殺菌方法による牛乳の違い |
| ■ |
低温長時間殺菌法(LTLT) |
|
62℃〜65℃で30分の殺菌を行なう方式。現在では殆ど生産されていないものの、最も生乳の特質を残した牛乳。 |
|
| ■ |
高温短時間殺菌法(HTST) |
|
72℃〜75℃で15秒の殺菌を行なう方式。欧米で主流の方式で、低温殺菌牛乳の部類に属する方式。わが国では一部の中小メーカーが生産している。 |
|
| ■ |
超高温殺菌法(UHT) |
|
85℃6分の予備加熱後、120℃〜140℃で0.5秒〜4秒の殺菌を行なう方式で、わが国の大部分の牛乳がこの殺菌方法で製造されている。 |
|
| ■ |
超超高温殺菌法(LL) |
|
85℃6分の予備加熱後、130℃〜150℃で0.5秒〜4秒の殺菌を行なう方式。日持ちするため自動販売機などでも売られている牛乳で、ロングライフ牛乳と呼ばれる。なお、この方式においてパックの消毒に用いられる過酸化水素の残留の怖れが一部では懸念されている。 |
|
上記低温長時間殺菌法(LTLT)や高温短時間殺菌法(HTS)などは一般に低温殺菌牛乳と呼ばれ、パスツールの名に因んで「パスチャライズドミルク」とも呼ばれています。この2種類は有害な病原菌だけを死滅させ、有用な乳酸菌はもとより、牛乳の栄養や風味を残した本来の牛乳と言えます。欧米ではこの牛乳が主流で、高温殺菌の牛乳が敬遠されているのが現状です。しかし、わが国では法律上で殺菌温度の上限がないために大部分の牛乳メーカーが殺菌温度を上げ、賞味期限の長い牛乳の製造を増やして来ました。この方がメーカーにとっては合理的で大量生産が可能で企業収益が上がるからです。
|
|
| 牛乳の利用法 |
牛乳は、 飲用の他、各種乳製品の原料やヴィシソワーズなどのスープやクリームシチューなどの煮物、或は粥やフレンチトースト、飛鳥鍋などの料理、ケーキや洋菓子などの製菓原料としても利用されています。一般的な利用法として
飲用にする場合は、加熱したり冷却してそのまま飲む他、砂糖や鶏卵、蜂蜜、ジャム、ジュース、きな粉、胡麻などを好みで加える場合もありますし、コーンフレークなどのシリアル食品にかけて食べることも一般的です。なお、
特殊な例としては入浴剤として利用される場合もあり、一部では牛乳が美容に効果があるとされていますが、科学的には効果のほどは不明です。
このように牛乳は 様々な用途に用いるため、用途に従って各種タンパク質が分離されており、たとえばカゼインは食品用途や工業用途、印鑑、繊維などに、またラクトアルブミンはワクチン製造などの医療用途に用いられています。また、最近は中国などで需要が増えてチーズなどの価格が高騰する一方で、日本では生産過剰によって牛乳が大量に廃棄されるほどとなっているため、他にも医薬製造など様々な用途が模索されています。
|
| 良い牛乳の選び方 |
良い牛乳、すなわち最も生乳に近く、安全で安心な牛乳とは、成分無調整で低温殺菌によるノンホモ瓶牛乳です。このような牛乳を選ぶことがよい牛乳選びだということになります。
まずは「加工乳」と呼ばれる牛乳を避け、「成分無調整」の表示がある牛乳を選ぶのが最低限の選び方です。加工乳は脱脂粉乳や無塩バター、合成添加物など生乳の本来の成分を失った工業製品であり、メーカーの利益のみを追求した牛乳となっているからです。
次に殺菌温度に注目します。殺菌温度は大まかに「高温殺菌」と「低温殺菌」とがありますが、100℃以上での高温加熱殺菌は牛乳に豊富に含まれる消化吸収のよい可溶性カルシウムが破壊される栄養上の問題、さらには過酸化水素の毒性も問題となります。わが国では殆どが100℃以上での高温殺菌の牛乳となっていますが、100℃以下の低温殺菌の牛乳を選ぶのが適切です。なお、140℃の高温で殺菌するロングライフ牛乳はパックの消毒に用いられる過酸化水素の残留の怖れも一部で指摘されており、従って問題外です。一般には「パスチャラチャライズ牛乳」と呼ばれている牛乳で、牛乳パックに記載されていますので、その表示を見て選ぶようにしましょう。
最後に、市場では殆ど販売されてはいませんが、ホモジナイズ処理(均質化処理)がなされていないノンホモ牛乳と呼ばれる牛乳を選ぶことが適切です。ホモジナイズ処理とは過度の圧力を加えて天然の生乳中の脂肪球を粉々に細粒化する処理のことで、単純に舌触りのよさと腐っているように感じさせないための見せかけの処理です。この処理もまた生乳の成分を損ない、アメリカでは心臓病の原因であるという学説もあるほどなので、そんな訳で、出来ればノンホモ牛乳を選ぶようにしましょう。なお、さらにこだわるならば、過酸化水素の残留が心配されるパック牛乳よりは瓶の牛乳を選ぶのが過酸化水素の毒性を心配しなくてもよいでしょう。
|
| 牛乳の世界史 |
食物としての乳の利用は動物の家畜化と共に始まりました。牛の乳が飲料として最初に利用されたのは、まずは中東においてです。山羊や羊が家畜化されたのも、紀元前9000年〜8000年頃の中東でした。山羊と羊は反芻動物で、乾燥した草を食べることに適応した哺乳類です。このような草は人間にはそのまま利用できないものの、備蓄等は比較的容易です。当初、動物の飼育は食肉または衣服製作のために行なわれていましたが、耕作されていない草地を食料源として利用するためにはより効率的な酪農という方法が存在することが後に明らかになります。ある動物を肉のために殺すとすると、その栄養価はたとえばその動物から1年間に採れる乳と同等かも知れません。生きていればその動物からはさらに何年もの間乳が採れるでしょうし、1頭丸々の肉と違って、乳は1日1日にちょうど利用しやすい分量だけ使うことができます。
紀元前7000年頃、トルコの一部で牛の遊牧が行なわれていました。なお、新石器時代にブリテン諸島で乳が利用されていた証拠が見つかっています。チーズとバターの利用はヨーロッパとアジアの一部、また、アフリカの一部に広まっています。このように牛の畜養は元々はユーラシア的な習慣でしたが、
大航海時代以降、世界に広がるヨーロッパ諸国の植民地に導入されます。
それに対して、日本と同じく例外的に牛乳の飲用が普及しなかった国として中国が挙げられます。たとえば金王朝によって監禁された欽宗の悲劇として、茶を飲ませてもらえず、牛乳(という粗末なもの)を与えられたというエピソードが存在するくらいです。ただし日本と同様、現在の中国でも酪農と牛乳は一般に普及しています。
今日、世界的に牛乳がひとつの産業として大規模に生産されており、先進国では自動化された搾乳設備を持つ酪農業者によってその大部分が生産されています。今日、乳製品と牛乳の生産量が最も大きい国はインドで、これにアメリカと中国が次いでいます。なお、牛の品種のあるものは、たとえばホルスタインのように牛乳生産量の向上に特化して改良されたもので、アメリカ合衆国の乳牛の90%、イギリスの乳牛の85%がホルスタインだとされます。アメリカの代表的な乳牛品種は、ホルスタインの他、エアシャーやブラウンスイス、ガーンジー、ジャージー種、ミルキング・ショートホーンなどが挙げられます。
|
| 牛乳の日本史 |
物事には何にでも歴史があります。牛乳の歴史も然りです。
それでは、牛乳を飲む習慣はいつ頃日本に伝わったのでしょうか? 私たち日本人が常日頃から牛乳を飲むようになったのはいつ頃からのことなのでしょうか? 牛乳が日本に伝わったのはかなりの昔のことですが、日本人が牛乳を日頃から飲用するにはかなり時間がかかったようです。
| 日本に牛乳が知られたのはいつ? |
そもそも人類が牛乳を飲むようになったのはいつの頃からのことなのでしょうか?
6000年前の古代のメソポタミアの壁画には搾乳や乳を利用する様が描かれています。気の遠くなるほどの昔ですが、それに対して日本に牛乳が伝わったのは朝鮮半島を経て6世紀頃に伝わったとされています。
|
| 薬だった飛鳥・平安時代 |
日本人が搾乳や牛乳について知ることになったキッカケは、百済からもたられた医学書や経典と共に日本にやってきた牛乳の薬効や乳牛の飼育方法が書かれた書物からです。大化の改新の頃に皇室に牛乳が献上され、その豊富な栄養素から、牛乳は人の身体を良くする薬として喜ばれ、献上した者に和薬使主(やまとくすしのおみ)という「医者として牛乳を管理する者」という意味の称号が与えられたほどです。これが日本で牛乳が飲まれるキッカケだったわけですが、しかし、牛乳が庶民の口に入るようになるにはまだまだ先のことです。このように薬用として大事にされた牛乳は、毎日2300mlもの量が皇室に納められました。酪農が広まると、蘇という牛乳を1/10に煮詰めたものが税として納められるようになり、貴族の間にも健康維持や病気の時の健康の回復に薬として持て囃されるようになります。しかし、平安時代も末期を迎える頃には蘇を税として納める制度も廃れてゆきました。
|
| 将軍・徳川吉宗と牛乳 |
時代が下がって江戸時代に入ると、暴れん坊将軍で有名な八代将軍・徳川吉宗は外国人獣医から牛乳やバターが馬の治療に良いと薦められ、牛3頭をインドから輸入しました。千葉の牧場で飼育させ、これが現代の酪農へとつながってゆくのです。牛乳から作った蘇を将軍や大名の善に供え、滋養強壮剤として大層珍重されたと言います。江戸時代末期、外国人を見た前田留吉という人物が、外国人の大きな身体は牛乳を飲んでいるからだと考え、牛の飼育と搾乳を手懸けて販売するようになり、これが日本で初めての牛乳の販売となります。
|
| 文明開化と牛乳 |
皇室で毎日2回牛乳が飲まれていると新聞で報道されたのが明治4年のことです。日本中に牛乳の存在が知れわたるようになり、牛乳を飲むことが広まってゆきました。文明開化の真っ只中で、何をするにも欧米の真似をしていた日本人ですが、大名や旗本の屋敷跡で牛を飼って牛乳を売ることは、時代の流れと共に収入のなくなってしまった武士には恰好の事業となりました。牛乳屋を経営していたのは公爵や子爵で、大きな缶に牛乳を入れて牛乳配達員が各家庭を回って量り売りをしました。そして、時代と共に缶が瀬戸物瓶やガラス瓶へと容器も変わってゆきます。そうした中で、1869年に初めて日本人がアイスクリームを製造販売するなどして、牛乳はどんどん日本人の生活の中へと入ってゆきました。
|
| 参考:牛乳容器の変遷 |
| ■ |
ブリキ缶 |
|
量り売りの時代には、牛乳は大きなブリキの缶に入れられていました。明治時代になると180mlの小さなブリキ缶に入れられ、天秤棒で配達されていました。 |
|
| ■ |
ガラス瓶 |
|
瀬戸物の瓶の使用期間は短く、直ぐにガラス瓶に入った牛乳が売られるようになります。決まった形もなく、様々な形の牛乳瓶がありました。大正時代には瓶の蓋が王冠栓になっているものが広まり、昭和に入って色のつかない透明の瓶に紙のキャップをすることで法律が整いました。180mlの時代が長く続きますが、学校給食の始まりをキッカケに1本の量は200mlへと変わってゆきました。 |
|
| ■ |
紙パック |
|
昭和31年に初めての紙パック入り牛乳が発売されました。通称三角牛乳です。軽くて扱いが容易な紙パック牛乳は東京オリンピックにも採用され、瞬く間に普及してゆきました。そして、現在あるブリック型のものや1リットル入りの容器に使われているケーブルトップ型などが登場して現在に至ります。 |
|
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|
| 【2】牛乳とその効用&レシピ |
牛乳には一体どんな効用があるのでしょうか? 本節では牛乳と睡眠の関係をはじめ、その効果的な利用法などを取り上げ解説しました。
|
| 牛乳は栄養密度の高いバランス食品 |
本来、子牛を育てるための栄養源である牛乳は、同じほ乳類である私たちにとっても理想的な栄養食品です。コップ1杯(約200ml)で1日に必要なカルシウム量の約3分の1が摂れるばかりか、良質な蛋白質やビタミン類などたくさんな栄養素が牛乳にはバランスよく含まれています。栄養が豊富だとカロリーが高いと思われがちですが、同じカロリーの他の食品を食べるよりもバランスよく効率的に栄養素を摂ることができます。
| ◆ |
栄養素密度とは? |
|
食品のエネルギー100kcal当たりに含まれている栄養素の量のことを栄養素密度と言います。従って、少ないカロリーで栄養素が豊富な牛乳は栄養素密度の高い優れた食品と言うことができます。 |
|
|
| 老若男女、みんなに嬉しい牛乳パワー |
カルシウムが欠かせない成長期の子どもにはもちろん、骨の健康や生活習慣病、ダイエットが気になる大人にも、牛乳には嬉しい働きが満載です。そのまま飲んだり、コーヒーなどの他、或は飲み物や料理に混ぜたり、好きな方法で気軽に摂り入れましょう。
| ■ |
こんな時こそ牛乳パワー |
|
- 外食など偏った食生活の栄養バランスアップに
- 臭いの強いものを食べた後の口臭予防に
- お酒の後に飲んでアルコールの分解をサポート
- 眠れない時に飲んでぐっすり安眠効果
- 食欲がない時、ダイエット中の栄養補給に
- 辛い料理と一緒に飲んで辛さをマイルドに
- イライラしがちな人のカルシウム補給に
- 運動後に飲んで速やかに筋肉疲労を回復
|
|
|
| 参考1:賞味期限が過ぎた牛乳は飲んで大丈夫? |
食品の期限表示には「賞味期限」と「消費期限」の2種類があります。賞味期限は、定められた方法で保存した場合、品質が充分保たれる期間のことで、要するに「美味しく食べられる期限」を意味しています。一方「消費期限」の方は、製造日を含めて概ね5日以内に品質が急速に劣化する食品に表示されるもので、要するに衛生上の危害が発生する恐れのない期間で「安全に食べられる期限」のことを意味します。ですから、この消費期限を過ぎたものは食べないようにしましょう。
現在流通している牛乳の殆どは、超高温瞬間殺菌(120〜150℃で1〜3秒)したもので、この牛乳には、定められた方法(10℃以下で冷却)で保存した場合に牛乳本来の美味しさや品質が充分に保たれていることを示す「賞味期限」が表示してあります。
全国飲用牛乳公正取引協議会のガイドラインによると、10℃での保存期間中における細菌数の変化衛生的な汚染の指標とされている大腸菌群の有無などの細菌試験の他、外観や風味が正常であるかなどの検査をすることとなっています。これらの試験の結果を総合的に判断して安全性や品質が充分に保たれる期間が製造日からどのくらいまでかを確認して、そこから導き出された日数に安全係数0.7を掛けて「賞味期限」を設定しています。たとえばその日数が製造日から18日間の場合なら、18×0.7
=12.6ですから、賞味期限は12日間ということになり、念を入れて多少短めに設定されるのです。従って牛乳を開封しないで冷蔵庫に保存して置いたものなら、2日くらい賞味期限が過ぎたとしても何の問題もなく、飲んでもよいでしょう。
何れにせよ、開封した牛乳は2日目までには飲むのがベストです。気になるようでしたら、異臭がしないか、口に少し含んで味が変わっていないか確かめてみましょう。また、鍋で沸騰してみてカッテージチーズのような固まりが出来なければ大丈夫です。
|
| 参考2:牛乳はいつ飲むのが効果的? |
牛乳はいつ飲んでも構いませんが、夜に摂取することで特に次の3つの効果が期待できます。
- 人間の身体には血液中のカルシウム濃度を一定に保つシステムが備わっています。睡眠中は血液中のカルシウム濃度が低くなりやすいため、骨のカルシウムが溶け出して血液中のカルシウム濃度を一定に保つ働きをします。そこで就寝前に牛乳を飲むことで血液中のカルシウム濃度の低下を防ぐことができ、カルシウムの骨からの溶出を予防することができるのです。
- 牛乳の蛋白質が消化酵素によって分解されて出来るオピオイドペプチドは、中枢神経及び末梢神経に作用して沈静的に働くものが認められ、眠りを誘うとされています。また、牛乳中の必須アミノ酸のトリプトファンは、体内で消化吸収されて誘眠効果のあるセロトニンに変換され、さらにその何割かは睡眠ホルモンと言われるメラトニンになると言われています。
- 睡眠中は成長ホルモンの分泌が活発になるため、牛乳中の蛋白質やカルシウムが骨や骨格を形成するのに役立つため、特に成長期の子どもには効果的です。
このように牛乳には、夜の摂取によってカルシウムが溶け出すのを防ぐ、睡眠を促す、成長ホルモンを分泌を促進する作用などが認められています。
ちなみに、就寝前の牛乳飲用には睡眠の質を向上させるという研究データが報告されています。就寝前の牛乳及びアルコール飲用の睡眠の質への影響について研究したあるデータによると、睡眠の質の自覚的総合判断であるスタンフォード睡眠スコア(睡眠の質が最低の場合7点となり、値が低いほど睡眠の質が高い)では、牛乳200ml飲用が熟睡に相当する2点台のスコアを示したそうで、また、アルコール&牛乳飲用も2.5点とこれに近い数値を示したと言います。またこの他、牛乳中のカルシウムには交感神経の働きを抑制かる作用があります。ストレスから来るイライラや不安、緊張などは自律神経が交感神経優位の時に起こりがちですが、こんな時に温めた1杯の牛乳が適度に空腹感を満たし気分をリラックスさせて安眠へ導いてくれるのです。
|
| トリプトファンと牛乳 |
| 眠りは健康を守り、不老長寿をもたらす |
| ■ |
眠りのメカニズムが明らかになった |
|
脳内ホルモンと言われる神経伝達物質の研究が進み、眠りに対してメラトニンというホルモンが重要な働きをしていることが明らかになってきました。メラトニンは脳にある松果体から分泌され、夜暗くなると分泌が高まり、朝になって明るくなると分泌が減少します。実験で充分に睡眠が足りている若者にメラトニンを与えて昼寝させたところ簡単に寝ついて、しかも深い眠りに入ったそうです。このことからも分かるように、メラトニンは眠りに入らせ熟睡させるのに大切な物質であるのです。そんな訳で、現在アメリカではメラトニンはドラッグストアでも市販されていて、不眠症に悩む人たちが常用していると言います。その他、メラトニンは海外旅行をした時の時差ボケの解消にも効果があり、これを利用している人も少なくありません。 |
|
| ■ |
メラトニンの分泌を増やすには |
|
メラトニンは、同じく脳内ホルモンであるセロトニンを材料にして作られます。セロトニンは心身の興奮や活動を鎮め、休ませるように作用します。つまり、脳の中のセロトニンが増えることによって心身の興奮が鎮まり、さらにセロトニンを材料にメラトニンの分泌が増加して心地よい眠りに誘われるというわけです。従って、上手に眠りに入り熟睡するにはセロトニンやメラトニンの分泌を増やすことが大切なことが分かります。昔から眠れない時に温かい牛乳を飲むとよいと言われますが、これはセロトニンやメラトニンの分泌を増やすひとつの方法だったわけです。実はセロトニンはトリプトファンというアミノ酸から作られますが、牛乳にはこのトリプトファンがたくさん含まれているのです。トリプトファンを材料にしてセロトニンやメラトニンの分泌が増えますし、温かい飲み物で心身もリラックスします。また、牛乳に豊富なカルシウムには神経の興奮を鎮め、精神を安定させる作用があるので、それらが相俟って眠りにつくのを助けるという次第です。牛乳の他トリプトファンを多く含む食品としては、鶏卵や牛レバー、豆腐、人乳(母乳)、調整粉乳(赤ちゃん用粉ミルク)、プロセスチーズなどがあります。なお、動物性のタンパク質を摂り過ぎると、他のアミノ酸が邪魔をして脳に入るトリプトファンを少なくするとも言われていいて、たとえば肉類の食べ過ぎは眠りを妨げる原因になります。 |
|
| ■ |
眠りの妙薬メラトニンの分泌を促進させるためには |
|
メラトニンの分泌を高めるためには、精神的にリラックスし、心身の緊張をほぐすことも大切です。眠れない時に「羊が一匹、ヒツジが二匹」などと数えるのも、数えることに意識を集中して心身をリラックスさせる方法です。時計の刻む音や雨垂れの音、隣に寝ている人の寝息などに耳をすましてみるのもよい方法かも知れません。静かな単調なリズムの音楽を聴くのもよいですし、市販されている入眠のための音楽や自然の音などのCDやテープをかけるのも、セロトニンやメラトニンの分泌を増やすのに効果があると思います。その他、日中は明るいところで過ごす、夜は明りの強いところは避けることなども、メラトニンを増やすのに大切だと言われています。 |
|
| ■ |
メラトニンは不老長寿の薬でもある |
|
メラトニンという物質は、実は不老長寿の薬でもあると言われています。
ストレスは老化や生活習慣病の重要な原因です。免疫力を高めることで色々な病気の予防になるだけでなく、癌の予防や治療にも役立つのではないかと研究が進められています。活性酸素は動脈硬化を進め、老化の重要な原因となります。
メラトニンの分泌は、子どもの頃に多く、その後次第に減ってゆき、50歳を超えると10歳頃の10分の1以下になります。ですから、これを外から補ってやれば、人類が求めてきた不老長寿の薬になるのではないかとすら言われているのです。薬として飲むかどうかは別として、老化防止や健康増進に役立つメラトニンの分泌を増やすには、ゆっくりと心身を休めて、グッスリよく眠ることが大切だと言うことになります。 |
|
| ■ |
メラトニンの作用 |
|
- 眠りを起こさせる
- 生体のリズムを整える
- ストレスを緩和する
- 免疫力を増強する
- 活性酸素の害を減らす
- 老化防止
|
|
|
| メラトニンと睡眠 |
メラトニンは脊椎動物の脳の中心部にある松果体という器官から分泌するホルモンです。メラトニンは、先にも触れたように睡眠など体のリズムに深く関係し、夜間に多く分泌され、睡眠を促し、身体を休ませる作用があるとして注目を集めています。また、メラトニンは、睡眠促進効果だけでなく若返りホルモンとして注目を集め、寿命を延ばす効果でも話題です。
昼間日光に当たると脳内物質のセロトニンが増え、これが夜になると睡眠をもたらすメラトニンに変わります。このため、体内のメラトニンの量を増やすには、昼間は太陽の下で活動し、夜は暗くして寝ることが大切です。しかし、現代人は、このような習慣がつけづらくなってきていますので、メラトニンを多く含む食品によってメラトニンを摂り入れることを考えることも得策でしょう。
|
| メラトニンとケール及び牛乳 |
植物の中でもキャベツの原種と言われるアブラナ科のケールはメラトニンを大量に含んでいます。ケールを含む他の植物と比べればトマトの15倍、バナナの16倍、一般に出回るキャベツの37倍にもなると言われます。このようにケールにメラトニンが大量に含まれているため、より安全で手軽にメラトニンを摂ることができます。また、メラトニンはトウモロコシにも含まれています。
なお、セロトニンはトリプトファンというアミノ酸を原料にしています。トリプトファンを摂取する食材として代表的なのが牛乳です。そのため、これに適度な糖分を加えるとより効果的です。糖分はトリプトファンが吸収されるのを助けるからです。牛乳にハチミツを加えるのもよいでしょう。
|
|
| ホットミルクは睡眠に効果的 |
| 睡眠に有効と言われるホットミルク |

ホットミルクは睡眠に有効と言われています。しかし、これは特に牛乳の成分が知られていない昔からどの国でも言われてきたことです。このことは、ホットミルクを飲むと自然と眠気が出てくるという経験からの生活の知恵と言ってよいでしょう。
寝る前のホットミルクが睡眠を促す理由は牛乳の成分にあります。もちろん温められた牛乳が胃腸を温めるために寝つきやすくなるということもあるでしょう。胃腸の温度が上昇すると、そのあと体温を下げようという働きが起こりますが、この時に深い眠りに入ってゆけるのです。これは、ぬるめのお風呂やシャワーを浴びると、その直後に体温が下がってきてよく眠れることと同様の原理です。
|
| 牛乳のトリプトファンが効く |
牛乳には、安眠及び快眠に役立つ成分が豊富に含まれています。たとえば必須アミノ酸の一種であるトリプトファンもその要素のひとつです。これは牛乳から発見されたアミノ酸で、眠りに不可欠な栄養素であると言われます。
牛乳のトリプトファンが体内に入ると、腸管から吸収され、脳に届きます。すると松果体でトリプトファンからセロトニンが作られますが、これも安らかな眠りに大切な成分です。セロトニンが少なくなると、鬱病になったり気分が塞ぎ込んだりすることが知られていますが、このセロトニンがさらに代謝されるとメラトニンに分解されます。そして、睡眠ホルモンという別名があることからも分かるように、メラトニンは眠りに欠かせない成分です。体内でメラトニンが合成され分泌されますが、それも体外からトリプトファンを摂取してこそできることなのです。そのため、もしもトリプトファンの摂取量が少なくなると、気分の変化を起こし、睡眠障害になりやすくなると言われているのです。
|
| 牛乳のカルシウムがイライラを鎮める |
ホットミルクが睡眠に効果があるのには、以上で説明したような理由がありますが、その他にも牛乳の成分として見逃せないのはカルシウムです。カルシウムは骨を作る成分として知られていますが、その他にも神経伝達の際にカルシウムが必要となります。もしもカルシウムが不足すると、神経の伝達がうまくゆかなくなり、イライラすることになるわけです。そのため、寝る前にホットミルクを飲むことは、カルシウム不足によるイライラを鎮め、睡眠を促してくれるわけです。
ただ、ここで注意点としては、カルシウムだけを摂っていると、摂取したカルシウムが血液中に溢れてしまい、痙攣や震えが起こることがあるということで、そのため、カルシウムを摂ることによって却ってイライラしやすい状況になってしまうこともあるのです。これを防ぐには、カルシウムと同時にマグネシウムを摂取することです。牛乳には多少のマグネシウムが含まれているので安心です。もしも万全を期したいのなら、夕食時にアーモンドや胡桃などの種実類を食べることがオススメです。こうすることでマグネシウムを確実に摂取することができます。その他にもカルシウムの吸収を高めるにはビタミンDも不可欠です。ビタミンDが含まれる魚を夕食時に食べると、ホットミルクの睡眠効果が倍増します。また、昼間は太陽の光を浴びながら外をウォーキングすると、これまた体内でビタミンDが合成されます。なお、その他にもホットミルクが睡眠に役立つ理由として、ビタミンB1やB2、B12と言ったビタミンB群が豊富に含まれていることが挙げられます。ホットミルクにはその他ビタミンA(レチノール)やカリウムも豊富に含まれているのですが、特にビタミンB群は神経伝達をスムーズにする働きがあるため、脳と深く関係のある睡眠にとって極めて大切なのです。
|
|
| バナナ牛乳を睡眠前に |
| オススメはバナナ牛乳 |
牛乳にはイライラを解消してくれるカルシウムはもちろんトリプトファンというアミノ酸が含まれていて、体内で睡眠物質に変化し、安らかな睡眠をもたらしてくれます。その牛乳のもたらす効果をさらに増強してくれるバナナをプラスするのがオススメです。中々寝付けなかったり、眠れても直ぐに目が覚めてしまったりと、不規則な生活が続いて一番辛いのが不眠ですが、そんな時には是非バナナ牛乳を試してみて下さい。バナナ牛乳は、ストレスを緩和し、安らかな睡眠をもたらしてくれることでしょう。
|
| トリプトファンとセロトニン |
トリプトファンとは牛乳から発見された必須アミノ酸の一種で、人間の身体にとって非常に大切なアミノ酸のひとつです。それというのも、このトリプトファンが体内に入るとセロトニンという物質に変化するのですが、このセロトニンが非常に重要なのです。セロトニンはある意味で人間の安心感をを作り出してくれる脳内ホルモンで、要するにセロトニンが分泌されると、心が落ち着き、癒されるという効果があるのです。これが不安感を解消したり、逆立っている神経を落ち着かせてくれるわけです。
生活が不規則な人の不眠の原因は、寝ようと思っても神経が高ぶったままで中々寝つけなかったり、ストレスや疲れが溜まっているからで、だからこそセロトニンの活躍が大切になるのです。そして、そのセロトニンの前段階となるトリプトファンは、忙しい人にとってとても大切なアミノ酸になるということです。
|
| バナナ牛乳がよい理由 |
そんな効果があるトリプトファンですが、残念ながら人間の体内ではつくることができません。従ってトリプトファンは食物から摂るしかないのです。トリプトファンが多く含まれるのは赤身の魚や肉類、大豆類、そして乳製品です。カツオやマグロの赤身、牛肉の赤身などはとてもよいのですが、さすがに寝る前に魚や肉を食べるわけにはゆきません。幸い牛乳にもたくさんのトリプトファンが含まれているので、そこで寝る前でも飲める牛乳がオススメだということになるわけです。苦手でない人は牛乳にきな粉や黒ごまなどを加えて、きな粉牛乳や黒ゴマ牛乳にするとさらに効果的です。ただ、トリプトファンはそれだけではセロトニンにはならない、トリプトファンはビタミンB6と合成して初めて有効なセロトニンが生成されるのです。だから、バナナがオススメとなるのです。それというのも、バナナにはビタミンB6が豊富に含まれているので、寝る前にバナナ牛乳を飲めば効果抜群というわけです。そんな訳で、寝る前に摂取するということと含まれる成分から考えて、安眠のためにはバナナ牛乳が最適だということになるわけです。
|
| 牛乳以外でトリプトファンを摂取するには? |
トリプトファンは赤身の魚や肉、大豆製品、乳製品などに多く含まれています。牛乳が苦手で飲めないという人は、夕食時にカツオや大豆製品を食べるとかチーズを2切れくらい食べるとかでもトリプトファンは摂取できます。ヨーグルトもいいでしょう。かつお節でも構いません。なお、不眠解消のためだけでなく、トリプトファンはストレス解消やイライラを抑えたり心の安らぎを与えてくれる大切な成分なので、生活が不規則な人は日頃から積極的に摂取するように心懸けるとよいでしょう。また、トリプトファンには空腹感を抑制する効果もあるとのことなので、夜間に食べ過ぎてしまう人やダイエット中の人にもオススメです。
|
| バナナ牛乳レシピ |
ミキサーやジューサーに牛乳入れて、バナナを1口大に千切って入れてミックスします。バナナはたっぷり1本入れた方がいいでしょう。なお、バナナで充分な甘さがあるので、わざわざ砂糖などを加える必要はありません。なお、冷たい方がいい人は氷を1〜2個一緒にミックスするのもよいでしょう。これにヨーグルトを加えると、さらに美味しさもアップします。さらにこれにきな粉を加えるならスプーン3杯位が目安です。こんな具合でとても簡単です。バナナ牛乳は便秘解消にもオススメなので、早速毎晩続けましょう。
|
|
| 不眠症を解消するハチミツ入り牛乳 |
ストレス社会を反映してか、現代人には不眠症が広がっていると言います。眠りたいのに眠れないというのは非常に辛いことです。そんな不眠症の解消にもハチミツは一役買ってくれます。ホットミルクに甘さが欲しいという方は、寝る前にハチミツ入りの牛乳を飲んでみてはどうでしょうか。これだけでも寝つきがぐんとよくなり、眠りやすくなること請け合いです。
不眠症の最大の原因はまず第一にストレスです。人は何か悩みがあったり不安を感じている時に眠れなくなります。これは狩猟時代の防衛本能の名残で、外敵から身を守るために緊張状態では眠れないように人体は設計されているのです。そんな厄介なストレスを緩和し、心の興奮を鎮めてくれるのが、身体の中で生成される天然の精神安定剤であるセロトニンという物質です。従って、セロトニンの分泌を増やせばストレスを抑えぐっすり眠れるようになります。しかし、セロトニンを増やす肝腎の原料がなければ、セロトニンの分泌を増やすことは当然ながらできません。それがトリプトファンという必須アミノ酸なのです。しかも牛乳の中にはこのトリプトファンがたくさん含まれているのです。そんな訳で昔から牛乳は人を安らかな眠りに誘う効果がある飲み物とされてきたのです。それは要するに、牛乳を飲めば、セロトニンがよりたくさん作られるということでもあります。この牛乳にハチミツをミックスするとどうなるでしょうか? 実はハチミツに含まれるブドウ糖にはトリプトファンが身体に吸収されるのを助ける効果があるのです。従って、ナイトミルクにハチミツを足せばよりセロトニンを増やせるというわけです。不眠症の時だけでなく、ストレスを感じて参っている時などにも、このハチミツ入り牛乳は効果的です。ハチミツ入り牛乳はイライラ気分を鎮めるのを助けてくれることでしょう。なお、不眠症の患者さんにハチミツとレモン汁を混ぜたものを飲ませたらぐっすり眠れたという話もあります。また、ドイツやフランスでは、寝る前のハチミツが絶好の睡眠剤になると唱えている研究者もいます。ハチミツだけの飲んでも、それなりに睡眠効果があるようです。
|
| 参考3:眠りを誘うナイトミルク |
ベッドに入る前に1杯のホットミルク。ドラマや映画などでそんなシーンを見たことのある人も多いかも知れません。昔から牛乳は安らかな眠りに誘う効果がある飲み物とされてきました。精神を病んでいた英国の女流作家ヴァージニア・ウルフも、眠れない夜は夫の薦めでホットミルクを飲んでいたと言います。一体なぜ牛乳は不眠によいとされているのでしょうか?
| 睡眠ホルモン・メラトニンとは? |
牛乳が安らかな睡眠に効果があると言われるその秘密の鍵は、牛乳に含まれるメラトニンにあります。メラトニンは脳の松果体という器官から分泌されるホルモンで、睡眠ホルモンと呼ばれることがあります。それというのも、メラトニンには脈拍や体温、血圧を低下させるなど睡眠を促す作用があるのです。さらにメラトニンは夜間に多く分泌されるという性質も持っています。これはメラトニン産生が光によって抑制されるためで、昼間の光が弱まると徐々に産生量が増えてゆき、真夜中頃にピークに達するのです。その後減少し始め、翌朝になると極端に減って、覚醒が起こるという次第です。ちなみに、メラトニン分泌量は年齢と共に減少するのですが、お年寄りが中々寝つけなかったり、明け方に目が醒めてしまうのはこのためです。
こうした性質を活かして、アメリカなどではメラトニンのサプリメントも販売されており、時差ぼけ予防に愛用するビジネスマンや国際線客室乗務員も多いと言われます。メラトニンを含む牛乳が格好の催眠薬となるのも頷ける話です。
|
| オススメはナイトミルク |
最近フィンランドで、催眠効果の高い牛乳としてナイトミルク人気を呼んでいるそうです。ナイトミルクとは夜間に搾乳された牛乳のことを言います。人間と同じく昼行性動物の牛が夜間により多くのメラトニンを産生するのは当たり前といえば当たり前の話ですが、何とナイトミルクのメラトニン含有量は通常の3〜4倍になるのだと言います。
実はフィンランドではたくさんの人が睡眠障害に悩んでおり、女性の11%、男性の7%が毎日のように昼間の眠気を感じていると言います。さらに労働者の半分以上が睡眠障害などストレスによる何らかの症状を持っているという話もあります。その背景には90年代初期の景気後退があります。不況に伴う失業や短期契約の増加といった雇用環境の悪化が働く人々のメンタルヘルスを低下させたのです。フィンランドの人々は健康に敏感だと言われますが、そのような人たちなるが故に、健やかな眠りを取り戻したいという思いは真剣なものに違いありません。そんな訳で添加成分もなく安心して飲めるナイトミルクに注目と期待が寄せられているのも納得できるというものです。
|
| ナイトミルクで生活リズムを取り戻し、心穏やかな日々を |
厳しい時代に生き、心のバランスを失いがちな点では、私たち日本人もフィンランドの人たちとさして違いがありません。何と言っても不眠を招くのは不規則な生活と心のストレスです。最近日本国内でも発売されているナイトミルクを飲むことで生活のリズムを取り戻し、健やかな日々を過ごしてはどうでしょうか。牛乳のカルシウム成分や仄かな香りもきっと心を和ませてくれるはずです。
|
|
| 参考4:牛乳を使った料理のレシピ |
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|