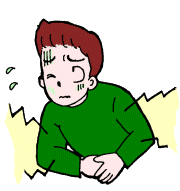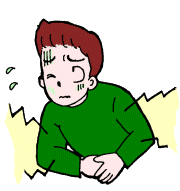| 【1】ノロウィルスとは? |
この冬もノロウィルスによる感染症が流行しています。
本節ではノロウィルスとはどのようなウィルスなのか、その症状や感染経路について取り上げ解説しました。
|
| 冬も油断できない!~冬場の食中毒とノロウィルスに注意~ |
冬の到来と共に、ノロウイルスによる集団食中毒のニュースがちょくちょく聞かれるようになりました。食中毒の発生は夏場だけに限らず、特に冬場にはノロウイルスによる食中毒や感染症が多くなります。日本での食中毒患者数の53%はノロウイルスが原因で、そのノロウイルスによる食中毒の70%は11~2月に集中して発生しているのです。
ノロウイルスは、世界中で急性胃腸炎の原因として1年を通じて見られ、特に温帯地域の冬に多いとされています。日本でもかつては「腹に来た風邪」とか「風邪による腹痛や下痢」などと言われた疾患の原因の一つで、口からウイルスが入ったことで感染(経口感染)します。
|
| 11月?2月に集中するノロウィルス |
この冬、ノロウイルスが全国で猛威を振るっています。
毎年各地でノロウイルスの集団感染が発生し、老人施設などでは死亡者が出たと報じられるなど、その流行が気になる季節がやってきました。ノロウイルスに感染すると、激しい腹痛や嘔吐・下痢に見舞われ、脱水や嘔吐物の誤嚥による肺炎など深刻な症状に至ることもあります。健康な大人が感染した場合は2~3日で回復しますが、体力の弱ったお年寄りなどは、場合によっては死に至ることもあるので注意が必要です。食中毒の原因は、一般にサルモネラや病原性大腸菌O-157などの細菌性食中毒、或はフグやキノコなどに含まれる自然毒食中毒が知られています。また、食中毒と言えば湿気が多く細菌の繁殖しやすい梅雨から夏の時期というイメージがありますが、しかし、冬季にはウイルス性食中毒が頻発し、その大多数はノロウイルスというウイルスが原因です。毎年10月頃から1~2月をピークに全国的に流行しています。
| ■ |
ノロウイルス食中毒予防強化期間 |
|
ノロウイルス食中毒予防強化期間が始まっています。食中毒なら蒸し暑い時期のもののような気がしますが、患者数を調べると平成24年にもっとも増加したのは12月の7981人、次いで11月の2897人、3番目は1月で2819人と忘年会や新年会など会食の機会が多い時期に集中していました。原因物質を見るとウイルス由来が大きな割合を占める時期と重なっており、予防強化月間が11月から1月に設定されている理由が分かるというものです。 |
|
| ■ |
ノロウイルスに変異株 世界的に流行拡大か!?
~変異株の出現で感染者が増大する傾向~ |
|
昨年度(2012年4月~13年3月)、日本国内でのノロウイルスの感染者数は1万7千人強と、06~07年度の3万1千人強に次ぐ大発生となっています。また、検出されたノロウイルスの遺伝子を解析したところ、今年の流行はGII/4という遺伝子領域が変化した新しい変異株によることが分かったそうです。ノロウイルスは1995年以来、2~3年ごとに新たにGII/4の変異型が出現しており、そのたびに感染者の増加傾向が見られています。12年後半には、日本だけでなく豪州や英国、米国、オランダ、フランスなどでも同様な変異株が発見され、流行拡大の傾向を示していたそうです。 |
|
|
| ノロウィルスの特徴 |
 ノロウイルスはヒトの腸内でのみ増殖するため、患者や感染者の糞便や吐物には大量のウイルスが含まれています。海水中のウイルスを二枚貝(アサリやカキ等)が溜め込む(=濃縮する)性質があります。[ヒト→糞便・吐物→トイレ→下水処理場→河川→海→二枚貝→ヒト」と自然界を循環しています。感染力が非常に強く、食中毒の他に糞便や吐物・手指を介してヒトからヒトへ感染します。また、ノロウイルスは乾燥すると空中に漂い、これが口に入って感染することもあります。特に保育園や小・中学校、病院、老人ホームなどの施設でヒトからヒトへの感染が多く、冬~春季(11月~4月)に多発します。
ノロウイルスとロタウイルスは共に下痢、嘔吐を主徴とする胃腸炎をおこしますが、ノロウイルスはロタウイルスに比べ幅広い年齢層に罹患する傾向があります。秋から年末にかけてはノロウイルスが、そして、1~4月にかけてはロタウイルスが主に流行します。ノロウイルスは、カキ等の二枚貝の生食による食中毒がよく知られていますが、僅かなウイルスが口の中に入るだけでも感染する、つまり人から人への感染力も非常に強いウイルスです。乳児期から成人まで幅広く感染します。嘔気や嘔吐、下痢が主症状で、一般に症状は軽症です。ただし、老人や免疫力の低下した乳児では重症化して死亡することもあります。保育所や幼稚園、小学校などの小児や、病院や老人ホーム、福祉施設などの成人でも集団発生が見られることがあり、とにかく注意が必要です。
| ■ノロウイルスはどこが違うの? |
| ■ |
新鮮でもダメ! 冷蔵してもダメ! |
|
新鮮だからといって安心してはいけません。カキに限らず食べ物がノロウイルスに汚染されていれば感染の可能性があります。冷蔵してもウイルスは死んだりしません。 |
| ■ |
非常に少量で発症 |
|
非常に少量(数個から100個程度)でも感染しますから、“ちょっと汚したぐらい”と思っても安心できません。 |
| ■ |
人から人にうつります(感染症) |
|
人間の体内でのみ増え、糞便の中に多量に出てきます。感染力が強く、トイレの後の手指や嘔吐物の飛沫(=空気中に飛び散ること)からでも感染しますから特に注意が必要です。 |
| ■ |
消毒薬が効かない |
|
消毒アルコールや塩化ベンザルコニウムなどの逆性石けん液(※洗面所等にある薬用石鹸液)では消毒効果が低いので、熱湯または次亜塩素酸を使用しましょう。 |
| ■ |
感染しても発症しない人がいる |
|
米国での実験例では、ウイルスに感染しても症状が出ない人(=不顕性感染者)が32%であったと言われています。 |
|
| ◆ |
ちょっと専門的に |
|
ノロウイルスは、1972年に米国の小学校で発生した集団胃腸炎患者の糞便から直径約30nmの小型の球形ウイルスとして発見され、電子顕微鏡でなければ観察できないほど小さいウイルス粒子の形から、従来は「小型球形ウイルス(Small
Round Structured Virus :SRSV)」と呼ばれていた古株のウイルスです。なお、SRSVという名称は最近まで用いられ、2002年夏の国際学会で最初に患者が出た米国の町の名前を取ってNVと名づけられました。また、日本でも平成9年5月に食品衛生法の改正で、小型球形ウィルス(SRSV)が食中毒の原因物質に追加されました。アメリカと同様、日本でも従来は「SRSV(小型球形ウイルス)」とされてきましたが、近時の遺伝子解析や学会の状況等を踏まえて、さらに平成15年8月の食品衛生法により、病因物質が小型球形ウィルスから「ノロウイルス」に改められました。お陰で、以前は原因が分からず、いわゆる「おなかの風邪」のひとつとされていたケースがノロウイルス感染と分かり、以来にわかに患者数が増加したという次第です。ちなみに、小型球形ウィルスは電子顕微鏡で観察したとき小さな球形の構造をしている一群のウィルスを総称していますが、実際にはウィルス性食中毒の殆どはノロウィルスが原因で、行政的に小型球形ウィルスはノロウィルス(ノーウォーク様ウィルス)を示していました。従って、食中毒事例で小型球形ウィルス、ノーウォーク様ウィルスと従来呼ばれていたものはノロウィルスということになります。 |
|
|
| ノロウィルスの症状と潜伏期間 |
主な症状は吐き気や嘔吐、そして下痢です。通常は便に血液は混じりません。また、熱も余り高くならないことが多いです。通常これらの症状が1から2日続いた後治癒し、後遺症もありません。また、感染しても発症しない場合や軽い風邪のような症状の時もあります。ただ、小児では嘔吐が多く、嘔吐及び下痢は1日数回から、ひどい時には10回以上の時もあります。また、ノロウイルスに感染してから発症までの潜伏時間は24~48時間で、その主な症状は吐き気や嘔吐、激しい腹痛、下痢、発熱(軽度)などで、感染性胃腸炎と診断されます(※感染性胃腸炎の原因には他に、他種のウイルスや細菌、寄生虫などもあります)。ノロウイルスには特効薬がなく、水分などを補給する輸液や整腸剤などの対症療法が主となります。一般に発症後1~2日ほどで回復しますが、子どもやお年寄りなどは重症化し、長引くこともあります。厄介なのはノロウイルスの感染力が非常に強いことで、症状が消えても糞便からのウイルスの排出が3~7日間も続くことです。ノロウイルスは糞便1グラム中に1億個以上、嘔吐物1グラム中に100万個以上が存在するのですが、10~100個程度のウイルスが口から入っただけでも感染するということです。
|
| ノロウイルス感染症の原因 |
 ノロウイルスによる食中毒は、以前はノロウイルスに汚染された牡蠣やアサリ、シジミなどの二枚貝によるものが最も多いと言われていました。ただし、ノロウイルスは貝類自体には感染しないと考えられていて、ウイルスが貝の体内で直接増殖するわけではありません。実際には貝は大量の海水を取り込み、プランクトンなどの餌を体内に蓄積するのですが、それと同じメカニズムで海水中のウイルスも体内で濃縮・蓄積されると考えられています。ところが、近年はこういった二枚貝が食中毒の原因となることは減少しており、牡蠣が食材とされる集団食中毒も激減しています。疫学的には牡蠣以外の食材、或は直接・間接的なウイルスへの接触による、原因の余りハッキリしない感染経路が圧倒的であると考えられています。
人から人への感染は糞口感染とも呼ばれます。経口感染の場合、ノロウイルスは口から入ってきて、食道や胃を通って小腸の壁で感染し、増殖します。そして、増殖して多くなったウイルスが腸の中で便と混じってゆくわけですが、その結果ウとともイルスは感染者の糞便と共に排出される他、嘔吐がある場合は胃に僅かに逆流した腸液と共に嘔吐物にも混じって排出されます。そうして出て来た糞便や嘔吐物の一部は目に見えないような少量ですが、これが広範囲に飛び散ります。また、手洗いを充分にしないと、ウイルスは手の指の間などにしぶとく残っています。知らず知らずのうちに、衣服や食器など様々な経路で広がったウイルスがごく僅かに混入した食品などを介して再び経口的に感染して広がってゆくことになるのです。なお、しばしば聞かれるのは、まず子どもが感染性胃腸炎に罹って家で吐いたり下痢をしたりして、それを世話したお母さんが同じような症状を訴えて病院にゆくということです。またノロウイルスの場合、少数のウイルスが侵入しただけでも感染・発病が成立すると考えられており、僅かな糞便や嘔吐物が乾燥した中に含まれているウイルス粒子が空気を介して経口感染することもあると言われています。
| ■ノロウイルス感染症の感染経路 |
| 口から入ったノロウイルスは、胃を通り過ぎて十二指腸や小腸上部で繁殖します。そのため酸性にも強く、さらに消毒アルコールや逆性石鹸にも抵抗性を持っています。 |
|
| ■ |
人からの感染 |
|
- 感染した人の糞便や嘔吐物に触れた手指を介しての二次感染
- 糞便や嘔吐物が乾燥して細かな塵や埃と共に舞い上がり、体内に取り込まれる塵埃(じんあい)感染
|
|
| ■ |
食品からの感染 |
|
- 感染した人が充分に手を洗わずに調理した食品を食べた場合
- ウイルスが下水処理施設から河川に排出され、内臓に蓄積された牡蠣やシジミなどの二枚貝を不充分な加熱処理で食べた場合
|
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|
| 【2】ノロウィルスの治療と予防 |
ノロウィルスの治療法や検査法に加え、その予防法について解説します。
|
| ノロウイルス感染症の検査 |
下痢や嘔吐の症状があっても、ノロウイルスによる病気かどうか症状からだけでは中々特定することが出来ないので、医者はウイルス学的に診断をつけことになります。通常、患者の糞便や吐物を用いて検査を行ないます。そして、ウイルスというのはとても小さいもので、通常の顕微鏡では見ることが出来ないので、そのため、より細かい粒子を見ることが出来る電子顕微鏡を用いて調べたり、或はウイルスの遺伝子を増幅して間接的にウイルスを検出する方法を使ったりします。また、酵素を用いて簡便にウイルスと反応させることでで検出を行なうスクリーニング検査もありますが、これは少量のウイルスでは検出されないこともあります。ただし、現時点ではこのノロウイルス検出方法は何れも保険で認められていないため、外来で検査をしようとなると簡単な検査で数千円、精密検査だと1万円から2万円ほど費用がかかってしまいます。何れにせよ、医師の立場から見ると、原因がはっきりしたとしても治療法が変わるわけではないので、一般の内科の外来で診断確定のために検査をすることはまずありません。しかし、少量のウイルスでも感染の原因となること、そして、高齢者や乳幼児では重症になることもあるため、病院や老人施設、給食関連施設等では、ノロウイルスは職場管理上問題となってきます。職種によっては、ノロウイルス感染症の可能性がないか、もしくは可能性が低いことを確定する必要性も考えられます。そのため、そういった時には上記で触れたような検査をする意味もあるわけです。
|
| ノロウイルス感染症の治療方法 |
現在このウイルスに効果のある抗ウイルス剤はありません。すなわち、ノロウィルス感染戦傷に対する特効薬はない状態なのです。症状の持続する期間は短いですから、その間に脱水症にならないように出来る限り水分の補給をすることが一番大切で、必要に応じて市販のイオン飲料等で水分を補給する必要があります。水分を補給しても吐いてしまうような場合は、
早めに医療機関を受診して、場合によっては病院で点滴をしてもらうことも必要になるでしょう。 また、抗生物質は効果がありませんし、下痢止め薬は下痢の期間を遷延させることで却って病気の回復を遅らせることがあるので、通常は使用しません。その他は吐き気止めや整腸剤などの薬を使用する対症療法が一般的です。下痢が長びく場合には下痢止めの薬を投与することもありますが、上記の理由から最初から用いるべきではありません。なお、体力の弱い高齢の方や乳幼児は誤って吐いた物を喉に詰まらせて窒息する危険性もあるので、充分に注意が必要です。
| ■ |
感染性胃腸炎に罹ったら |
|
- 症状が続く期間は比較的短いですが、脱水症状を防ぐための水分補給や安静が大切です。
- ノロウイルスによる感染性胃腸炎に特効薬はありません。治療は症状に応じた輸液や整腸剤などの対症療法に限られます。
- 乳幼児や高齢者、基礎疾患を持っているなど抵抗力の弱い方が感染すると重症になることがあるので、早めに医療機関を受診しましょう。
- 周囲の方への二次感染を防ぐため、症状がある間の入浴はシャワーのみにするか、一番最後に利用し、浴槽に入る前によくお尻を洗いましょう。
- 症状が治まってからも便にウイルスが排出(感染してから1週間~1か月程度)されているので、手洗いなどの手指衛生対策をしっかりと行なって下さい。
|
|
|
| ノロウイルス感染症の予防方法 |
日頃からの予防方法としては、食事前やトイレの後などにおいて、まずは石鹸を使ってお湯などでしっかりと手を洗うことが大切です。また、食品中のウイルスは、加熱により感染性をなくすことができます。食品の中心温度が
85℃ 1分以上になるようにしっかり熱を通して食べましょう。さらに、下痢や嘔吐などの症状がある人は食品を取り扱う作業を控えましょう。
感染経路を考えると、手洗い及び調理器具の衛生管理が重要です。手洗いは、調理を行なう前、飲食業を行なっている場合は食事を提供する前、食事の前、トイレに行った後、下痢等の患者の汚物処理やオムツ交換等を行った後などに、手袋をして直接触れないようにしていても必ず行ないましょう。石鹸を充分に泡立て、手の指の間、爪の間、手首などまでしっかり洗うことが大切です。石鹸自体にはノロウイルスを直接死滅する効果はありませんが、通常の水洗いでは落としにくい手の脂等の汚れを落とすことでウイルスを手指から剥がれやすくする効果があります。また、ノロウイルスの活動性を無くすための温度と時間については、現時点で正確な数値はありませんが、同じようなウイルスから推定すると、食品の中心温度85度以上で1分間以上の加熱を行なえば感染性はなくなると考えられています。そのため、特に子どもやお年寄りなどの抵抗力の弱い方は、加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱することが予防として有効です。なお、家庭内や集団で生活している施設においてノロウィルスが発生した場合、集団感染を防ぐためには、ノロウイルスに感染した人の糞便や吐物からの二次感染、人から人への直接感染、飛沫感染を予防する必要があります。ノロウイルス感染による嘔吐や下痢では、嘔吐物や糞便ともに大量にウイルスが存在しているので、その取り扱いには十分に注意が必要になります。無造作に手で触ったりすることのないようくれぐれも注意しましょう。また、ノロウイルスは乾燥すると容易に空中に漂い、これが口に入って感染することがあるので、吐物や糞便は乾燥しないうちに床等に残らないよう速やかに処理し、処理した後はウイルスが屋外に出て行くよう空気の流れに注意しながら充分に喚気を行なうことが感染防止にとって重要になります。殺菌には熱湯或は家庭用に販売されている液体の塩素系漂白剤、殺菌剤を使用します。ただし、アルコールや逆性石鹸には余り殺菌効果はありません。さらに、汚れてしまった洋服や布団類は、付着した汚物中のウイルスが飛び散らないように処理する必要があります。まず使い捨てのマスクと手袋を着用し、便や嘔吐物はペーパータオル等で取り除き、ビニール袋に入れます。残った糞便や嘔吐物の上にペーパータオルを被せ、その上から50~100倍に薄めた市販の塩素系漂白剤を充分浸るように注ぎ、汚染場所を広げないようにペーパータオルでよく拭きます。そうした後で洗剤を入れた水の中で静かに揉み洗いします。下洗いした洋服類の消毒は85度以上、かつ1分間以上の熱水洗濯が適していますが、家庭であれば普通に洗濯をした後、乾燥機にかける、スチームアイロンを使用するなどの手段も有効でしょう。
| ■予防の基本は手洗い |
| 予防の基本は手洗いです。充分な時間(30秒以上)をかけて洗いましょう。 |
|
|
- まず水で洗う
- 石鹸をつけてよく泡立てる
- 手の甲を伸ばすようにこすって洗う
- 指の間を洗う
- 指先や爪の間を念入りに洗う
- 親指はねじるように洗う
- 水でよく洗い流し、清潔なタオルなどで拭く
|
|
|
|
|
| ■生食は厳禁!しっかりと加熱処理を |
|
ノロウイルスは湯通し程度の加熱では死滅しないので、中心部まで充分に加熱(85℃&1分間以上)しましょう。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 感染予防&食中毒予防のポイント |
| ■ |
最も有効な予防対策は手洗い |
|
- トイレの後、調理前、食事の前には必ず流水と石鹸による手洗いをしましょう。
- ノロウイルスに汚染された可能性のある食材(貝類等)の取扱い、特に加熱しないで食べる食材(サラダ等)の取扱い、そして、調理への移行時にも注意しまししょう。
- タオルの共用は二次感染防止の観点からやめましょう。
|
|
| ■ |
食品を充分に加熱 |
|
- ウイルスに汚染されている可能性のある食品は、中心温度85度以上で1分間以上加熱して食べます。
- 生で(加熱しないで)食べる食品(野菜&果物等)はしっかり洗います。
|
|
| ■ |
調理器具の洗浄&消毒を徹底 |
|
- 洗剤等を用いて調理器具等をよく洗った後、次亜塩素酸ナトリウム(200ppm=0.02%)で浸すように拭くなどして消毒を徹底します。
- 加熱しないで食べる食品は、俎板や包丁等の調理器具を専用のものとして使い分けたり、或はウイルスに汚染されている可能性のある食品に使用した調理器具を使い回しする場合には充分に洗浄と消毒を行ないます。
|
|
| ■ |
調理する人の健康管理を徹底 |
|
- 下痢や嘔吐等の症状がある時は直接食品に触れる作業をしないようにしましょう。
- 症状が回復してからも便の中にウイルスの排泄が続くことがあるので、暫くは直接食品に触れる作業をしないようにします。
|
|
| ■ |
糞便や嘔吐物を適切に処理 |
|
- 糞便や嘔吐物を処理する際には、使い捨ての手袋やマスク、ガウン等を着用し、処理する方が感染しないよう注意します。
- 汚染した床は、乾燥させないよう速やかに次亜塩素酸ナトリウム(1000ppm=0.1%)で、汚染場所の外側から中心に向かって浸すように拭くなど、汚染を広げないよう注意して処理します。
|
|
|
| 間違ったノロウイルス対策してない?うっかり感染するNG習慣 |
| ■ |
手洗いをしているから大丈夫だと思い込む |
|
ノロウイルスなど感染症の予防には手洗いはとても大切です。しかし、爪は伸びていませんか? 爪が伸びていると、爪の間にウイルスが入ってしまうため、手洗いの効果がない場合があります。子どもの爪は常に短くしておくように気をつけましょう。 |
|
| ■ |
汚染した衣類や雑巾を子どもの前で洗う |
|
部屋の中で汚物のついた衣類や雑巾を洗い、部屋の中に干していませんか? 処理の際に吸い込むと感染してしまう恐れのある飛沫が発生します。最低でも3mは遠ざける必要があります。特に子どもは別室に連れて行くのがよいでしょう。洗剤を入れた水の中でもみ洗いをして飛沫を吸い込まないように気をつけるようにして下さい。 |
|
| ■ |
家族で同じ手洗いタオルを使う |
|
タオルについたウイルスは死なずに残っています。そのため、ウイルスがついたタオルで手を拭いて、その手で口に触れると、当然ながら感染の危険が高まります。家族で別々の手洗いタオルを用意しましょう。 |
|
| ■ |
手洗いに固形石鹸を使う |
|
固形石鹸では保管時不潔になりやすいです。よって、1回ずつ個別に使える液体石鹸を使いましょう。 |
|
| ■ |
感染している人をお風呂に入れる |
|
身体が汚れてしまった場合、お風呂に入りたくなりと思いますが、万が一、身体に僅かでも汚物がついている状態で入浴すると、そこから感染する可能性もあります。家族が感染し、発症してしまった場合は、湯船を使うのを止め、お風呂の椅子やスポンジなども別々にするか、塩素系漂白剤で消毒した方がよいでしょう。どうしてもお風呂に入りたい場合は、最後に入るようにしましょう。また、湯船に浸かる前にしっかりお尻を洗うことも忘れずに。 |
|
| ■ |
症状が治まったからと素手でオムツ交換をする |
|
ノロウイルスは感染しても通常3日以内に回復します。しかし、症状が治まってもウイルスは10日ほど排出されていることがあるのです。よって、幼児がノロウィルスに感染した場合は、特にオムツの取り扱いには特に注意しましょう。 |
|
| ■ |
吐いてしまった場所だけ消毒する |
|
嘔吐物は想像以上に遠くまで飛び散っています。床から1mの高さで吐くと、カーペットでは最大1.8m、フローリングでは2.3mも飛び散ると言われています。カーペットの場合は毛足の長さにも影響されますが、広い範囲を消毒しましょう。 |
|
| ■ |
ウイルス除去のために衣類やタオルをまとめて洗濯機で洗う |
|
ウイルスで汚れてしまったものは、つい洗濯機で洗ってしまいたくなるはず。しかし、ノロウイルスは通常の洗剤では殺菌できないため、感染していない人のものまで汚染されてしまう可能性があるのです。洗濯機で洗う時は、ちょっと大変ですが、感染してしまった人の衣類やタオルは分けて、塩素系漂白剤で消毒してから洗濯するようにしましょう。 |
|
|
| 参考:乳酸菌で感染予防対策 |
| ■ |
乳酸菌飲料の軽減効果を確認 |
|
乳酸菌にはノロウイルスによる感染症胃腸炎の発熱を緩和する効果を確認したという研究結果が最近関心を集めているそうです。それによると、免疫力の弱い高齢者を対象に乳酸菌(ラクトバチルス
カゼイ シロタ株)を摂取してもらい、同ウイルスによる感染性胃腸炎の防御効果について調べたそうです。実験では被験者を2グループ(乳酸菌飲用と非飲用)に分けて長期間データを収集したところ、実験開始2か月後、施設内にてノロウイルス感染症胃腸炎が多くの被験者に発症した際にその発生率において両グループ間に大きな差は見られなかったものの、37℃以上の発熱日数について、乳酸菌飲用グループでは非飲用グループに比べて明らかな軽減がみられたそうです。ノロウイルスへの効果(乳酸菌飲用による発熱症状軽減)の確認は世界初だそうで、乳酸菌を継続的に摂取することで有用菌の増加並びに有害菌の減少など腸内環境の改善が認められたのだそうです。 |
|
| ■ |
免疫力を高め、感染を防ぐ効果も |
|
特効薬がないとされるノロウイルスですが、手洗いやうがい、調理器具の除菌など日常における予防対策はもちろん、継続的な乳酸菌飲料摂取など身体の中からの予防対策も推奨されます。そんな訳で、乳酸菌の日頃からの摂取は、低下したNK細胞(ナチュラルキラー細胞)の活性の再活性化を促す効果も認められており、抵抗力の低い高齢者の免疫力を高める対策として、また、感染症を防ぐ効果が期待されています。 |
|
| ■ |
母乳に含まれるラクトフェリンにノロウィルス抑制効果 |
|
最新の研究報告によると、なんと母乳に含まれるたんぱく質であるラクトフェリンにノロウイルスを抑制する働きがあるということが分かったそうです。ある研究によると、ラクトフェリン100mg配合のミルクやヨーグルトをほぼ毎日摂った人は、週1回の人のノロウイルス感染の割合が約7%だったのに対し、僅か0.6%にとどまっていたそうです。この冬、ノロウイルス対策として注目のラクトフェリン。ヨーグルトやサプリメントなど新たなアイテムも増えてきているので、予防によいかも知れません。 |
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|
| 【3】住まいにおけるノロウィルス対策 |
ノロウィルス対策には、掃除や消毒を含む住まいから見直す必要があります。
本節では住まいを中心としたノロウィルス対策を取り上げ解説しました。
|
| 住まいから始めるノロウィルス対策 |
| ■ |
ノロウィルス上陸前にしておきたい準備 |
|
- 容易に洗濯できない、クリーニング店などへの持込が必須の大型のラグやソファカバー、クッション等は取り外しておいた方が無難です。
インテリアや美観の点で抵抗を感じる方もいると思いますが、その上に嘔吐物を吐かれてしまうと難儀です。できれば感染シーズンが終わるまで撤去して保管するか、仮にその上で嘔吐された際に容易に洗濯のできる別の布カバーなどを施しておくことをオススメします。また、クリーニング店への持込の際には密封した上で、正直に申告して下さい。嘔吐物のノロウィルスは気温5度の環境で30日間生き続けるそうで、感染力を有しますので、クリーニング店の人をも感染させてしまう可能性があるからです。
- 次亜塩素酸ナトリウムの入った消毒剤(家庭用ではキッチンハイターなど)を準備しておきます。
- 使い捨てゴム手袋や大型ゴミ袋などを用意しておきます。
|
|
| ■ |
ノロウィルスに感染してしまったら |
|
ノロウィルスは主に経口感染します。ならばマスクで口を塞ぎ、手洗いを励行し、生の貝類の摂取を控えれば万事OKのように思われますが、どんなに気をつけていても、外食の際にノロウィルスに汚染された食べ物に当たってしまうこともあります。生野菜サラダやサンドウィッチなど加熱されずに供される食べ物には特に注意が必要です。また、公共スペースの絨毯やカーペットなどに付着したまま乾燥した嘔吐物を吸い込んでしまうことによる空気感染(塵埃感染)もあり、気が抜けません。
- 家族の誰かが感染してしまった場合
- 嘔吐物は密閉して廃棄すること
トイレで嘔吐・下痢した場合でも飛沫が床や壁やドアノブに付着している可能性があります。トイレ掃除に使用する雑巾などは再利用するものではなく、使い捨てのお掃除シートやウエスなどが適しています。これらも使用後、密閉して廃棄しますが、廃棄の際に次亜塩素酸ナトリウムをかけておくとより安心です。ただ、この掃除の際に注意しなければならないのが、通常の感覚であれば消毒用エタノールや逆性石鹸(病院などで殺菌消毒のために使われているような石鹸)を噴霧したり、これで手を消毒したりということが有効ですが、ノロウィルスに対しては殆ど効果が見られないということを認識しておかねばならないということです。消毒を意図するのであれば次亜塩素酸ナトリウム溶液を使用して下さい。もっとも床材や建具によっては腐食したり変色したりする恐れがあるので、よく考えて使用して下さい。
- 嘔吐物の付いたものを洗濯する場合には、予洗いの後次亜塩素酸ナトリウム溶液(塩素濃度約200~1000ppm)に漬け込んで消毒した後に洗濯すること。
- 洗濯物は部屋干しを避け、また屋外に干すよりも乾燥機を使い高温度で乾燥させること
- 乾燥機が無い場合には、乾燥後スチームアイロンをかけると安心
- 次亜塩素酸ナトリウムを使わない場合
- 85度以上の湯で1分間以上の熱水洗濯、後に乾燥機にて乾燥すること
- 洗濯できない、または取り外しの難しい畳の上やカーペット上に吐かれてしまった場合
- 手袋をして充分拭き取った後、乾燥してしまう前に熱湯をかけて1分以上放置し、その後に念入りに拭き取ること
- 熱湯をかけることも次亜塩素酸ナトリウム溶液をかけることも何らかの事情でできない場合
- 嘔吐物が乾燥した後にも飛び散らないよう、拭き取った場所の上にビニールシートなどをかけて密閉し、このままウィルスが死滅するまで1ヶ月以上保存すること
- 注意:
- ノロウィルスに感染した家族との手拭タオル等の共用は止めましょう。
- ノロウィルスに感染後、症状が治まっても、その糞便にウイルスは3日~1週間ほどもの間、排出され続ける点に注意して下さい。ノロウィルスに罹った家族のいる住まいのトイレ掃除、またノロウィルスに家族の誰かが罹患した住まいへの訪問(特にトイレの使用)の際には、充分な手洗いと清潔なタオルでの手拭きなどを心懸けて下さい。
|
|
|
| ノロウィルスの消毒法 |
| ノロウィルスの消毒について |
| ■ |
消毒について |
|
ノロウイルスに有効な消毒法は加熱による消毒と塩素系消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム)による消毒です。
- 加熱による消毒(85度以上で1分間以上の加熱。熱湯につけ込む等)
汚染された衣類、リネン類の消毒に用います。
- 塩素系消毒剤等(次亜塩素酸ナトリウム)による消毒
塩素濃度0.02~0.1%(200~1000ppm)の消毒液を用いて消毒しますが、消毒する対象によって塩素濃度が異なります。
- 0.02%=200ppm使用液の対象
- 蛇口やドアノブ、手すり、便座等他の人が触れる箇所などの環境消毒
- 調理器具&食器の消毒
- 汚物を洗い落とした後の衣類やリネン類など
- 0.1%=1000ppm使用液の対象
|
|
| ■ |
消毒における注意点 |
|
- 塩素系消毒剤等は時間が経つと効果が低下するため、なるべく最近購入したものを使います。また、消毒液は作りおきせず、その都度使い切って下さい。
- 汚物などの有機物が残っていると消毒効果が著しく低下します。
- 塩素系消毒剤等は金属を腐食させることがあるので、消毒後10分ほど経った後に水拭きします。
- 使用する際は換気を充分に行なって下さい。
- 塩素系消毒剤等は皮膚に対する刺激作用があるので、ビニール手袋などを使用しましょう。
- 手指や皮膚の消毒には使用しないで下さい。
|
|
|
| 消毒液の作り方 |
ノロウイルスの消毒に次亜塩素酸ナトリウムを使うとよいとされています。薬局などで売っていますが、家庭にある塩素系漂白剤でも簡単に作ることができます。
| ■ |
消毒液の作り方 |
|
- ノロウイルスの消毒液について~時間が経ったものは新しく作るようにしましょう~
ノロウイルスの消毒について次亜塩素酸ナトリウム(塩素濃度200ppm)を使うと言われています。薬局などでも売っていますが、家庭にある塩素系漂白剤でも簡単に作ることができます。
- 素系漂白剤で消毒液を作る
次亜塩素酸ナトリウム液は薬局はやインターネットで購入できますが、買いに行ったり取り寄せたりと時間がかかることがあります。もしも家庭に塩素系漂白剤があればそれを代用して作ることができます。
- 便や嘔吐物が付着した床や衣類、トイレなどの消毒をする場合
濃度 0.1%(1000ppm)の消毒液で消毒して下さい。まずは500mlの空のペットボトルを用意して、その中にペットボトルキャップ2杯の塩素系漂白剤を入れます。漏斗を使うとこぼさずに作れます。そして、その中に水を加えて全体を500mlにして出来上がりです。
- オモチャや調理器具、直接手で触れる部分などの消毒をする場合
濃度 0.02%(200ppm)の消毒液で消毒します。2Lの空のペットボトルを用意して、その中に上記と同じようにペットボトルキャップ2杯の塩素系漂白剤を入れ、そこに水を加えて全体量を2Lにして出来上がりです。
- 注意:
時間の経過と共に消毒薬の効果が減少しますので、なるべく1回ごとに作り直すようにして下さい。また、処理する時には必ず使い捨てのビニールの手袋や捨てられる雑巾やペーパーを使用しましょう。汚物等が飛び散らないようにメガネやゴーグル、マスクをつけることをオススメします。なお、拭いた雑巾やペーパーはゴミ袋の袋をよく閉じて捨てるようにして下さい。
|
|
|
| ノロウイルスの殺菌 |
ノロウイルスは漂白剤を使わなくても1分間以上の煮沸消毒で殺菌ができます。台所でよく使う布巾はなるべく普段から煮沸消毒することがよいとされます。また、黄ばみに対しては、塩素系漂白剤がなくても重曹を使ってもよいでしょう。目安として、水2Lに塩と重曹をそれぞれ大さじ3~4杯入れて布巾と一緒に煮沸し、暫くしてから洗って乾かします。重曹は薄めて絨毯などに吹きかけてもしみが落ちるようです。何れにせよ、キッチンは日頃から清潔にしておくよう心懸けたいものです。
|
|
| 参考:ノロウイルスと赤ちゃん |
| ノロウイルスと赤ちゃん |
ノロウイルスは少ないウイルス量でも感染しやすく、感染力が強いウイルスと言われています。赤ちゃんや幼児、お年寄りなどは成人と違って抵抗力が弱いためにノロウイルス感染しやすく、お世話をする方は充分に気をつけて下さい。また、赤ちゃんや幼児、お年寄りなどは自分で身を守ることができないため、ノロウイルスが直接原因でなく、嘔吐物を誤って喉などに詰まらせ、亡くなってしまうケースが多く発生していますので、その点にも注意して下さい。また、家族や周囲にノロウイルスの方がいる場合は、ノロウイルスに感染した人の嘔吐物や糞便などに注意し、処理するようにして下さい。ノロウイルスは二次感染が非常に多く、特に赤ちゃんは何でも舐めたり食べたりしますので、お母さんや世話をする人は、うがいと手洗いを小まめにし、家庭内を衛生的に保つよう心懸けましょう。
|
| 赤ちゃんがノロウイルスに罹ってしまったら |
赤ちゃんがノロウイルスに感染した場合のノロウイルスの症状は成人と同じですが、赤ちゃんや幼児は嘔吐の症状がきつく現われることが多いとされます。ノロウイルスの症状である嘔吐や下痢が続くと体力を消耗し、脱水症状を起こしやすくなるので、上手に水分補給してあげて下さい。また、水分だけでなく栄養との両面から補うことでノロウイルスから早く回復し、赤ちゃんも元気になります。
|
| ノロウイルスとオムツ |
ノロウイルスの特徴のひとつに、下痢の症状が治まっても、およそ一週間、長い場合では1ヶ月程度の間、便の中にノロウイルスが排泄されることです。そのことを踏まえ、赤ちゃんやお年寄りのオムツ交換や取扱には注意が必要です。
| ● |
ノロウイルスの感染を防ぐためのオムツ交換は、使い捨て手袋やエプロン、マスクをつけ、汚物は絶対に素手では触らないようにします。オムツ交換にはオムツ専用の敷物やマットなどを用い、汚れがひどい場合は処分します。また、オムツ交換の場所は子供の遊び場などではなく、一定の決めた場所で取り替え、周辺が汚れたら直ぐに掃除や消毒をします。 |
| ● |
オムツ交換が終わったら、取り除ける便はトイレに流し、速やかにビニール袋に入れて密封し、各自治体の廃棄方法に従って処分します。 |
| ● |
布オムツの場合は、取り除ける便はトイレに流し、洗剤を入れた水(できればお湯)で揉み洗いをし、オムツを洗った水はトイレに捨てます。その後、塩素系漂白剤(市販品はハイターなどの名称で販売されています)に浸け、他のものと別にお洗濯します。部屋干しせずに、消毒の意味もあるので天日に当てます。その後更にアイロンを当てると効果があります。なお、塩素系漂白剤の希釈や浸け置き時間は商品によって異なりますので取扱注意をよく読んで使用して下さい。 |
| ● |
使った手袋も速やかにビニール袋に入れ密封し、各自治体の廃棄方法に従い処分します。 |
| ● |
処理が終わったら、他の場所などに触れないようにし、直ぐに石鹸を用いて念入りに手洗いをします。 |
|
|
| 吸収のよい飲み物 |
| ■ |
ノロウイルスに罹ったら水分補給を |
|
ノロウイルスが原因で下痢や嘔吐が続く場合、脱水症状に気をつけなければいけません。通常は、脱水症状が悪化しないよう、医師の診断後、水分補給していれば、ノロウイルスは命にかかわるような病気ではありません。なお、吐き始めてから3~4時間くらいは水分でさえ受けつけませんので摂取には注意が必要です。 |
|
| ■ |
吸収のよい飲み物を |
|
家庭ではミネラルウォーターや湯冷まし、お茶などが一般的ですが、これらは電解質を含んでいないので吸収が遅く、そのため、たくさんの水分が必要になります。ノロウイルス対策で電解質を含んだ身近な飲み物と言うと、スポーツドリンクという名称で販売されているものが思い浮かびますが、これを人肌程度に温めて飲むと吸収がよいです。もっとも、スポーツドリンク等は甘みがあるため弱った胃腸には余りよくないという意見も一部にはあるようです。スポーツドリンクが家庭にない場合は0.9%の食塩水を作ることで代用でき、これなら甘みもないので心配は要りません。こちらも人肌程度に温めて飲みます。 |
|
| ■ |
参考:0.9%食塩水の作り方 |
|
水100mlに対して0.9gの食塩を加えたものが0.9%食塩水になります。500mlなら4.5g、1リットルなら9gで、その目安は、要するに料理で言うひとつまみです。なお、衛生面で考えて、やはり作り置きせず、そのつど作るのがよいでしょう。 |
|
|
| 参考:乳幼児嘔吐下痢症と薬 |
冬期から春先にかけて多発する「乳幼児嘔吐下痢症」は、その大半がウィルスを原因とする感染性胃腸炎であり、中でもノロウィルスとロタウィルスによるものが多くなっています。ノロウィルスは10月から1月に、ロタウィルスは1月から3月にかけて流行します。原因ウィルスの種類に関わらず、乳幼児下痢症の主な症状は下痢や悪心・嘔吐・発熱・腹痛であり、2~3日間の潜伏期間を経て発症します。また感染者は、発症後1週間程度に渡って糞便中にウィルスを排出し感染源となります。人から人への糞口感染が主要感染ルートですが、ウィルスで汚染された食品を介した非細菌性食中毒により集団発生することもあります。
発症初期は発熱と嘔吐の症状が見られ、その後、下痢症状が強くなることが多く、排便回数は1日10数回に及ぶこともあります。便の色は白色から黄白色が典型的ですが、緑白色や茶褐色の場合もあります。通常、嘔吐は3日ほど、下痢は7日ほどで自然治癒します。治療は、病原ウィルスに有効な薬剤が無いため対症療法が中心となりますが、下痢症状がある場合でも止瀉剤は原則として使用されません。下痢はウィルスを体外に排除するための生体防御反応であり、この反応を薬剤で抑制することで感染症の回復が遅れる可能性があるためです。ただし、下痢が長期間続いて体力が極度に消耗した場合などは一時的に止瀉剤を使用する場合もあります。何れにせよ自己判断で止瀉剤を服用せず、症状が改善しない場合は再度医師の診察を受けるべきでしょう。
ちなみに乳幼児嘔吐下痢症の場合、一般的に使用されるのが整腸剤と制吐剤の組み合わせです。整腸剤はウィルス感染によってバランスの崩れた腸内細菌叢を正常に戻すことを目的としています。しかし、吐き気が強い場合には、内服させても反射的に吐いてしまう場合も多く、そのような場合には、まずドンペリドン(商品名:ナウゼリン)などの制吐作用のある坐剤を使用し、嘔吐の症状が治まってから内服薬を飲ませることが必要になります。また、ナウゼリン坐剤を使用してから嘔吐に対する薬効が発現するまでの時間は、患者の病態、ウィルスの種類や数、精神的な要因などが関与するため一律には言えませんが、同剤は肛門内に挿入後約2時間で最高血中濃度に達する(成人でのデータ)ことから、挿入1~2時間後には吐き気が減弱している可能性が高いと考えられます。そのため、坐剤の使用後1~2時間を目安に内服薬を服用させるとよいでしょう。なおナウゼリンの場合、坐剤の最高血中濃度到達時間は2時間ですが、内服薬(ドライシロップ、錠剤)では約30分と比較的早くなっています。ナウゼリンを坐剤から内服薬に切り替える場合には、坐剤挿入後7時間(消失半減期)を過ぎてから内服を開始することが望ましいとされています。
| ◆ |
豆知識:子どの下痢について |
|
下痢は身体が原因となる細菌やウィルスを外に出すために行なっている「正常な」反応です。下痢止めを使って無理に下痢を止めてしまうと、細菌やウィルス、それらが出す毒素などが体内に長い間とどまってしまい、却って経過が長引いたり悪化したりします。特に子どもの場合、無闇に下痢止めを飲ませることはやめましょう。 |
|
|
|
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|
| 【4】家庭で出来る食中毒予防 |
|
| 二次感染を防ぐために |
| ■二次感染を防ぐための注意点 |
| 患者の下痢便や嘔吐物には大量のウイルスが含まれていますので、その処理には充分に注意する必要があります。 乾燥した嘔吐物や下痢便のかけらが風に乗って舞い上がり、そばを通った人が吸い込んだり、その人の身体に付着して、最終的に飲み込むことによって感染する場合があります。その上、下痢の症状がなくなった後も、患者の便には暫くウイルスの排出が続くと考えられるので、症状が治まっても安心は出来ません。汚物を処理する際には使い捨ての手袋を使用し、用便後や調理前の手洗いを徹底しましょう。なお、殺菌には熱湯ないしは0.05から0.1%の次亜塩素酸ナトリウムを使用します。そして、調理器具や衣類、タオル等は熱湯(85℃以上)で1分以上の加熱が有効です。また、市販の塩素系漂白剤(通常は5~10%次亜塩素酸ナトリウム)なら50~100倍に薄めて(※原液10ミリリットルを1リットルの水で薄めるなど)使用します。 |
|
| ■ |
有効な消毒の方法 |
|
- 85℃以上の熱湯で1分間以上加熱消毒する
- 塩素系漂白剤(※次亜塩素酸ナトリウム液)を適切に薄めた消毒液で消毒する
- 消毒用アルコールは余り効果はない
|
|
| ■ |
消毒が必要なところ |
|
- ドアノブや蛇口、手すり、子どものオモチャなど手の触れるところにウイルスが付着する可能性がある
- 感染した人の嘔吐物や便には1g中に100万個~10億個の多量のウイルスが含まれている。トイレや床など嘔吐物や便で汚染された箇所は徹底して消毒をすること
|
|
| ■ |
どうやって消毒するのか |
|
- 調理器具やオモチャなど:よく洗った後、消毒液に10分くらい漬けてから水洗いする
- ドアノブや蛇口、手すりなど:消毒液をよく染み込ませたペーパータオル等で拭いた後、10分くらいしてから水拭きする
|
|
| ■ |
お風呂に入る時に気をつけること |
|
- 下痢などの症状がある人は1番最後に入るか、シャワーのみにする
- 症状のある人が浴槽に入った後は、湯船等をよく洗い、消毒する
|
|
| ■ |
汚物の処理方法 |
|
- 患者の便や嘔吐物を処理する時は使い捨ての手袋とマスクを着用する
- 便や嘔吐物はペーパータオル等で取り除き、ビニール袋に入れる
- 残った便や嘔吐物の上にペーパータオルを被せ、その上から50~100倍に薄めた市販の塩素系漂白剤を充分浸るように注ぎ、汚染場所を広げないようにペーパータオルでよく拭く
- ウイルスは乾燥すると空気中に漂い、これが口に入って感染することがあるので、便や嘔吐物を乾燥させないことが重要
|
|
| ■調理と配膳に関する注意点 |
| 人によってはノロウィルスに感染しても発病せずに(※これを不顕性感染と呼びます)、ノロウイルスを便から排出し続けている場合があります。保護者などの大人の方が知らないうちに子どもにノロウイルスを感染させてしまう可能性も決して低くありません。そのため、家庭では以下の注意点を守るように心懸けましょう。 |
|
| ● |
調理の前と後で流水や石鹸(※液体石けんが推奨されます)による手洗いをしっかりと行なうこと |
| ● |
貝類をその内臓を含んだままで加熱調理する際には充分に加熱して調理し、貝類を調理した俎板や包丁は直ぐに熱湯消毒すること |
| ● |
食事を配膳する際にも手洗いをすることが推奨される。特に自分が下痢や吐き気がある場合は必ず行なうこと |
|
| ■家庭における注意点 |
| 学校や職場、施設内でノロウイルス感染による嘔吐や下痢が発生しても、その最初の発端は家庭内での感染による場合が多いと言われます。特に子どもや高齢者は健康な成人よりもずっとノロウイルスに感染し発病しやすいですから、家庭内での注意が肝要です。 |
|
| ● |
何度も言うように、最も重要な予防方法は手洗いです。帰宅時や食事前には、家族の方々全員が流水や石鹸による手洗いを行なうように心懸けること |
| ● |
貝類の内臓を含んだ生食は時にノロウイルス感染の原因となることを知っておくこと。特に高齢者や乳幼児は避ける方が無難 |
| ● |
調理や配膳は充分に流水及び石鹸で手を洗ってから行なうこと |
| ● |
衣服や物品、嘔吐物を洗い流した場所の消毒は,次亜塩素酸系消毒剤(※濃度は200ppm以上、家庭用漂白剤の場合は約200倍程度に薄める)を使用する。(※なお、次亜塩素酸系消毒剤を使って手や指など身体の消毒をすることは絶対に止めるようにしてて下さい。) |
|
|
| 適切な手洗い&うがいの方法 |
手洗い及びうがいは様々な感染症の予防の基本です。日常の健康管理はもちろん、感染症の予防のためにも、日頃から手洗いとうがいの励行をオススメします。
| ■手洗いの方法 |
| 外で様々なものに触れることを通して、手は想像以上に細菌等に汚染されています。手を洗うことで、知らないうちに手に付着した細菌等を洗い流してしまうことは、非常に効果的な感染症の予防方法です。 |
|
|
- 手を水で濡らし、石鹸を泡立てる。また、固形石鹸の場合は水で濯いで元に戻しておく
- 手の甲、そして手の平から親指、指の付け根、指と指の間を丁寧に洗ってゆく
- 爪の隙間を注意して洗う。このとき歯ブラシなどを使って洗うと効果的
- さらに10~15秒以上揉み洗いをする。この作業が手についた細菌等を洗い流すのに効果的
- 清潔なタオルで手を拭き乾かす
|
|
|
|
| ■うがいの方法 |
| 喉も手と同じように外の空気に直接さらされる部分です。喉は細菌等を身体の中に進入させない働きを持っているのですが、そのため喉には驚くほどの細菌等が付着しています。従って細菌等を取り除くためには、適切な方法によるうがいが必要です。 |
|
|
- うがいがしやすい量(20ml)の水ないしはうがい薬を希釈したもの、またはお茶(お茶には殺菌作用があるので意外と効果的)などをコップに取る
- まず残った食べ物などを取り除く目的で、口に1)で用意した水を含んで強くうがいする
- 次に、上を向いて喉の奥まで液が回るように15秒程うがいする
- (3)と同様に15秒程度のうがいを何度か繰り返す
|
|
|
|
| ■手洗いの方法 |
| ● |
調理の前 |
| ● |
生の肉や魚、卵に触った後 |
| ● |
盛付けの前 |
| ● |
食事の前 |
| ● |
トイレやオムツ交換の後 |
| ● |
動物に触った後 |
|
|
|
| 家庭で出来る食中毒予防のポイント |
| ■食中毒予防の3原則 |
 |
食中毒の大部分は細菌によるものです。
食中毒を予防するためには次のことを守ることが大切です。 |
|
| ■ |
細菌をつけない~洗う・分ける・包む |
|
食中毒菌が手や調理器具を介して食品に付着し、増えることで食中毒を起こすことがあります。
やはり、基本は手洗いです。自らが細菌の運び屋にならないように、こまめに手を洗いましょう。もちろん調理器具もしっかりと洗いましょう。さらに包丁・マナ板は肉用・魚用・野菜用に分けて使うとより効果的です。また、肉や魚などを保存する時は、他の食品に肉汁がかからないよう袋や容器に小分けしてしまいましょう。 |
|
| ■ |
細菌を増やさない~冷凍・冷蔵・室温で長く放置しない |
|
一般に食中毒菌は室温状態(10℃~40℃)の時に急速に増殖します(※腸炎ビブリオは8~10分で2倍に増えます)。従って、冷凍食品の解凍を室温で行なうことは禁物です。中心部が解凍されるまでの時間に表面温度は室温と同じ状態が続くので、細菌を増やすことになります。従って、冷凍された食品の解凍は、冷蔵庫内で行うか、電子レンジを使いましょう。
なお、冷蔵庫で保存しなければならない食品を買った場合は、寄り道せずに、帰ったら直ぐ冷蔵庫に入れましょう。また、冷蔵庫や冷凍庫の詰めすぎにも注意しましょう。そして、作った料理は早めに食べるように心懸けましょう。 |
|
| ■ |
>細菌をやっつける~中心まで加熱・調理器具の殺菌 |
|
加熱して調理する食品は、中心部が85℃以上で1分以上充分に加熱しましょう。また、残った食品を温め直す時も充分に加熱します。さらに、調理器具は漂白剤や熱湯などで定期的に消毒するとよいでしょう。
※注意:ただし、加熱できる食品は限られています。また、食中毒菌が作り出す毒素の中には熱に強いもの(黄色ブドウ球菌が作り出すエンテロトキシンなど)もあるため、加熱したから大丈夫という過信は禁物です。 |
|
| ■家庭で出来る食中毒予防の6つのポイント |
家庭での食事が原因の食中毒も数多く発生しています。もっとも、一般に食中毒と言うと、レストランや旅館などの飲食店での食事が原因と思われがちです。しかし、いささか旧聞に属しますが、学校給食等が原因となって過去に例を見ない規模の腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒が多発した1996年の事件にも見られるように、毎日のように食べている学校の給食や家庭の食事でも食中毒が発生する危険性はたくさん潜んでいます。実際、食中毒は家庭でも発生しているのです。ただ家庭での食中毒の発生の場合は、症状が軽かったり発症する人が1人や2人のことが多いことから風邪や寝冷えなどと思われがちで、食中毒とは気づかれずに重症になったり、場合によっては死亡する例もあるので、こちらも充分な注意が必要です。
食中毒予防のポイントは以下で挙げる6つです。そして、食中毒予防の3原則は、食中毒菌を「付けない・増やさない・殺す」です。「6つのポイント」はこの3原則から成っています。これらのポイントをきちんと守ることで家庭での食中毒をなくしましょう。簡単な予防方法をきちんと守れば食中毒は必ず予防できます。 |
|
| ■1: |
食品の購入をする時 |
|
消費期限などをよく確認して購入し、温度管理が必要なものは早く持ち帰ることが大事です。 |
|
| ■2: |
食品を保存する時 |
|
冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫はマイナス15℃以下で保存し、詰めすぎないように注意しましょう。 |
|
| ■3: |
下準備の時 |
|
生の肉や魚・卵を取り扱った後は必ず手洗いをし、包丁やマナ板・フキンなどの台所用品は使った後で直ぐに洗剤と流水でよく洗うことを心懸けましょう。 |
|
| ■4: |
調理の時 |
|
調理の前は必ず手洗いをして、食品を冷蔵庫から出したら早く調理し、加熱調理する場合は中心までしっかり火を通すように心懸けましょう。 |
|
| ■5: |
食事の時 |
|
調理した食品は室温で長く置かないで、早めに食べるように心懸けましょう。 |
|
| ■6: |
食品が残った時 |
|
残った食品は、速く冷えるように容器に小分けをして冷蔵庫で保存します。食べる時は再加熱をし、怪しいなと思ったら思い切って捨てるように心懸けましょう。 |
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|