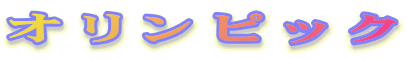| 【1】オリンピックとは?〜オリンピック精神とその課題〜 |
オリンピックとは何か。近代オリンピックの精神と現状について簡単に解説しました。
|
| オリンピックの精神 |
| ■ |
オリンピックとは |
|
オリンピックは4年に1度開催される世界的なスポーツの祭典です。スポーツを通した人間育成と世界平和を究極の目的とし、夏季大会と冬季大会を行なっています。2012年にはロンドンで記念すべき第30回オリンピック競技大会が開催され、世界204の国・地域から選手が参加し26競技302種目が実施されました。
クーベルタンが唱えたオリンピズム、すなわちオリンピックの精神とは、「スポーツを 通して心身を向上させ、文化・国籍など様々な違いを乗り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって平和でよりよい世界の実現に貢献すること」です。この理想は今も変わらず受け継がれ、彼は「近代オリンピックの父」と呼ばれています。近年では従来のテーマであるスポーツと文化に環境が加わり、オリンピックは世界中の人々が地球環境について考える機会にもなりました。アスリート達が生み出す興奮と感動、そして環境保護への取り組みが、きっと世界中の人をより強く固く結んでゆくことでしょう。 通して心身を向上させ、文化・国籍など様々な違いを乗り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって平和でよりよい世界の実現に貢献すること」です。この理想は今も変わらず受け継がれ、彼は「近代オリンピックの父」と呼ばれています。近年では従来のテーマであるスポーツと文化に環境が加わり、オリンピックは世界中の人々が地球環境について考える機会にもなりました。アスリート達が生み出す興奮と感動、そして環境保護への取り組みが、きっと世界中の人をより強く固く結んでゆくことでしょう。 |
|
| ■ |
オリンピックの精神 |
|
第4回ロンドンオリンピック(1908)の陸上競技では、アメリカとイギリスとの対立が絶え間なく起こり、両国民の感情のもつれは収拾できないほどに悪化していました。その時に行なわれた教会のミサで、《このオリンピックで重要なことは、勝利することより、むしろ参加することであろう》というメッセージが語られました。このメッセージを当時のIOC会長のクーベルタンが取り上げ、《勝つことではなく、参加することに意義があるとは至言である。人生において重要なことは、成功することではなく、努力することである。根本的なことは、征服したかどうかにあるのではなく、よく戦ったかどうかにある》と、このように述べたそうです。
オリンピックには、もちろん《より速く、より高く、より強く》という言葉もありますから、《参加することに意義がある》という言葉は、弱くてもよい、負けてもよいという意味では決してありません。ただし、ドーピングをしようが何をしようが、とにかくどんな手段を用いても、ただ勝てばよいのだということでもありません。オリンピックに限らず、スポーツマンシップとは、その競技会に参加し、ひたすら純粋に勝つために正しく努力することにこそ意義があるということです。 |
|
|
| オリンピックムーブメント |
オリンピック・ムーブメントとは、国際オリンピック委員会(IOC)の統括の下、オリンピックの精神(オリンピズム)に従って、スポーツ通じて平和でよりよい世界の実現を目指す活動です。この活動は世界中で行なわれており、オリンピックの五輪のマークがそのシンボルとされています。IOCは《オリンピック憲章に従い、オリンピズム(オリンピックの精神)を普及させる》という大切な役割を担っています。IOCは205の国と地域を承認しており、夏季及び冬季のオリンピック競技大会を主催しています。
| ■ |
主要な機関 |
|
オリンピック・ムーブメントは様々な個人・団体によって進められています。国内オリンピック委員会(NOC)と国際競技連盟(IF)もそのひとつです。NOCはオリンピック競技大会時に選手団を派遣する母体となります。日本では日本オリンピック委員会(JOC)がこれに当たります。もう一方のIFは各競技を統括する国際団体で、オリンピック競技では各競技の運営に関して全ての権限を保有しています。また、国際オリンピック・アカデミー(IOA)と国内オリンピックアカデミー(NOA)では、それぞれオリンピズムに沿った教育と普及活動が展開されています。 |
|
| ■ |
オリンピック・ムーブメントの活動 |
|
オリンピック・ムーブメントの代表的な活動として、ドーピングの撲滅や女性の参画、経済支援などが挙げられます。筋肉増強剤などの禁止薬物を使用し、競技力の向上を図るドーピングは不正行為であるだけでなく、身体への影響も大きいため、IOCが中心となって1999年に世界アンチドーピング機構を設立し、撲滅運動を推進しています。たとえばオリンピックについて、古代から第1回アテネ大会まで女性の参加は認められていませんでしたが、IOCの女性達、ワーキンググループによる長年の活動によって、今では多くの女性が参加できるようになりました。また、ソリダリティと呼ばれる経済支援は、経済的に恵まれない国及び地域の選手やコーチに対してIOCなどが中心となって資金提供を行なうもので、奨学金制度やスポーツ施設を整備することによって国及び地域の区別なく専門知識を伸ばし、技術水準を向上できるようサポートしています。さらに身体障害者を対象とした世界最高峰のスポーツ競技大会であるパラリンピックもオリンピック・ムーブメントのひとつで、オリンピックの直後に同じ場所で開催され、競技レベルも急激に上昇しています。このようにオリンピック・ムーブメントとよばれる活動は様々な組織や人々によって日夜続けられているのです。 |
|
|
| オリンピックとその課題 |
| ■ |
オリンピックと政治 |
|
オリンピックが世界的大イベントに成長するに従って、オリンピックは政治に左右されるようになってゆきました。たとえば1968年のメキシコ大会ではオリンピックは黒人差別を訴える場と化し、1972年のミュンヘン大会ではアラブのゲリラによるイスラエル選手に対するテロ事件まで起きてしまいました(ミュンヘンオリンピック事件)。また、1976年のモントリオール大会になると、ニュージーランドのラグビーチームの南アフリカ遠征に反対してアフリカ諸国22ヶ国がボイコットを行なう事態を招きました。そして1980年のモスクワ大会では、ソ連のアフガニスタン侵攻に反発したアメリカ・西ドイツ・日本などの西側諸国が相次いでボイコットを行ない、それに対して1984年ロサンゼルス大会では、今度は東ヨーロッパ諸国が報復ボイコットを行ない、参加したのはルーマニアだけという有様でした。 |
|
| ■ |
商業主義とプロ化〜大会の継続的運営と商業主義〜 |
|
オリンピックは巨大化するに従って財政負担の増大が大きな問題となり、1976年の夏季大会では大幅な赤字を出し、その後、夏季・冬季とも立候補都市が1〜2都市だけという状態が続きました。それに対して1984年のロサンゼルス大会は画期的な大会で、オリンピックをショービジネス化したとされます。すなわち、大会の大規模化と共に開催に伴う開催都市と地元政府の経済的負担が問題となっていたわけですが、ピーター・ユベロスが組織委員長を務めた1984年のロサンゼルス大会では商業活動と民間の寄付を本格的に導入することによって地元の財政的負担を軽減し、オリンピック大会の開催を継続することが可能になりました。その結果2億1500万ドルもの黒字を計上しました。それを契機として、アディダスや電通などを始めとした企業から一大ビジネスチャンスとして注目されるようになったのです。すなわち、スポンサーを一業種一社に絞ることによりスポンサー料を吊り上げ、聖火リレー走者からも参加費を徴収することなどにより黒字化を達成したのです。その後「オリンピックは儲かる」との認識が広まって立候補都市が激増、各国のオリンピック委員会とスポーツ業界の競技レベル・政治力・経済力などが問われる総力戦の様相を呈するようになりました。そのため、誘致運動だけですら途方もない金銭が投入される様になってゆくのです。そして、その流れはプロ選手の参加を促し、1992年のバルセロナ大会ではバスケットボール種目でアメリカのNBA所属の選手によるドリームチームが結成され、大きな話題となりました。元々オリンピックは発足当初からアマ選手のみに参加資格を限って来ましたが、旧共産圏(ソビエト連邦やキューバなど)のステートアマ問題などもあり、1974年にオーストリア首都ウィーンで開催された第75回IOC総会でオリンピック憲章からアマチュア条項を削除することになりました。さらに観客や視聴者の期待にも応える形でプロ選手の参加が段階的に解禁されるようになってゆきました。当初はテニスなど限られてましたが、後にバスケットボール、サッカー、野球などに拡大されてゆきます。なお、現在のIOCの収入構造は、47%が世界各国での放送権料で、45%がTOPスポンサーからの協賛金、5%が入場料収入、3%が五輪マークなどのライセンス収入となっており、このうち90%を大会組織委員会と各国五輪委員会、各競技団体に配布する形で大会の継続的運用を確保しています。
1989年12月のマルタ会談をもって冷戦が終結してからオリンピックの政治的な色合いは薄くなってステート・アマも殆どがその姿を消しましたが、しかしその反面、ドーピングの問題や過度の招致合戦によるIOC委員に対する接待や賄賂など、オリンピックに内外で不正に関与する人物及び組織の倫理面にまつわる問題が度々表面化するようになってゆきました。また、1984年ロサンゼルス大会の後、フアン・アントニオ・サマランチ主導で商業主義(利権の生成、放映権と提供料の高額化)が加速したと言われ、また、かつて誘致活動としてIOC委員へ賄賂が提供されたことなどが問題になりました。さらには年々巨大化する大会で開催費用負担が増額する傾向がありましたが、ジャック・ロゲの代になり、これまで増え続けていた競技種目を減らし、大会規模を維持することで一定の理解を得るようになりました。 |
|
| ◆参考図書1 |
 |
| ■ |
小川勝・著 |
|
『オリンピックと商業主義』 |
|
集英社新書0645、集英社・2012年06月刊、777円 |
|
オリンピックをテレビ観戦していると、他のスポーツイベントとは「風景」が違うことに気づく。それは「会場に広告看板がない」からだ。クーベルタンが理想を掲げて創始した近代オリンピックの「格式」は、そのような形で今も守られている。だが舞台裏では、莫大な放映権料やスポンサー料がIOCの懐を潤し、競技自体にまで影響を及ぼすという実態がある。一方で、その資金のおかげで税金の投入が回避され、途上国の選手が参加できるという現実もある。果たして、オリンピックが「商業主義」を実践するのは是なのか非なのか。本書は、五輪礼賛でも金権批判でもないスタンスで、この問題を深く掘り下げる。 |
|
|
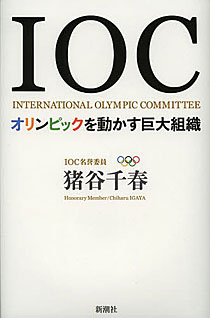 |
| ■ |
猪谷千春・著 |
|
『IOC オリンピックを動かす巨大組織』 |
|
新潮社・2013年02月刊、1,470円 |
|
五輪開催地はいかに決まるのか?東京招致の鍵は?世界最大の祭典を操る組織の全貌を、30年にわたり委員を務めた著者が明かす。 |
|
|
|
|
|
|
| 応援しよう!ソチ・オリンピック |
2014年2月6日(土)〜23日(日)の会期で、“Hot. Cool. Yours.”(ホット、クール、みんなの大会)のテーマの下に、第22回冬季オリンピックがロシアのソチで開催されます。なお、パラリンピックは、3月7日(金)から16日(日)までの会期で同地にて開催の予定です。
アスリート達の熱い戦いが始まります。さあ、みんなで選手達の活躍を応援しましょう。 |
 |
|
|
|
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|
| 【2】オリンピックの歴史〜古代オリンピックと近代オリンピック〜 |
古代ギリシア・ローマ世界で行なわれた古代オリンピックとその精神を現代に復活させた近代オリンピック。本節では、その両者のオリンピックの歴史を振り返ってみました。
|
| 古代オリンピックとその歴史 |
オリンピックの歴史は今から約2300年前に遡ります。古代ギリシャのオリンピア地方で行なわれていたオリンピア祭典競技がそれです。起源には諸説ありますが、元々は神々を崇める体育や芸術の競技祭だったとされています。しかし、その後数々の戦乱に巻き込まれた古代オリンピックは393年を最後に幕を閉じてしまいました。
本節では古代オリンピックの由来とその変遷を簡単に追いました。
| 古代オリンピックの誕生〜その由来と神話〜 |
古代オリンピックは神々を信仰するひとつの形としての体育や芸術の競技祭でした。このような競技祭には他にもコリントのイストミアン・ゲームズやネメアのネメアン・ゲームズ、デルフォイのピシアン・ゲームズなどがあり、オリンピアのオリンピア・ゲームズと合わせて4大祭典競技として知られています。オリンピア・ゲームズは競技の保護者が強力であり、また、資料が多く残っていることから後世有名になりましたが、当時はどの競技大祭も同等でした。
| ■ |
古代オリンピックの由来と神 |
|
ギリシア神話に残る祭の起源には諸説あって、ホメロスによれば、トロイア戦争で死んだパトロクロスの死を悼むためアキレウスが競技会を行なったというもので、これがオリュンピア祭の由来であるとする説があります。別の説によれば、約束を破ったアウゲイアース王を攻めたヘラクレスが、勝利後ゼウス神殿を建て、ここで4年に1度競技会を行なったとされます。また別の説によれば、エリス王オイノマオスとの戦車競走で細工をして王の馬車を転倒させて王を殺し、その娘ヒッポダメイアと結婚したペロプスが企てに協力した御者のミュルティロスが邪魔になったので殺し、その後願いが叶ったことを感謝するためにゼウス神殿を建てて競技会を開いたが、ペロプスの没後も競技会は続き、これが始まりだとするものです。どうやら最後の神話が由来としては有力視されているようですが、何れにせよ、神話に残る競技会は何らかの事情で断絶し、有史以後の祭典とは連続性を持ちません。なお、これらの伝承のうちの幾つかは、エリス市民らがオリンピックの由来を権威付けるために後に創作したものも含むと考えられているそうです。 |
|
| ■ |
古代オリンピックの誕生 |
|
古代オリンピックの起こりは古代ギリシャ人が残した伝説の中に書き残されていますが、歴史家たちはその発祥を前9世紀頃としています。戦乱から国民を救おうとしたエリスは神託を受けて、各ポリスへと赴いてオリンピックの開催を促したことがきっかけになったとされます。こうして、紀元前776年最初のオリンピック競技大祭が行なわれ、ギリシャ全土が競技を承認しました。ただし、競技の勝利者には月桂樹の冠が与えられ、アルフェイオス川にある柱に名が刻まれるだけだったそうです。 |
|
| ■ |
聖なる休戦 |
|
古代オリンピックは、使者が各地を回り開催を知らせ、戦争を中断させる役目を持っていました。そのため、古代オリンピックは「聖なる休戦」と呼ばれ、1169年もの間に僅か一度の例外を除いてこの決まりが守られました。期間は初めのうちは1ヶ月間だったものが、後に3ヶ月間まで延びています。 |
|
| ■ |
古代オリンピックと暦 |
|
オンピックが4年に1回開催されるようになったのは暦と関係があります。古代のギリシャは太陰暦を使っていましたが、これは太陽暦と8年間に3ヶ月のズレを生むた、え、そこでそのつど閏月を設けたものの、8年は長いのでその半分を区切れ目としたということです。 |
|
|
| 古代オリンピックの歴史 |
| ■ |
初期の古代オリンピック |
|
古代ギリシアにおいて信じられた直接の起源は次のようなものです。伝染病の蔓延に困ったエリス王イピトスがアポロン神殿でお伺いを立ててみたところ、争いを止め、競技会を復活せよという啓示を得ました。イピトスはこの通り競技会を復活させることにし、仲の悪かったスパルタ王リュクルゴスと協定を結びました。それは、オリュンピアの地に武力を使って入る者は神に背く者であるというもので、この文字が彫られた金属製の円盤がヘラの神殿に捧げられました(ただし、協定を結んだとされるリュクルゴス王が実在したかどうか不明のため、この由来には疑問視する声もあります)。勝者はエリスのコロイボスでした。こうしてエリス領地内のオリュンピアで始まったオリンピックですが、最初のうちの記録は残っていません。記録に残る最初のオリュンピア祭は紀元前776年に行なわれたもので、古代オリンピックの回数を数える時にはこの大会をもって第1回と数えるのが習わしになっています。ただし、先の円盤の作成年代などから推測して、この古代オリンピックの開始年はもう少し遡ると考えられています。また、競技会の行なわれた季節は麦の刈り入れが終わり、農民が若干暇になるユリウス暦の8月だったと考えられています。
最初はエリスとスパルタの2国のみの参加だったオリュンピア大祭は、正確に4年に1度開催され続け、次第に参加国も増えてきます。そして、ついに全ギリシア諸国が参加するようになったのです。そして、この大会はギリシア共通で使われる暦の単位にもなり、オリュンピアードという単位がそれで、これはあるオリュンピア大祭が開催されてから次の大祭が開催されるまでの4年間を示し、年を特定するためには「第○○オリュンピアードの第n年」と数えます。 |
|
| ■ |
中期の古代オリンピック |
|
オリュンピア大祭はエリス州のゼウスの神殿が建てられたオリュンピアの聖域にある競技場(スタディオン等)で開催されました。開催1か月前には開催を告げる使者がギリシア全体を回り、大会開催中の1か月の間は休戦となりました。後に参加都市国家が増えると、休戦期間はオリンピック開催時を含め前後に合計3か月伸びました。この休戦期間をエケテイリアと言いますが、この休戦はオリュンピアに向かう競技者や観客の旅の安全を保障するためでした。また、ゼウスは旅行者の守護神で、オリュンピア祭への旅の道はとりわけゼウスによって加護されると考えられました。そして、この禁を破った国はオリュンピア祭への参加が拒否された他、他国から外交関係を絶たれることにもなったのです。事実スパルタはこの禁を犯してエケテイリアの時期に他国を攻めたため、オリュンピア大祭に参加できなかったことがあります。この他、オリュンピアをピサに征服されたエリスがオリュンピア大祭開催中にオリュンピアに攻め込んだこともあります。
大祭は、初期にはスタディオン走のみで1日で終了しました。その後次第に競技種目が増え、紀元前472年には5日間の大競技会となりました。参加資格があるのは健康で成年のギリシア人の自由人男子のみで、女や子供、奴隷は参加できませんでした。全裸で競技が行なわれたのは不正を防ぐためでした。勝者には勝利の枝と勝利を示すリボンのタイニアが両腕に巻かれ、ゼウス神官よりオリーブの冠が授与され自身の像を神域に残す事が許されました。オリーブの冠を授かった者は神と同席することを許された(競技会後オリュンピアの神殿敷地内に優勝者の像が造られることに由来します)者として故郷で盛大に迎えられました。祖国の神殿に像が作られた競技者もいるし、税が免除されることもあったそうです。何れにしても祖国の歴史にながく名が刻まれることになったのです。競技会は大神ゼウスに捧げられる最大の祭典でもあり、祭りであるので殺し合いは固く禁じられました。従って、格闘技で相手を殺した勝者にはオリーブの冠は贈られませんでしたが、逆に勝者であれば死者であっても冠が贈られました。実際、パンクラティオンで相手が降参するのと同時に倒れて死んだ勝者に対して審判が冠を授けたと言います。審判は極めて初期はエーリス王が当たりましたが、競技の数が多くなるとエリス市民から籤で審判が選ばれました。また選ばれた審判達は、オリンピック期間中、神官として扱われました。審判はエリスに設けられた専門の施設で競技規則について10か月に渡り専門家から教えを受けましたが、その間に続々と各国から選手が集まり、1か月前になると、選手と共に合宿練習をして、練習試合の間にまた規則の確認を行ないました。また、予選もここで行なわれました。
大会直前になると、エリスからオリュンピアまで全選手及び役員が行進しましたが、その距離は50キロ以上になりました。競技会初日は開会式兼儀式が行なわれ、最終日は勝者のための宴がまる1日かけて催され、競技は間の3日間で行なわれました。競技は第1回からの伝統である192メートル(1スタディオン)のスタディオン走の他、ディアウロス走(中距離走)、ドリコス走(長距離走)、五種競技、円盤投、やり投、レスリング、ボクシング(拳闘)、パンクラティオン、戦車競走などがありました。少年競技の部もありましたが、種目は多くありませんでした。なお、戦車競走では、勝者への冠は御者ではなく馬車の所有者に与えられたため、女性でオリーブの冠を授かった者が2名います。また、体育の他、詩の競演なども行なわれました。そして、最終種目は武装競走で、盾を手に1スタディオンを走って往復するものでした。なお、女性の参加と観戦に関しては研究者の間で意見が分かれていて、そもそも競技大祭中はオリュンピアには女は入れなかったという説、神殿と競技場には入れずに外でテントを張って待っていたという説、競技場内でもフィールドに立ちさえしなければ実質的には咎めはなかったという説、未婚女性に限り競技場観客席での観戦が許されたという説があります。ただ、少なくともエーリスの女神官が観戦していたことだけは確からしい。女人禁制の掟を破った者は崖から突き落とされる(実質的には死刑)というルールでありましたが、記録に残る限り適用例はなく、象徴的なルールであったとも考えられています。 |
|
| ■ |
末期の古代オリンピック |
|
祖国でのオリンピック優勝者への過剰な褒章が逆に大祭の腐敗を生むことになりました。祖国が優勝者に支払う報奨金は跳ね上がり、褒章欲しさに不正を働く者、審判を買収する者が出て、オリュンピア大祭は腐敗していったのです。そのため、買収を行なった者とそれに応じた者は以後の大祭から追放されるだけでなく、多額の罰金が科せられました。この罰金を元に、オリュンピアにザーネスと呼ばれる不正を象徴する見せしめのゼウス像が作られましたが、そのゼウス像の数は増える一方で、記録によれば最終的には11体までザーネスが建てられたとされ、今日のオリュンピアに残されているのはその基部のみとなっています。
なお、ローマは途中からギリシア都市国家に混じって参加を許されたが、ローマは後にギリシア全土を征服し、その属州に編入しました。そのローマによる征服後もオリュンピア祭は続けられたのですが、暴君として知られるローマ皇帝ネロは、自分が出場して勝者となるために第211回オリュンピア競技会の日程を本来行なうべき65年から無理やり67年にずらしたのみならず、たとえ競技に敗れても優勝扱いになってさえいます。また、彼は自分の歌を披露するため音楽競技を追加しました。こうした不正のお陰でネロは7種目で優勝したとされますが、その競技内容は悲惨で、特に音楽競技は聴くに堪えない劣悪なものだったと言います。もちろんこのようなネロの権力の濫用と不正に対する批判は強く、この祭時を変えさせてまで開催を強行した大祭は後に正式な大祭とされず、ネロの死後公式記録から抹消されてしまいました。しかし、変更された祭時は戻される事なくそのままで、最後の第293回大祭までこれは変わっていません。ただし、ネロの死後この大会の存在そのものがエリスの公式記録から抹殺されたため、この大会をオリュンピア大会と認めない研究者もいます。
最末期、キリスト教が広まるにつれ、異教ローマ神の祭典であるオリュンピアは次第に廃れてゆきました。313年にローマはキリスト教を正式に認め、392年にキリスト教を国教としましたが、この時キリスト教以外の宗教は禁じられたことによりオリュンピア大祭も禁じられることになりました。最後の第293回オリュンピア祭は翌393年に開催され、これが古代オリンピック最後の年となりました。この後ローマの異教神殿破壊令によりオリュンピアは神域を破壊され、その長い歴史の幕を閉じたのです。ただし、この最後のオリンピックについては残念ながら記録が残っていいません。記録に残る最後の古代オリンピックは369年の第287回オリンピュア祭で、それも拳闘の勝者のみが記録されています。このためこの回を最終回とする研究者もいます。しかし、その後1990年代になってから、オリュンピアで末期の361年の第285回オリュンピア祭までの全競技の勝者を記録した青銅板が発掘されました。それまでは、末期、キリスト教が広まってからのオリュンピアはエリスとその近隣諸都市だけで細々と行なわれていたと考えられていたのですが、青銅板の最後の記録、361年までは、広くギリシア語圏内から競技者が参加していたことが判明しました。この青銅板が後世の偽作であると疑う意見もありますが、確たる証拠はなく、ひとまずこれが末期古代オリンピックに関する主流の見方になっています。 |
|
| ◆参考図書2 |
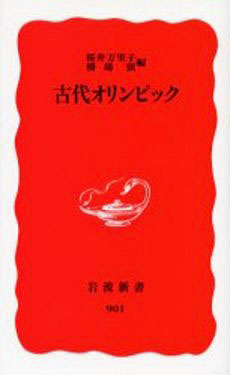 |
| ■ |
桜井万里子+橋場弦・編 |
|
『古代オリンピック』 |
|
岩波新書・新赤版901、岩波書店・2004年07月刊、798円 |
|
裸の走者が駆け、戦車が競技場を揺るがす。熱狂する観客、勝利者の頭上の聖なるオリーヴの冠?紀元前八世紀のギリシアから古代ローマ時代に至るまで、実に千二百年近くの命脈を保った古代オリンピック競技会を、最新の考古学・歴史学の成果を踏まえて語る。競技の詳細、会期中の休戦、優勝者の得る利益についてなど、興味深い話題は尽きない。 |
|
|
|
|
|
| 近代オリンピックへの道〜近代オリンピックとその歴史〜 |
古代オリンピックから1500年後、フランスの教育者であったピエール・ド・クーベルタン男爵の働きかけによってオリンピックは復活の道を歩み始めます。1894年、彼がパリ国際会議において提唱した「オリンピック復興」は満場一致で可決され、2年後の1896年、ギリシャのアテネで記念すべき第1回オリンピック競技大会が開催されました。大会のシンボルとして馴染み深い五輪のマークも実は彼が考案したもので、世界五大陸の団結を表しています。
| ■ |
近代オリンピックへの胎動 |
|
393年に最後の古代オリンピックが行なわれてから時は流れ、ギリシャのペロポネソス半島に埋まったオリンピアの遺跡と共に、崇高なる精神と強靭な肉体を作るスポーツの祭典はいつしか忘れられてゆきました。それが、11世紀に入ると、キリスト教中心の世界観が漸く崩れ、市民の権利が伸張してゆきましたが、そうした社会情勢の変化の中でイタリアのフィレンツェを中心にルネッサンス運動が進展し、古代オリンピックについての文献も読まれ研究されるようになりました。ルネッサンスの影響はイギリスにまで波及し、一般のイギリス人の間にも古代オリンピック大会に興味を持つ人が出現してきました。1812年には、ロバート・ドーバーが、競技自体はお遊戯同然ではあったものの、コッツワルド・オリンピック大会という運動会を、1850年にはウィリアム・ブルック博士がマッチ・ウェンロック・オリンピック大会という総合競技大会を開いています。
近代オリンピックへの動きは、イギリスほど長期的・具合的には進みませんでしたが、他のヨーロッパ各地でも徐々に表われ始めました。1881年にはエルンスト・クルチウスによってギリシャのオリンピア遺跡が発掘され、1859年には国内だけの地域的な催しではありましたが、ギリシヤ・オリンピックが開かれています。そうした中で、近代オリンピックの父と呼ばれるピエール・ド・クーベルタンが登場します。彼は1863年にフランスで生まれ、1883年にイギリスに渡って「スポーツを通した教育」の存在を知ります。1889年にはフランス政府からの命令でアメリカを訪れ、つぶさにアメリカの教育機関とスポーツ施設を見て回ります。このような国際交流によって、クーベルタンは「スポーツの世界は万国共通でなければならない」という考えを抱くようになったのです。 |
|
| ■ |
オリンピックの復興が決定 |
|
1892年11月25日、フランスに帰ったクーベルタンは、ソルボンヌ大学での講演でオリンピック競技大会復興に対する支持と協力を要請していますが、残念ながら大した協力は得られず、その時の試みは失敗に終わりました。その後1884年にパリで万国博覧会が開かれますが、クーベルタンはこの機会を利用して一気にオリンピック復興を協議しようと考え、プロジェクトチームを作って議題を決めました。初め反応は鈍かったものの、徐々に国際的な賛同を得ることに成功しました。こうしてオリンピック大会の復興宣言は、1894年6月23日、満場一致で可決され、第1回は1896年にギリシヤのアテネで開催されることになりました。そして、大会開催に関する最高の権威を持つ国際オリンピック委員会が設立され、その会長にはギリシヤ出身の知識人であるビケラスが就任します。こうして1896年4月5日、国王が開会を宣言し、オリンピック賛歌が演奏され、祝砲が響き渡り、鳩が一斉に舞い上がり、漸くクーベルタンの努力が実を結び、オリンピック競技が始まりました。第1回近代オリンピック大会は大成功を収め、15世紀ぶりにオリンピック精神は甦ったのです。 |
|
| ■ |
日本におけるオリンピック |
|
日本の「オリンピック運動の父」は、東京高等師範学校(現在の筑波大学)の校長で、柔道の普及に努めた嘉納治五郎です。1909年、彼はアジア初となるIOC委員に就任、日本のオリンピック参加へ向け、大日本体育協会(現在の日本体育協会)を設立しました。1911年には国内選考会を開催、陸上短距離の三島弥彦やマラソンの金栗四三を代表選手に選出し、翌1912年、スウェーデンのストックホルムで開催された第5回オリンピック競技大会で、日本は初のオリンピック参加を果たしています。
日本が初めてオリンピックに参加したのは、1912年に開催されたストックホルム夏季大会です。これはオリンピックの普及に腐心したクーベルタン男爵の強い勧めによるものですが、上でも述べたように、嘉納治五郎を初めとする日本側関係者の努力も大きかったのです。最初は男子陸上のみによる参加でしたが、1928年アムステルダム大会からは女子選手も参加しました。また、このストックホルム夏季大会で嘉納治五郎は日本人初のIOC委員として参加しました。また、男子陸上の選手として参加したのは短距離の三島弥彦とマラソン選手の金栗四三で、この2名が日本人初のオリンピック選手として大会に参加したのです。
日本選手のメダル獲得、ベルリン大会から始まったラジオ実況中継、聖火ランナーなどにより日本でのオリンピックに対する関心が増し、1940年の夏の大会を東京に、1940年の冬の大会を札幌に招致することに成功しましたが、これらの大会は日中戦争(支那事変)の激化もあり、自ら開催権を返上することになります。戦後の1948年ロンドン大会には、戦争責任からドイツと共に日本は参加を許されず、1952年ヘルシンキ夏季大会より復帰しています。日本国内での開催は、夏季オリンピックを東京、冬季オリンピックを札幌(これらはそれぞれアジア地区で最初の開催でもあります)及び長野で行なっています。
さらに、2020年の夏季オリンピックの開催地に東京が選出され、2度目の夏季オリンピックの開催が決定しました。なお、余談ながらオリンピックの開催年は全国高等学校野球選手権大会の日程が調整されることがあり、1992年の第74回全国高等学校野球選手権大会ではバルセロナオリンピックの終了を待って8月10日から開催され、逆に2008年の第90回全国高等学校野球選手権記念大会では北京オリンピックとの重複を可能な限り避けるために大会史上最早の8月2日から開催されたこともあります。 |
|
|
[ ページトップ ] [アドバイス トップ]
|
|